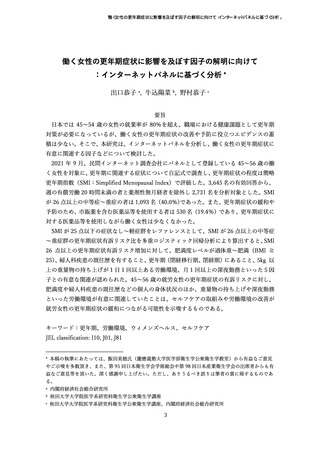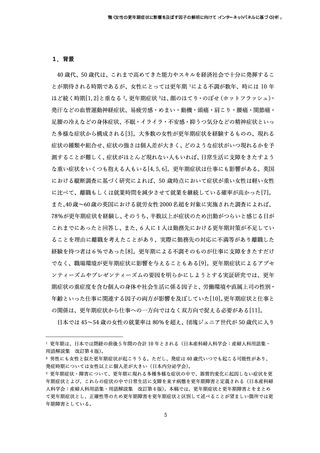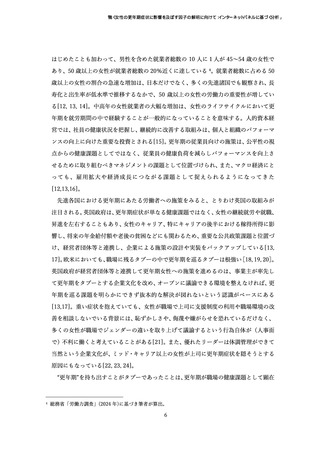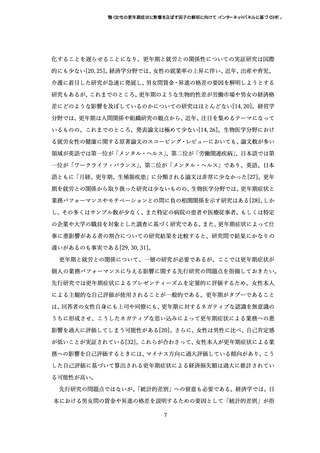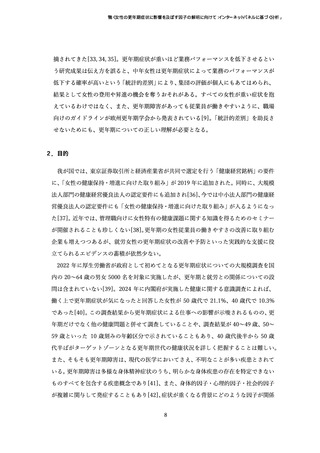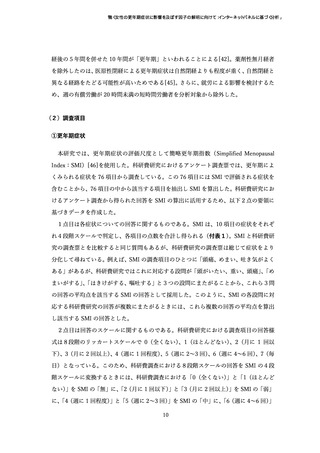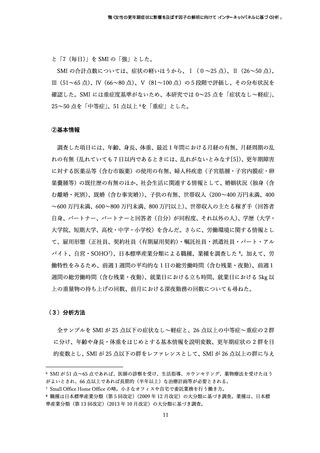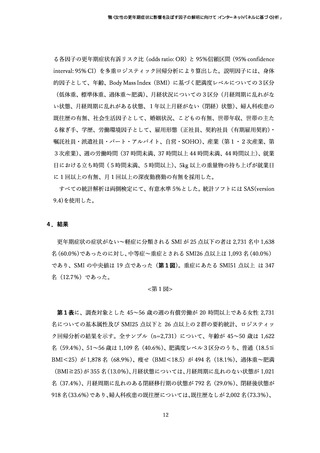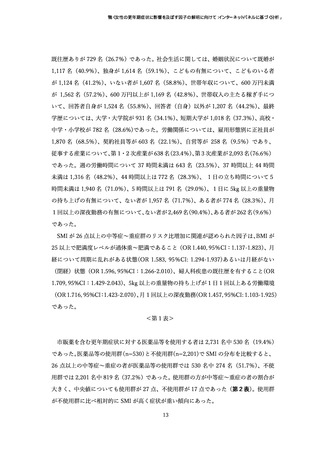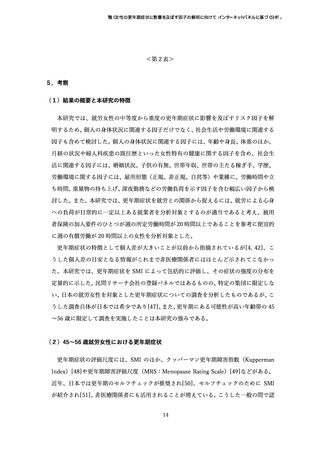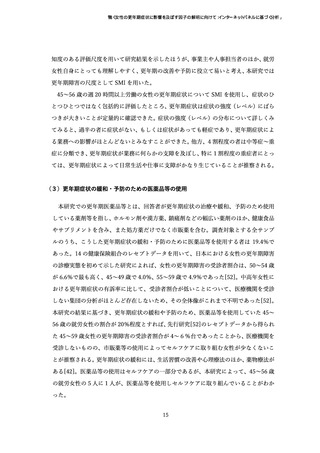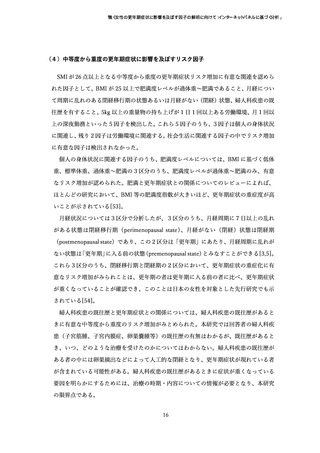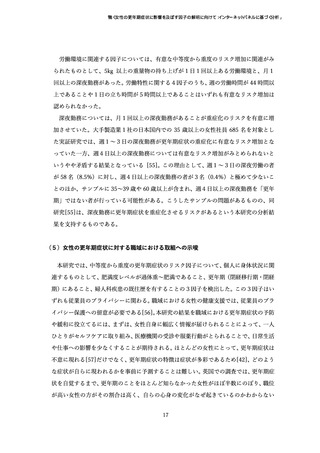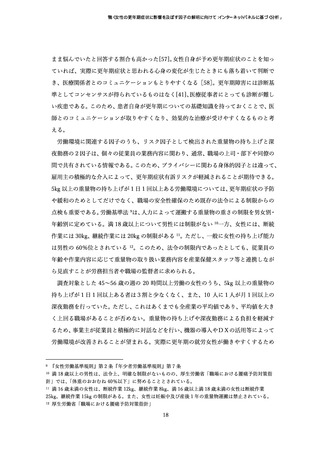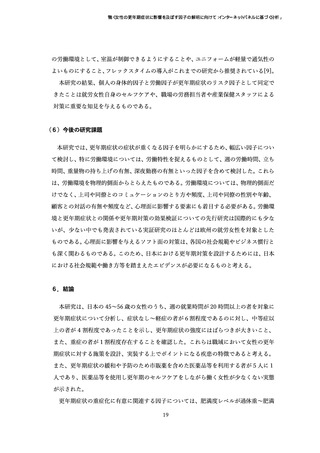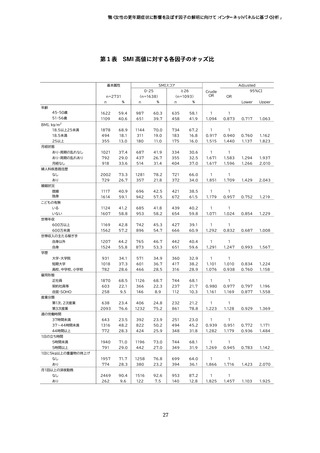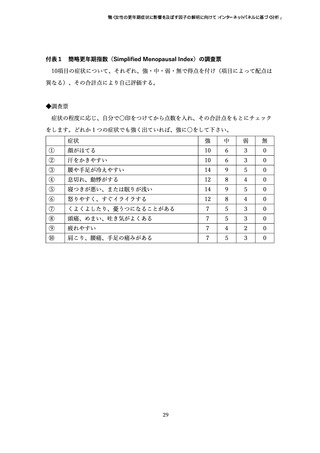よむ、つかう、まなぶ。
働く女性の更年期症状に影響を及ぼす因子の解明に向けて:インターネットパネルに基づく分析 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.esri.cao.go.jp/jp/esri/archive/e_dis/2025/e_dis401.html |
| 出典情報 | 働く女性の更年期症状に影響を及ぼす因子の解明に向けて:インターネットパネルに基づく分析(6/9)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ESRI Discussion Paper Series No.401
「働く女性の更年期症状に影響を及ぼす因子の解明に向けて:インターネットパネルに基づく分析」
化することを遅らせることになり、更年期と就労との関係性についての実証研究は国際
的にも少ない[20, 25]。経済学分野では、女性の就業率の上昇に伴い、近年、出産や育児、
介護に着目した研究が急速に発展し、男女間賃金・昇進の格差の要因を解明しようとする
研究もあるが、これまでのところ、更年期のような生物的性差が労働市場や男女の経済格
差にどのような影響を及ぼしているのかについての研究はほとんどない[14, 20]。経営学
分野では、更年期は人間関係や組織研究の観点から、近年、注目を集めるテーマになって
いるものの、これまでのところ、発表論文は極めて少ない[14, 26]。生物医学分野におけ
る就労女性の健康に関する原著論文のスコーピング・レビューにおいても、論文数が多い
領域が英語では第一位が「メンタル・ヘルス」
、第二位が「労働関連疾病」、日本語では第
一位が「ワークライフ・バランス」
、第二位が「メンタル・ヘルス」であり、英語、日本
語ともに「月経、更年期、生殖器疾患」に分類される論文は非常に少なかった[27]。更年
期を就労との関係から取り扱った研究は少ないものの、生物医学分野では、更年期症状と
業務パフォーマンスやモチベーションとの間に負の相関関係を示す研究はある[28]。しか
し、その多くはサンプル数が少なく、また特定の病院の患者や医療従事者、もしくは特定
の企業や大学の職員を対象とした調査に基づく研究である。また、更年期症状によって仕
事に悪影響がある者の割合についての研究結果を比較すると、研究間で結果にかなりの
違いがあるのも事実である[29, 30, 31]。
更年期と就労との関係について、一層の研究が必要であるが、ここでは更年期症状が
個人の業務パフォーマンスに与える影響に関する先行研究の問題点を指摘しておきたい。
先行研究では更年期症状によるプレゼンティーズムを定量的に評価するため、女性本人
による主観的な自己評価が使用されることが一般的である。更年期がタブーであること
は、回答者の女性自身にも上司や同僚にも、更年期に対するネガティブな認識を無意識の
うちに形成させ、こうしたネガティブな思い込みによって更年期症状による業務への悪
影響を過大に評価してしまう可能性がある[20]。さらに、女性は男性に比べ、自己肯定感
が低いことが実証されている[32]。これらが合わさって、女性本人が更年期症状による業
務への影響を自己評価するときには、マイナス方向に過大評価している傾向があり、こう
した自己評価に基づいて算出される更年期症状による経済損失額は過大に推計されてい
る可能性が高い。
先行研究の問題点ではないが、
「統計的差別」への留意も必要である。経済学では、日
本における男女間の賃金や昇進の格差を説明するための要因として「統計的差別」が指
7
「働く女性の更年期症状に影響を及ぼす因子の解明に向けて:インターネットパネルに基づく分析」
化することを遅らせることになり、更年期と就労との関係性についての実証研究は国際
的にも少ない[20, 25]。経済学分野では、女性の就業率の上昇に伴い、近年、出産や育児、
介護に着目した研究が急速に発展し、男女間賃金・昇進の格差の要因を解明しようとする
研究もあるが、これまでのところ、更年期のような生物的性差が労働市場や男女の経済格
差にどのような影響を及ぼしているのかについての研究はほとんどない[14, 20]。経営学
分野では、更年期は人間関係や組織研究の観点から、近年、注目を集めるテーマになって
いるものの、これまでのところ、発表論文は極めて少ない[14, 26]。生物医学分野におけ
る就労女性の健康に関する原著論文のスコーピング・レビューにおいても、論文数が多い
領域が英語では第一位が「メンタル・ヘルス」
、第二位が「労働関連疾病」、日本語では第
一位が「ワークライフ・バランス」
、第二位が「メンタル・ヘルス」であり、英語、日本
語ともに「月経、更年期、生殖器疾患」に分類される論文は非常に少なかった[27]。更年
期を就労との関係から取り扱った研究は少ないものの、生物医学分野では、更年期症状と
業務パフォーマンスやモチベーションとの間に負の相関関係を示す研究はある[28]。しか
し、その多くはサンプル数が少なく、また特定の病院の患者や医療従事者、もしくは特定
の企業や大学の職員を対象とした調査に基づく研究である。また、更年期症状によって仕
事に悪影響がある者の割合についての研究結果を比較すると、研究間で結果にかなりの
違いがあるのも事実である[29, 30, 31]。
更年期と就労との関係について、一層の研究が必要であるが、ここでは更年期症状が
個人の業務パフォーマンスに与える影響に関する先行研究の問題点を指摘しておきたい。
先行研究では更年期症状によるプレゼンティーズムを定量的に評価するため、女性本人
による主観的な自己評価が使用されることが一般的である。更年期がタブーであること
は、回答者の女性自身にも上司や同僚にも、更年期に対するネガティブな認識を無意識の
うちに形成させ、こうしたネガティブな思い込みによって更年期症状による業務への悪
影響を過大に評価してしまう可能性がある[20]。さらに、女性は男性に比べ、自己肯定感
が低いことが実証されている[32]。これらが合わさって、女性本人が更年期症状による業
務への影響を自己評価するときには、マイナス方向に過大評価している傾向があり、こう
した自己評価に基づいて算出される更年期症状による経済損失額は過大に推計されてい
る可能性が高い。
先行研究の問題点ではないが、
「統計的差別」への留意も必要である。経済学では、日
本における男女間の賃金や昇進の格差を説明するための要因として「統計的差別」が指
7