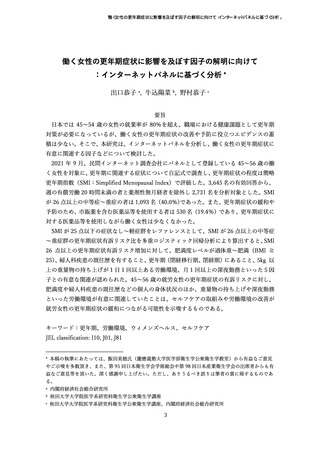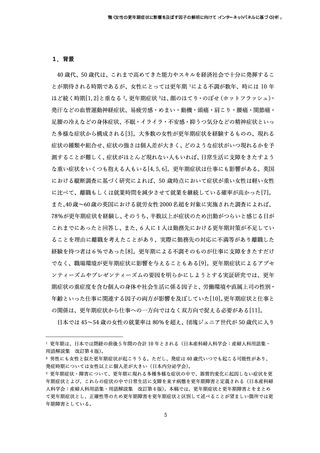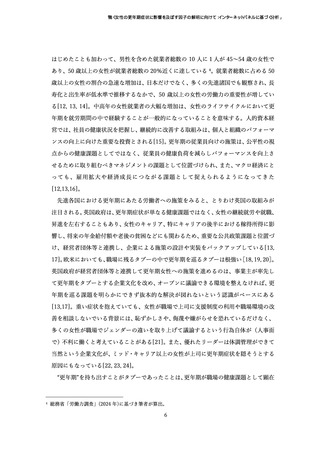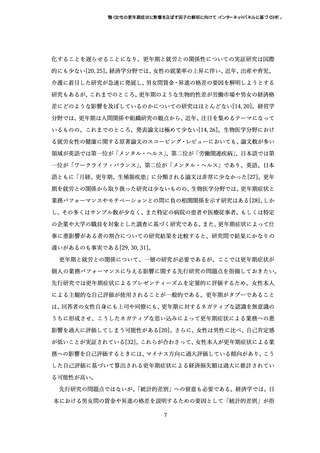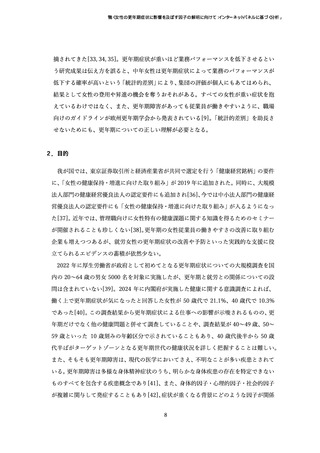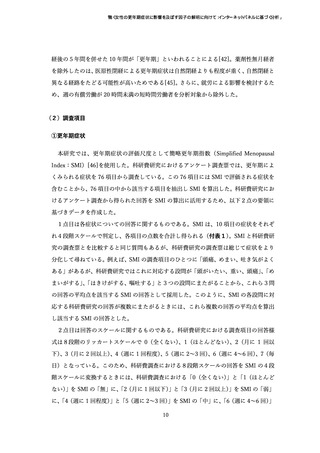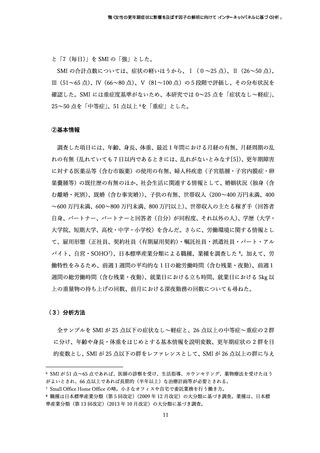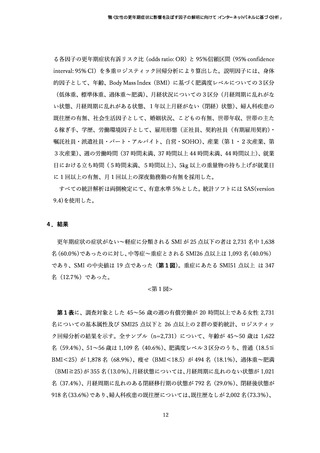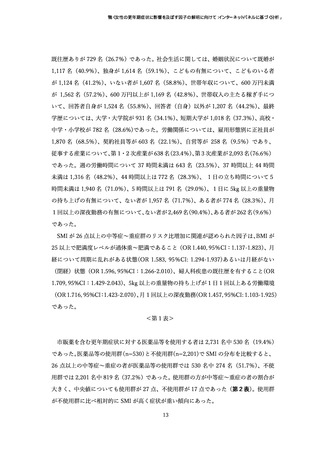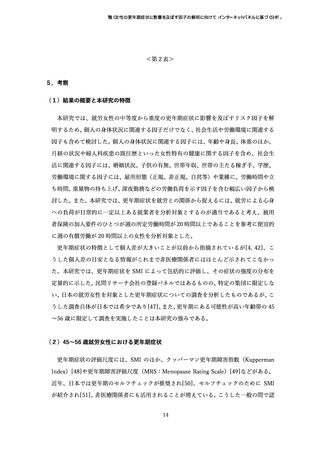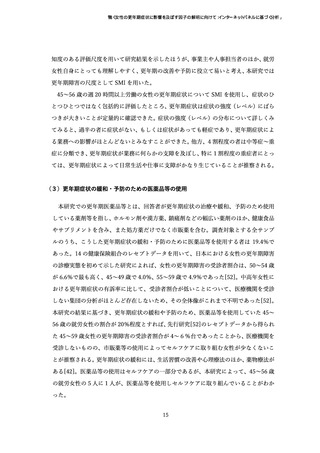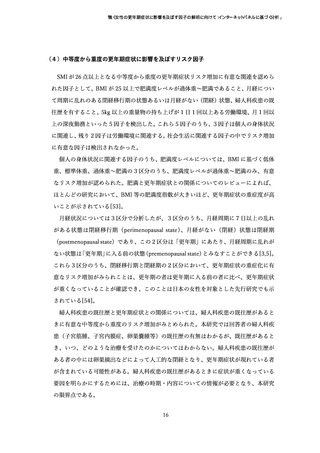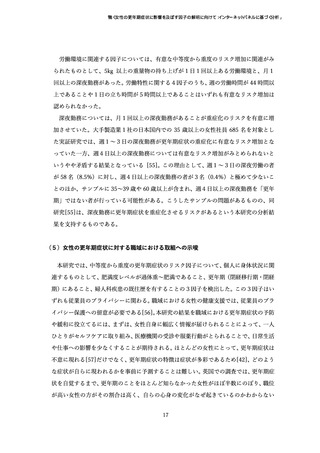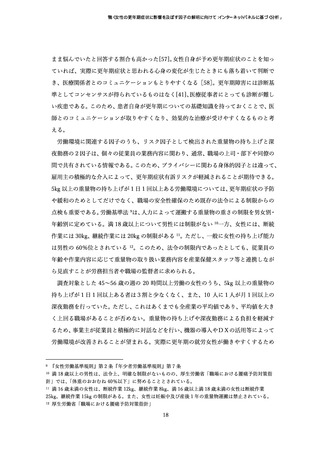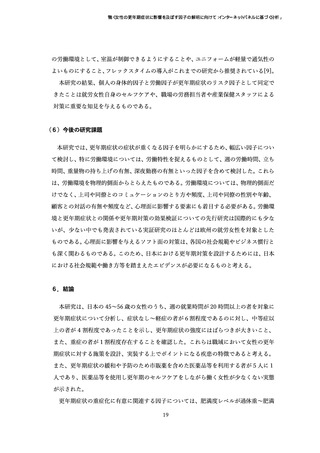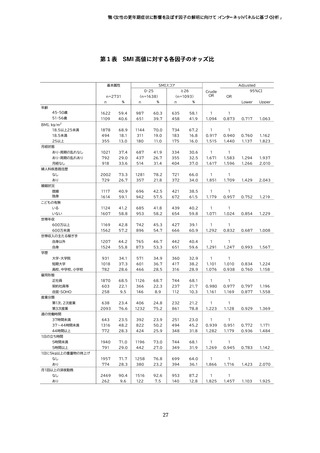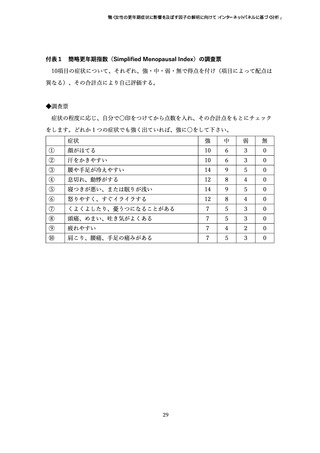よむ、つかう、まなぶ。
働く女性の更年期症状に影響を及ぼす因子の解明に向けて:インターネットパネルに基づく分析 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.esri.cao.go.jp/jp/esri/archive/e_dis/2025/e_dis401.html |
| 出典情報 | 働く女性の更年期症状に影響を及ぼす因子の解明に向けて:インターネットパネルに基づく分析(6/9)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ESRI Discussion Paper Series No.401
「働く女性の更年期症状に影響を及ぼす因子の解明に向けて:インターネットパネルに基づく分析」
はじめたことも加わって、男性を含めた就業者総数の 10 人に1人が 45~54 歳の女性で
あり、50 歳以上の女性が就業者総数の 20%近くに達している 4。就業者総数に占める 50
歳以上の女性の割合の急速な増加は、日本だけでなく、多くの先進諸国でも観察され、長
寿化と出生率が低水準で推移するなかで、50 歳以上の女性の労働力の重要性が増してい
る[12, 13, 14]。中高年の女性就業者の大幅な増加は、女性のライフサイクルにおいて更
年期を就労期間の中で経験することが一般的になっていることを意味する。人的資本経
営では、社員の健康状況を把握し、継続的に改善する取組みは、個人と組織のパフォーマ
ンスの向上に向けた重要な投資とされる[15]。更年期の従業員向けの施策は、公平性の視
点からの健康課題としてではなく、従業員の健康負荷を減らしパフォーマンスを向上さ
せるために取り組むべきマネジメントの課題として位置づけられ、また、マクロ経済にと
って も、雇用 拡大や経済成 長につな がる課題とし て捉えら れるようにな ってき た
[12,13,16]。
先進各国における更年期にあたる労働者への施策をみると、とりわけ英国の取組みが
注目される。英国政府は、更年期症状が単なる健康課題ではなく、女性の継続就労や就職、
昇進を左右することもあり、女性のキャリア、特にキャリアの後半における稼得所得に影
響し、将来の年金給付額や老後の貧困などにも関わるため、重要な公共政策課題と位置づ
け、経営者団体等と連携し、企業による施策の設計や実装をバックアップしている[13,
17]。欧米においても、職場に残るタブーの中で更年期を巡るタブーは根強い[18, 19, 20]
。
英国政府が経営者団体等と連携して更年期女性への施策を進めるのは、事業主が率先し
て更年期をタブーとする企業文化を改め、オープンに議論できる環境を整えなければ、更
年期を巡る課題を明らかにできず抜本的な解決が図れないという認識がベースにある
[13,17]。重い症状を抱えていても、女性が職場で上司に支援制度の利用や職場環境の改
善を相談しないでいる背景には、恥ずかしさや、侮蔑や嫌がらせを恐れているだけなく、
多くの女性が職場でジェンダーの違いを取り上げて議論するという行為自体が(人事面
で)不利に働くと考えていることがある[21]。また、優れたリーダーは体調管理ができて
当然という企業文化が、ミッド・キャリア以上の女性が上司に更年期症状を隠そうとする
原因にもなっている[22, 23, 24]。
“更年期”を持ち出すことがタブーであったことは、更年期が職場の健康課題として顕在
4
総務省「労働力調査」(2024 年)に基づき筆者が算出。
6
「働く女性の更年期症状に影響を及ぼす因子の解明に向けて:インターネットパネルに基づく分析」
はじめたことも加わって、男性を含めた就業者総数の 10 人に1人が 45~54 歳の女性で
あり、50 歳以上の女性が就業者総数の 20%近くに達している 4。就業者総数に占める 50
歳以上の女性の割合の急速な増加は、日本だけでなく、多くの先進諸国でも観察され、長
寿化と出生率が低水準で推移するなかで、50 歳以上の女性の労働力の重要性が増してい
る[12, 13, 14]。中高年の女性就業者の大幅な増加は、女性のライフサイクルにおいて更
年期を就労期間の中で経験することが一般的になっていることを意味する。人的資本経
営では、社員の健康状況を把握し、継続的に改善する取組みは、個人と組織のパフォーマ
ンスの向上に向けた重要な投資とされる[15]。更年期の従業員向けの施策は、公平性の視
点からの健康課題としてではなく、従業員の健康負荷を減らしパフォーマンスを向上さ
せるために取り組むべきマネジメントの課題として位置づけられ、また、マクロ経済にと
って も、雇用 拡大や経済成 長につな がる課題とし て捉えら れるようにな ってき た
[12,13,16]。
先進各国における更年期にあたる労働者への施策をみると、とりわけ英国の取組みが
注目される。英国政府は、更年期症状が単なる健康課題ではなく、女性の継続就労や就職、
昇進を左右することもあり、女性のキャリア、特にキャリアの後半における稼得所得に影
響し、将来の年金給付額や老後の貧困などにも関わるため、重要な公共政策課題と位置づ
け、経営者団体等と連携し、企業による施策の設計や実装をバックアップしている[13,
17]。欧米においても、職場に残るタブーの中で更年期を巡るタブーは根強い[18, 19, 20]
。
英国政府が経営者団体等と連携して更年期女性への施策を進めるのは、事業主が率先し
て更年期をタブーとする企業文化を改め、オープンに議論できる環境を整えなければ、更
年期を巡る課題を明らかにできず抜本的な解決が図れないという認識がベースにある
[13,17]。重い症状を抱えていても、女性が職場で上司に支援制度の利用や職場環境の改
善を相談しないでいる背景には、恥ずかしさや、侮蔑や嫌がらせを恐れているだけなく、
多くの女性が職場でジェンダーの違いを取り上げて議論するという行為自体が(人事面
で)不利に働くと考えていることがある[21]。また、優れたリーダーは体調管理ができて
当然という企業文化が、ミッド・キャリア以上の女性が上司に更年期症状を隠そうとする
原因にもなっている[22, 23, 24]。
“更年期”を持ち出すことがタブーであったことは、更年期が職場の健康課題として顕在
4
総務省「労働力調査」(2024 年)に基づき筆者が算出。
6