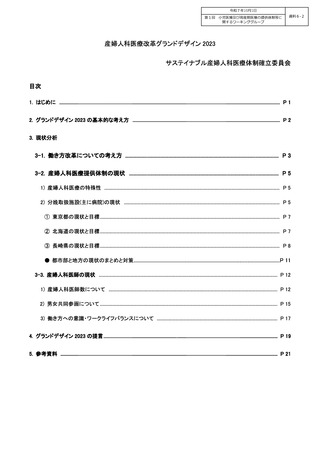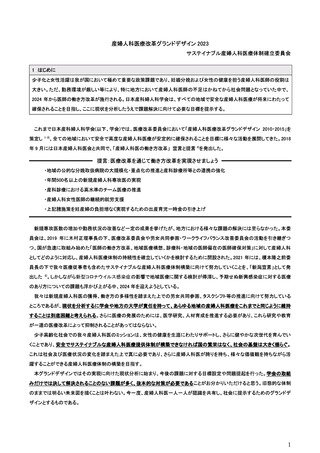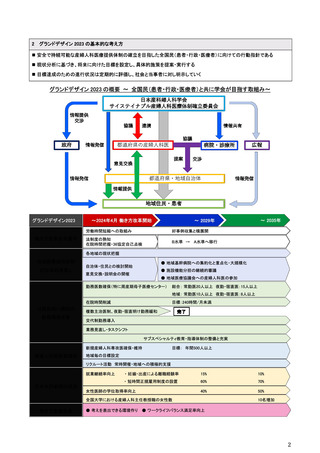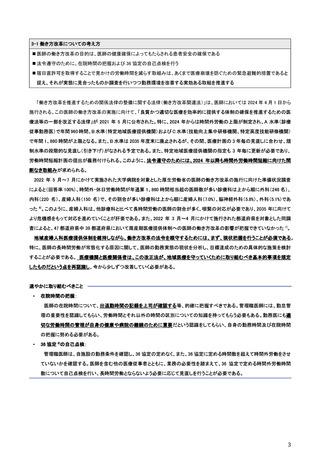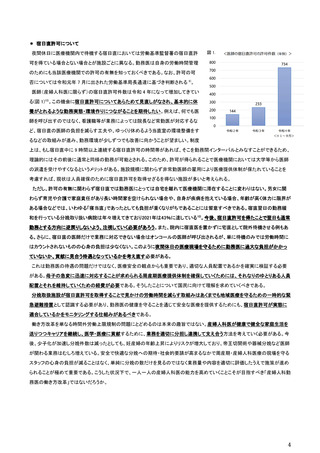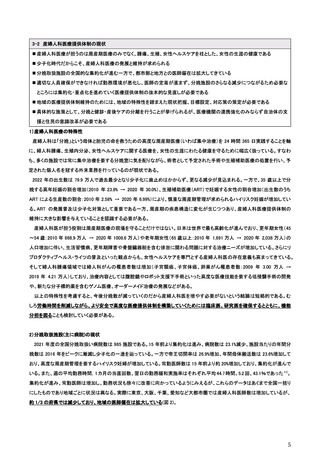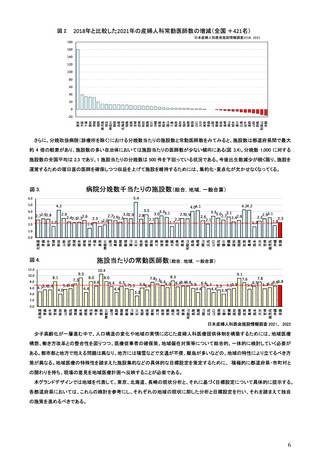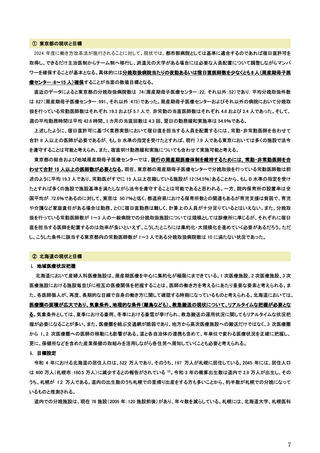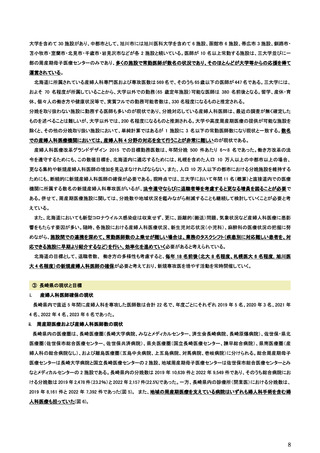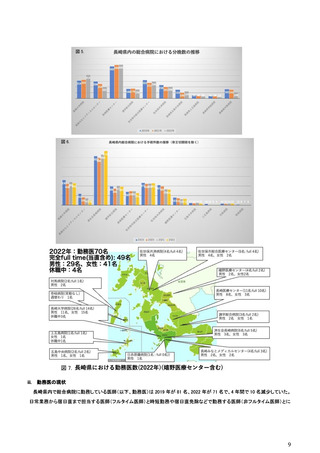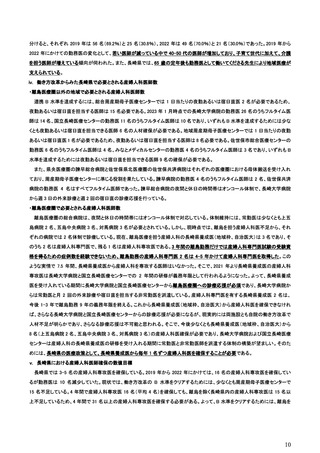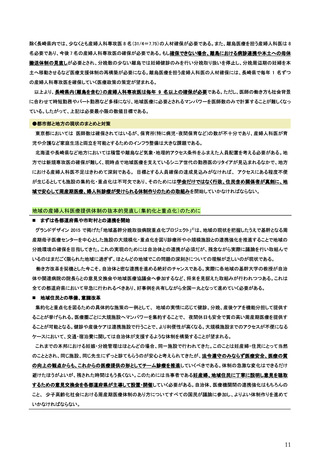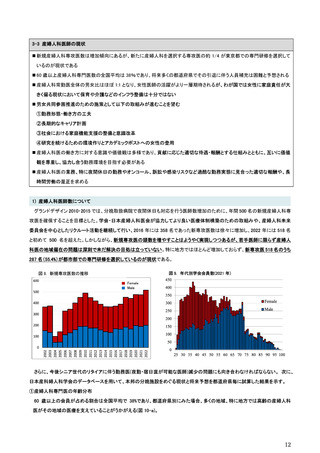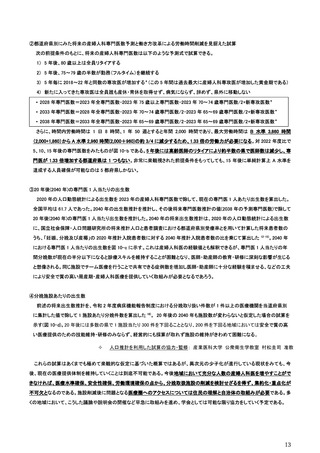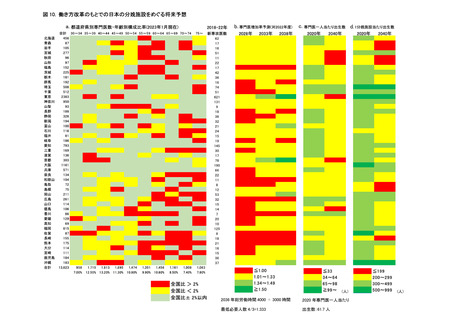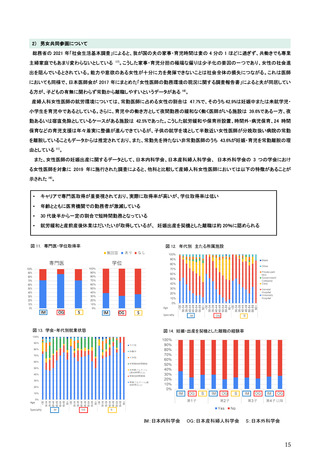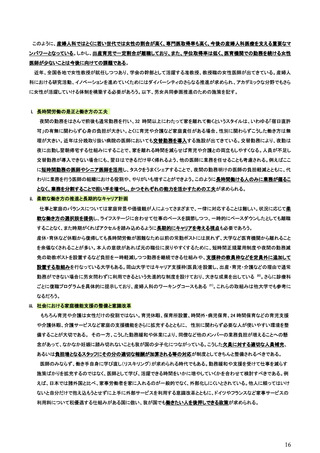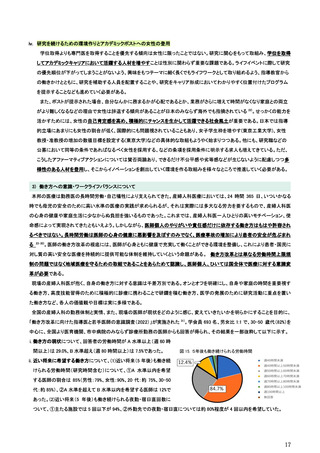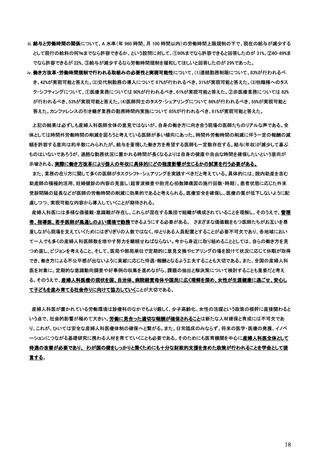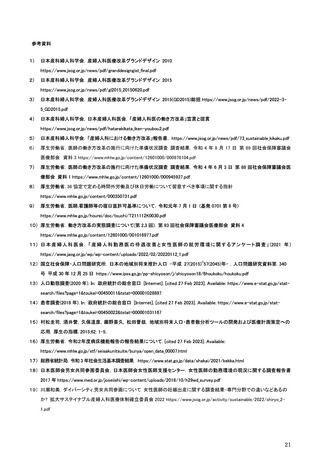よむ、つかう、まなぶ。
資料6-2_三浦構成員提出資料2 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |
| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
産婦人科医療改革グランドデザイン 2023
サステイナブル産婦人科医療体制確立委員会
1 はじめに
少子化と女性活躍は我が国において極めて重要な政策課題であり、妊娠分娩および女性の健康を担う産婦人科医師の役割は
大きい。ただ、勤務環境が厳しい等により、特に地方において産婦人科医師の不足はかねてから社会問題となっていた中で、
2024 年から医師の働き方改革が施行される。日本産科婦人科学会は、すべての地域で安全な産婦人科医療が将来にわたって
確保されることを目指し、ここに現状を分析したうえで課題解決に向けて必要な目標を提示する。
これまで日本産科婦人科学会(以下、学会)では、医療改革委員会において「産婦人科医療改革グランドデザイン 2010・2015」を
策定し 1-3)、全ての地域において安全で高度な産婦人科医療が安定的に確保されることを目標に様々な活動を展開してきた。2018
年 9 月には日本産婦人科医会と共同で、「産婦人科医の働き方改革」 宣言と提言 4)を発出した。
提言:医療改革を通じて働き方改革を実現させましょう
・地域の公的な分娩取扱病院の大規模化・重点化の推進と産科診療所等との連携の強化
・年間500名以上の新規産婦人科専攻医の実現
・産科診療における高水準のチーム医療の推進
・産婦人科女性医師の継続的就労支援
・上記諸施策を妊産婦の負担増なく実現するための出産育児一時金の引き上げ
新規専攻医数の増加や勤務状況の改善など一定の成果を挙げたが、地方における様々な課題の解決には至らなかった。本委
員会は、2019 年に木村正理事長の下、医療改革委員会や男女共同参画・ワークライフバランス改善委員会の活動を引き継ぎつ
つ、国が急速に取組み始めた「医師の働き方改革、地域医療構想、診療科・地域の医師偏在の医師確保対策」に対して産婦人科
としてどのように対応し、産婦人科医療体制の持続性を確立していくかを検討するために開設された。2021 年には、榎本隆之前委
員長の下で我々医療従事者も含めたサステイナブルな産婦人科医療体制構築に向けて努力していくことを、「新潟宣言」として発
出した 5)。しかしながら新型コロナウイルス感染症の影響で地域医療に関する検討が停滞し、予期せぬ新興感染症に対する医療
のあり方についての課題も浮かび上がる中、2024 年を迎えようとしている。
我々は新規産婦人科医の獲得、働き方の多様性を踏まえた上での男女共同参画、タスクシフト等の推進に向けて努力している
ところであるが、現状を分析するに学会や地方の大学が責任を持って、あらゆる地域の産婦人科医療をこれまでと同じように維持
することは到底困難と考えられる。さらに医療の発展のためには、医学研究、人材育成を推進する必要があり、これら研究や教育
が一連の医療改革によって抑制されることがあってはならない。
少子高齢化社会での我々産婦人科医のミッションは、女性の健康を生涯にわたりサポートし、さらに健やかな次世代を育んでい
くことであり、安全でサステイナブルな産婦人科医療提供体制が構築できなければ国の繁栄はなく、社会の基盤は大きく揺らぐ。
これは社会及び医療状況の変化を踏まえた上で真に必要であり、さらに産婦人科医が誇りを持ち、様々な価値観を持ちながら活
躍することができる産婦人科医療体制の構築を目指す。
本グランドデザインではその実現に向けた現状分析に始まり、今後の課題に対する目標設定や問題提起を行った。学会の取組
みだけでは決して解決されることのない課題が多く、抜本的な対策が必要であることがお分かりいただけると思う。旧態的な体制
のままでは明るい未来図を描くことは叶わない。今一度、産婦人科医一人一人が認識を共有し、社会に提示するためのグランドデ
ザインとするものである。
1
サステイナブル産婦人科医療体制確立委員会
1 はじめに
少子化と女性活躍は我が国において極めて重要な政策課題であり、妊娠分娩および女性の健康を担う産婦人科医師の役割は
大きい。ただ、勤務環境が厳しい等により、特に地方において産婦人科医師の不足はかねてから社会問題となっていた中で、
2024 年から医師の働き方改革が施行される。日本産科婦人科学会は、すべての地域で安全な産婦人科医療が将来にわたって
確保されることを目指し、ここに現状を分析したうえで課題解決に向けて必要な目標を提示する。
これまで日本産科婦人科学会(以下、学会)では、医療改革委員会において「産婦人科医療改革グランドデザイン 2010・2015」を
策定し 1-3)、全ての地域において安全で高度な産婦人科医療が安定的に確保されることを目標に様々な活動を展開してきた。2018
年 9 月には日本産婦人科医会と共同で、「産婦人科医の働き方改革」 宣言と提言 4)を発出した。
提言:医療改革を通じて働き方改革を実現させましょう
・地域の公的な分娩取扱病院の大規模化・重点化の推進と産科診療所等との連携の強化
・年間500名以上の新規産婦人科専攻医の実現
・産科診療における高水準のチーム医療の推進
・産婦人科女性医師の継続的就労支援
・上記諸施策を妊産婦の負担増なく実現するための出産育児一時金の引き上げ
新規専攻医数の増加や勤務状況の改善など一定の成果を挙げたが、地方における様々な課題の解決には至らなかった。本委
員会は、2019 年に木村正理事長の下、医療改革委員会や男女共同参画・ワークライフバランス改善委員会の活動を引き継ぎつ
つ、国が急速に取組み始めた「医師の働き方改革、地域医療構想、診療科・地域の医師偏在の医師確保対策」に対して産婦人科
としてどのように対応し、産婦人科医療体制の持続性を確立していくかを検討するために開設された。2021 年には、榎本隆之前委
員長の下で我々医療従事者も含めたサステイナブルな産婦人科医療体制構築に向けて努力していくことを、「新潟宣言」として発
出した 5)。しかしながら新型コロナウイルス感染症の影響で地域医療に関する検討が停滞し、予期せぬ新興感染症に対する医療
のあり方についての課題も浮かび上がる中、2024 年を迎えようとしている。
我々は新規産婦人科医の獲得、働き方の多様性を踏まえた上での男女共同参画、タスクシフト等の推進に向けて努力している
ところであるが、現状を分析するに学会や地方の大学が責任を持って、あらゆる地域の産婦人科医療をこれまでと同じように維持
することは到底困難と考えられる。さらに医療の発展のためには、医学研究、人材育成を推進する必要があり、これら研究や教育
が一連の医療改革によって抑制されることがあってはならない。
少子高齢化社会での我々産婦人科医のミッションは、女性の健康を生涯にわたりサポートし、さらに健やかな次世代を育んでい
くことであり、安全でサステイナブルな産婦人科医療提供体制が構築できなければ国の繁栄はなく、社会の基盤は大きく揺らぐ。
これは社会及び医療状況の変化を踏まえた上で真に必要であり、さらに産婦人科医が誇りを持ち、様々な価値観を持ちながら活
躍することができる産婦人科医療体制の構築を目指す。
本グランドデザインではその実現に向けた現状分析に始まり、今後の課題に対する目標設定や問題提起を行った。学会の取組
みだけでは決して解決されることのない課題が多く、抜本的な対策が必要であることがお分かりいただけると思う。旧態的な体制
のままでは明るい未来図を描くことは叶わない。今一度、産婦人科医一人一人が認識を共有し、社会に提示するためのグランドデ
ザインとするものである。
1