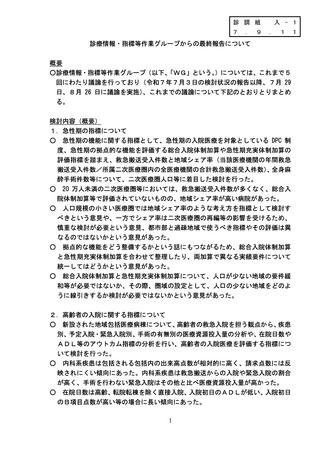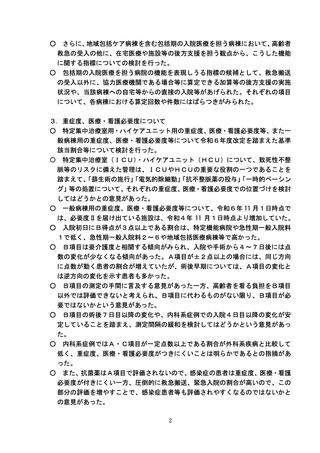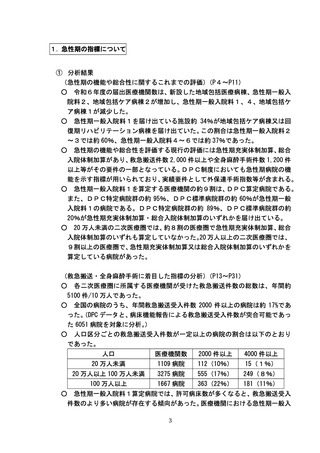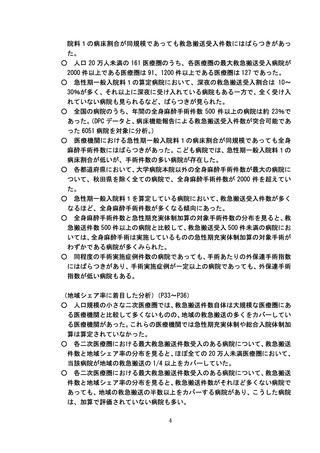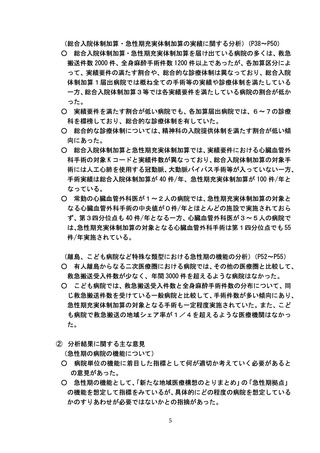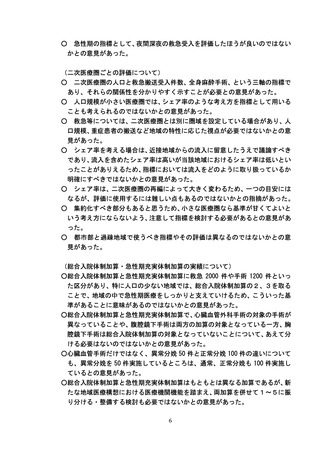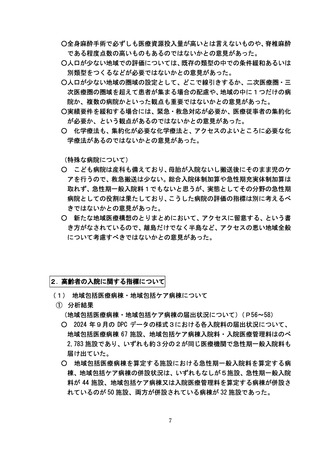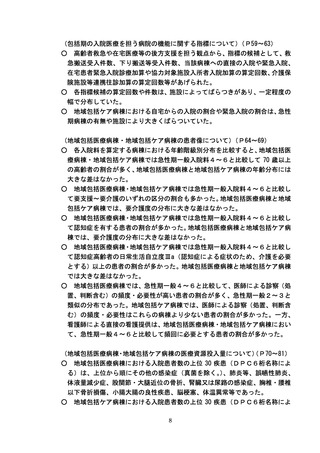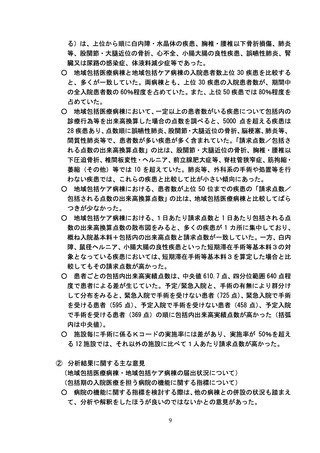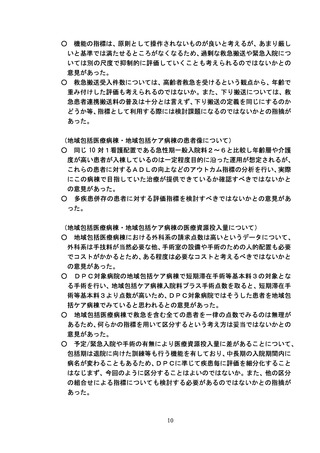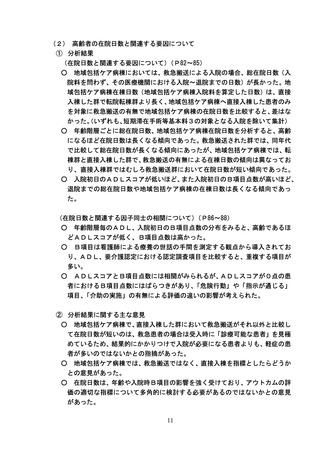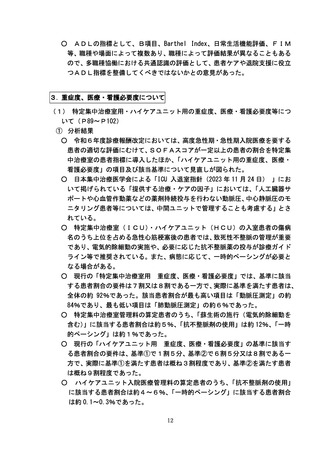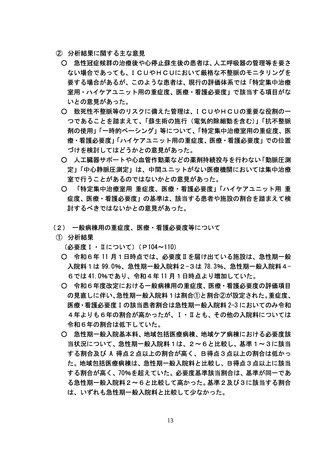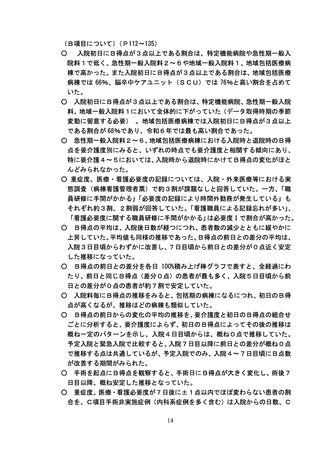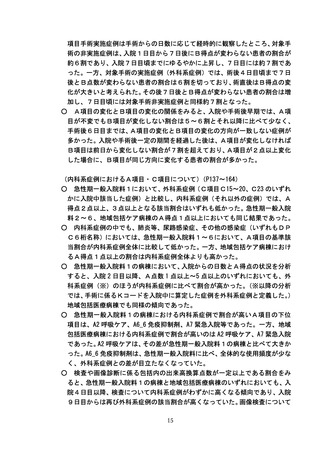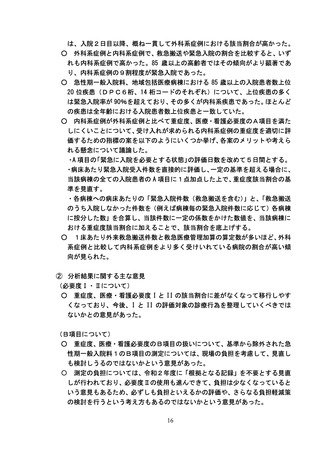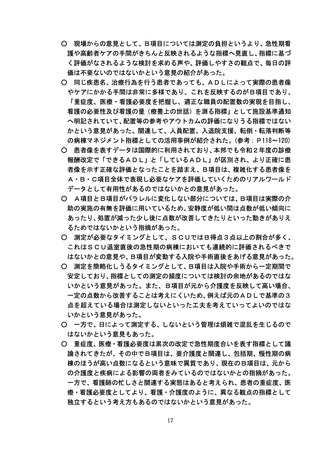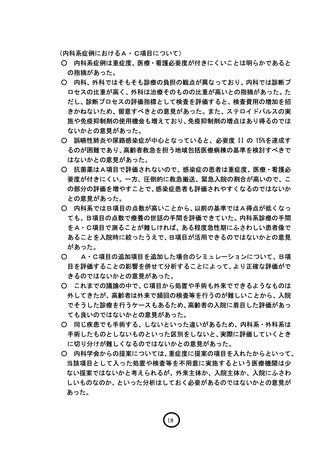よむ、つかう、まなぶ。
入ー1 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00281.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第11回 9/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○
現場からの意見として、B項目については測定の負担というより、急性期看
護や高齢者ケアの手間がきちんと反映されるような指標へ見直し、指標に基づ
く評価がなされるような検討を求める声や、評価しやすさの観点で、毎日の評
価は不要ないのではないかという意見の紹介があった。
○ 同じ疾患名、治療行為を行う患者であっても、ADLによって実際の患者像
やケアにかかる手間は非常に多様であり、これを反映するのがB項目であり、
「重症度、医療・看護必要度を把握し、適正な職員の配置数の実現を目指し、
看護の必要性及び看護の量(療養上の世話)を測る指標」として施設基準通知
へ明記されていて、配置等の参考やアウトカムの評価になりうる指標ではない
かという意見があった。関連して、人員配置、入退院支援、転倒・転落判断等
の病棟マネジメント指標としての活用事例が紹介された。(参考:P118~120)
○ 患者像を表すデータは国際的に利用されており、本邦でも令和2年度の診療
報酬改定で「できるADL」と「しているADL」が区別され、より正確に患
者像を示す正確な評価となったことを踏まえ、B項目は、複雑化する患者像を
A・B・C項目全体で表現し必要なケアを評価していくためのリアルワールド
データとして有用性があるのではないかとの意見があった。
○ A項目とB項目がパラレルに変化しない部分については、B項目は実際の介
助の実施の有無を評価に用いているため、安静度が低い間は点数が低い傾向に
あったり、処置が減った少し後に点数が改善してきたりといった動きがありえ
るためではないかという指摘があった。
○ 測定が必要なタイミングとして、SCUではB得点3点以上の割合が多く、
これはSCU退室直後の急性期の病棟においても連続的に評価されるべきで
はないかとの意見や、B項目が変動する入院や手術直後をあげる意見があった。
○ 測定を簡略化しうるタイミングとして、B項目は入院や手術から一定期間で
安定しており、指標としての測定の頻度については検討の余地があるのではな
いかという意見があった。また、B項目が元から介護度を反映して高い場合、
一定の点数から改善することは考えにくいため、例えば元のADLで基準の3
点を超えている場合は測定しないといった工夫を考えていってよいのではな
いかという意見があった。
○ 一方で、日によって測定する、しないという管理は煩雑で混乱を生じるので
はないかという意見もあった。
○ 重症度、医療・看護必要度は累次の改定で急性期度合いを表す指標として議
論されてきたが、その中でB項目は、要介護度と関連し、包括期、慢性期の病
棟のほうが高い点数になるという意味で異質であり、現在のB項目は、元から
の介護度と疾病による影響の両者をみているのではないかとの指摘があった。
一方で、看護師の忙しさと関連する実態はあると考えられ、患者の重症度、医
療・看護必要度としてより、看護・介護度のように、異なる観点の指標として
独立するという考え方もあるのではないかという意見があった。
17
現場からの意見として、B項目については測定の負担というより、急性期看
護や高齢者ケアの手間がきちんと反映されるような指標へ見直し、指標に基づ
く評価がなされるような検討を求める声や、評価しやすさの観点で、毎日の評
価は不要ないのではないかという意見の紹介があった。
○ 同じ疾患名、治療行為を行う患者であっても、ADLによって実際の患者像
やケアにかかる手間は非常に多様であり、これを反映するのがB項目であり、
「重症度、医療・看護必要度を把握し、適正な職員の配置数の実現を目指し、
看護の必要性及び看護の量(療養上の世話)を測る指標」として施設基準通知
へ明記されていて、配置等の参考やアウトカムの評価になりうる指標ではない
かという意見があった。関連して、人員配置、入退院支援、転倒・転落判断等
の病棟マネジメント指標としての活用事例が紹介された。(参考:P118~120)
○ 患者像を表すデータは国際的に利用されており、本邦でも令和2年度の診療
報酬改定で「できるADL」と「しているADL」が区別され、より正確に患
者像を示す正確な評価となったことを踏まえ、B項目は、複雑化する患者像を
A・B・C項目全体で表現し必要なケアを評価していくためのリアルワールド
データとして有用性があるのではないかとの意見があった。
○ A項目とB項目がパラレルに変化しない部分については、B項目は実際の介
助の実施の有無を評価に用いているため、安静度が低い間は点数が低い傾向に
あったり、処置が減った少し後に点数が改善してきたりといった動きがありえ
るためではないかという指摘があった。
○ 測定が必要なタイミングとして、SCUではB得点3点以上の割合が多く、
これはSCU退室直後の急性期の病棟においても連続的に評価されるべきで
はないかとの意見や、B項目が変動する入院や手術直後をあげる意見があった。
○ 測定を簡略化しうるタイミングとして、B項目は入院や手術から一定期間で
安定しており、指標としての測定の頻度については検討の余地があるのではな
いかという意見があった。また、B項目が元から介護度を反映して高い場合、
一定の点数から改善することは考えにくいため、例えば元のADLで基準の3
点を超えている場合は測定しないといった工夫を考えていってよいのではな
いかという意見があった。
○ 一方で、日によって測定する、しないという管理は煩雑で混乱を生じるので
はないかという意見もあった。
○ 重症度、医療・看護必要度は累次の改定で急性期度合いを表す指標として議
論されてきたが、その中でB項目は、要介護度と関連し、包括期、慢性期の病
棟のほうが高い点数になるという意味で異質であり、現在のB項目は、元から
の介護度と疾病による影響の両者をみているのではないかとの指摘があった。
一方で、看護師の忙しさと関連する実態はあると考えられ、患者の重症度、医
療・看護必要度としてより、看護・介護度のように、異なる観点の指標として
独立するという考え方もあるのではないかという意見があった。
17