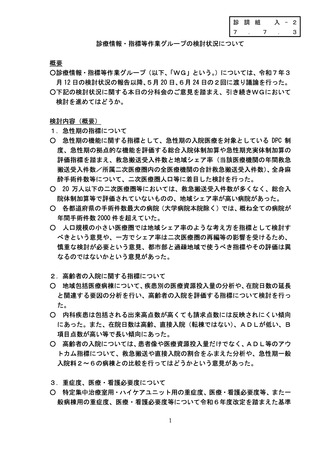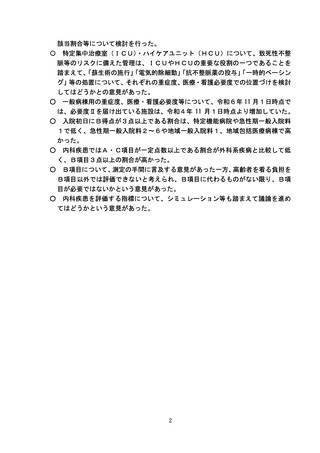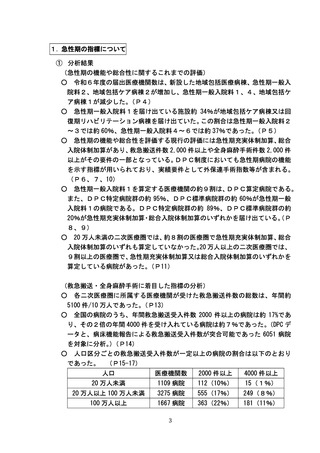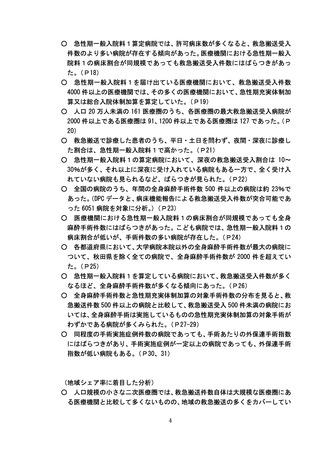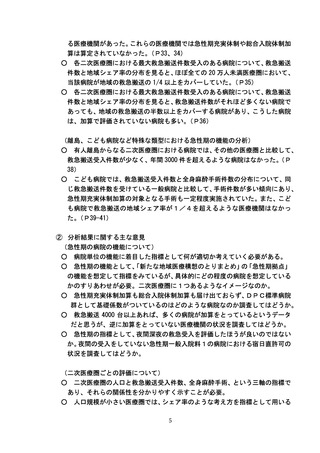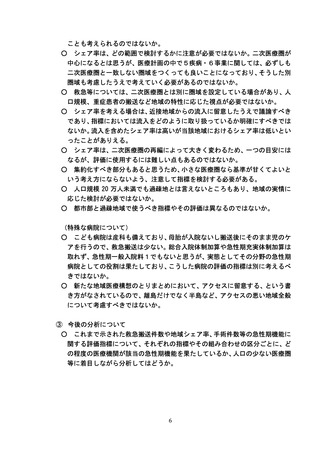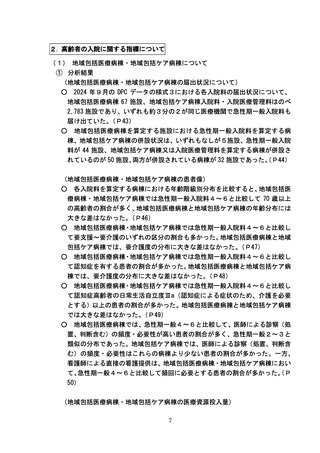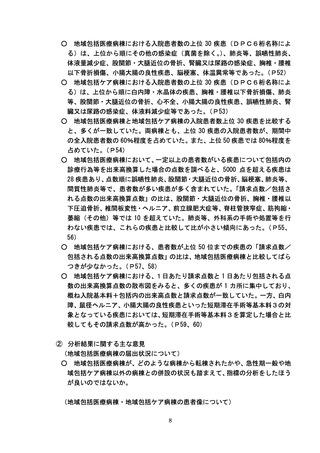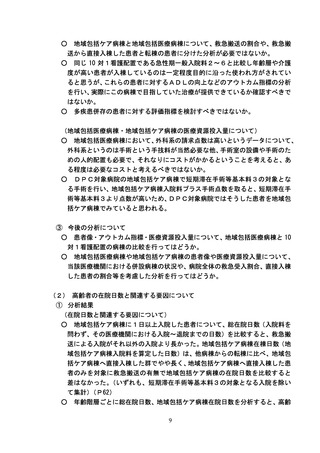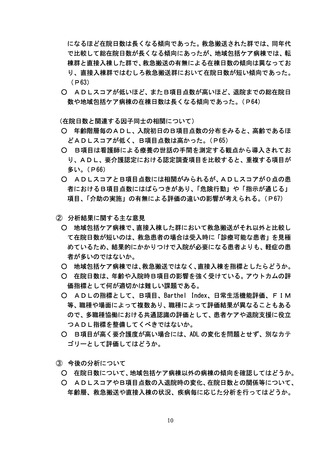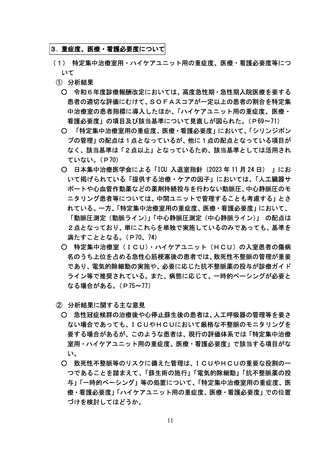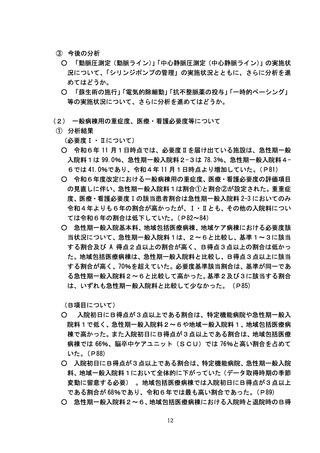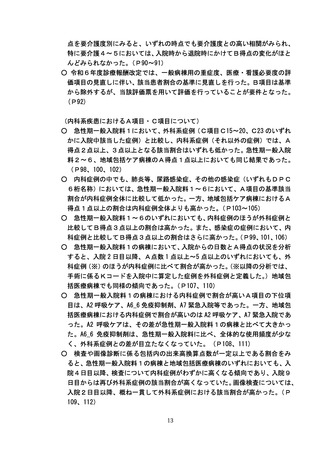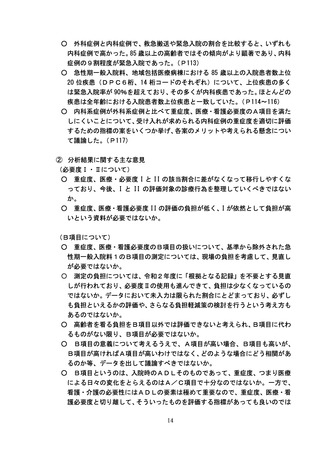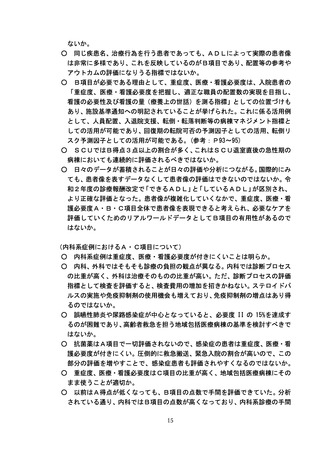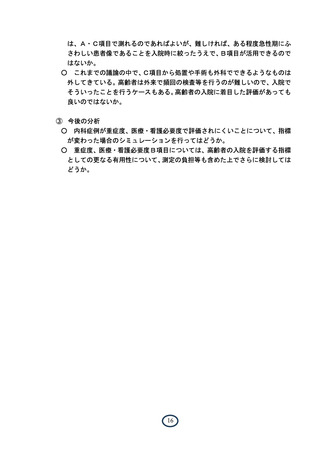よむ、つかう、まなぶ。
入ー2 (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00276.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第6回 7/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ないか。
○ 同じ疾患名、治療行為を行う患者であっても、ADLによって実際の患者像
は非常に多様であり、これを反映しているのがB項目であり、配置等の参考や
アウトカムの評価になりうる指標ではないか。
○ B項目が必要である理由として、重症度、医療・看護必要度は、入院患者の
「重症度、医療・看護必要度を把握し、適正な職員の配置数の実現を目指し、
看護の必要性及び看護の量(療養上の世話)を測る指標」としての位置づけも
あり、施設基準通知への明記されていることが挙げられた。これに係る活用例
として、人員配置、入退院支援、転倒・転落判断等の病棟マネジメント指標と
しての活用が可能であり、回復期の転院可否の予測因子としての活用、転倒リ
スク予測因子としての活用が可能である。(参考:P93~95)
○ SCUではB得点3点以上の割合が多く、これはSCU退室直後の急性期の
病棟においても連続的に評価されるべきではないか。
○ 日々のデータが蓄積されることが日々の評価や分析につながる。国際的にみ
ても、患者像を表すデータなくして患者像の評価はできないのではないか。令
和2年度の診療報酬改定で「できるADL」と「しているADL」が区別され、
より正確な評価となった。患者像が複雑化していくなかで、重症度、医療・看
護必要度A・B・C項目全体で患者像を表現できると考えられ、必要なケアを
評価していくためのリアルワールドデータとしてB項目の有用性があるので
はないか。
(内科系症例におけるA・C項目について)
○ 内科系症例は重症度、医療・看護必要度が付きにくいことは明らか。
○ 内科、外科ではそもそも診療の負担の観点が異なる。内科では診断プロセス
の比重が高く、外科は治療そのものの比重が高い。ただ、診断プロセスの評価
指標として検査を評価すると、検査費用の増加を招きかねない。ステロイドパ
ルスの実施や免疫抑制剤の使用機会も増えており、免疫抑制剤の増点はあり得
るのではないか。
○ 誤嚥性肺炎や尿路感染症が中心となっていると、必要度 II の 15%を達成す
るのが困難であり、高齢者救急を担う地域包括医療病棟の基準を検討すべきで
はないか。
○ 抗菌薬はA項目で一切評価されないので、感染症の患者は重症度、医療・看
護必要度が付きにくい。圧倒的に救急搬送、緊急入院の割合が高いので、この
部分の評価を増やすことで、感染症患者も評価されやすくなるのではないか。
○ 重症度、医療・看護必要度はC項目の比重が高く、地域包括医療病棟にその
まま使うことが適切か。
○ 以前はA得点が低くなっても、B項目の点数で手間を評価できていた。分析
されている通り、内科ではB項目の点数が高くなっており、内科系診療の手間
15
○ 同じ疾患名、治療行為を行う患者であっても、ADLによって実際の患者像
は非常に多様であり、これを反映しているのがB項目であり、配置等の参考や
アウトカムの評価になりうる指標ではないか。
○ B項目が必要である理由として、重症度、医療・看護必要度は、入院患者の
「重症度、医療・看護必要度を把握し、適正な職員の配置数の実現を目指し、
看護の必要性及び看護の量(療養上の世話)を測る指標」としての位置づけも
あり、施設基準通知への明記されていることが挙げられた。これに係る活用例
として、人員配置、入退院支援、転倒・転落判断等の病棟マネジメント指標と
しての活用が可能であり、回復期の転院可否の予測因子としての活用、転倒リ
スク予測因子としての活用が可能である。(参考:P93~95)
○ SCUではB得点3点以上の割合が多く、これはSCU退室直後の急性期の
病棟においても連続的に評価されるべきではないか。
○ 日々のデータが蓄積されることが日々の評価や分析につながる。国際的にみ
ても、患者像を表すデータなくして患者像の評価はできないのではないか。令
和2年度の診療報酬改定で「できるADL」と「しているADL」が区別され、
より正確な評価となった。患者像が複雑化していくなかで、重症度、医療・看
護必要度A・B・C項目全体で患者像を表現できると考えられ、必要なケアを
評価していくためのリアルワールドデータとしてB項目の有用性があるので
はないか。
(内科系症例におけるA・C項目について)
○ 内科系症例は重症度、医療・看護必要度が付きにくいことは明らか。
○ 内科、外科ではそもそも診療の負担の観点が異なる。内科では診断プロセス
の比重が高く、外科は治療そのものの比重が高い。ただ、診断プロセスの評価
指標として検査を評価すると、検査費用の増加を招きかねない。ステロイドパ
ルスの実施や免疫抑制剤の使用機会も増えており、免疫抑制剤の増点はあり得
るのではないか。
○ 誤嚥性肺炎や尿路感染症が中心となっていると、必要度 II の 15%を達成す
るのが困難であり、高齢者救急を担う地域包括医療病棟の基準を検討すべきで
はないか。
○ 抗菌薬はA項目で一切評価されないので、感染症の患者は重症度、医療・看
護必要度が付きにくい。圧倒的に救急搬送、緊急入院の割合が高いので、この
部分の評価を増やすことで、感染症患者も評価されやすくなるのではないか。
○ 重症度、医療・看護必要度はC項目の比重が高く、地域包括医療病棟にその
まま使うことが適切か。
○ 以前はA得点が低くなっても、B項目の点数で手間を評価できていた。分析
されている通り、内科ではB項目の点数が高くなっており、内科系診療の手間
15