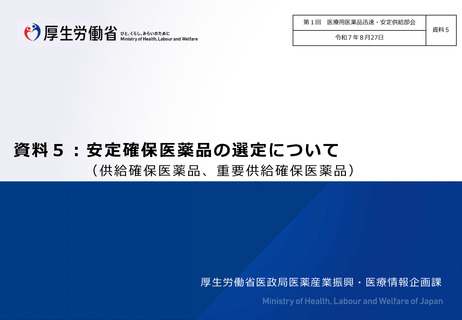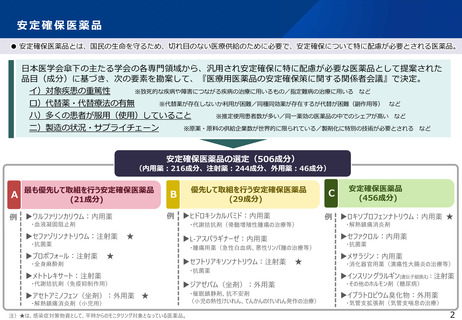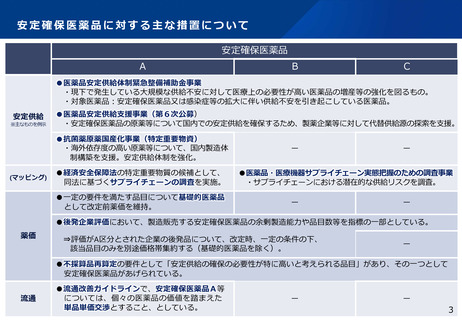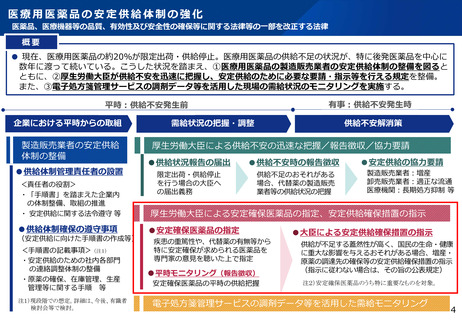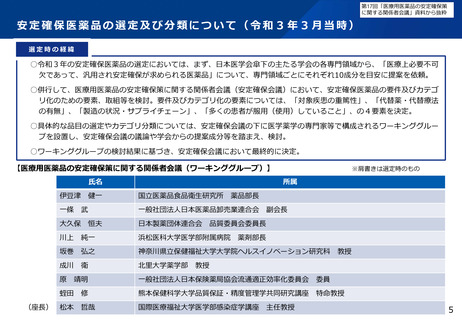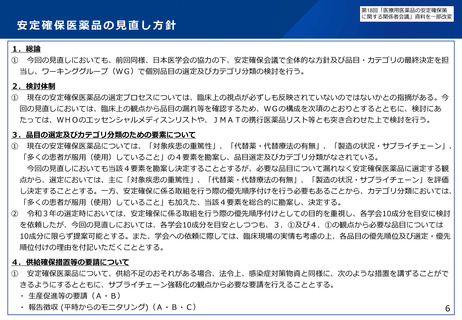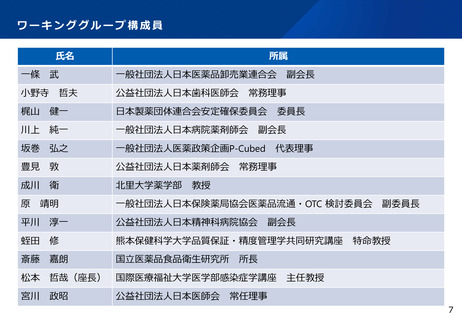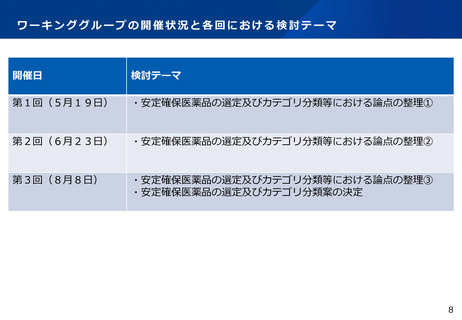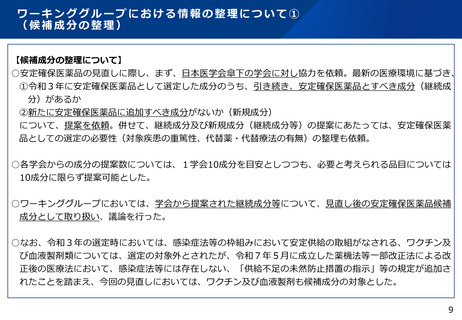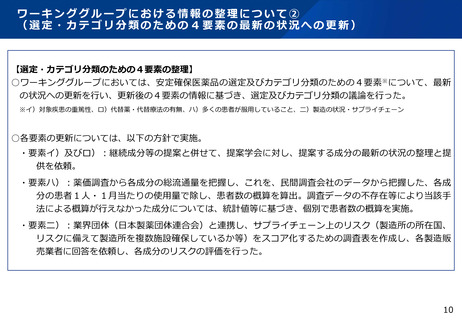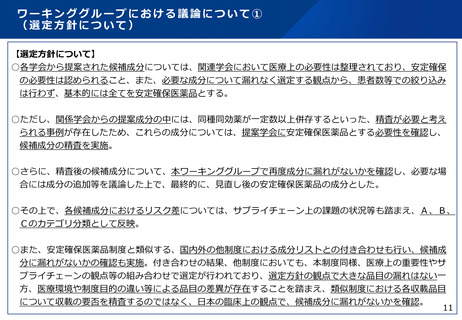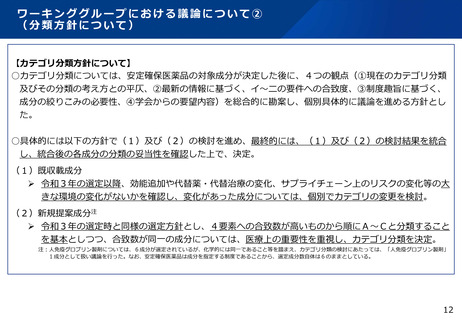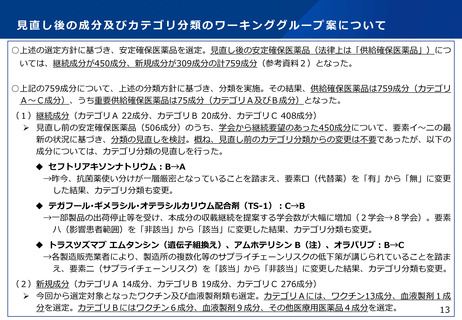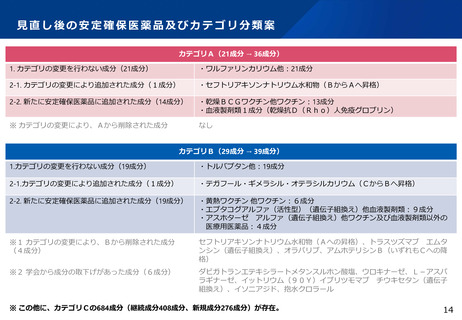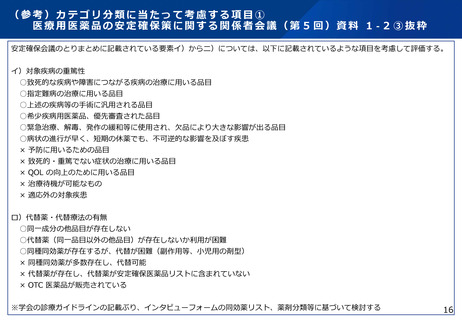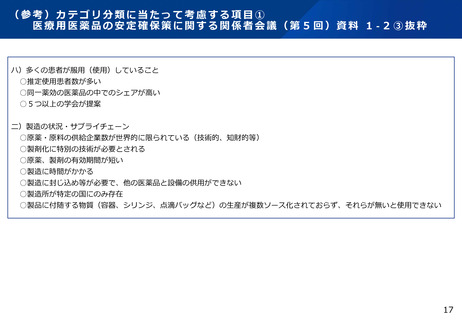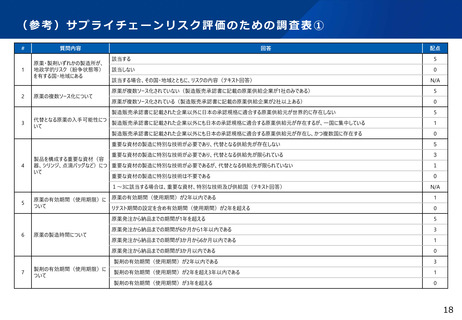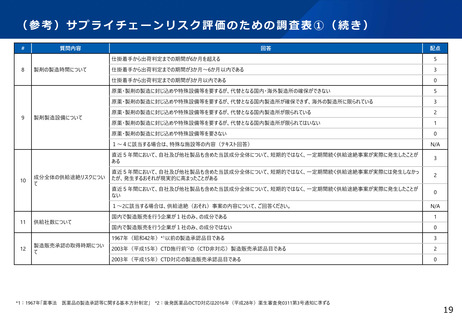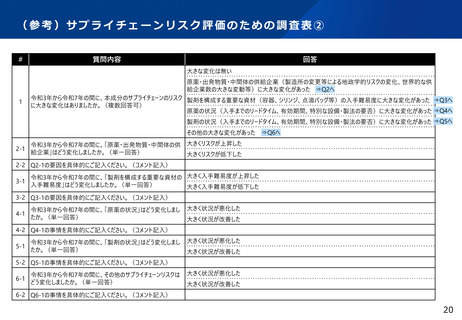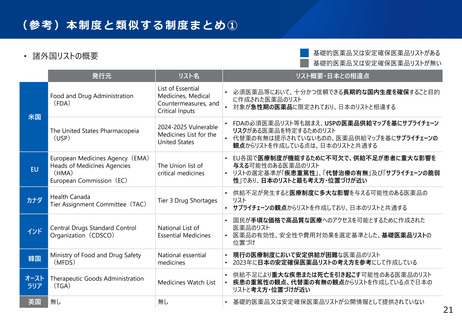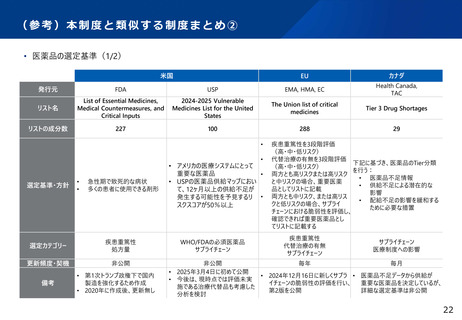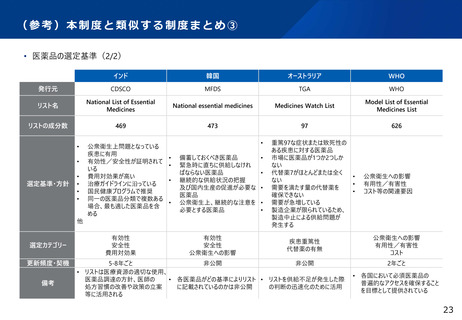よむ、つかう、まなぶ。
資料5 安定確保医薬品の選定について (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ワーキンググループにおける議論について②
(分類方針について)
【カテゴリ分類方針について】
○カテゴリ分類については、安定確保医薬品の対象成分が決定した後に、4つの観点(①現在のカテゴリ分類
及びその分類の考え方との平仄、②最新の情報に基づく、イ~ニの要件への合致度、③制度趣旨に基づく、
成分の絞りこみの必要性、④学会からの要望内容)を総合的に勘案し、個別具体的に議論を進める方針とし
た。
○具体的には以下の方針で(1)及び(2)の検討を進め、最終的には、(1)及び(2)の検討結果を統合
し、統合後の各成分の分類の妥当性を確認した上で、決定。
(1)既収載成分
令和3年の選定以降、効能追加や代替薬・代替治療の変化、サプライチェーン上のリスクの変化等の大
きな環境の変化がないかを確認し、変化があった成分については、個別でカテゴリの変更を検討。
(2)新規提案成分注
令和3年の選定時と同様の選定方針とし、4要素への合致数が高いものから順にA~Cと分類すること
を基本としつつ、合致数が同一の成分については、医療上の重要性を重視し、カテゴリ分類を決定。
注:人免疫グロブリン製剤については、6成分が選定されているが、化学的には同一であること等を踏まえ、カテゴリ分類の検討にあたっては、「人免疫グロブリン製剤」
1成分として扱い議論を行った。なお、安定確保医薬品は成分を指定する制度であることから、選定成分数自体は6のままとしている。
12
(分類方針について)
【カテゴリ分類方針について】
○カテゴリ分類については、安定確保医薬品の対象成分が決定した後に、4つの観点(①現在のカテゴリ分類
及びその分類の考え方との平仄、②最新の情報に基づく、イ~ニの要件への合致度、③制度趣旨に基づく、
成分の絞りこみの必要性、④学会からの要望内容)を総合的に勘案し、個別具体的に議論を進める方針とし
た。
○具体的には以下の方針で(1)及び(2)の検討を進め、最終的には、(1)及び(2)の検討結果を統合
し、統合後の各成分の分類の妥当性を確認した上で、決定。
(1)既収載成分
令和3年の選定以降、効能追加や代替薬・代替治療の変化、サプライチェーン上のリスクの変化等の大
きな環境の変化がないかを確認し、変化があった成分については、個別でカテゴリの変更を検討。
(2)新規提案成分注
令和3年の選定時と同様の選定方針とし、4要素への合致数が高いものから順にA~Cと分類すること
を基本としつつ、合致数が同一の成分については、医療上の重要性を重視し、カテゴリ分類を決定。
注:人免疫グロブリン製剤については、6成分が選定されているが、化学的には同一であること等を踏まえ、カテゴリ分類の検討にあたっては、「人免疫グロブリン製剤」
1成分として扱い議論を行った。なお、安定確保医薬品は成分を指定する制度であることから、選定成分数自体は6のままとしている。
12