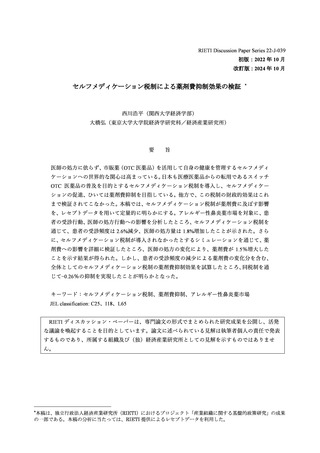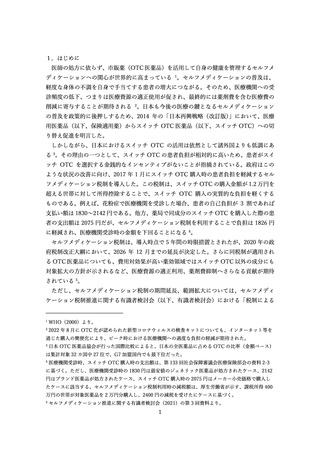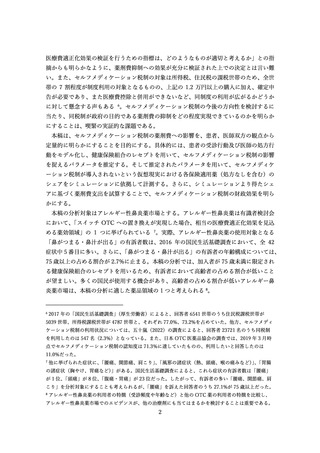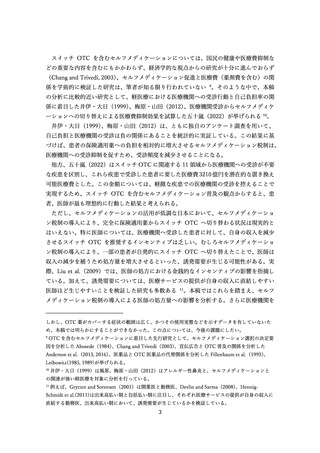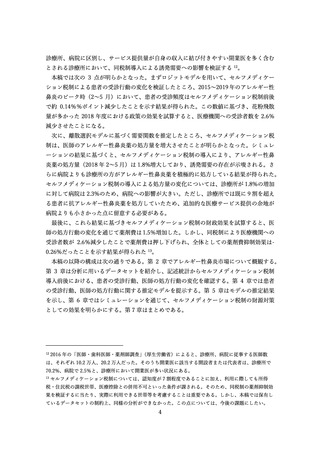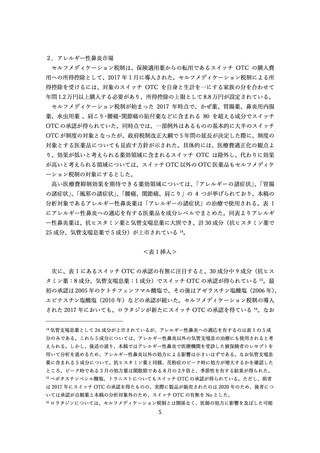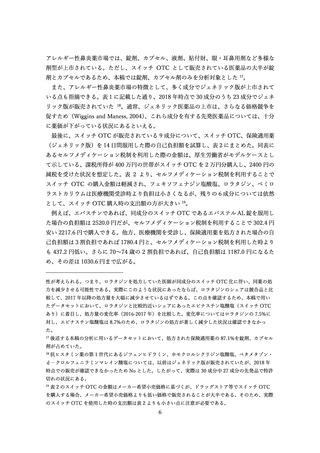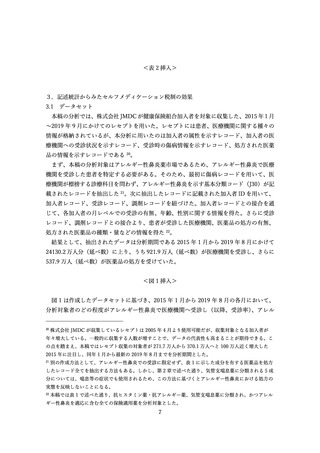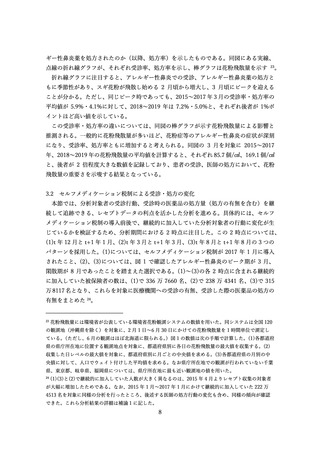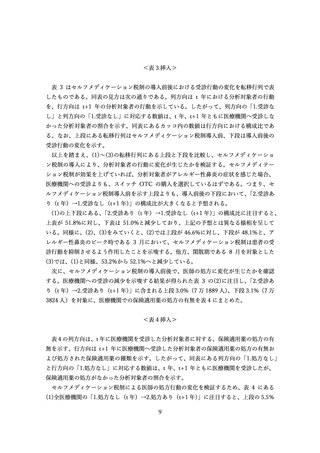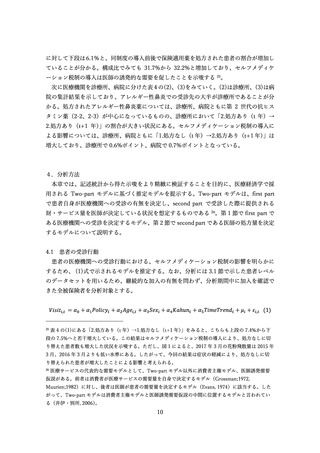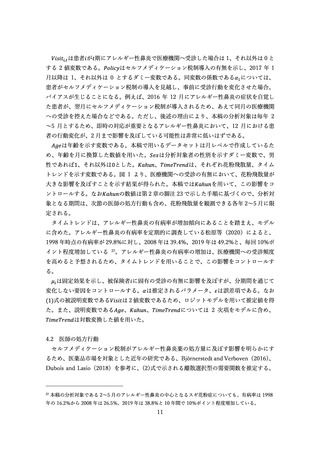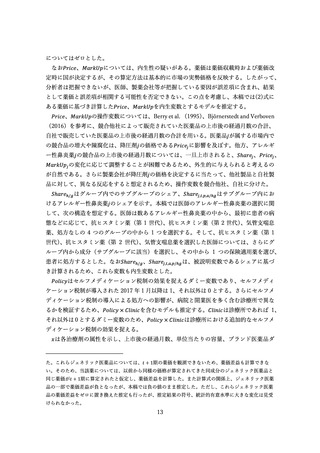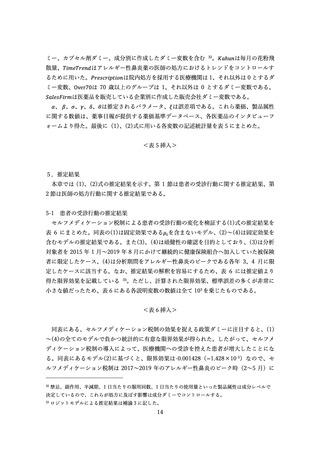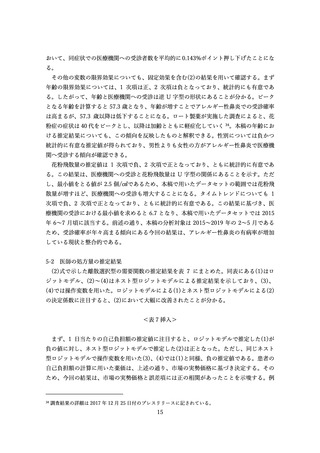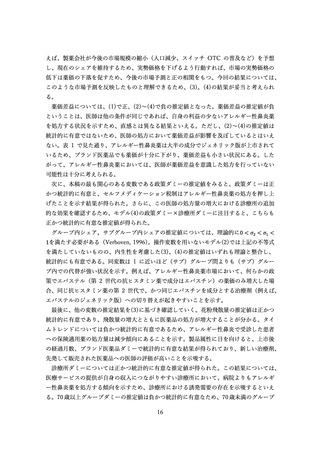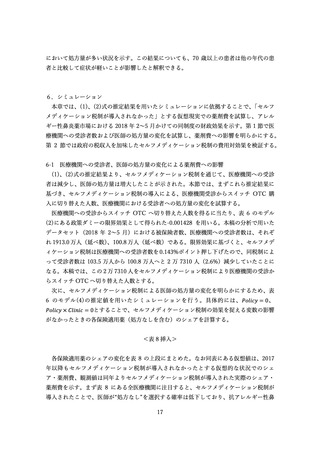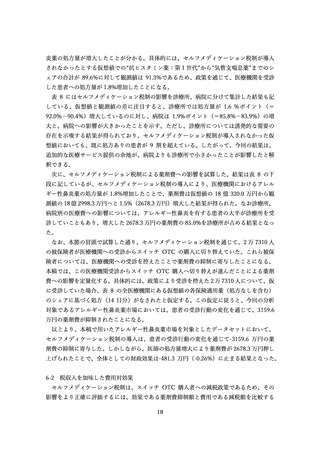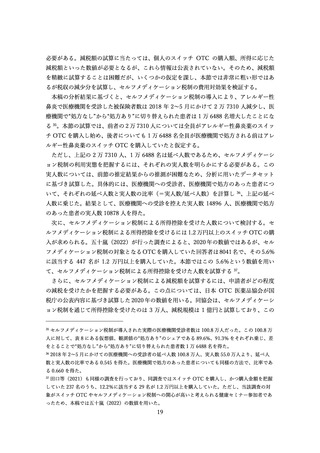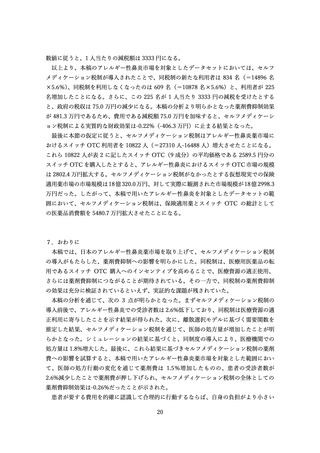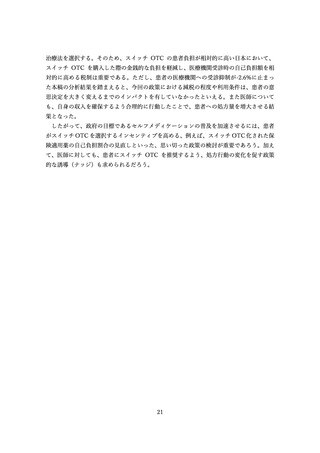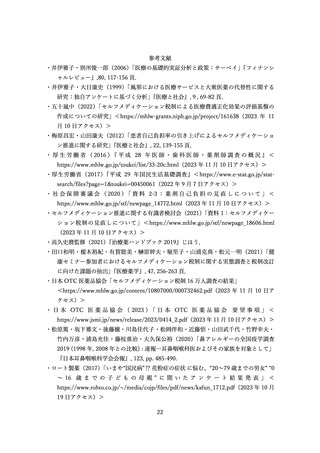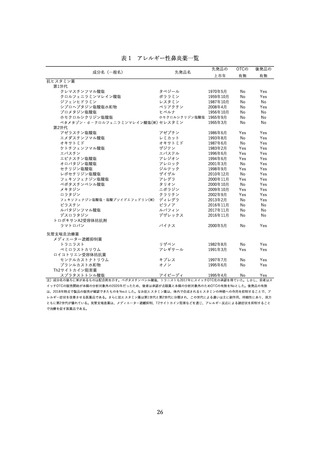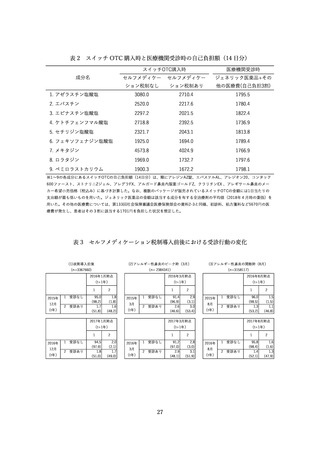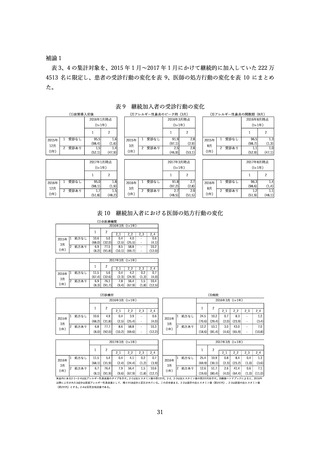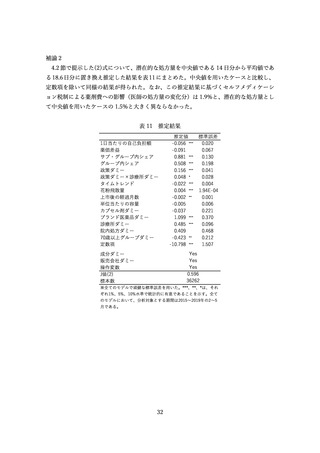よむ、つかう、まなぶ。
参考資料4.セルフメディケーション税制による 薬剤費抑制効果の検証(西川・大橋 RIETI Discussion Paper Series 22-J-039(2022)(独)経済産業研究所) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59938.html |
| 出典情報 | セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会(第4回 7/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
スイッチ OTC を含むセルフメディケーションについては、国民の健康や医療費抑制な
どの重要な内容を含むにもかかわらず、経済学的な視点からの研究が十分に進んでおらず
(Chang and Trivedi, 2003)
、セルフメディケーション促進と医療費(薬剤費を含む)の関
係を学術的に検証した研究は、筆者が知る限り行われていない 9。そのような中で、本稿
の分析に比較的近い研究として、軽医療における医療機関への受診行動と自己負担率の関
係に着目した井伊・大日(1999)、梅原・山田(2012)、医療機関受診からセルフメディケ
ーションへの切り替えによる医療費抑制効果を試算した五十嵐(2022)が挙げられる 10。
井伊・大日(1999)、梅原・山田(2012)は、ともに独自のアンケート調査を用いて、
自己負担と医療機関の受診は負の関係にあることを統計的に実証している。この結果に基
づけば、患者の保険適用薬への負担を相対的に増大させるセルフメディケーション税制は、
医療機関への受診抑制を促すため、受診頻度を減少させることになる。
他方、五十嵐(2022)はスイッチ OTC に関連する 11 領域から医療機関への受診が不要
な疾患を区別し、これら疾患で受診した患者に要した医療費 3210 億円を潜在的な置き換え
可能医療費とした。この金額については、軽微な疾患での医療機関の受診を控えることで
実現するため、スイッチ OTC を含むセルフメディケーション普及の観点からすると、患
者、医師が最も理想的に行動した結果と考えられる。
ただし、セルフメディケーションの活用が低調な日本において、セルフメディケーショ
ン税制の導入により、完全に保険適用薬からスイッチ OTC へ切り替わる状況は現実的と
はいえない。特に医師については、医療機関へ受診した患者に対して、自身の収入を減少
させるスイッチ OTC を推奨するインセンティブは乏しい。むしろセルフメディケーショ
ン税制の導入により、一部の患者が自発的にスイッチ OTC へ切り替えたことで、医師は
収入の減少を補うため処方量を増大させるといった、誘発需要が生じる可能性がある。実
際、Liu et al.(2009)では、医師の処方における金銭的なインセンティブの影響を指摘し
ている。加えて、誘発需要については、医療サービスの提供が自身の収入に直結しやすい
医師ほど生じやすいことを検証した研究も多数ある 11。本稿ではこれらを踏まえ、セルフ
メディケーション税制の導入による医師の処方量への影響を分析する。さらに医療機関を
しかし、OTC 薬がカバーする症状の範囲は広く、かつその使用実態などを示すデータを有していないた
め、本稿では明らかにすることができなかった。この点については、今後の課題にしたい。
9
OTC を含むセルフメディケーションに着目した先行研究として、セルフメディケーション選択の決定要
因を分析した Abosede(1984)
、Chang and Trivedi(2003)
、宣伝広告と OTC 普及の関係を分析した
Anderson et al.(2013, 2016)
、医薬品と OTC 医薬品の代替関係を分析した Fillenbaum et al.(1993)
、
Leibowitz(1985, 1989)が挙げられる。
10
井伊・大日(1999)は風邪、梅原・山田(2012)はアレルギー性鼻炎と、セルフメディケーションと
の関連が強い軽医療を対象に分析を行っている。
11
例えば、Grytten and Sorensen(2001)は開業医と勤務医、Devlin and Sarma(2008)
、Hennig-
Schmidt et al.(2011)は出来高払い制と包括払い制に注目し、それぞれ医療サービスの提供が自身の収入に
直結する勤務医、出来高払い制において、誘発需要が生じているかを検証している。
3
どの重要な内容を含むにもかかわらず、経済学的な視点からの研究が十分に進んでおらず
(Chang and Trivedi, 2003)
、セルフメディケーション促進と医療費(薬剤費を含む)の関
係を学術的に検証した研究は、筆者が知る限り行われていない 9。そのような中で、本稿
の分析に比較的近い研究として、軽医療における医療機関への受診行動と自己負担率の関
係に着目した井伊・大日(1999)、梅原・山田(2012)、医療機関受診からセルフメディケ
ーションへの切り替えによる医療費抑制効果を試算した五十嵐(2022)が挙げられる 10。
井伊・大日(1999)、梅原・山田(2012)は、ともに独自のアンケート調査を用いて、
自己負担と医療機関の受診は負の関係にあることを統計的に実証している。この結果に基
づけば、患者の保険適用薬への負担を相対的に増大させるセルフメディケーション税制は、
医療機関への受診抑制を促すため、受診頻度を減少させることになる。
他方、五十嵐(2022)はスイッチ OTC に関連する 11 領域から医療機関への受診が不要
な疾患を区別し、これら疾患で受診した患者に要した医療費 3210 億円を潜在的な置き換え
可能医療費とした。この金額については、軽微な疾患での医療機関の受診を控えることで
実現するため、スイッチ OTC を含むセルフメディケーション普及の観点からすると、患
者、医師が最も理想的に行動した結果と考えられる。
ただし、セルフメディケーションの活用が低調な日本において、セルフメディケーショ
ン税制の導入により、完全に保険適用薬からスイッチ OTC へ切り替わる状況は現実的と
はいえない。特に医師については、医療機関へ受診した患者に対して、自身の収入を減少
させるスイッチ OTC を推奨するインセンティブは乏しい。むしろセルフメディケーショ
ン税制の導入により、一部の患者が自発的にスイッチ OTC へ切り替えたことで、医師は
収入の減少を補うため処方量を増大させるといった、誘発需要が生じる可能性がある。実
際、Liu et al.(2009)では、医師の処方における金銭的なインセンティブの影響を指摘し
ている。加えて、誘発需要については、医療サービスの提供が自身の収入に直結しやすい
医師ほど生じやすいことを検証した研究も多数ある 11。本稿ではこれらを踏まえ、セルフ
メディケーション税制の導入による医師の処方量への影響を分析する。さらに医療機関を
しかし、OTC 薬がカバーする症状の範囲は広く、かつその使用実態などを示すデータを有していないた
め、本稿では明らかにすることができなかった。この点については、今後の課題にしたい。
9
OTC を含むセルフメディケーションに着目した先行研究として、セルフメディケーション選択の決定要
因を分析した Abosede(1984)
、Chang and Trivedi(2003)
、宣伝広告と OTC 普及の関係を分析した
Anderson et al.(2013, 2016)
、医薬品と OTC 医薬品の代替関係を分析した Fillenbaum et al.(1993)
、
Leibowitz(1985, 1989)が挙げられる。
10
井伊・大日(1999)は風邪、梅原・山田(2012)はアレルギー性鼻炎と、セルフメディケーションと
の関連が強い軽医療を対象に分析を行っている。
11
例えば、Grytten and Sorensen(2001)は開業医と勤務医、Devlin and Sarma(2008)
、Hennig-
Schmidt et al.(2011)は出来高払い制と包括払い制に注目し、それぞれ医療サービスの提供が自身の収入に
直結する勤務医、出来高払い制において、誘発需要が生じているかを検証している。
3