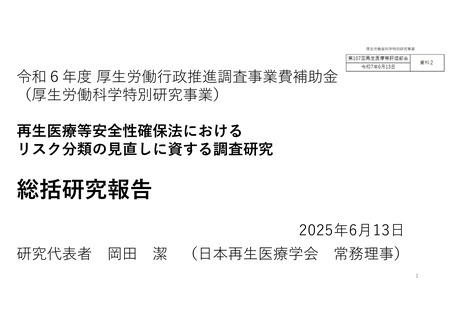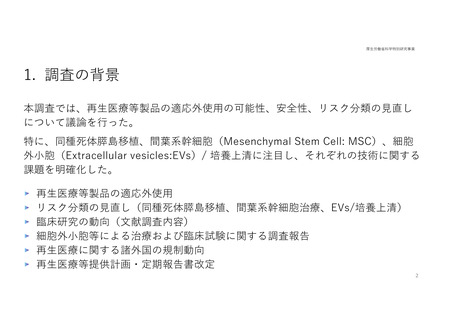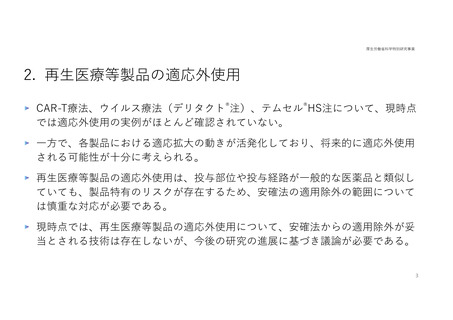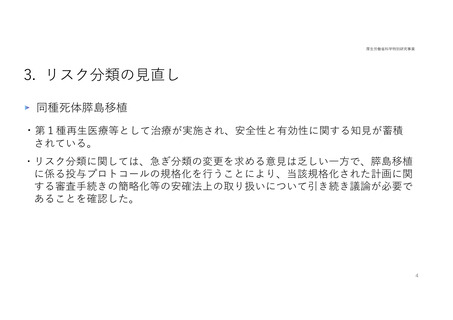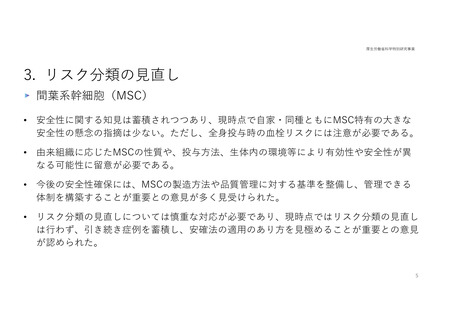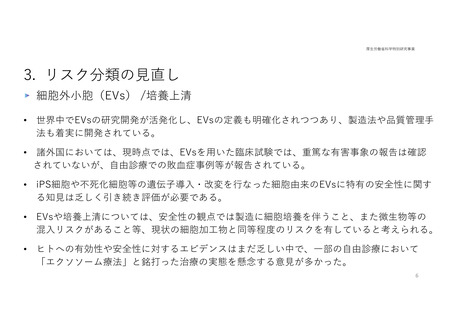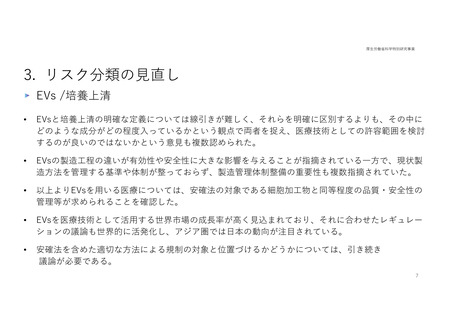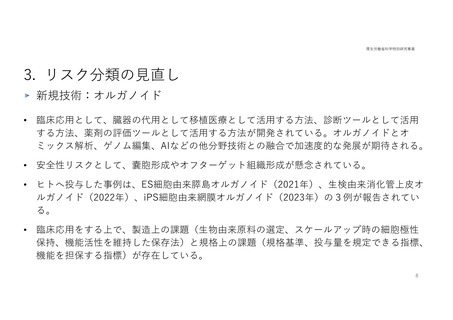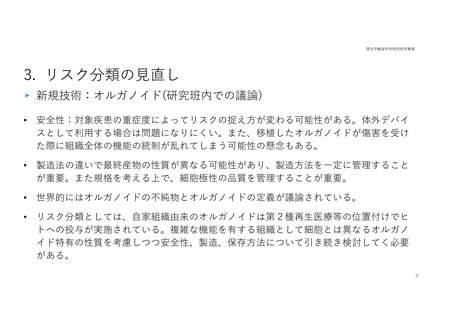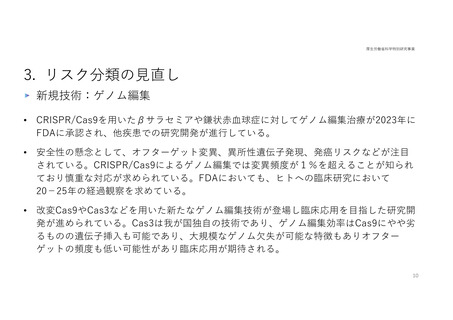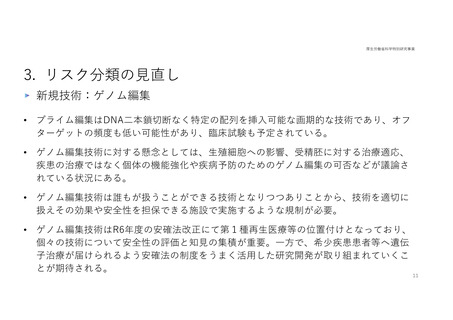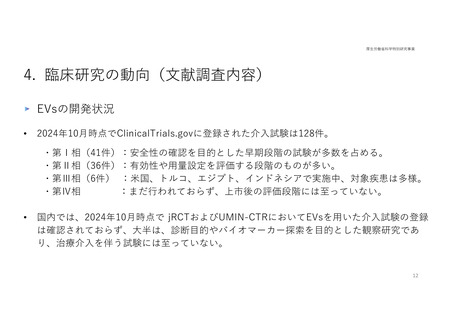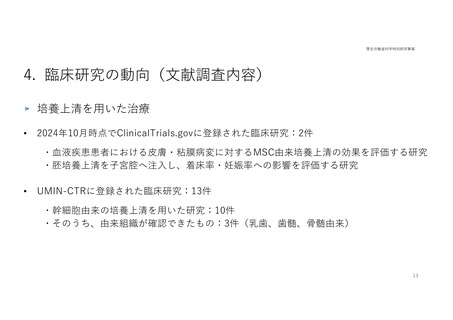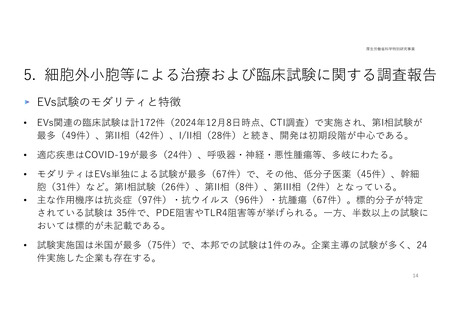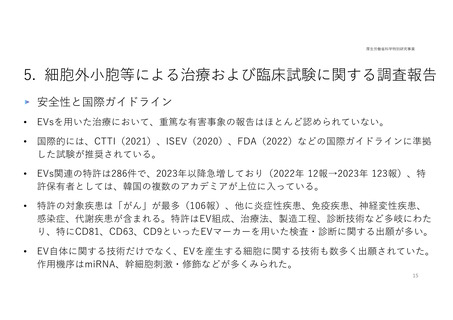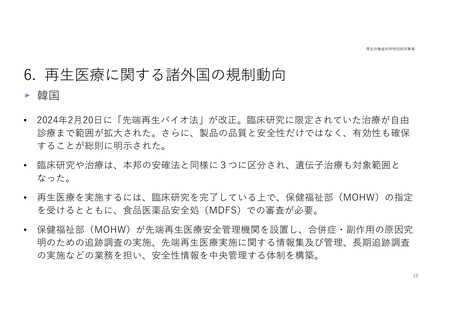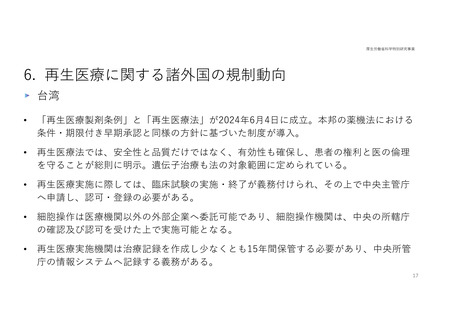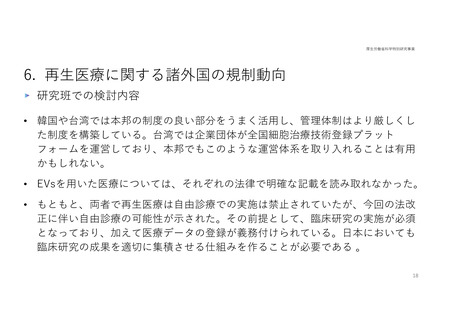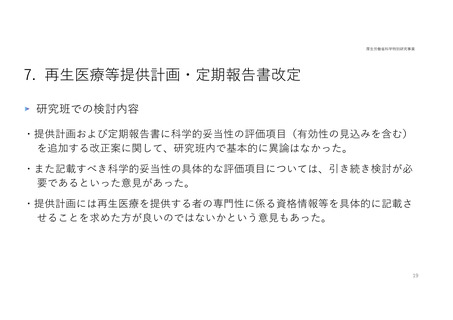よむ、つかう、まなぶ。
令和6年度 厚生労働科学特別研究事業 再生医療等安全性確保法におけるリスク分類の見直しに資する調査研究 総括研究報告書[404KB] (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
厚生労働省科学特別研究事業
3. リスク分類の見直し
新規技術:ゲノム編集
• CRISPR/Cas9を用いたβサラセミアや鎌状赤血球症に対してゲノム編集治療が2023年に
FDAに承認され、他疾患での研究開発が進行している。
• 安全性の懸念として、オフターゲット変異、異所性遺伝子発現、発癌リスクなどが注目
されている。CRISPR/Cas9によるゲノム編集では変異頻度が1%を超えることが知られ
ており慎重な対応が求められている。FDAにおいても、ヒトへの臨床研究において
20-25年の経過観察を求めている。
• 改変Cas9やCas3などを用いた新たなゲノム編集技術が登場し臨床応用を目指した研究開
発が進められている。Cas3は我が国独自の技術であり、ゲノム編集効率はCas9にやや劣
るものの遺伝子挿入も可能であり、大規模なゲノム欠失が可能な特徴もありオフター
ゲットの頻度も低い可能性があり臨床応用が期待される。
10
3. リスク分類の見直し
新規技術:ゲノム編集
• CRISPR/Cas9を用いたβサラセミアや鎌状赤血球症に対してゲノム編集治療が2023年に
FDAに承認され、他疾患での研究開発が進行している。
• 安全性の懸念として、オフターゲット変異、異所性遺伝子発現、発癌リスクなどが注目
されている。CRISPR/Cas9によるゲノム編集では変異頻度が1%を超えることが知られ
ており慎重な対応が求められている。FDAにおいても、ヒトへの臨床研究において
20-25年の経過観察を求めている。
• 改変Cas9やCas3などを用いた新たなゲノム編集技術が登場し臨床応用を目指した研究開
発が進められている。Cas3は我が国独自の技術であり、ゲノム編集効率はCas9にやや劣
るものの遺伝子挿入も可能であり、大規模なゲノム欠失が可能な特徴もありオフター
ゲットの頻度も低い可能性があり臨床応用が期待される。
10