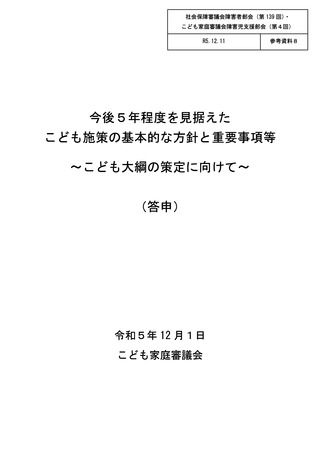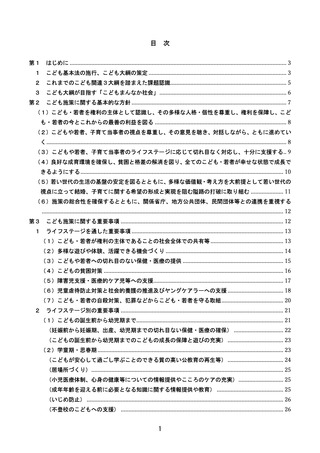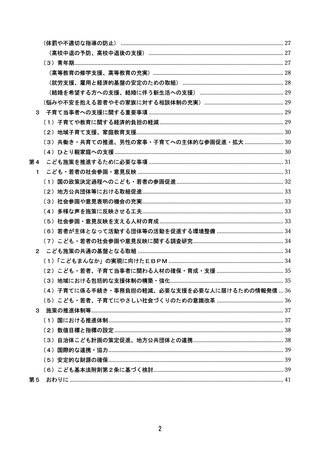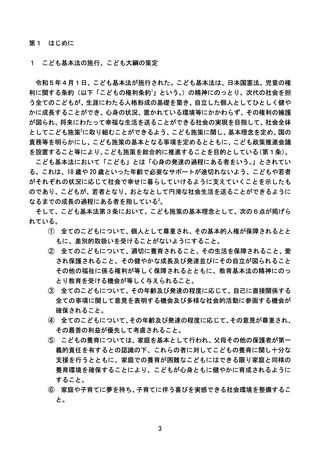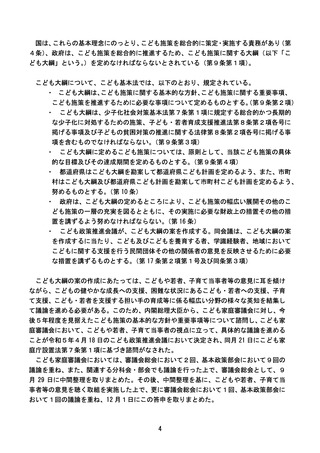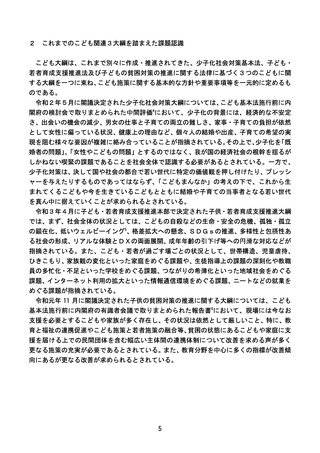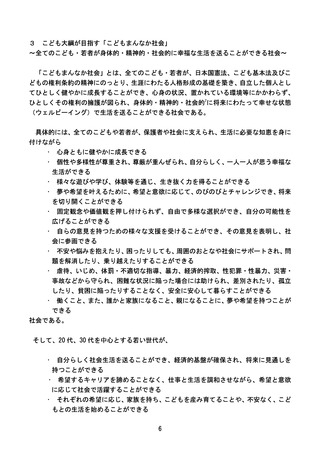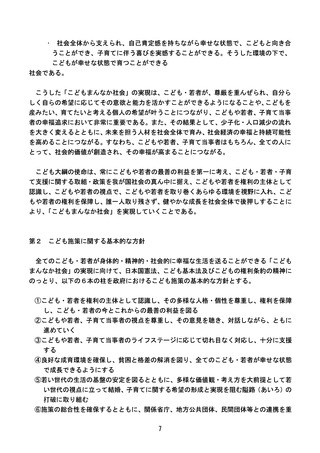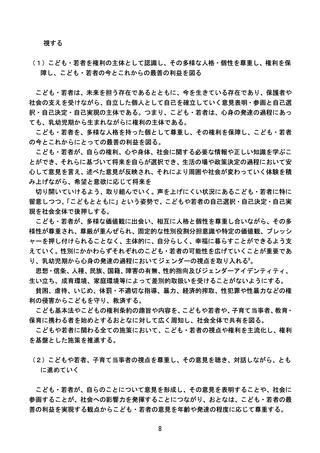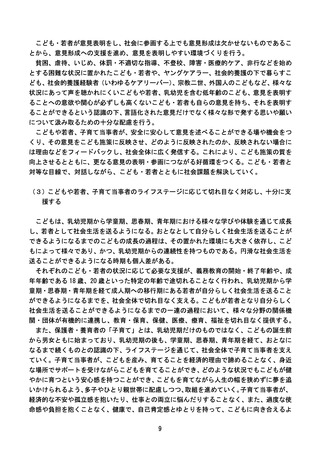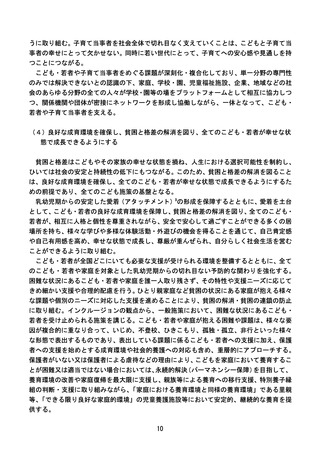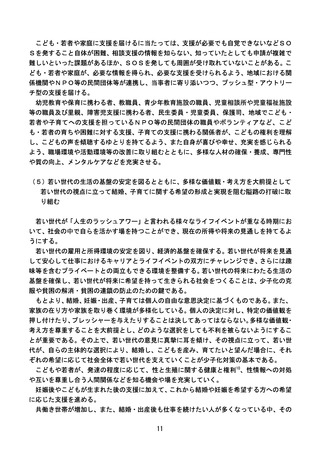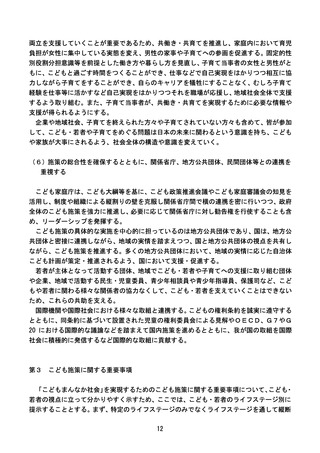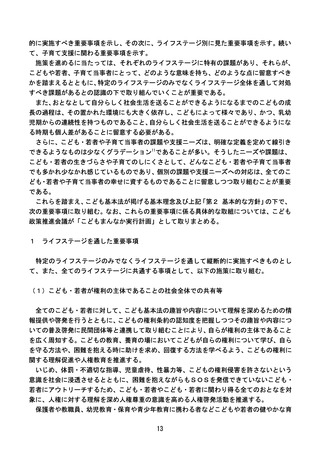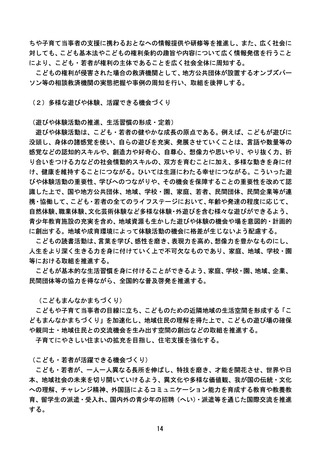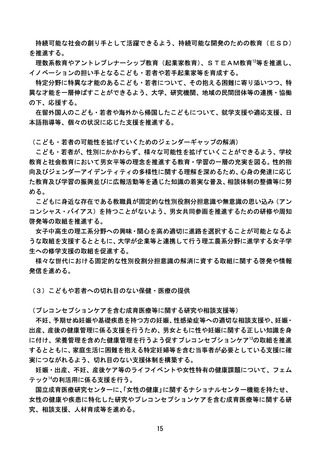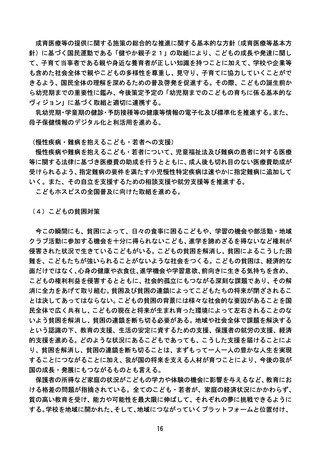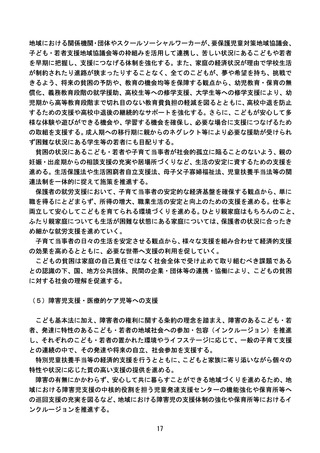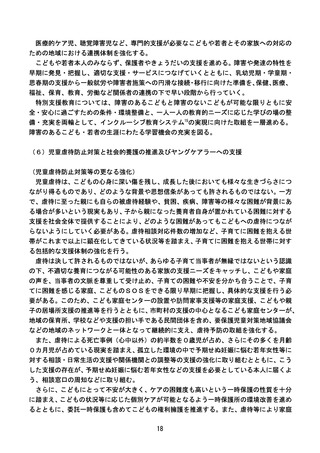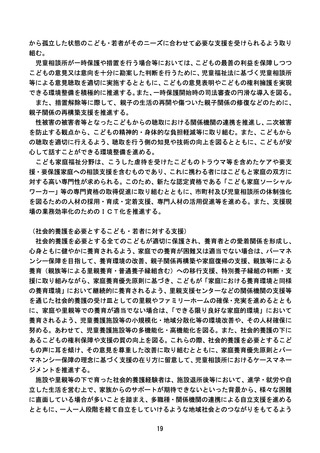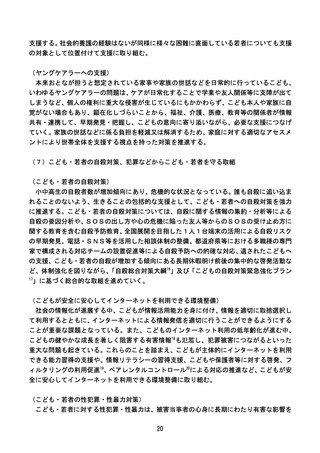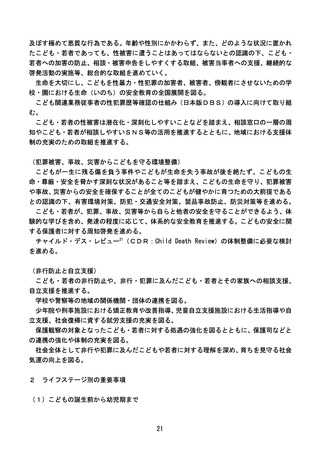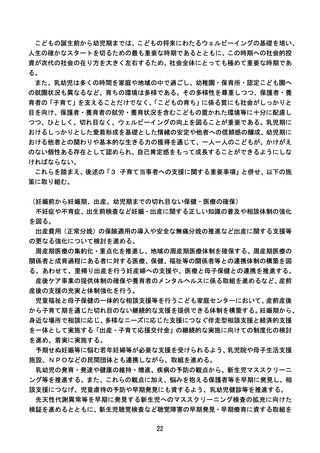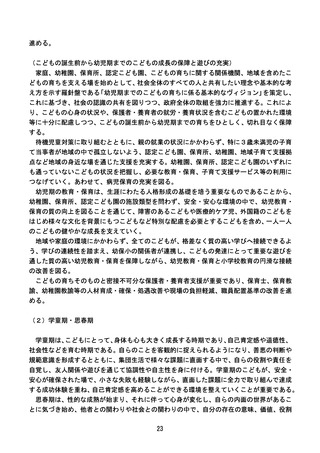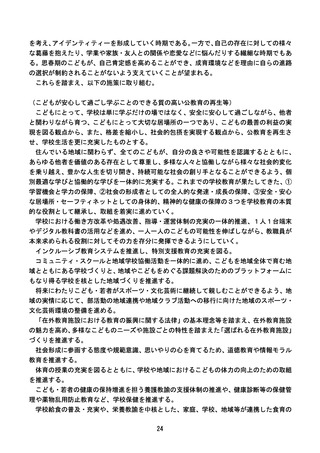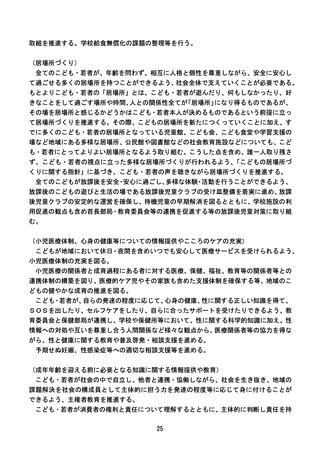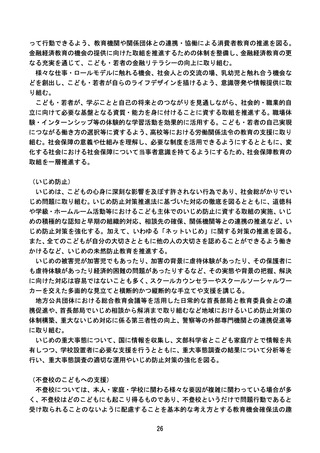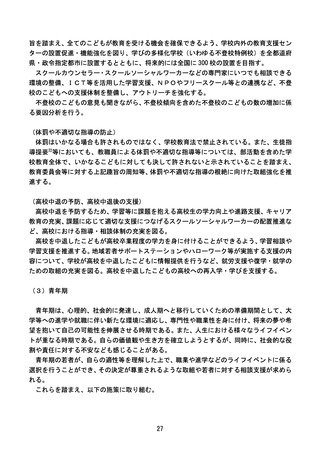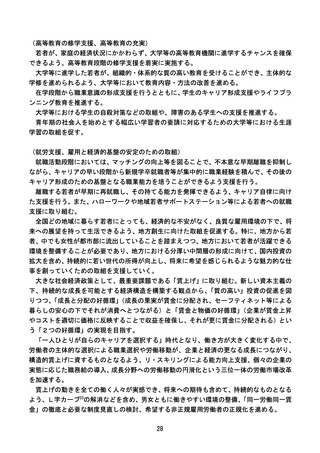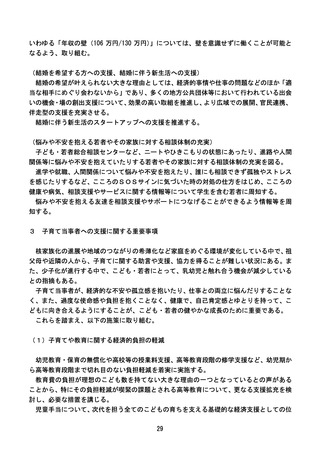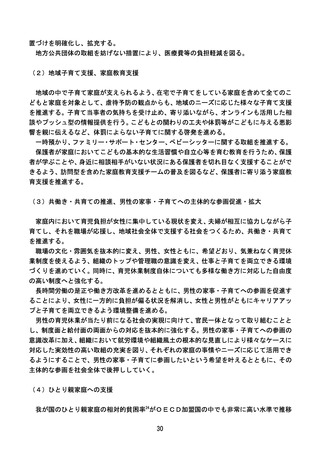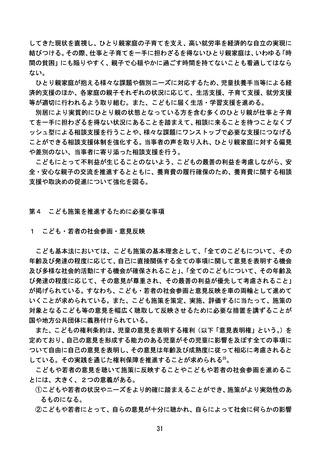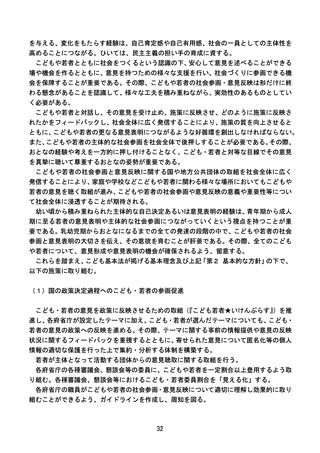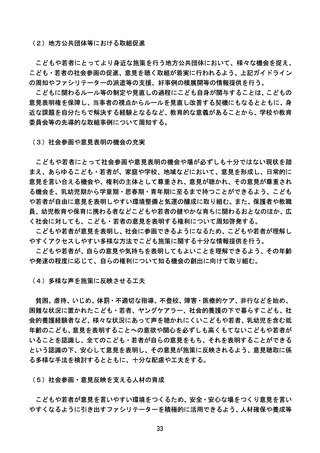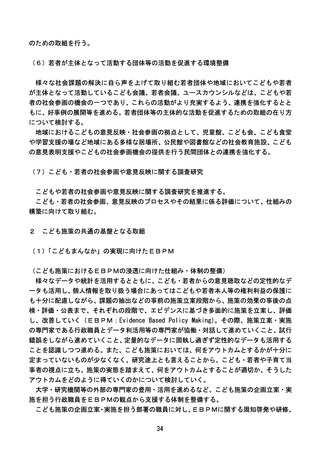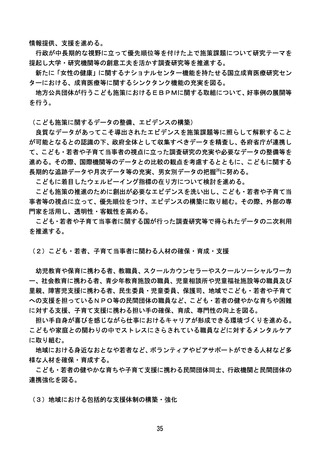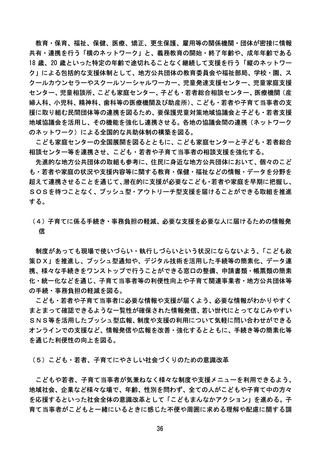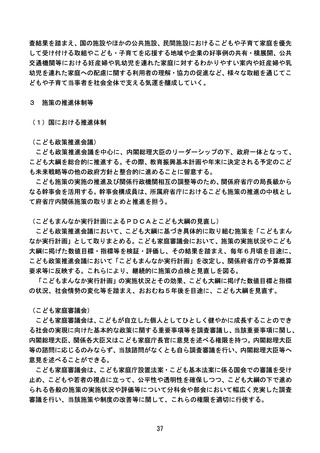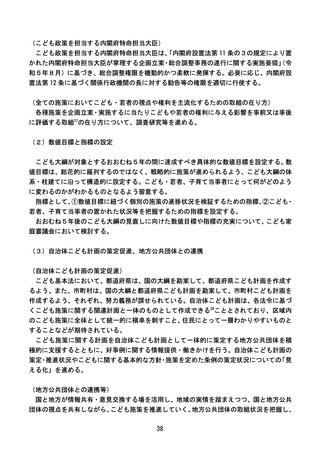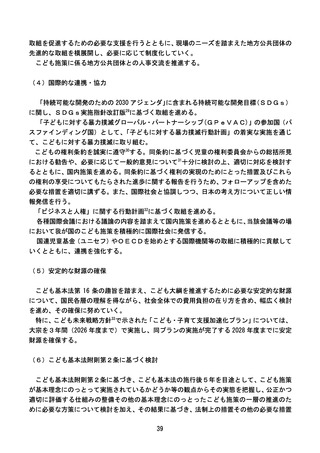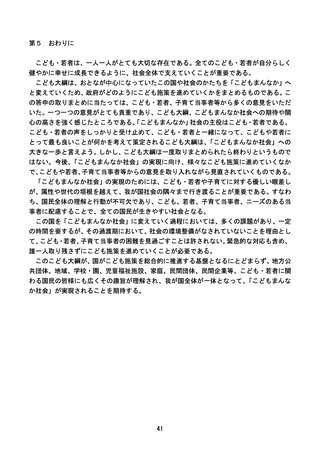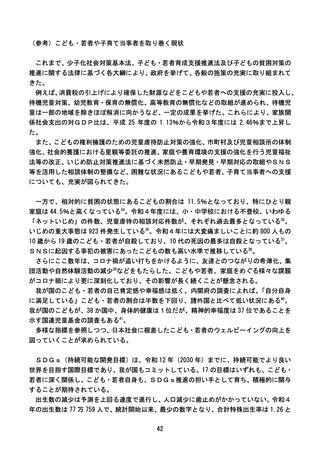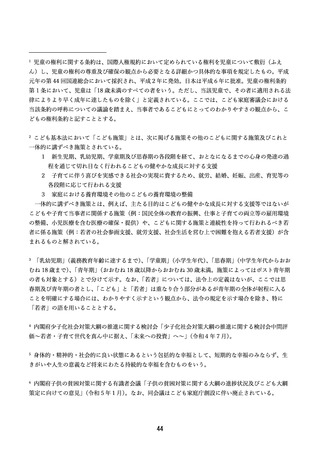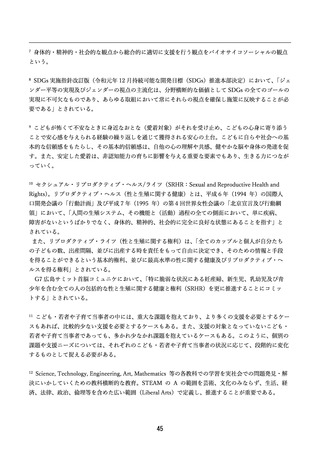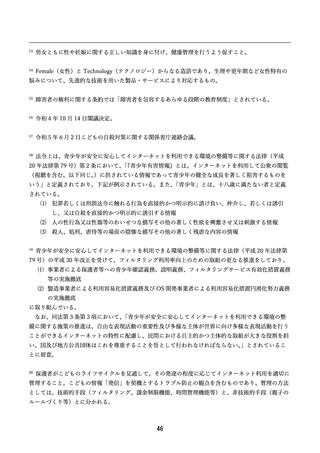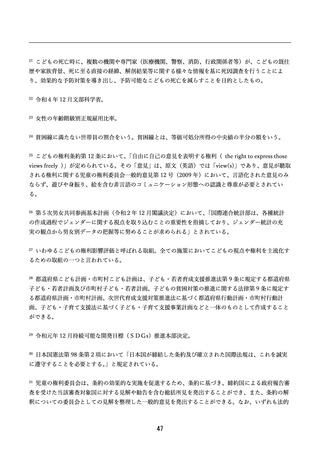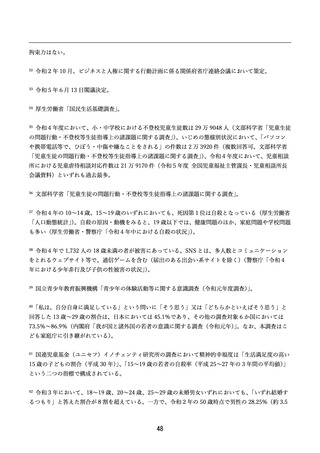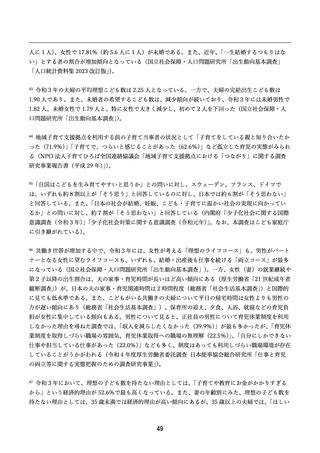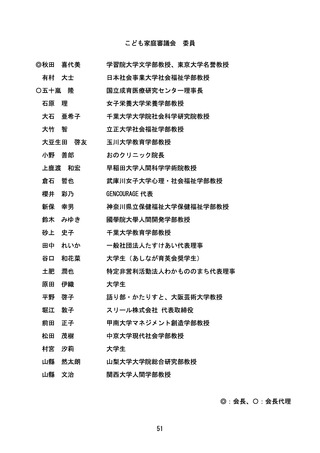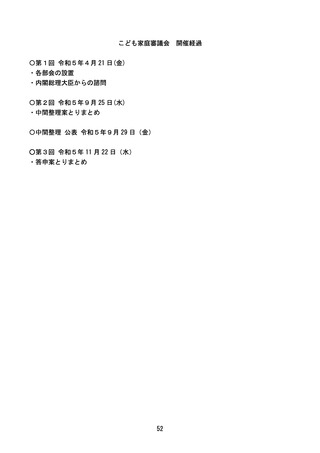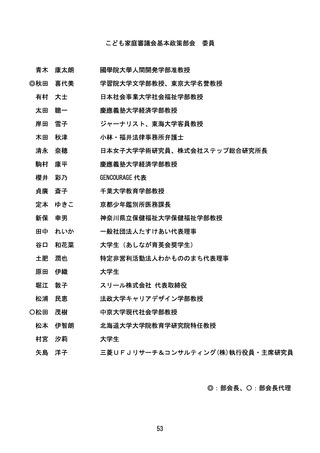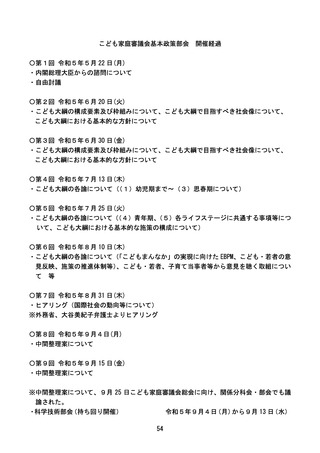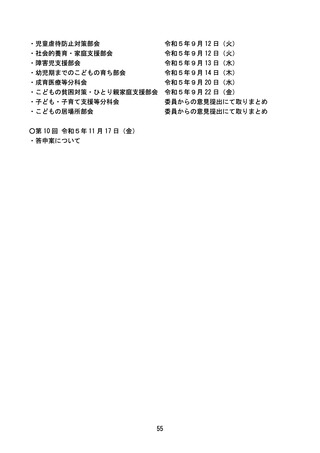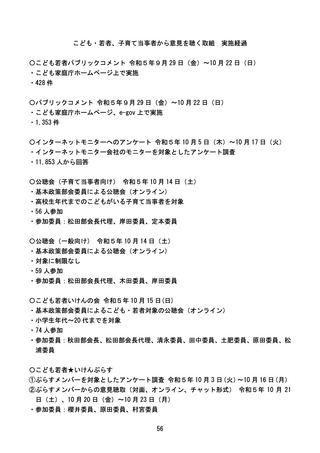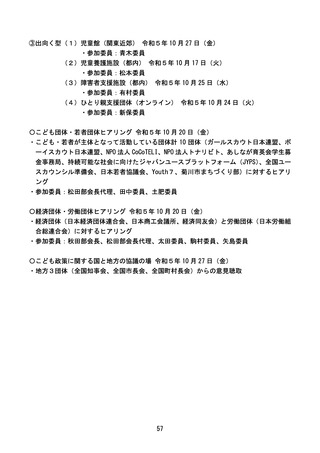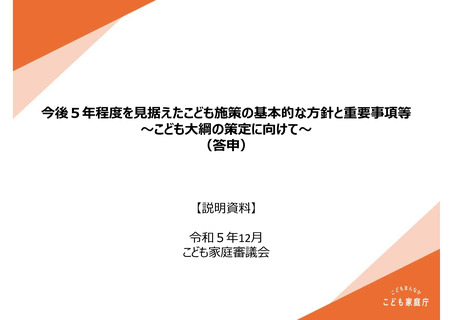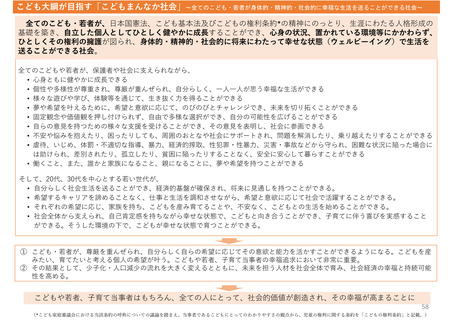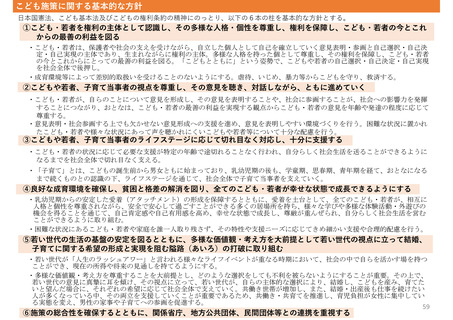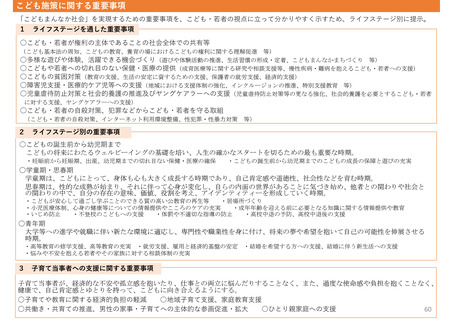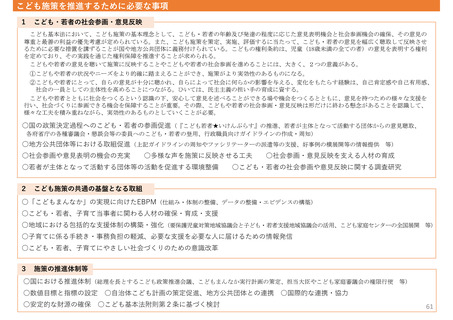よむ、つかう、まなぶ。
参考資料8 今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~(答申)[1.3MB] (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
身体的・精神的・社会的な観点から総合的に適切に支援を行う観点をバイオサイコソーシャルの観点
7
という。
SDGs 実施指針改訂版(令和元年 12 月持続可能な開発目標(SDGs)推進本部決定)において、
「ジェ
8
ンダー平等の実現及びジェンダーの視点の主流化は、分野横断的な価値として SDGs の全てのゴールの
実現に不可欠なものであり、あらゆる取組において常にそれらの視点を確保し施策に反映することが必
要である」とされている。
こどもが怖くて不安なときに身近なおとな(愛着対象)がそれを受け止め、こどもの心身に寄り添う
9
ことで安心感を与えられる経験の繰り返しを通じて獲得される安心の土台。こどもに自らや社会への基
本的な信頼感をもたらし、その基本的信頼感は、自他の心の理解や共感、健やかな脳や身体の発達を促
す。また、安定した愛着は、非認知能力の育ちに影響を与える重要な要素でもあり、生きる力につなが
っていく。
10
セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(SRHR:Sexual and Reproductive Health and
Rights)
。リプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関する健康)とは、平成6年(1994 年)の国際人
口開発会議の「行動計画」及び平成7年(1995 年)の第4回世界女性会議の「北京宣言及び行動綱
領」において、
「人間の生殖システム、その機能と(活動)過程の全ての側面において、単に疾病、
障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」と
されている。
また、リプロダクティブ・ライツ(性と生殖に関する権利)は、
「全てのカップルと個人が自分たち
の子どもの数、出産間隔、並びに出産する時を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手段
を得ることができるという基本的権利、並びに最高水準の性に関する健康及びリプロダクティブ・ヘ
ルスを得る権利」とされている。
G7 広島サミット首脳コミュニケにおいて、「特に脆弱な状況にある妊産婦、新生児、乳幼児及び青
少年を含む全ての人の包括的な性と生殖に関する健康と権利(SRHR)を更に推進することにコミッ
トする」とされている。
11
こども・若者や子育て当事者の中には、重大な課題を抱えており、より多くの支援を必要とするケー
スもあれば、比較的少ない支援を必要とするケースもある。また、支援の対象となっていないこども・
若者や子育て当事者であっても、多かれ少なかれ課題を抱えているケースもある。このように、個別の
課題や支援ニーズについては、それぞれのこども・若者や子育て当事者の状況に応じて、段階的に変化
するものとして捉える必要がある。
12
Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics 等の各教科での学習を実社会での問題発見・解
決にいかしていくための教科横断的な教育。STEAM の A の範囲を芸術、文化のみならず、生活、経
済、法律、政治、倫理等を含めた広い範囲(Liberal Arts)で定義し、推進することが重要である。
45
7
という。
SDGs 実施指針改訂版(令和元年 12 月持続可能な開発目標(SDGs)推進本部決定)において、
「ジェ
8
ンダー平等の実現及びジェンダーの視点の主流化は、分野横断的な価値として SDGs の全てのゴールの
実現に不可欠なものであり、あらゆる取組において常にそれらの視点を確保し施策に反映することが必
要である」とされている。
こどもが怖くて不安なときに身近なおとな(愛着対象)がそれを受け止め、こどもの心身に寄り添う
9
ことで安心感を与えられる経験の繰り返しを通じて獲得される安心の土台。こどもに自らや社会への基
本的な信頼感をもたらし、その基本的信頼感は、自他の心の理解や共感、健やかな脳や身体の発達を促
す。また、安定した愛着は、非認知能力の育ちに影響を与える重要な要素でもあり、生きる力につなが
っていく。
10
セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(SRHR:Sexual and Reproductive Health and
Rights)
。リプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関する健康)とは、平成6年(1994 年)の国際人
口開発会議の「行動計画」及び平成7年(1995 年)の第4回世界女性会議の「北京宣言及び行動綱
領」において、
「人間の生殖システム、その機能と(活動)過程の全ての側面において、単に疾病、
障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」と
されている。
また、リプロダクティブ・ライツ(性と生殖に関する権利)は、
「全てのカップルと個人が自分たち
の子どもの数、出産間隔、並びに出産する時を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手段
を得ることができるという基本的権利、並びに最高水準の性に関する健康及びリプロダクティブ・ヘ
ルスを得る権利」とされている。
G7 広島サミット首脳コミュニケにおいて、「特に脆弱な状況にある妊産婦、新生児、乳幼児及び青
少年を含む全ての人の包括的な性と生殖に関する健康と権利(SRHR)を更に推進することにコミッ
トする」とされている。
11
こども・若者や子育て当事者の中には、重大な課題を抱えており、より多くの支援を必要とするケー
スもあれば、比較的少ない支援を必要とするケースもある。また、支援の対象となっていないこども・
若者や子育て当事者であっても、多かれ少なかれ課題を抱えているケースもある。このように、個別の
課題や支援ニーズについては、それぞれのこども・若者や子育て当事者の状況に応じて、段階的に変化
するものとして捉える必要がある。
12
Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics 等の各教科での学習を実社会での問題発見・解
決にいかしていくための教科横断的な教育。STEAM の A の範囲を芸術、文化のみならず、生活、経
済、法律、政治、倫理等を含めた広い範囲(Liberal Arts)で定義し、推進することが重要である。
45