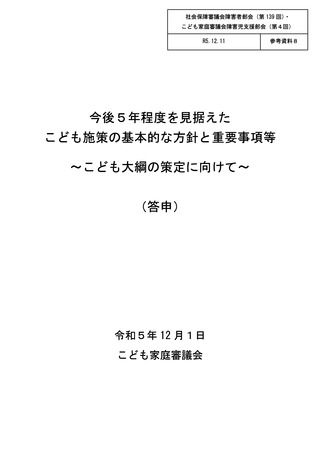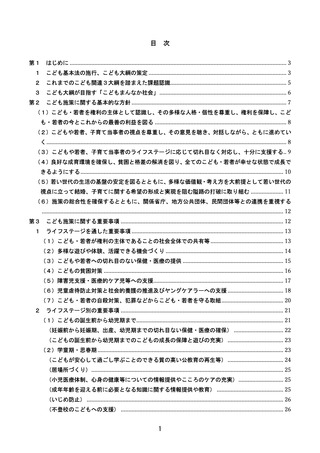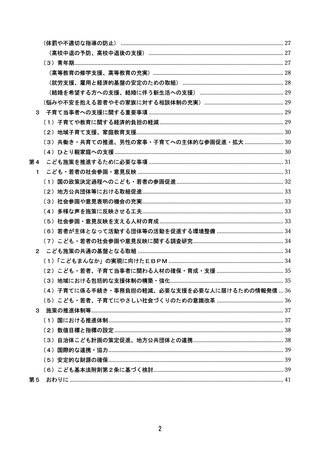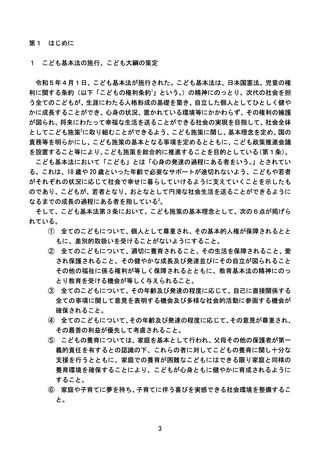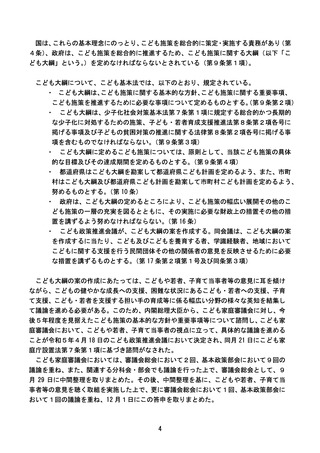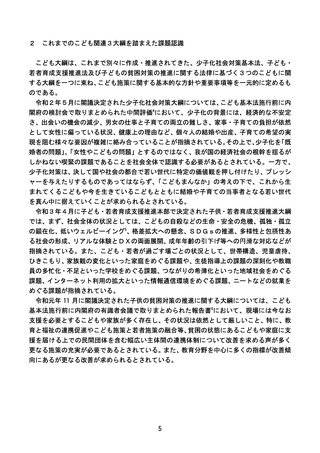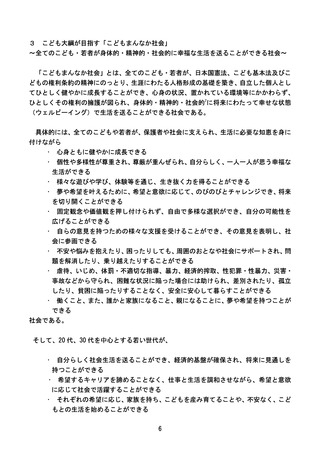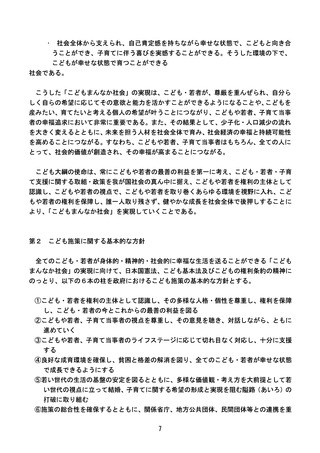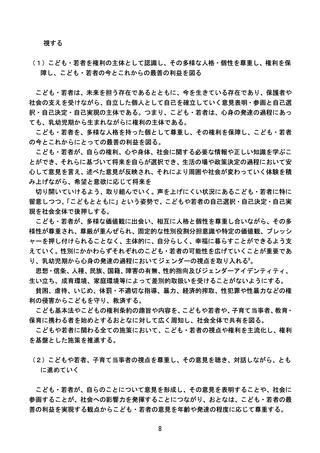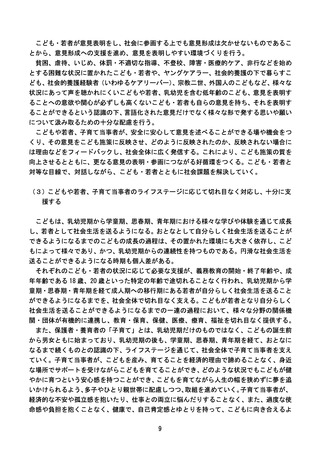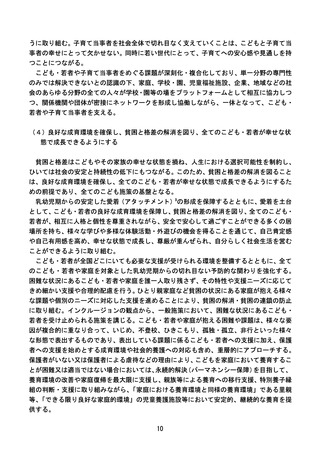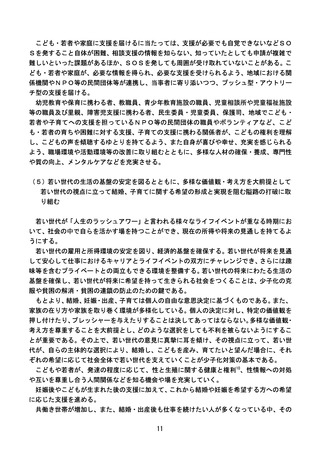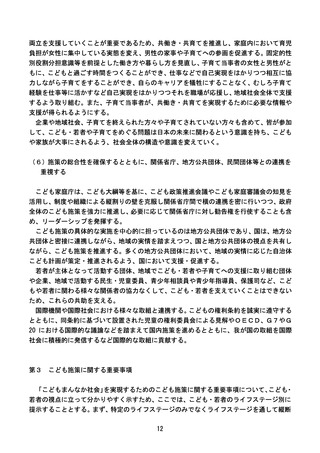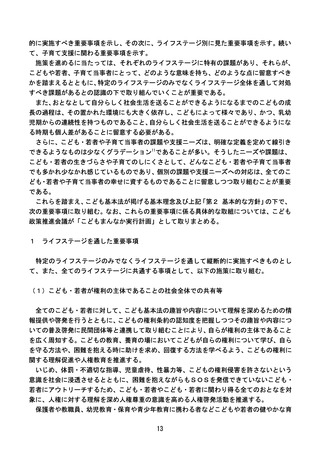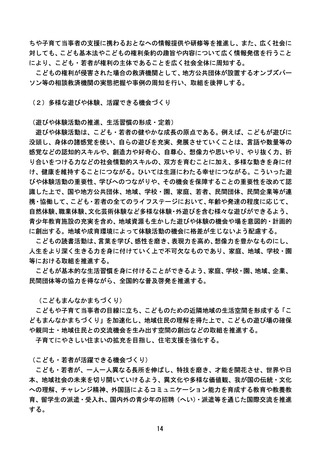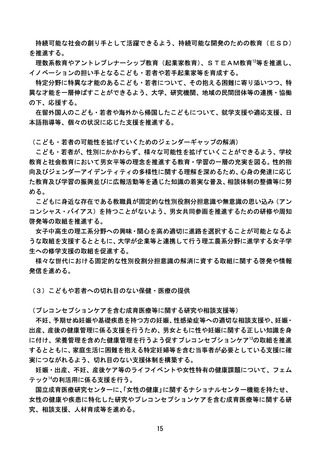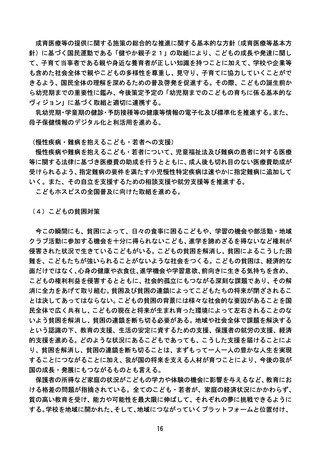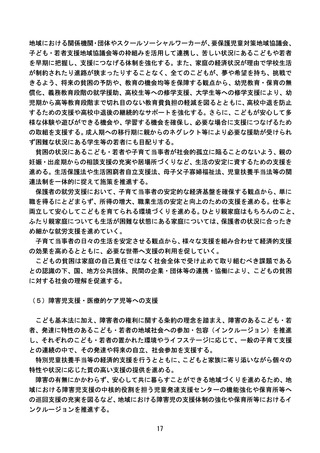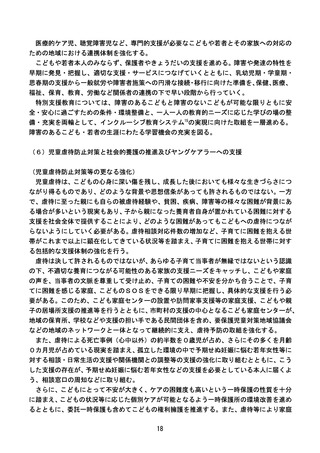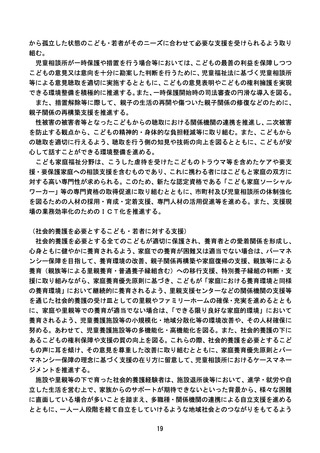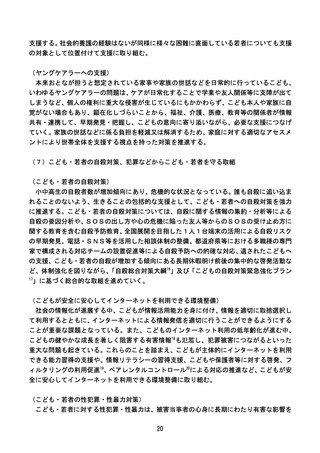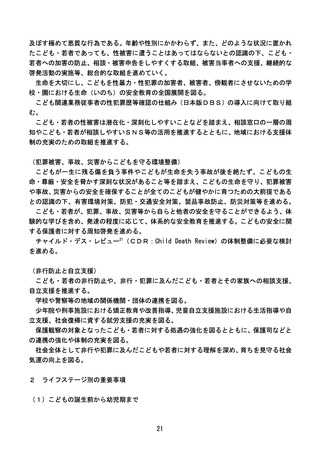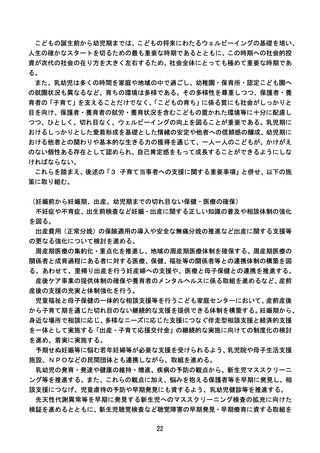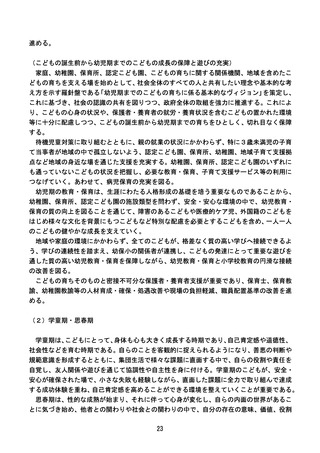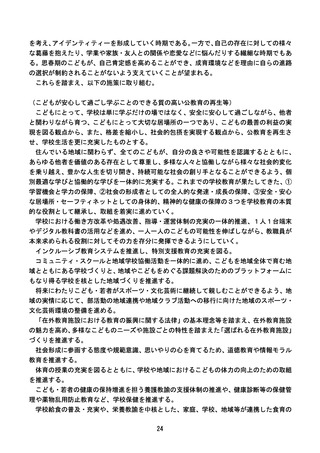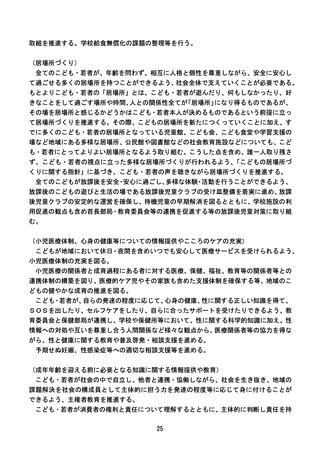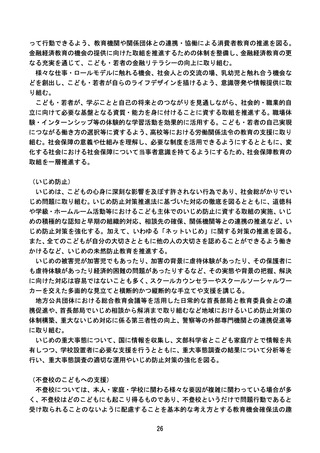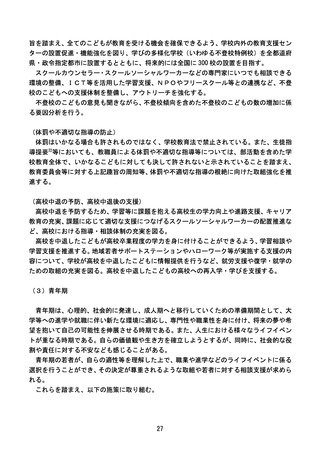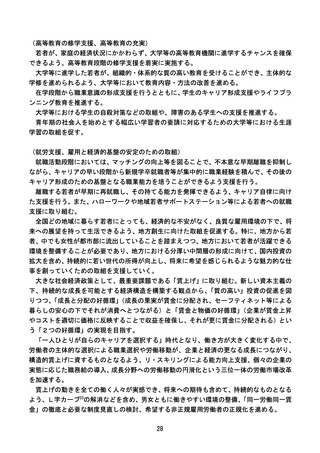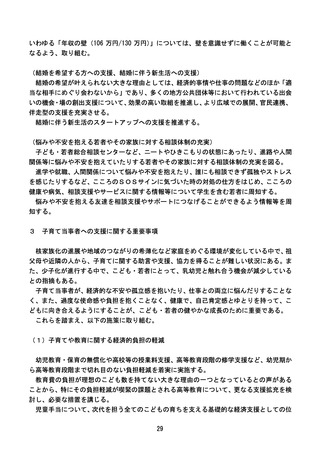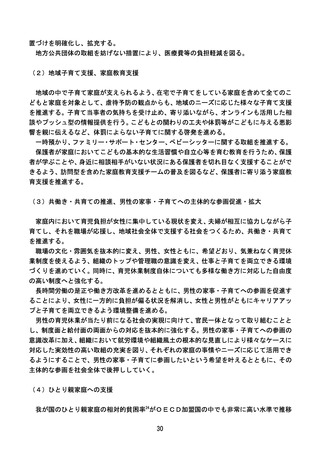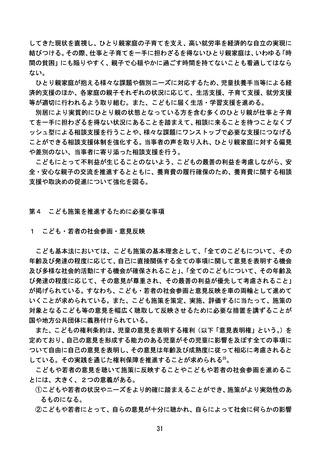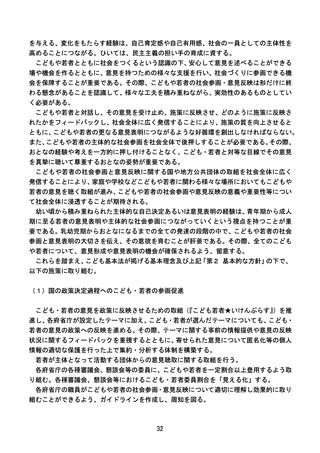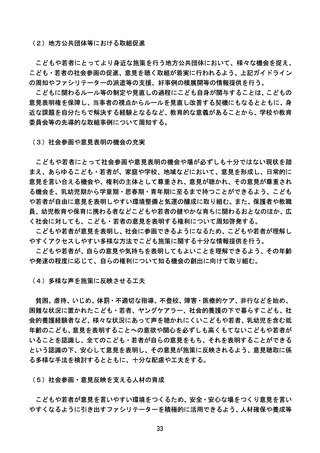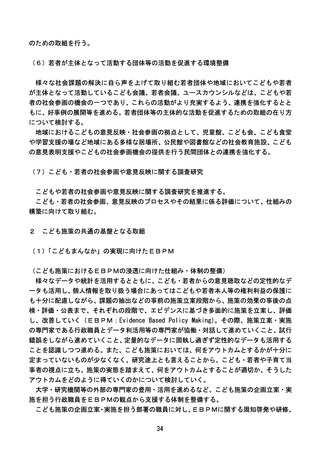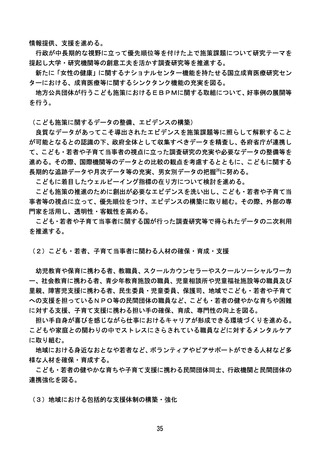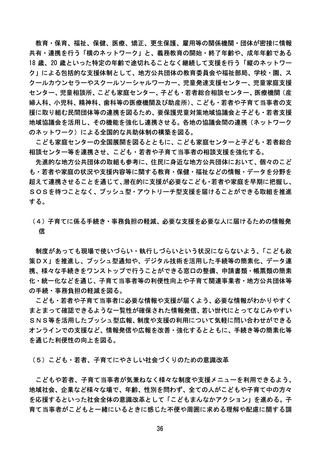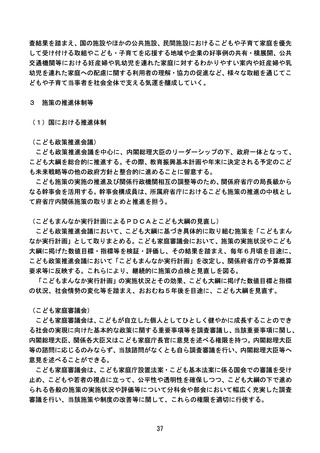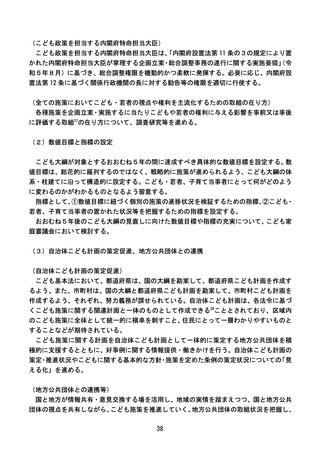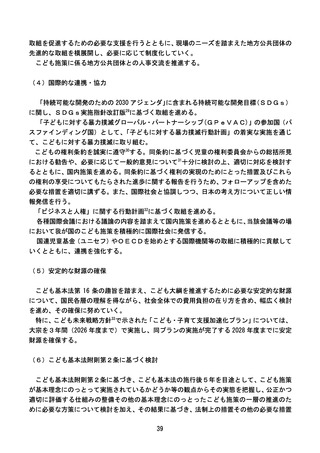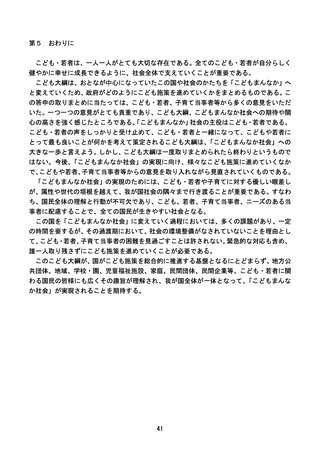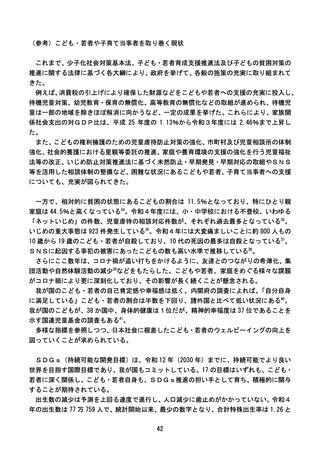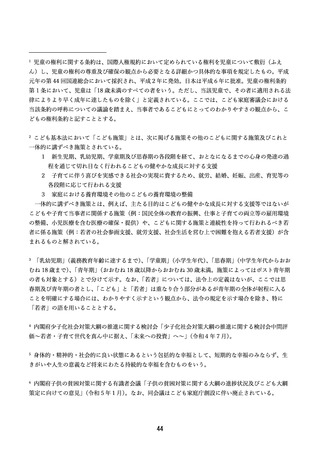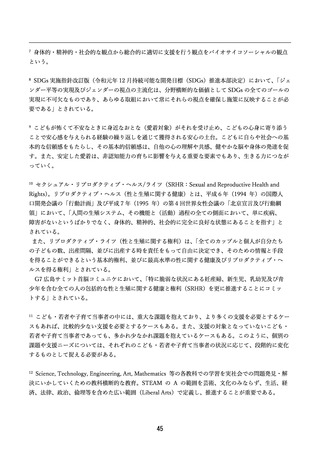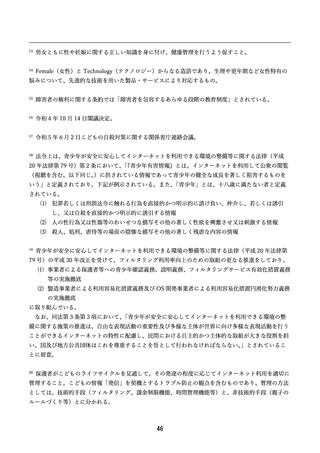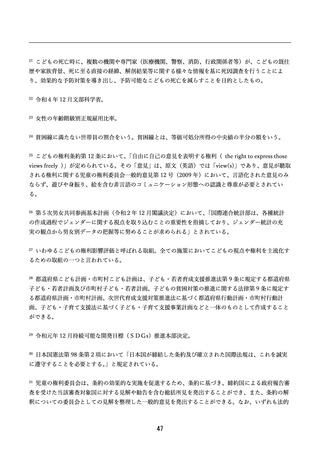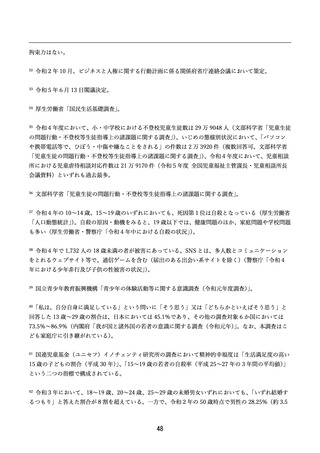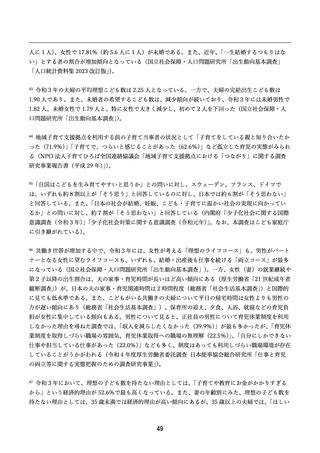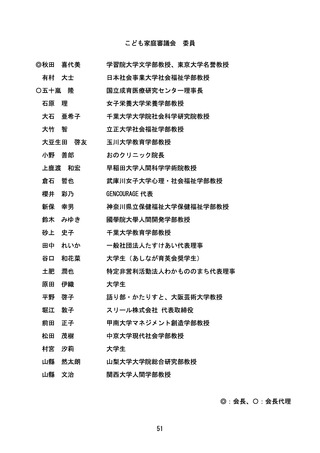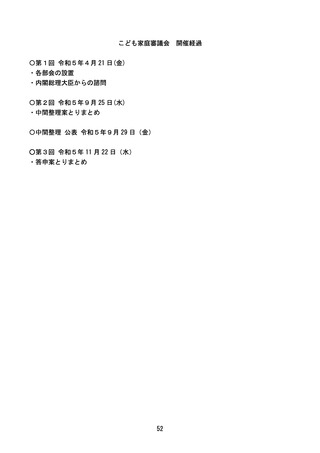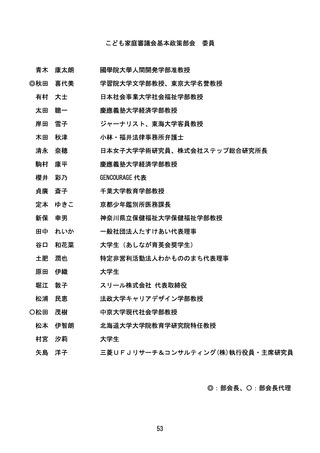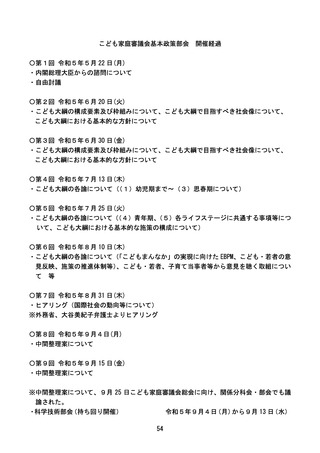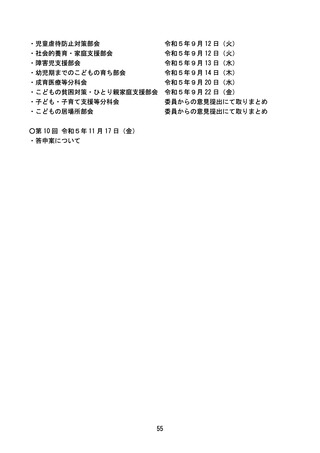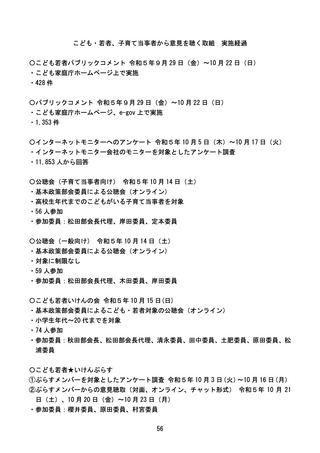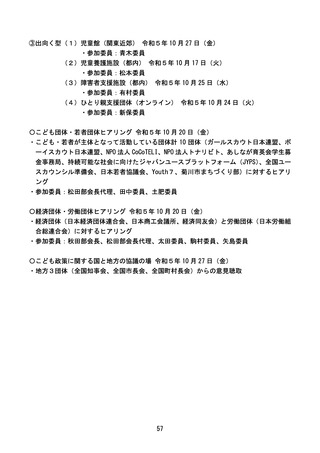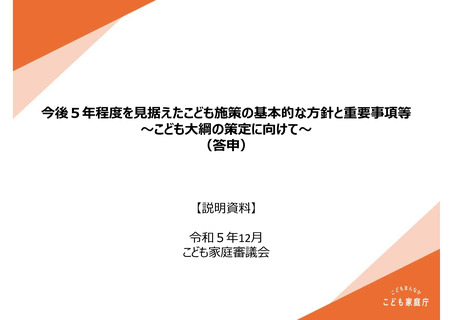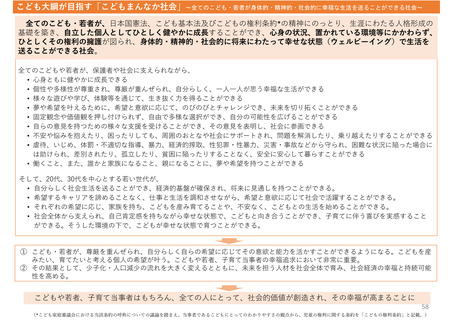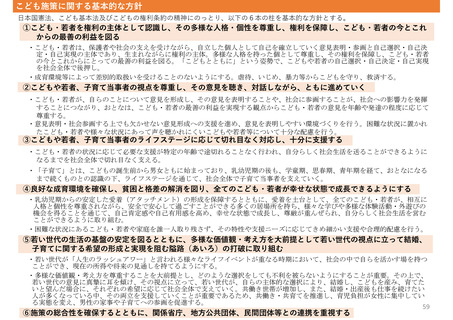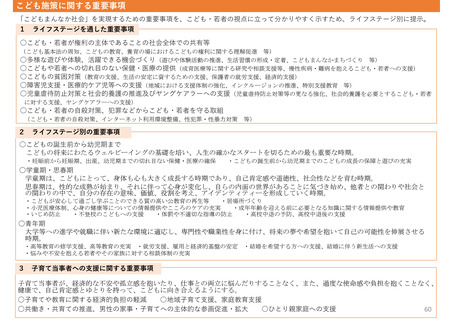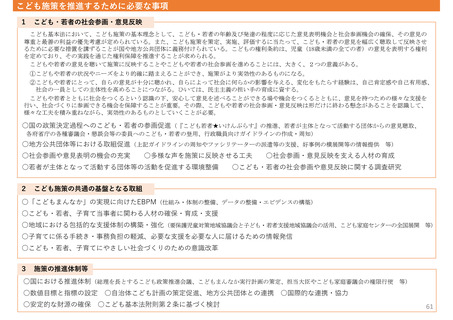よむ、つかう、まなぶ。
参考資料8 今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~(答申)[1.3MB] (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ちや子育て当事者の支援に携わるおとなへの情報提供や研修等を推進し、また、広く社会に
対しても、こども基本法やこどもの権利条約の趣旨や内容について広く情報発信を行うこと
により、こども・若者が権利の主体であることを広く社会全体に周知する。
こどもの権利が侵害された場合の救済機関として、地方公共団体が設置するオンブズパー
ソン等の相談救済機関の実態把握や事例の周知を行い、取組を後押しする。
(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり
(遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着)
遊びや体験活動は、こども・若者の健やかな成長の原点である。例えば、こどもが遊びに
没頭し、身体の諸感覚を使い、自らの遊びを充実、発展させていくことは、言語や数量等の
感覚などの認知的スキルや、創造力や好奇心、自尊心、想像力や思いやり、やり抜く力、折
り合いをつける力などの社会情動的スキルの、双方を育むことに加え、多様な動きを身に付
け、健康を維持することにつながる。ひいては生涯にわたる幸せにつながる。こういった遊
びや体験活動の重要性、学びへのつながりや、その機会を保障することの重要性を改めて認
識した上で、国や地方公共団体、地域、学校・園、家庭、若者、民間団体、民間企業等が連
携・協働して、こども・若者の全てのライフステージにおいて、年齢や発達の程度に応じて、
自然体験、職業体験、文化芸術体験など多様な体験・外遊びを含む様々な遊びができるよう、
青少年教育施設の充実を含め、地域資源も生かした遊びや体験の機会や場を意図的・計画的
に創出する。地域や成育環境によって体験活動の機会に格差が生じないよう配慮する。
こどもの読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにし、
人生をより深く生きる力を身に付けていく上で不可欠なものであり、家庭、地域、学校・園
等における取組を推進する。
こどもが基本的な生活習慣を身に付けることができるよう、家庭、学校・園、地域、企業、
民間団体等の協力を得ながら、全国的な普及啓発を推進する。
(こどもまんなかまちづくり)
こどもや子育て当事者の目線に立ち、こどものための近隣地域の生活空間を形成する「こ
どもまんなかまちづくり」を加速化し、地域住民の理解を得た上で、こどもの遊び場の確保
や親同士・地域住民との交流機会を生み出す空間の創出などの取組を推進する。
子育てにやさしい住まいの拡充を目指し、住宅支援を強化する。
(こども・若者が活躍できる機会づくり)
こども・若者が、一人一人異なる長所を伸ばし、特技を磨き、才能を開花させ、世界や日
本、地域社会の未来を切り開いていけるよう、異文化や多様な価値観、我が国の伝統・文化
への理解、チャレンジ精神、外国語によるコミュニケーション能力を育成する教育や教養教
育、留学生の派遣・受入れ、国内外の青少年の招聘(へい)
・派遣等を通じた国際交流を推進
する。
14
対しても、こども基本法やこどもの権利条約の趣旨や内容について広く情報発信を行うこと
により、こども・若者が権利の主体であることを広く社会全体に周知する。
こどもの権利が侵害された場合の救済機関として、地方公共団体が設置するオンブズパー
ソン等の相談救済機関の実態把握や事例の周知を行い、取組を後押しする。
(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり
(遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着)
遊びや体験活動は、こども・若者の健やかな成長の原点である。例えば、こどもが遊びに
没頭し、身体の諸感覚を使い、自らの遊びを充実、発展させていくことは、言語や数量等の
感覚などの認知的スキルや、創造力や好奇心、自尊心、想像力や思いやり、やり抜く力、折
り合いをつける力などの社会情動的スキルの、双方を育むことに加え、多様な動きを身に付
け、健康を維持することにつながる。ひいては生涯にわたる幸せにつながる。こういった遊
びや体験活動の重要性、学びへのつながりや、その機会を保障することの重要性を改めて認
識した上で、国や地方公共団体、地域、学校・園、家庭、若者、民間団体、民間企業等が連
携・協働して、こども・若者の全てのライフステージにおいて、年齢や発達の程度に応じて、
自然体験、職業体験、文化芸術体験など多様な体験・外遊びを含む様々な遊びができるよう、
青少年教育施設の充実を含め、地域資源も生かした遊びや体験の機会や場を意図的・計画的
に創出する。地域や成育環境によって体験活動の機会に格差が生じないよう配慮する。
こどもの読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにし、
人生をより深く生きる力を身に付けていく上で不可欠なものであり、家庭、地域、学校・園
等における取組を推進する。
こどもが基本的な生活習慣を身に付けることができるよう、家庭、学校・園、地域、企業、
民間団体等の協力を得ながら、全国的な普及啓発を推進する。
(こどもまんなかまちづくり)
こどもや子育て当事者の目線に立ち、こどものための近隣地域の生活空間を形成する「こ
どもまんなかまちづくり」を加速化し、地域住民の理解を得た上で、こどもの遊び場の確保
や親同士・地域住民との交流機会を生み出す空間の創出などの取組を推進する。
子育てにやさしい住まいの拡充を目指し、住宅支援を強化する。
(こども・若者が活躍できる機会づくり)
こども・若者が、一人一人異なる長所を伸ばし、特技を磨き、才能を開花させ、世界や日
本、地域社会の未来を切り開いていけるよう、異文化や多様な価値観、我が国の伝統・文化
への理解、チャレンジ精神、外国語によるコミュニケーション能力を育成する教育や教養教
育、留学生の派遣・受入れ、国内外の青少年の招聘(へい)
・派遣等を通じた国際交流を推進
する。
14