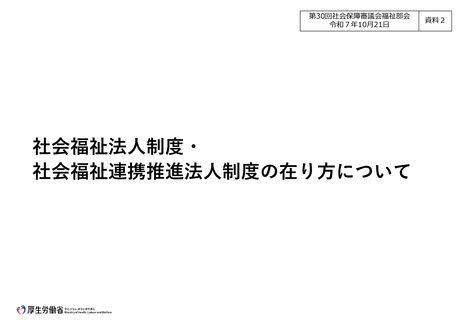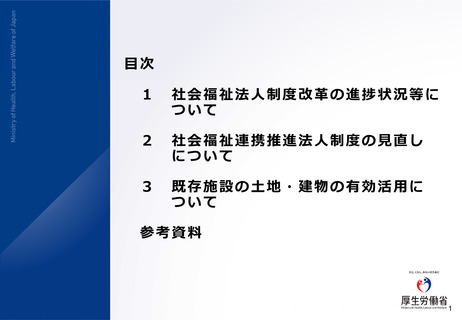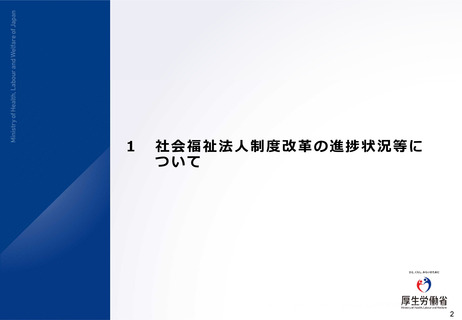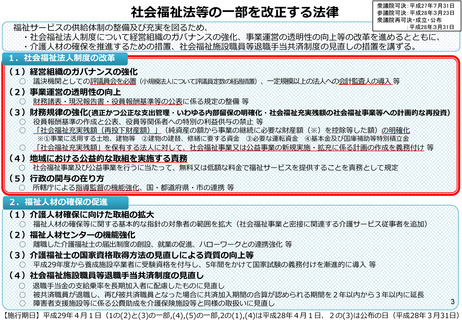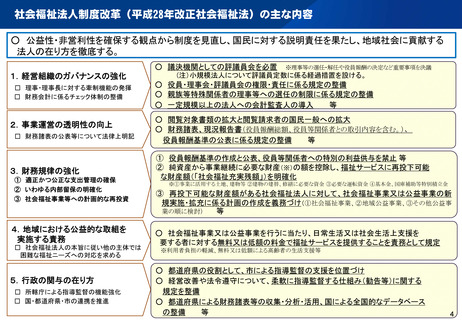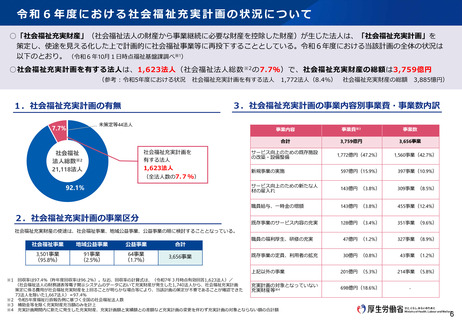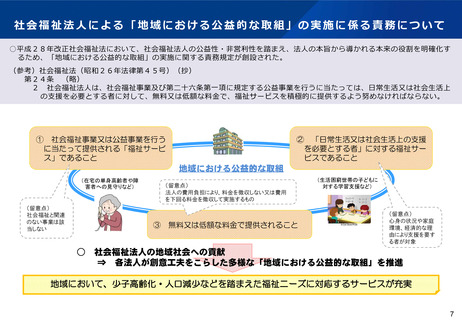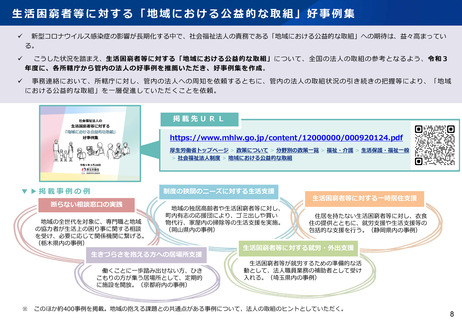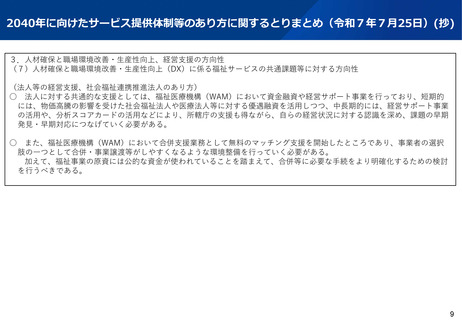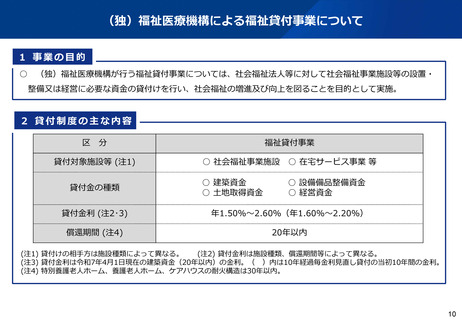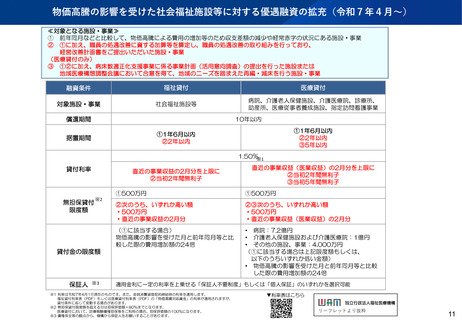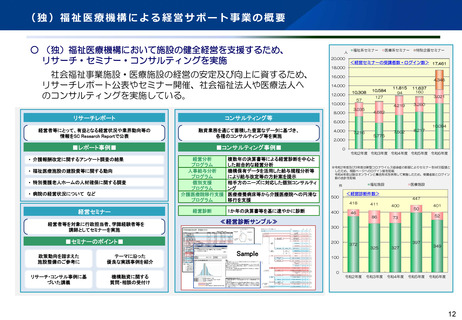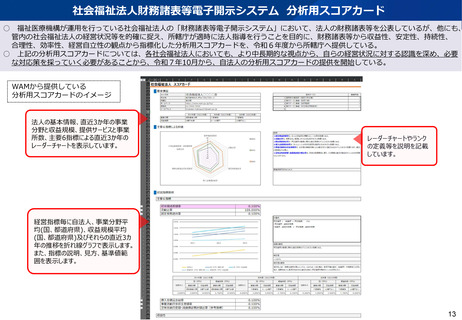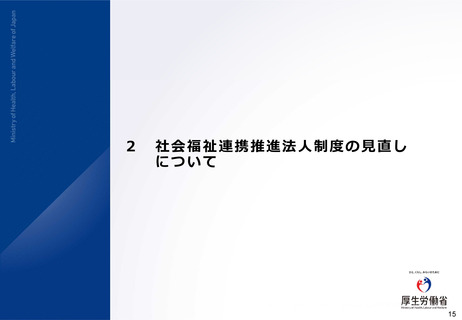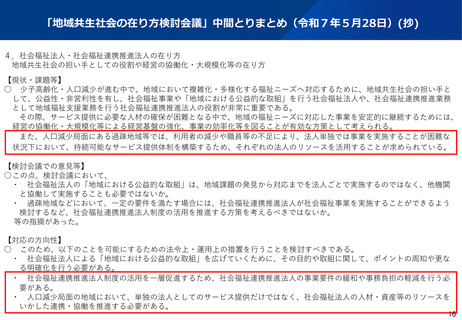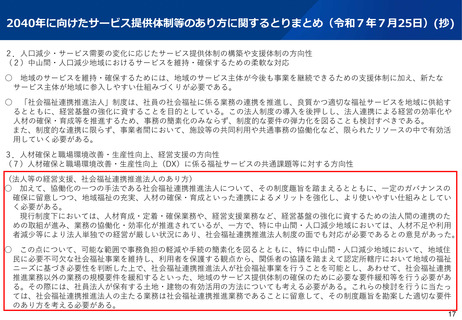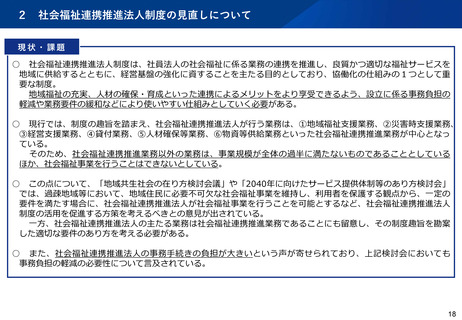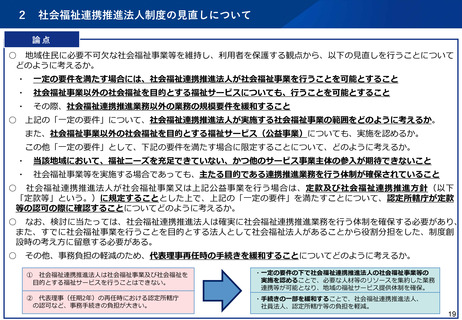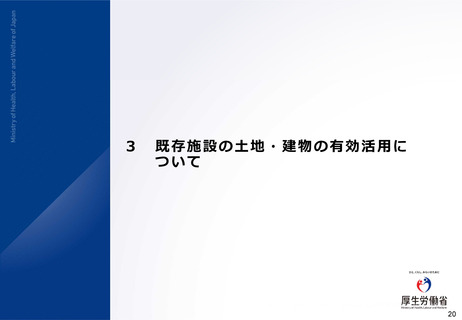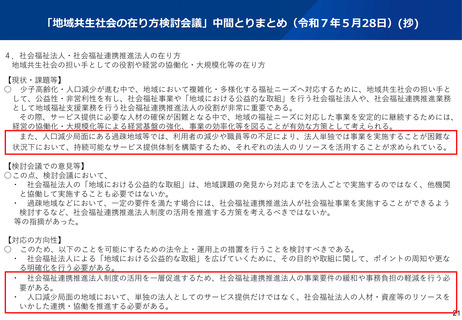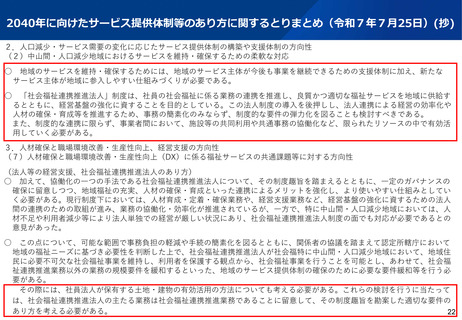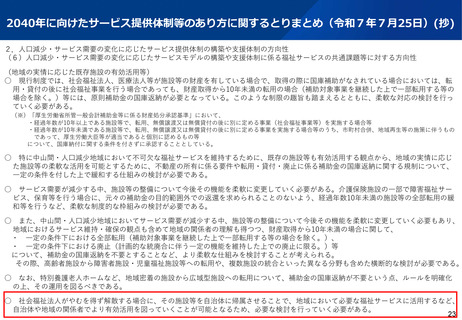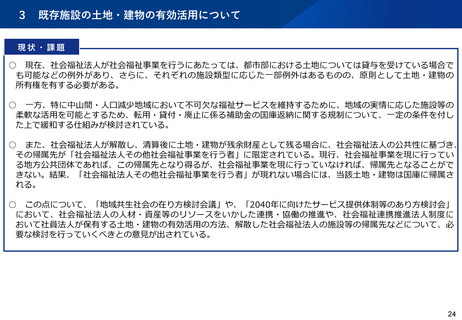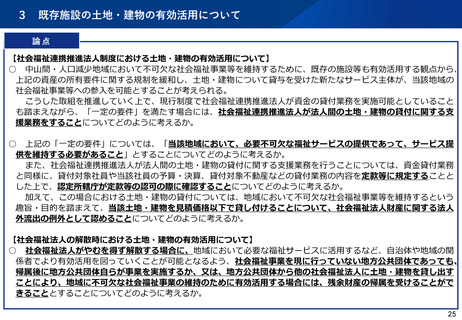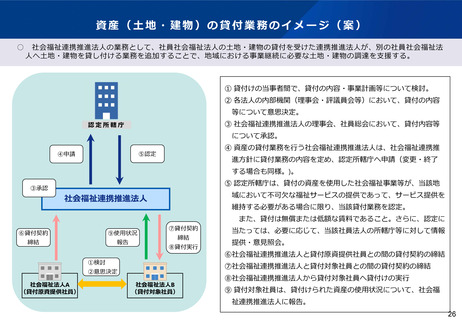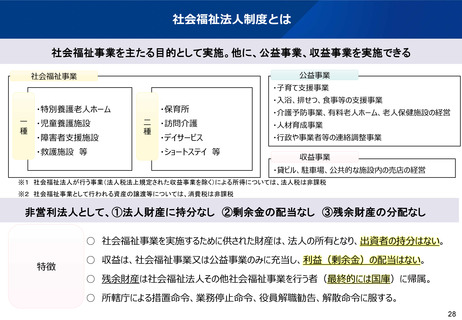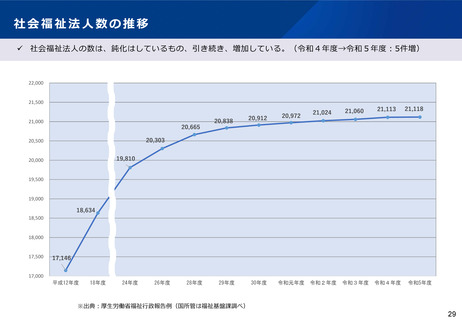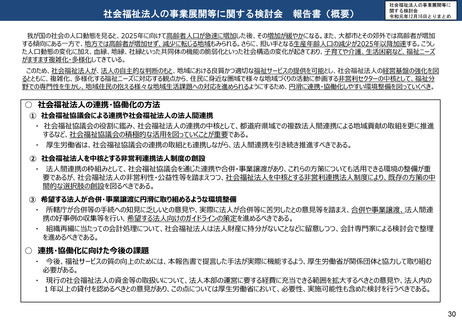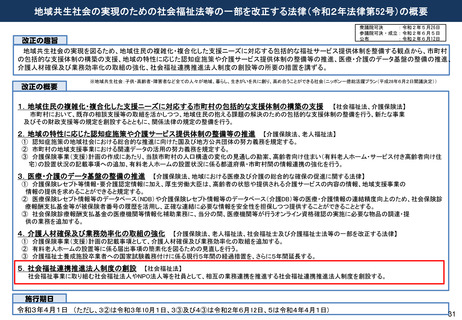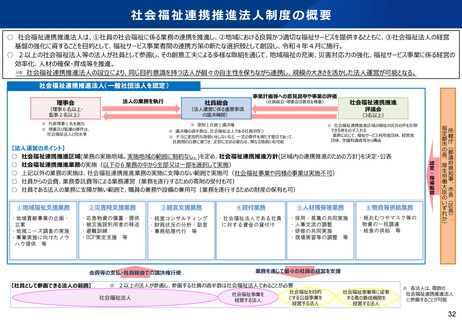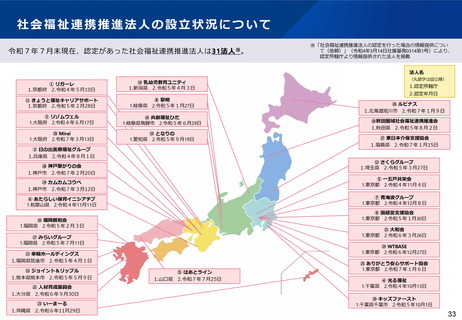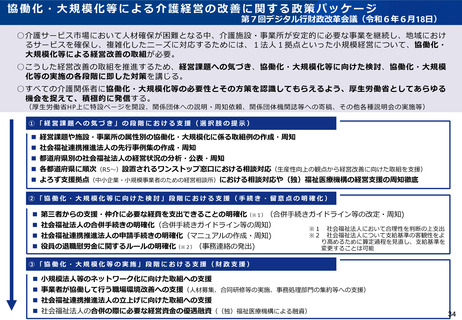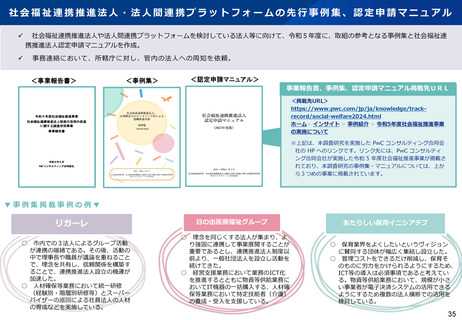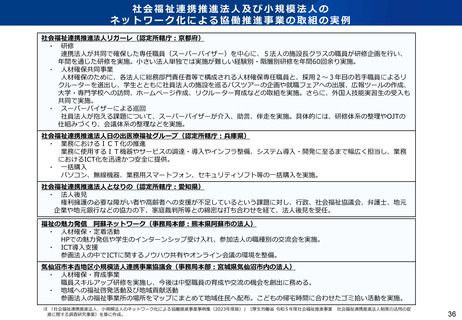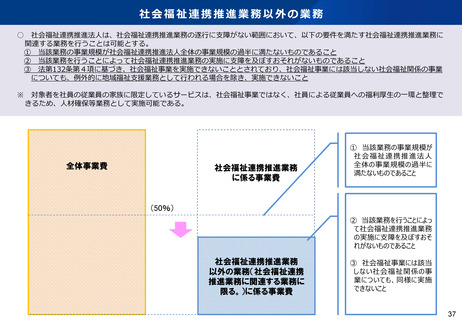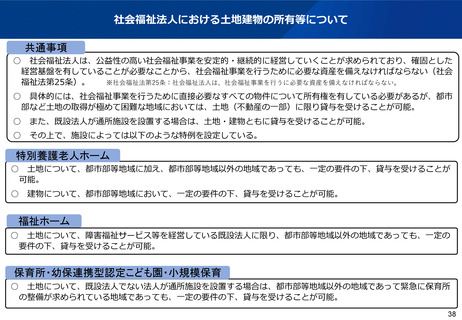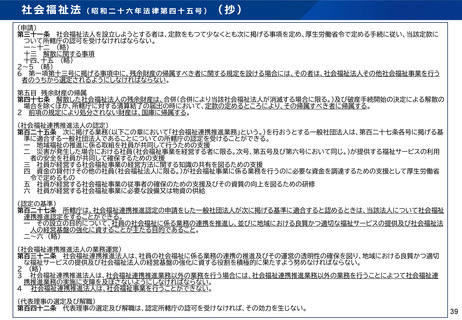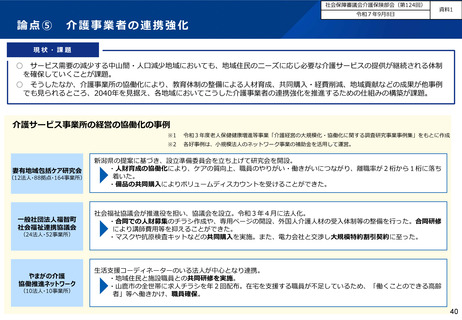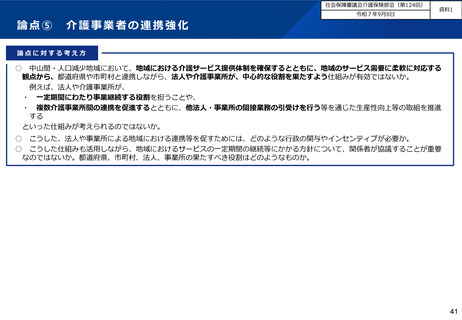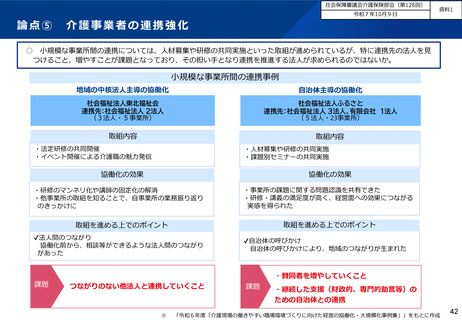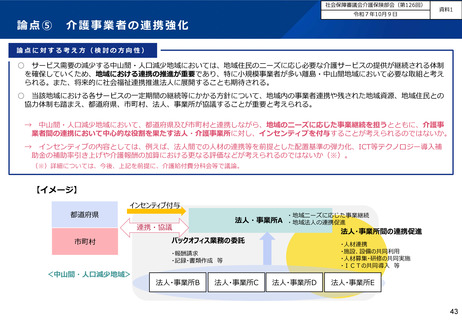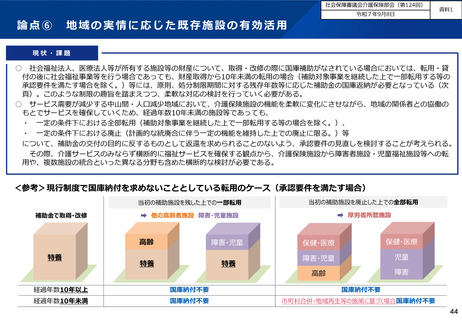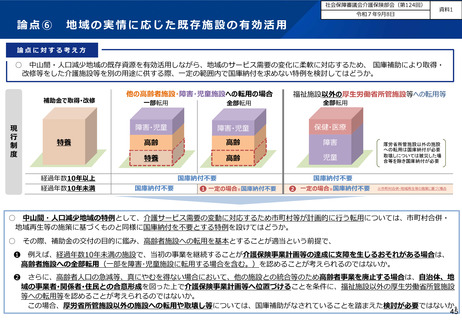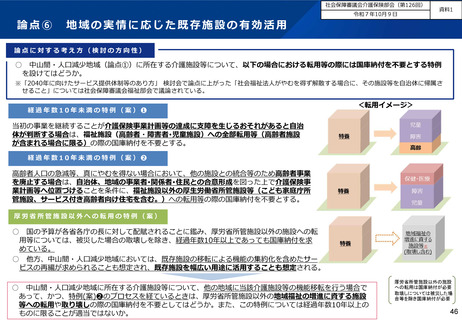よむ、つかう、まなぶ。
資料2 社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
社会福祉連携推進法人制度の概要
○ 社会福祉連携推進法人は、①社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、②地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、③社会福祉法人の経営
基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設し、令和4年4月に施行。
○ 2以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の
効率化、人材の確保・育成等を推進。
⇒ 社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能となる。
社会福祉連携推進法人(一般社団法人を認定)
法人の業務を執行
理事会
事業計画等への意見具申や事業の評価
社員総会
(理事6名以上・
監事2名以上)
社会福祉連携推進
(社員総会・理事会は意見を尊重)
評議会
(法人運営に係る重要事項
の議決機関)
※ 原則1社員1議決権
※ 社会福祉連携推進区域の福祉の状況の声を反映
できる者を必ず入れる
業務に応じて、福祉サービス利用者団体、経営者
団体、学識有識者等から構成
※ 議決権の過半数は、社会福祉法人である社員が持つ
※ 不当に差別的な取扱いをしないなど、一定の要件を満たす場合であって、
社員間の合意に基づき、定款に定める場合は、異なる取扱いも可能
認定・指導監督
【法人運営のポイント】
○ 社会福祉連携推進区域(業務の実施地域。実施地域の範囲に制約なし。)を定め、社会福祉連携推進方針(区域内の連携推進のための方針)を決定・公表
○ 社会福祉連携推進業務の実施(以下の6業務の中から全部又は一部を選択して実施)
○ 上記以外の業務の実施は、社会福祉連携推進業務の実施に支障のない範囲で実施可(社会福祉事業や同様の事業は実施不可)
○ 社員からの会費、業務委託費等による業務運営(業務を遂行するための寄附の受付も可)
○ 社員である法人の業務に支障が無い範囲で、職員の兼務や設備の兼用可(業務を遂行するための財産の保有も可)
①地域福祉支援業務
②災害時支援業務
③経営支援業務
④貸付業務
⑤人材確保等業務
⑥物資等供給業務
・地域貢献事業の企画・
立案
・地域ニーズ調査の実施
・事業実施に向けたノウ
ハウ提供 等
・応急物資の備蓄・提供
・被災施設利用者の移送
・避難訓練
・BCP策定支援 等
・経営コンサルティング
・財務状況の分析・助言
・事務処理代行 等
・社会福祉法人である社員
に対する資金の貸付け
・採用・募集の共同実施
・人事交流の調整
・研修の共同実施
・現場実習等の調整 等
・紙おむつやマスク等の
物資の一括調達
・給食の供給 等
会費等の支払・社員総会での議決権行使
【社員として参画できる法人の範囲】
業務を通じて個々の社員の経営を支援
※ 2以上の法人が参画し、参画する社員の過半数は社会福祉法人であることが必要
社会福祉法人
所轄庁(都道府県知事、市長(区長)、
指定都市の長、厚生労働大臣のいずれか)
※ 代表理事1名を選出
※ 理事及び監事の要件は、
社会福祉法人と同水準
(3名以上)
社会福祉事業を
経営する法人
社会福祉を目的
とする公益事業を
経営する法人
社会福祉事業等に従事
する者の養成機関を
経営する法人
※ 各法人は、複数の
社会福祉連携推進法人
に参画することが可能
32
○ 社会福祉連携推進法人は、①社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、②地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、③社会福祉法人の経営
基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設し、令和4年4月に施行。
○ 2以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の
効率化、人材の確保・育成等を推進。
⇒ 社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能となる。
社会福祉連携推進法人(一般社団法人を認定)
法人の業務を執行
理事会
事業計画等への意見具申や事業の評価
社員総会
(理事6名以上・
監事2名以上)
社会福祉連携推進
(社員総会・理事会は意見を尊重)
評議会
(法人運営に係る重要事項
の議決機関)
※ 原則1社員1議決権
※ 社会福祉連携推進区域の福祉の状況の声を反映
できる者を必ず入れる
業務に応じて、福祉サービス利用者団体、経営者
団体、学識有識者等から構成
※ 議決権の過半数は、社会福祉法人である社員が持つ
※ 不当に差別的な取扱いをしないなど、一定の要件を満たす場合であって、
社員間の合意に基づき、定款に定める場合は、異なる取扱いも可能
認定・指導監督
【法人運営のポイント】
○ 社会福祉連携推進区域(業務の実施地域。実施地域の範囲に制約なし。)を定め、社会福祉連携推進方針(区域内の連携推進のための方針)を決定・公表
○ 社会福祉連携推進業務の実施(以下の6業務の中から全部又は一部を選択して実施)
○ 上記以外の業務の実施は、社会福祉連携推進業務の実施に支障のない範囲で実施可(社会福祉事業や同様の事業は実施不可)
○ 社員からの会費、業務委託費等による業務運営(業務を遂行するための寄附の受付も可)
○ 社員である法人の業務に支障が無い範囲で、職員の兼務や設備の兼用可(業務を遂行するための財産の保有も可)
①地域福祉支援業務
②災害時支援業務
③経営支援業務
④貸付業務
⑤人材確保等業務
⑥物資等供給業務
・地域貢献事業の企画・
立案
・地域ニーズ調査の実施
・事業実施に向けたノウ
ハウ提供 等
・応急物資の備蓄・提供
・被災施設利用者の移送
・避難訓練
・BCP策定支援 等
・経営コンサルティング
・財務状況の分析・助言
・事務処理代行 等
・社会福祉法人である社員
に対する資金の貸付け
・採用・募集の共同実施
・人事交流の調整
・研修の共同実施
・現場実習等の調整 等
・紙おむつやマスク等の
物資の一括調達
・給食の供給 等
会費等の支払・社員総会での議決権行使
【社員として参画できる法人の範囲】
業務を通じて個々の社員の経営を支援
※ 2以上の法人が参画し、参画する社員の過半数は社会福祉法人であることが必要
社会福祉法人
所轄庁(都道府県知事、市長(区長)、
指定都市の長、厚生労働大臣のいずれか)
※ 代表理事1名を選出
※ 理事及び監事の要件は、
社会福祉法人と同水準
(3名以上)
社会福祉事業を
経営する法人
社会福祉を目的
とする公益事業を
経営する法人
社会福祉事業等に従事
する者の養成機関を
経営する法人
※ 各法人は、複数の
社会福祉連携推進法人
に参画することが可能
32