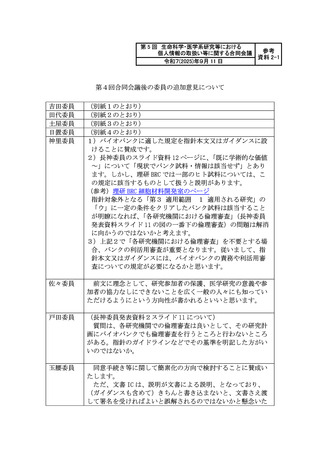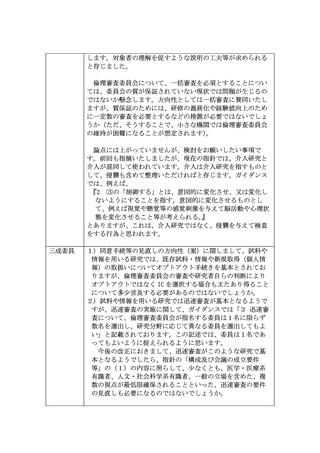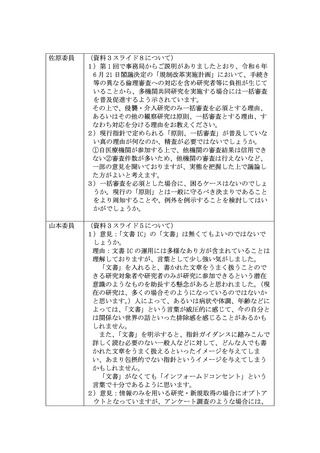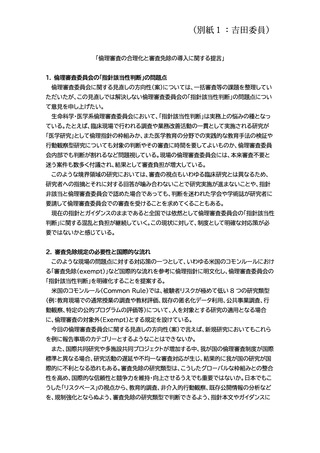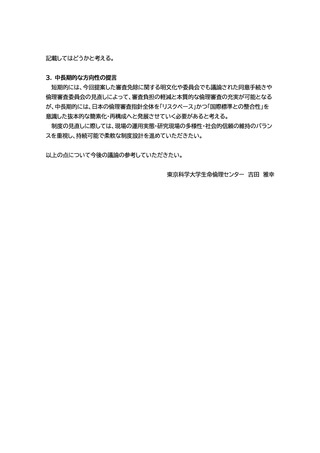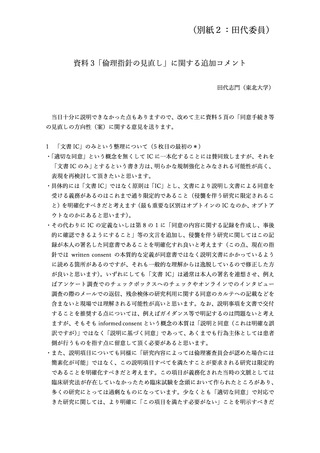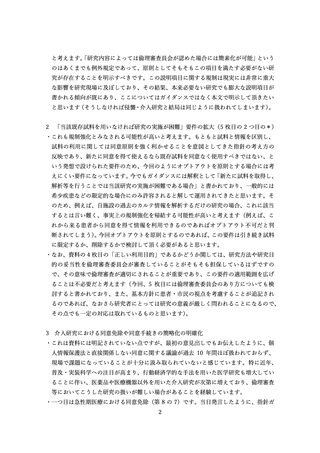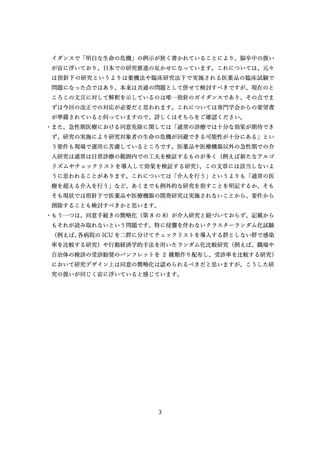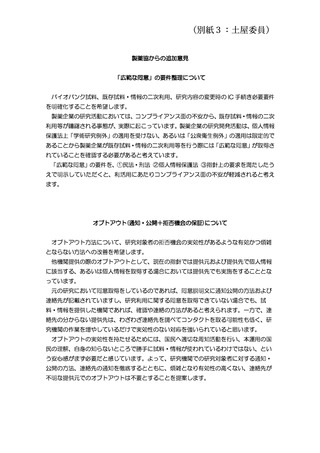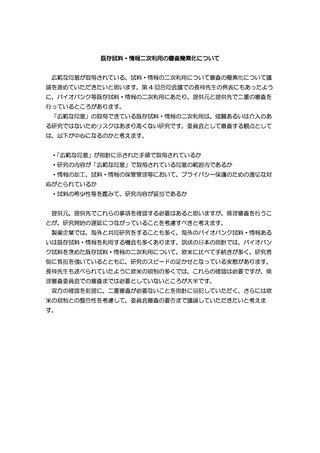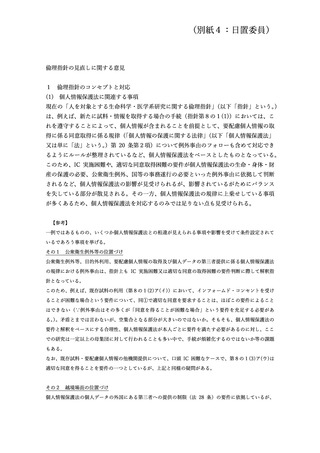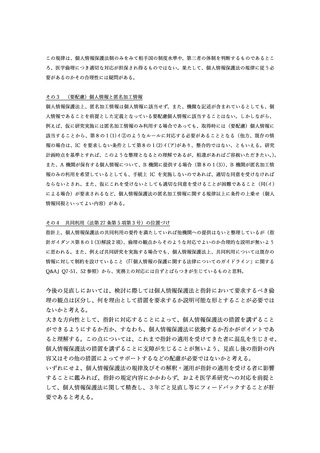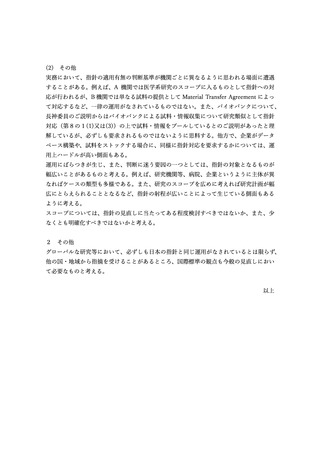よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2-1 : 第4回合同会議後の委員の追加意見 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63268.html |
| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第13回 9/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
イダンスで「明白な生命の危機」の例示が狭く書かれていることにより、脳卒中の扱い
が宙に浮いており、日本での研究推進の足かせになっています。これについては、元々
は指針下の研究というよりは薬機法や臨床研究法下で実施される医薬品の臨床試験で
問題になった点ではあり、本来は共通の問題として併せて検討すべきですが、現在のと
ころこの文言に対して解釈を示しているのは唯一指針のガイダンスであり、その点でま
ずは今回の改正での対応が必要だと思われます。これについては専門学会からの要望書
が準備されていると伺っていますので、詳しくはそちらをご確認ください。
・また、急性期医療における同意免除に関しては「通常の診療では十分な効果が期待でき
ず、研究の実施により研究対象者の生命の危機が回避できる可能性が十分にある」とい
う要件も現場で運用に苦慮しているところです。医薬品や医療機器以外の急性期での介
入研究は通常は日常診療の範囲内での工夫を検証するものが多く(例えば新たなアルゴ
リズムやチェックリストを導入して効果を検証する研究)、この文章には該当しないよ
うに思われることがあります。これについては「介入を行う」というよりも「通常の医
療を超える介入を行う」など、あくまでも例外的な研究を指すことを明記するか、そも
そも現状では指針下で医薬品や医療機器の開発研究は実施されないことから、要件から
削除することも検討すべきかと思います。
・もう一つは、同意手続きの簡略化(第 8 の 8)が介入研究と紐づいておらず、記載から
もそれが読み取れないという問題です。特に侵襲を伴わないクラスターランダム化試験
(例えば、各病院の ICU を二群に分けてチェックリストを導入する群としない群で感染
率を比較する研究)や行動経済学的手法を用いたランダム化比較研究(例えば、職場や
自治体の検診の受診勧奨のパンフレットを 2 種類作り配布し、受診率を比較する研究)
において研究デザイン上は同意の簡略化は認められるべきだと思いますが、こうした研
究の扱いが同じく宙に浮いていると感じています。
3
が宙に浮いており、日本での研究推進の足かせになっています。これについては、元々
は指針下の研究というよりは薬機法や臨床研究法下で実施される医薬品の臨床試験で
問題になった点ではあり、本来は共通の問題として併せて検討すべきですが、現在のと
ころこの文言に対して解釈を示しているのは唯一指針のガイダンスであり、その点でま
ずは今回の改正での対応が必要だと思われます。これについては専門学会からの要望書
が準備されていると伺っていますので、詳しくはそちらをご確認ください。
・また、急性期医療における同意免除に関しては「通常の診療では十分な効果が期待でき
ず、研究の実施により研究対象者の生命の危機が回避できる可能性が十分にある」とい
う要件も現場で運用に苦慮しているところです。医薬品や医療機器以外の急性期での介
入研究は通常は日常診療の範囲内での工夫を検証するものが多く(例えば新たなアルゴ
リズムやチェックリストを導入して効果を検証する研究)、この文章には該当しないよ
うに思われることがあります。これについては「介入を行う」というよりも「通常の医
療を超える介入を行う」など、あくまでも例外的な研究を指すことを明記するか、そも
そも現状では指針下で医薬品や医療機器の開発研究は実施されないことから、要件から
削除することも検討すべきかと思います。
・もう一つは、同意手続きの簡略化(第 8 の 8)が介入研究と紐づいておらず、記載から
もそれが読み取れないという問題です。特に侵襲を伴わないクラスターランダム化試験
(例えば、各病院の ICU を二群に分けてチェックリストを導入する群としない群で感染
率を比較する研究)や行動経済学的手法を用いたランダム化比較研究(例えば、職場や
自治体の検診の受診勧奨のパンフレットを 2 種類作り配布し、受診率を比較する研究)
において研究デザイン上は同意の簡略化は認められるべきだと思いますが、こうした研
究の扱いが同じく宙に浮いていると感じています。
3