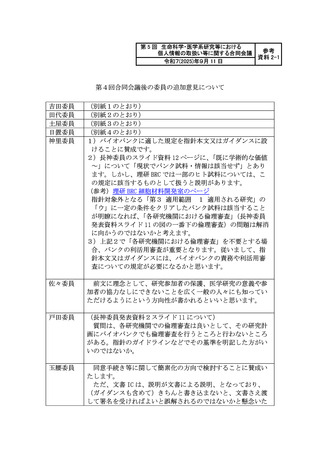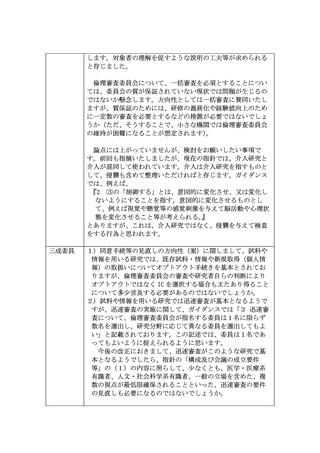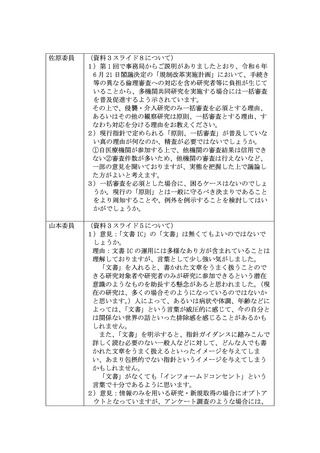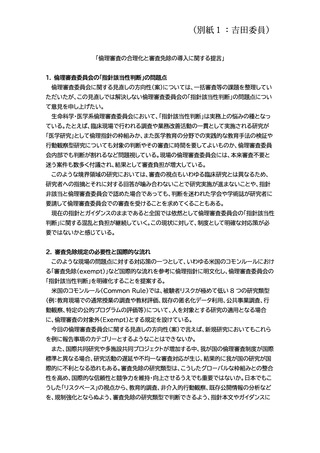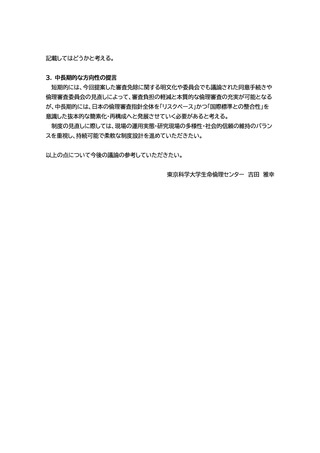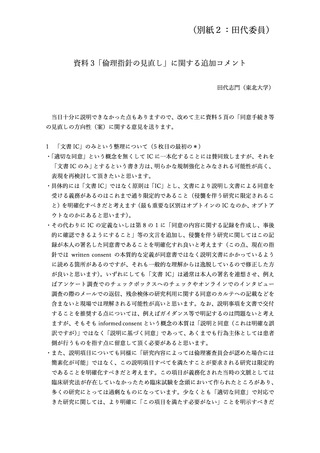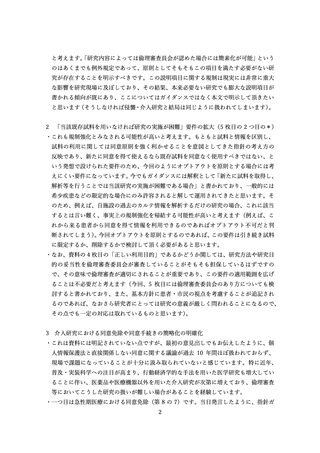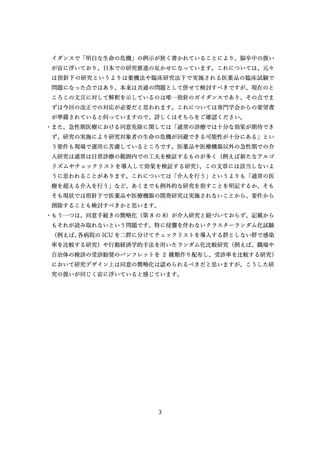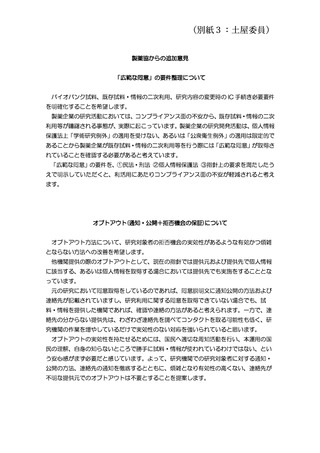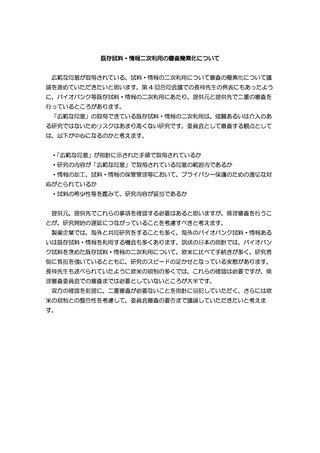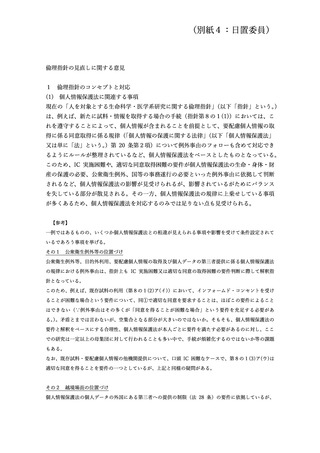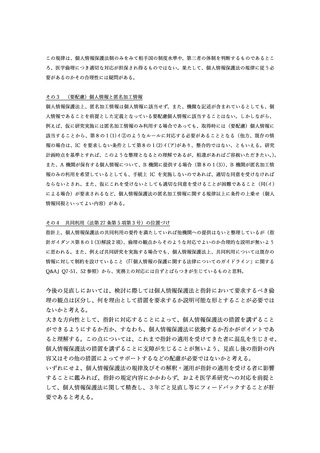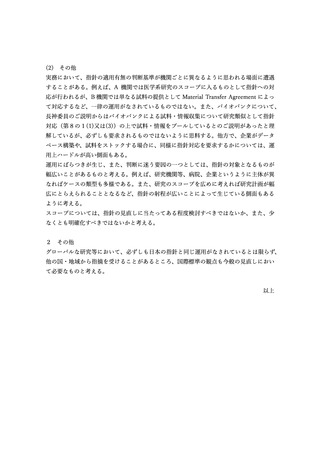よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2-1 : 第4回合同会議後の委員の追加意見 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63268.html |
| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第13回 9/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
します。対象者の理解を促すような説明の工夫等が求められる
と存じました。
倫理審査委員会について、一括審査を必須とすることについ
ては、委員会の質が保証されていない現状では問題が生じるの
ではないか懸念します。方向性としては一括審査に賛同いたし
ますが、質保証のためには、研修の義務化や経験値向上のため
に一定数の審査を必要とするなどの措置が必要ではないでしょ
うか(ただ、そうすることで、小さな機関では倫理審査委員会
の維持が困難になることが想定されます)。
論点には上がっていませんが、検討をお願いしたい事項で
す。前回も指摘いたしましたが、現在の指針では、介入研究と
介入が混同して使われています。介入は介入研究を指すものと
して、侵襲も含めて整理いただければと存じます。ガイダンス
では、例えば、
『2 ⑶の「制御する」とは、意図的に変化させ、又は変化し
ないようにすることを指す。意図的に変化させるものとし
て、例えば視覚や聴覚等の感覚刺激を与えて脳活動や心理状
態を変化させること等が考えられる。』
とありますが、これは、介入研究ではなく、侵襲を与えて検査
をする行為と思われます。
三成委員
1)同意手続等の見直しの方向性(案)に関しまして、試料や
情報を用いる研究では、既存試料・情報や新規取得(個人情
報)の取扱いについてオプトアウト手続きを基本とされてお
りますが、倫理審査委員会の審査や研究者自らの判断により
オプトアウトではなく IC を選択する場合もまたあり得ること
について多少言及する必要があるのではないでしょうか。
2)試料や情報を用いる研究では迅速審査が基本となるようで
すが、迅速審査の実施に関して、ガイダンスでは「3 迅速審
査について、倫理審査委員会が指名する委員は1名に限らず
数名を選出し、研究分野に応じて異なる委員を選出してもよ
い」と記載されております。この記述では、委員は1名であ
ってもよいように捉えられるように思います。
今後の改正におきまして、迅速審査がこのような研究で基
本となるようでしたら、指針の「構成及び会議の成立要件
等」の(1)の内容に照らして、少なくとも、医学・医療系
有識者、人文・社会科学系有識者、一般の立場を含めた、複
数の視点が最低限確保されることといった、迅速審査の要件
の見直しも必要になるのではないでしょうか。
と存じました。
倫理審査委員会について、一括審査を必須とすることについ
ては、委員会の質が保証されていない現状では問題が生じるの
ではないか懸念します。方向性としては一括審査に賛同いたし
ますが、質保証のためには、研修の義務化や経験値向上のため
に一定数の審査を必要とするなどの措置が必要ではないでしょ
うか(ただ、そうすることで、小さな機関では倫理審査委員会
の維持が困難になることが想定されます)。
論点には上がっていませんが、検討をお願いしたい事項で
す。前回も指摘いたしましたが、現在の指針では、介入研究と
介入が混同して使われています。介入は介入研究を指すものと
して、侵襲も含めて整理いただければと存じます。ガイダンス
では、例えば、
『2 ⑶の「制御する」とは、意図的に変化させ、又は変化し
ないようにすることを指す。意図的に変化させるものとし
て、例えば視覚や聴覚等の感覚刺激を与えて脳活動や心理状
態を変化させること等が考えられる。』
とありますが、これは、介入研究ではなく、侵襲を与えて検査
をする行為と思われます。
三成委員
1)同意手続等の見直しの方向性(案)に関しまして、試料や
情報を用いる研究では、既存試料・情報や新規取得(個人情
報)の取扱いについてオプトアウト手続きを基本とされてお
りますが、倫理審査委員会の審査や研究者自らの判断により
オプトアウトではなく IC を選択する場合もまたあり得ること
について多少言及する必要があるのではないでしょうか。
2)試料や情報を用いる研究では迅速審査が基本となるようで
すが、迅速審査の実施に関して、ガイダンスでは「3 迅速審
査について、倫理審査委員会が指名する委員は1名に限らず
数名を選出し、研究分野に応じて異なる委員を選出してもよ
い」と記載されております。この記述では、委員は1名であ
ってもよいように捉えられるように思います。
今後の改正におきまして、迅速審査がこのような研究で基
本となるようでしたら、指針の「構成及び会議の成立要件
等」の(1)の内容に照らして、少なくとも、医学・医療系
有識者、人文・社会科学系有識者、一般の立場を含めた、複
数の視点が最低限確保されることといった、迅速審査の要件
の見直しも必要になるのではないでしょうか。