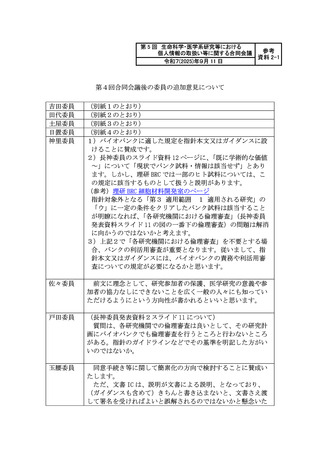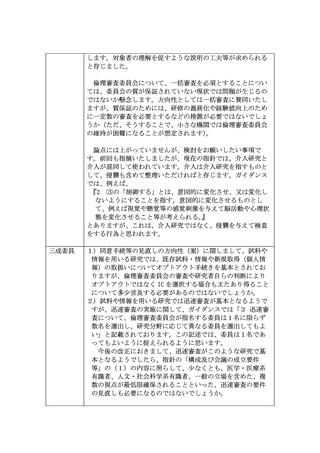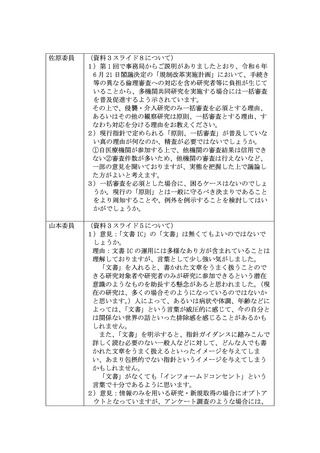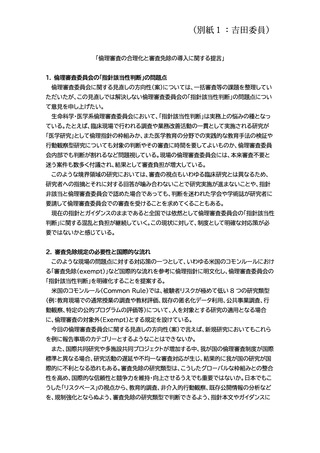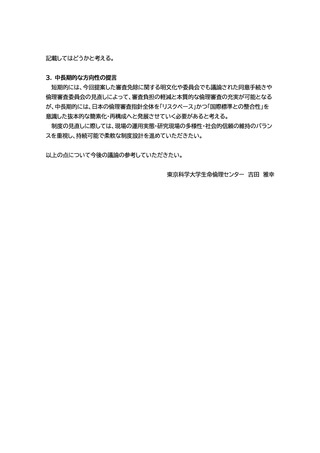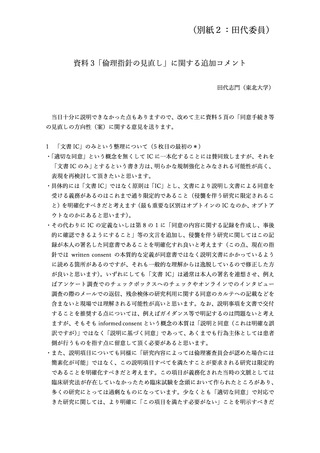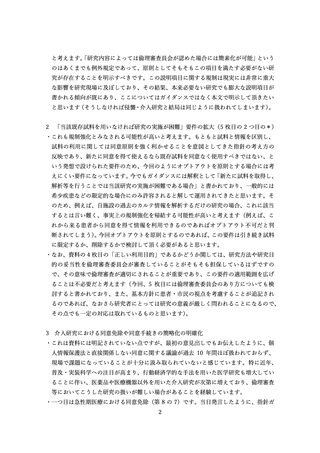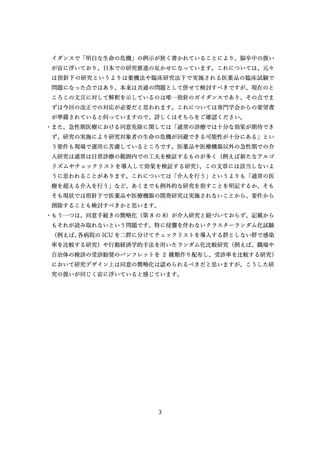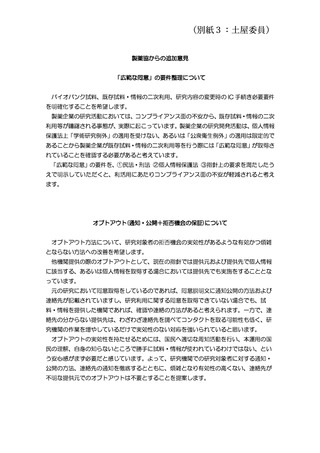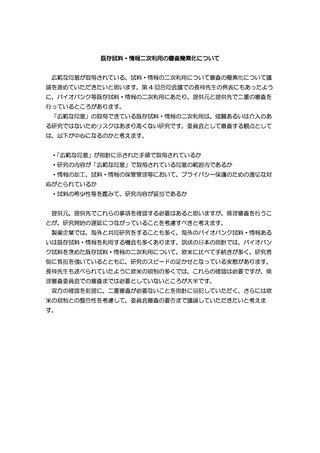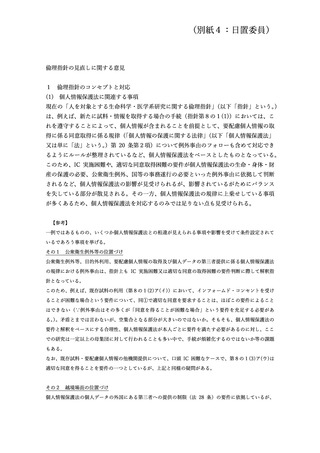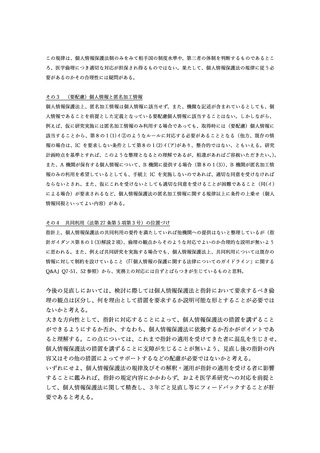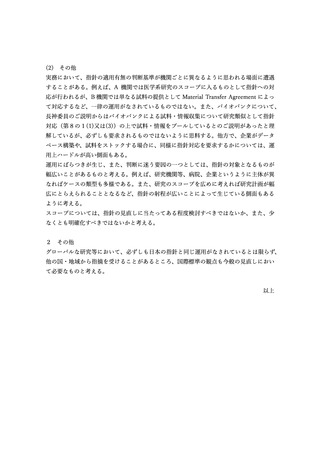よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2-1 : 第4回合同会議後の委員の追加意見 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63268.html |
| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第13回 9/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(別紙2:田代委員)
資料 3「倫理指針の見直し」に関する追加コメント
田代志門(東北大学)
当日十分に説明できなかった点もありますので、改めて主に資料 5 頁の「同意手続き等
の見直しの方向性(案)に関する意見を送ります。
1
「文書 IC」のみという整理について(5 枚目の最初の*)
・
「適切な同意」という概念を無くして IC に一本化することには賛同致しますが、それを
「文書 IC のみ」とするという書き方は、明らかな規制強化とみなされる可能性が高く、
表現を再検討して頂きたいと思います。
・具体的には「文書 IC」ではなく原則は「IC」とし、文書により説明し文書による同意を
受ける義務があるのはこれまで通り限定的であること(侵襲を伴う研究に限定されるこ
と)を明確化すべきだと考えます(最も重要な区別はオプトインの IC なのか、オプトア
ウトなのかにあると思います)。
・その代わりに IC の定義ないしは第 8 の 1 に「同意の内容に関する記録を作成し、事後
的に確認できるようにすること」等の文言を追加し、侵襲を伴う研究に関してはこの記
録が本人の署名した同意書であることを明確化すれ良いと考えます(この点、現在の指
針では written consent の本質的な定義が同意書ではなく説明文書にかかっているよう
に読める箇所があるのですが、それも一般的な理解からは逸脱しているので修正した方
が良いと思います)。いずれにしても「文書 IC」は通常は本人の署名を連想させ、例え
ばアンケート調査でのチェックボックスへのチェックやオンラインでのインタビュー
調査の際のメールでの返信、残余検体の研究利用に関する同意のカルテへの記載などを
含まないと現場では理解される可能性が高いと思います。なお、説明事項を文書で交付
することを推奨する点については、例えばガイダンス等で明記するのは問題ないと考え
ますが、そもそも informed consent という概念の本質は「説明と同意(これは明確な誤
訳ですが)
」ではなく「説明に基づく同意」であって、あくまでも行為主体としては患者
側が行うものを指す点に留意して頂く必要があると思います。
・また、説明項目についても同様に「研究内容によっては倫理審査員会が認めた場合には
簡素化が可能」ではなく、この説明項目すべてを満たすことが要求される研究は限定的
であることを明確化すべきだと考えます。この項目が義務化された当時の文脈としては
臨床研究法が存在していなかったため臨床試験を念頭において作られたところがあり、
多くの研究にとっては過剰なものになっています。少なくとも「適切な同意」で対応で
きた研究に関しては、より明確に「この項目を満たす必要がない」ことを明示すべきだ
資料 3「倫理指針の見直し」に関する追加コメント
田代志門(東北大学)
当日十分に説明できなかった点もありますので、改めて主に資料 5 頁の「同意手続き等
の見直しの方向性(案)に関する意見を送ります。
1
「文書 IC」のみという整理について(5 枚目の最初の*)
・
「適切な同意」という概念を無くして IC に一本化することには賛同致しますが、それを
「文書 IC のみ」とするという書き方は、明らかな規制強化とみなされる可能性が高く、
表現を再検討して頂きたいと思います。
・具体的には「文書 IC」ではなく原則は「IC」とし、文書により説明し文書による同意を
受ける義務があるのはこれまで通り限定的であること(侵襲を伴う研究に限定されるこ
と)を明確化すべきだと考えます(最も重要な区別はオプトインの IC なのか、オプトア
ウトなのかにあると思います)。
・その代わりに IC の定義ないしは第 8 の 1 に「同意の内容に関する記録を作成し、事後
的に確認できるようにすること」等の文言を追加し、侵襲を伴う研究に関してはこの記
録が本人の署名した同意書であることを明確化すれ良いと考えます(この点、現在の指
針では written consent の本質的な定義が同意書ではなく説明文書にかかっているよう
に読める箇所があるのですが、それも一般的な理解からは逸脱しているので修正した方
が良いと思います)。いずれにしても「文書 IC」は通常は本人の署名を連想させ、例え
ばアンケート調査でのチェックボックスへのチェックやオンラインでのインタビュー
調査の際のメールでの返信、残余検体の研究利用に関する同意のカルテへの記載などを
含まないと現場では理解される可能性が高いと思います。なお、説明事項を文書で交付
することを推奨する点については、例えばガイダンス等で明記するのは問題ないと考え
ますが、そもそも informed consent という概念の本質は「説明と同意(これは明確な誤
訳ですが)
」ではなく「説明に基づく同意」であって、あくまでも行為主体としては患者
側が行うものを指す点に留意して頂く必要があると思います。
・また、説明項目についても同様に「研究内容によっては倫理審査員会が認めた場合には
簡素化が可能」ではなく、この説明項目すべてを満たすことが要求される研究は限定的
であることを明確化すべきだと考えます。この項目が義務化された当時の文脈としては
臨床研究法が存在していなかったため臨床試験を念頭において作られたところがあり、
多くの研究にとっては過剰なものになっています。少なくとも「適切な同意」で対応で
きた研究に関しては、より明確に「この項目を満たす必要がない」ことを明示すべきだ