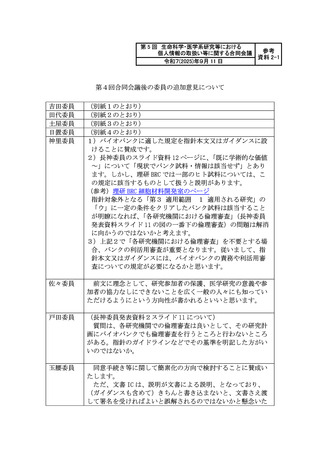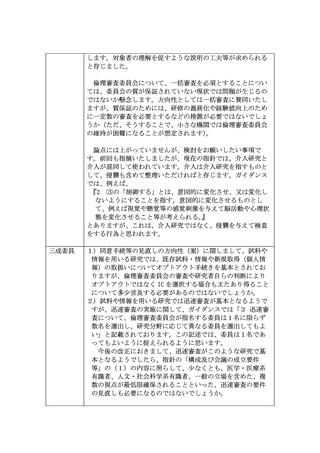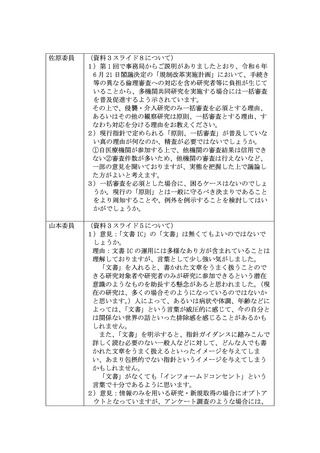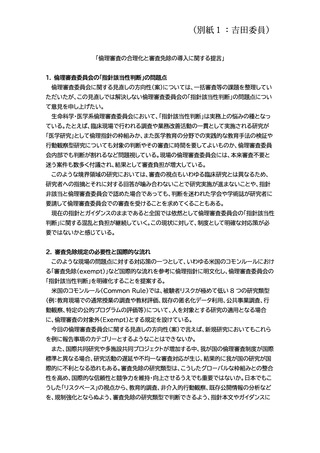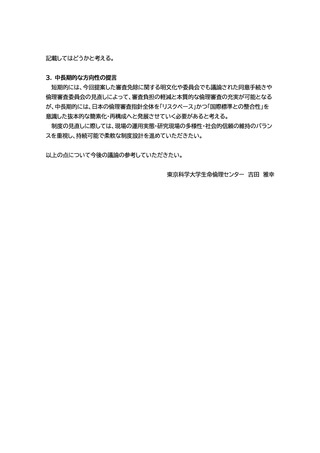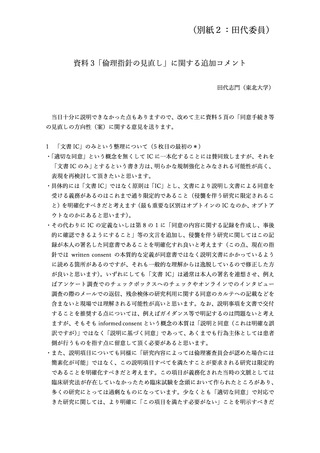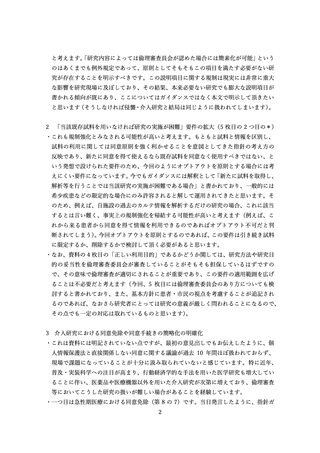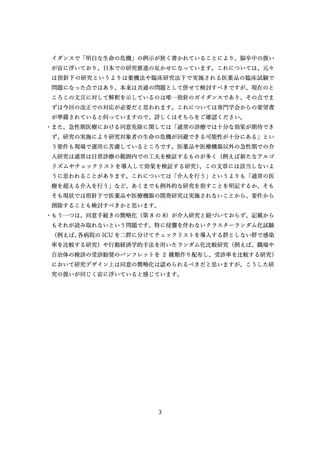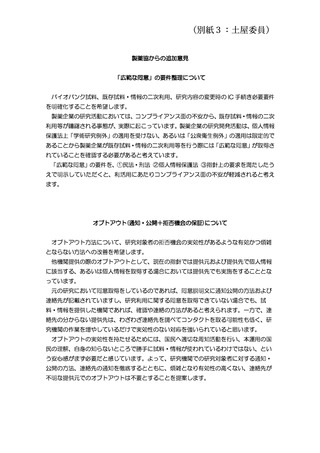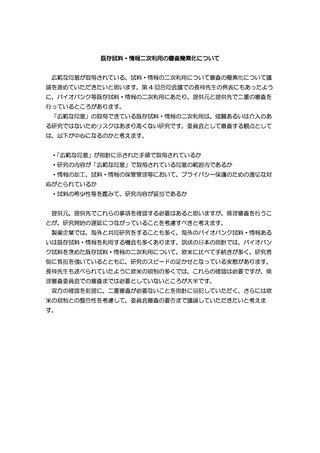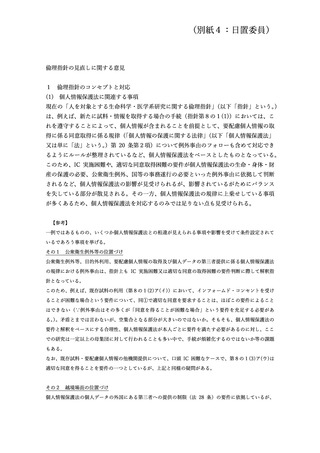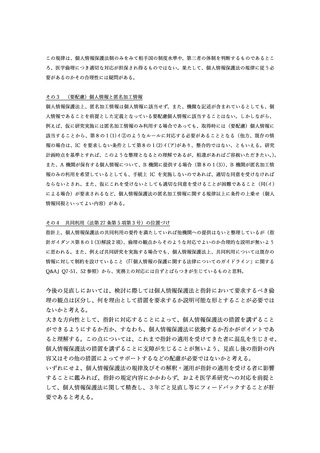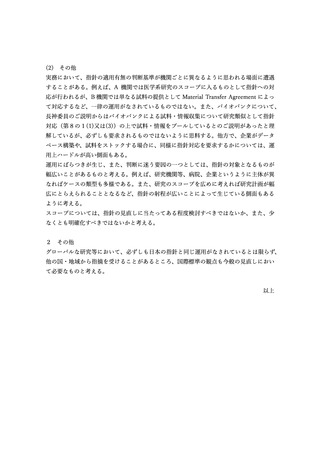よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2-1 : 第4回合同会議後の委員の追加意見 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63268.html |
| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第13回 9/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
と考えます。
「研究内容によっては倫理審査員会が認めた場合には簡素化が可能」という
のはあくまでも例外規定であって、原則としてそもそもこの項目を満たす必要がない研
究が存在することを明示すべきです。この説明項目に関する規制は現実には非常に重大
な影響を研究現場に及ぼしており、その結果、本来必要ない研究でも膨大な説明項目が
書かれる傾向が既にあり、ここについてはガイダンスではなく本文で明示して頂きたい
と思います(そうしなければ侵襲・介入研究と結局は同じように扱われてしまいます)。
2
「当該既存試料を用いなければ研究の実施が困難」要件の拡大(5 枚目の 2 つ目の*)
・これも規制強化とみなされる可能性が高いと考えます。もともと試料と情報を区別し、
試料の利用に関しては同意原則を強く利かせることを意図としてきた指針の考え方の
反映であり、新たに同意を得て使えるなら既存試料を同意なく使用すべきではない、と
いう発想で設けられた要件のため、今回のようにオプトアウトを原則とする場合には考
えにくい要件になっています。今でもガイダンスには解釈として「新たに試料を取得し、
解析等を行うことでは当該研究の実施が困難である場合」と書かれており、一般的には
希少疾患などの限定的な場合にのみ許容されると解して運用されてきたと思います。そ
のため、例えば、自施設の過去のカルテ情報を解析するだけの研究の場合、これに該当
するとは言い難く、事実上の規制強化を帰結する可能性が高いと考えます(例えば、こ
れから来る患者から同意を得て情報を利用できるのであればオプトアウト不可だと判
断されてしまう)。今回オプトアウトを原則とするのであれば、この要件は引き続き試料
に限定するか、削除するかで検討して頂く必要があると思います。
・なお、資料の 4 枚目の「正しい利用目的」であるかどうか関しては、研究方法や研究目
的の妥当性を倫理審査委員会が審査していることがそもそも担保しているはずですの
で、その意味で倫理審査が適切にされることが重要であり、この要件の適用範囲を広げ
ることは不必要だと考えます(今回、5 枚目には倫理審査委員会のあり方についても検
討すると書かれており、また、基本方針に患者・市民の視点を考慮することが追記され
るのであれば、なおさら研究者にとっては研究の意義が厳しく問われることになるので、
その点でも一定の対応は取れているものと思います)。
3
介入研究における同意免除や同意手続きの簡略化の明確化
・これは資料には明記されていない点ですが、最初の意見出しでもお伝えしたように、個
人情報保護法と直接関係しない同意に関する議論が過去 10 年間ほぼ扱われておらず、
現場で課題になっていることが十分に汲み取られていないと感じています。特に近年、
普及・実装科学への注目が高まり、行動経済学的な手法を用いた医学研究も増大してい
ることに伴い、医薬品や医療機器以外を用いた介入研究が次第に増えており、倫理審査
等においてこうした研究の扱いが難しい場合があることを経験しています。
・一つ目は急性期医療における同意免除(第 8 の 7)です。当日発言したように、指針ガ
2
「研究内容によっては倫理審査員会が認めた場合には簡素化が可能」という
のはあくまでも例外規定であって、原則としてそもそもこの項目を満たす必要がない研
究が存在することを明示すべきです。この説明項目に関する規制は現実には非常に重大
な影響を研究現場に及ぼしており、その結果、本来必要ない研究でも膨大な説明項目が
書かれる傾向が既にあり、ここについてはガイダンスではなく本文で明示して頂きたい
と思います(そうしなければ侵襲・介入研究と結局は同じように扱われてしまいます)。
2
「当該既存試料を用いなければ研究の実施が困難」要件の拡大(5 枚目の 2 つ目の*)
・これも規制強化とみなされる可能性が高いと考えます。もともと試料と情報を区別し、
試料の利用に関しては同意原則を強く利かせることを意図としてきた指針の考え方の
反映であり、新たに同意を得て使えるなら既存試料を同意なく使用すべきではない、と
いう発想で設けられた要件のため、今回のようにオプトアウトを原則とする場合には考
えにくい要件になっています。今でもガイダンスには解釈として「新たに試料を取得し、
解析等を行うことでは当該研究の実施が困難である場合」と書かれており、一般的には
希少疾患などの限定的な場合にのみ許容されると解して運用されてきたと思います。そ
のため、例えば、自施設の過去のカルテ情報を解析するだけの研究の場合、これに該当
するとは言い難く、事実上の規制強化を帰結する可能性が高いと考えます(例えば、こ
れから来る患者から同意を得て情報を利用できるのであればオプトアウト不可だと判
断されてしまう)。今回オプトアウトを原則とするのであれば、この要件は引き続き試料
に限定するか、削除するかで検討して頂く必要があると思います。
・なお、資料の 4 枚目の「正しい利用目的」であるかどうか関しては、研究方法や研究目
的の妥当性を倫理審査委員会が審査していることがそもそも担保しているはずですの
で、その意味で倫理審査が適切にされることが重要であり、この要件の適用範囲を広げ
ることは不必要だと考えます(今回、5 枚目には倫理審査委員会のあり方についても検
討すると書かれており、また、基本方針に患者・市民の視点を考慮することが追記され
るのであれば、なおさら研究者にとっては研究の意義が厳しく問われることになるので、
その点でも一定の対応は取れているものと思います)。
3
介入研究における同意免除や同意手続きの簡略化の明確化
・これは資料には明記されていない点ですが、最初の意見出しでもお伝えしたように、個
人情報保護法と直接関係しない同意に関する議論が過去 10 年間ほぼ扱われておらず、
現場で課題になっていることが十分に汲み取られていないと感じています。特に近年、
普及・実装科学への注目が高まり、行動経済学的な手法を用いた医学研究も増大してい
ることに伴い、医薬品や医療機器以外を用いた介入研究が次第に増えており、倫理審査
等においてこうした研究の扱いが難しい場合があることを経験しています。
・一つ目は急性期医療における同意免除(第 8 の 7)です。当日発言したように、指針ガ
2