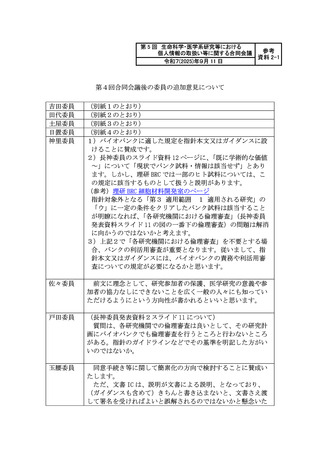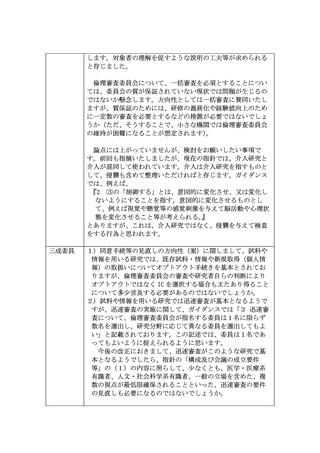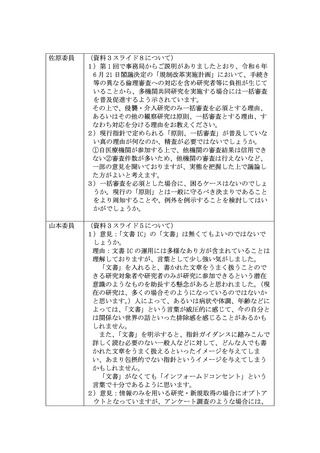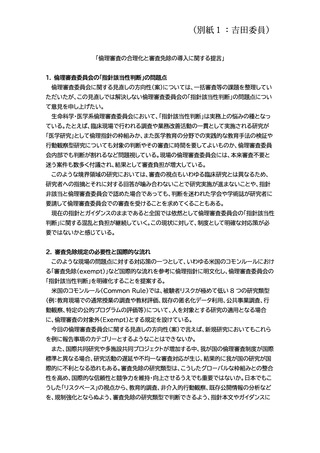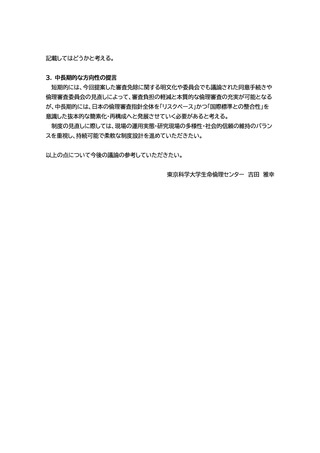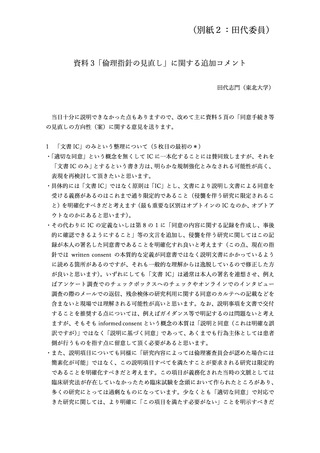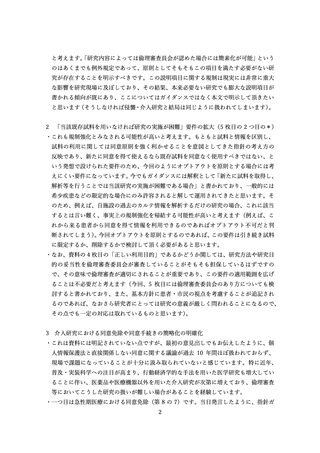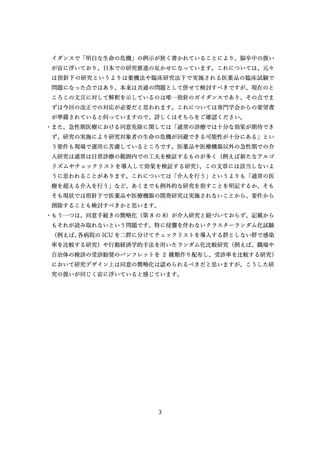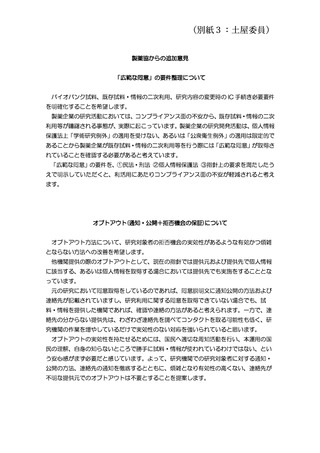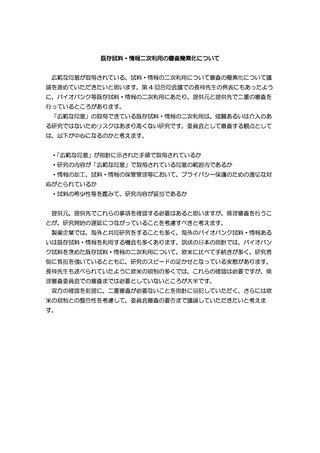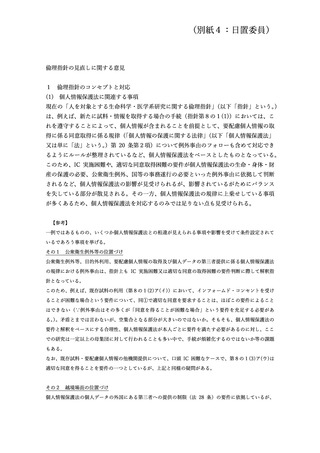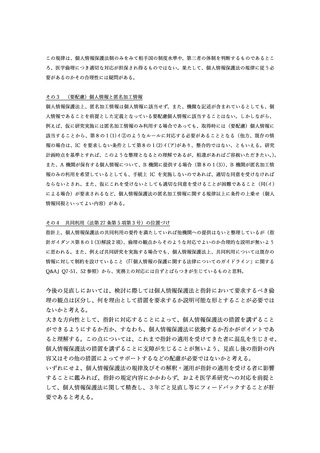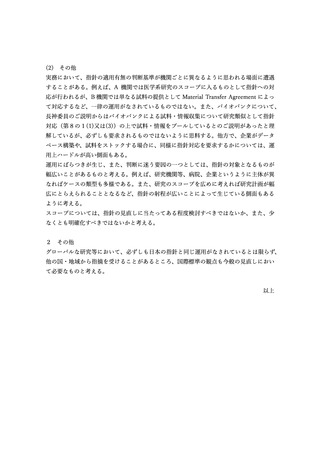よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2-1 : 第4回合同会議後の委員の追加意見 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63268.html |
| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第13回 9/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
この規律は、個人情報保護法制のみをみて相手国の制度水準や、第三者の体制を判断するものであるとこ
ろ、医学倫理につき適切な対応が担保され得るものではない。果たして、個人情報保護法の規律に従う必
要があるのかその合理性には疑問がある。
その3 (要配慮)個人情報と匿名加工情報
個人情報保護法上、匿名加工情報は個人情報に該当せず、また、機微な記述が含まれているとしても、個
人情報であることを前提とした定義となっている要配慮個人情報に該当することはない。しかしながら、
例えば、仮に研究実施には匿名加工情報のみ利用する場合であっても、取得時には(要配慮)個人情報に
該当することから、第8の1(1)イ②のようなルールに対応する必要があることとなる(他方、既存の情
報の場合は、IC を要求しない条件として第8の1(2)イ(ア)があり、整合的ではない、ともいえる。研究
計画時点を基準とすれば、このような整理となるとの理解であるが、相違があればご容赦いただきたい。)。
また、A 機関が保有する個人情報について、B 機関に提供する場合(第8の1(3))
、B 機関が匿名加工情
報のみの利用を希望しているとしても、手続上 IC を実施しないのであれば、適切な同意を受けなければ
ならないとされ、また、仮にこれを受けないとしても適切な同意を受けることが困難であること(同(イ)
による場合)が要求されるなど、個人情報保護法の匿名加工情報に関する規律以上に条件の上乗せ(個人
情報同視といってよい内容)がある。
その4 共同利用(法第 27 条第 5 項第 3 号)の位置づけ
指針上、個人情報保護法の共同利用の要件を満たしていれば他機関への提供はないと整理しているが(指
針ガイダンス第8の1(3)解説2項)、倫理の観点からそのような対応でよいのか合理的な説明が無いよう
に思われる。また、例えば共同研究を実施する場合でも、個人情報保護法上、共同利用については既存の
情報に対して制約を設けていること(『「
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関する
Q&A』Q7-51、52 参照)から、実務上の対応には自ずとばらつきが生じているものと思料。
今後の見直しにおいては、検討に際しては個人情報保護法と指針において要求するべき倫
理の観点は区分し、何を理由として措置を要求するか説明可能な形とすることが必要では
ないかと考える。
大きな方向性として、指針に対応することによって、個人情報保護法の措置を講ずること
ができるようにするか否か、すなわち、個人情報保護法に依拠するか否かがポイントであ
ると理解する。この点については、これまで指針の適用を受けてきた者に混乱を生じさせ、
個人情報保護法の措置を講ずることに支障が生じることが無いよう、見直し後の指針の内
容又はその他の措置によってサポートするなどの配慮が必要ではないかと考える。
いずれにせよ、個人情報保護法の規律及びその解釈・運用が指針の適用を受ける者に影響
することに鑑みれば、指針の規定内容にかかわらず、およそ医学系研究への対応を前提と
して、個人情報保護法に関して精査し、3年ごと見直し等にフィードバックすることが肝
要であると考える。
ろ、医学倫理につき適切な対応が担保され得るものではない。果たして、個人情報保護法の規律に従う必
要があるのかその合理性には疑問がある。
その3 (要配慮)個人情報と匿名加工情報
個人情報保護法上、匿名加工情報は個人情報に該当せず、また、機微な記述が含まれているとしても、個
人情報であることを前提とした定義となっている要配慮個人情報に該当することはない。しかしながら、
例えば、仮に研究実施には匿名加工情報のみ利用する場合であっても、取得時には(要配慮)個人情報に
該当することから、第8の1(1)イ②のようなルールに対応する必要があることとなる(他方、既存の情
報の場合は、IC を要求しない条件として第8の1(2)イ(ア)があり、整合的ではない、ともいえる。研究
計画時点を基準とすれば、このような整理となるとの理解であるが、相違があればご容赦いただきたい。)。
また、A 機関が保有する個人情報について、B 機関に提供する場合(第8の1(3))
、B 機関が匿名加工情
報のみの利用を希望しているとしても、手続上 IC を実施しないのであれば、適切な同意を受けなければ
ならないとされ、また、仮にこれを受けないとしても適切な同意を受けることが困難であること(同(イ)
による場合)が要求されるなど、個人情報保護法の匿名加工情報に関する規律以上に条件の上乗せ(個人
情報同視といってよい内容)がある。
その4 共同利用(法第 27 条第 5 項第 3 号)の位置づけ
指針上、個人情報保護法の共同利用の要件を満たしていれば他機関への提供はないと整理しているが(指
針ガイダンス第8の1(3)解説2項)、倫理の観点からそのような対応でよいのか合理的な説明が無いよう
に思われる。また、例えば共同研究を実施する場合でも、個人情報保護法上、共同利用については既存の
情報に対して制約を設けていること(『「
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関する
Q&A』Q7-51、52 参照)から、実務上の対応には自ずとばらつきが生じているものと思料。
今後の見直しにおいては、検討に際しては個人情報保護法と指針において要求するべき倫
理の観点は区分し、何を理由として措置を要求するか説明可能な形とすることが必要では
ないかと考える。
大きな方向性として、指針に対応することによって、個人情報保護法の措置を講ずること
ができるようにするか否か、すなわち、個人情報保護法に依拠するか否かがポイントであ
ると理解する。この点については、これまで指針の適用を受けてきた者に混乱を生じさせ、
個人情報保護法の措置を講ずることに支障が生じることが無いよう、見直し後の指針の内
容又はその他の措置によってサポートするなどの配慮が必要ではないかと考える。
いずれにせよ、個人情報保護法の規律及びその解釈・運用が指針の適用を受ける者に影響
することに鑑みれば、指針の規定内容にかかわらず、およそ医学系研究への対応を前提と
して、個人情報保護法に関して精査し、3年ごと見直し等にフィードバックすることが肝
要であると考える。