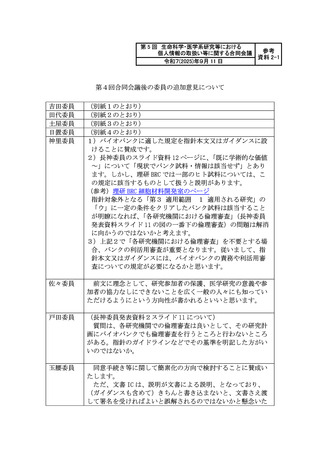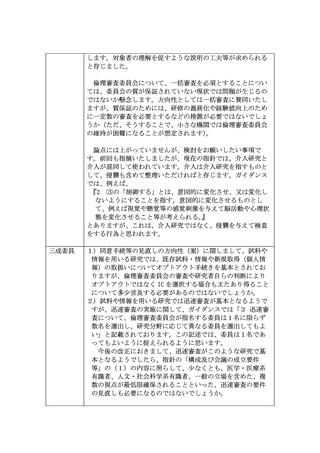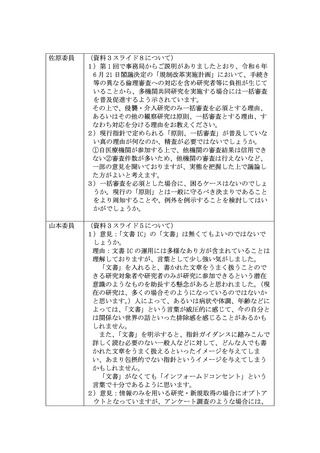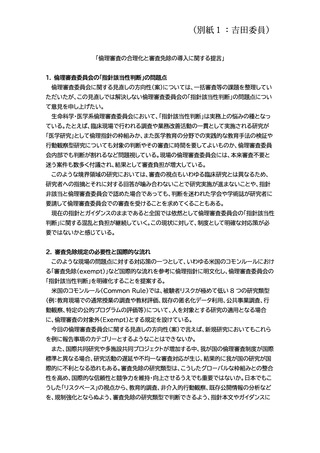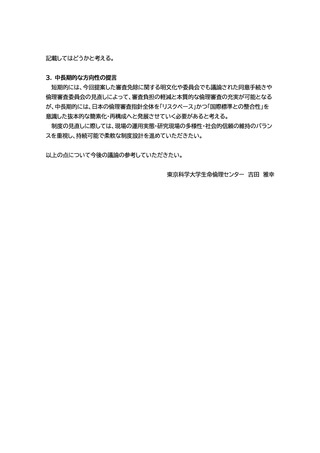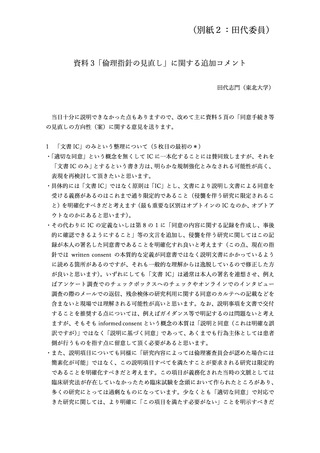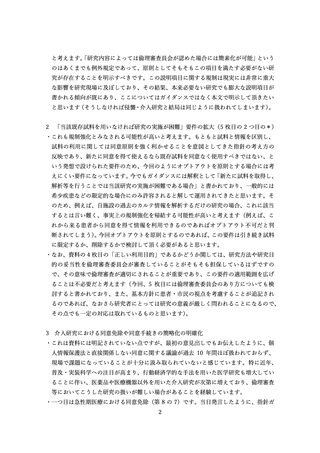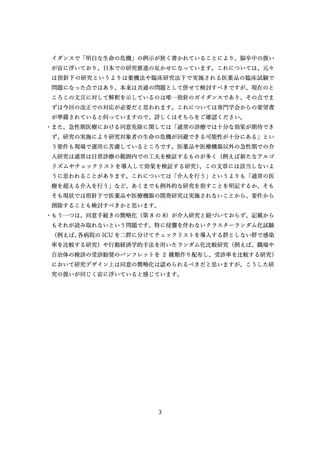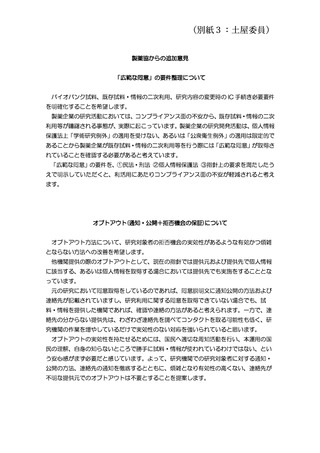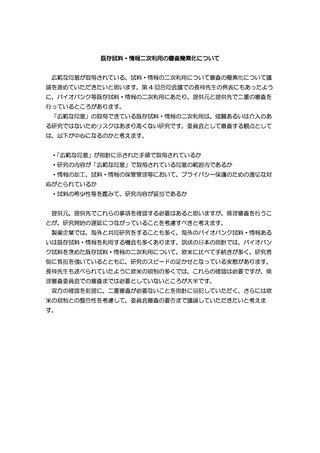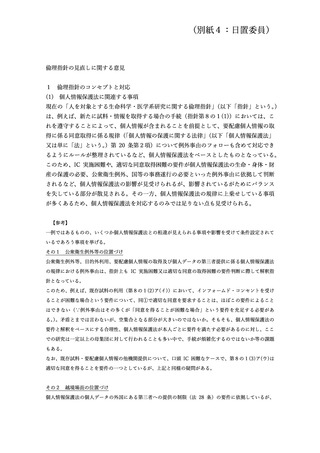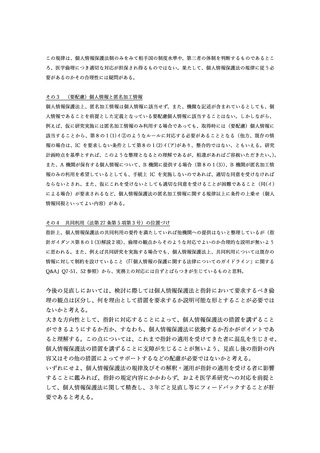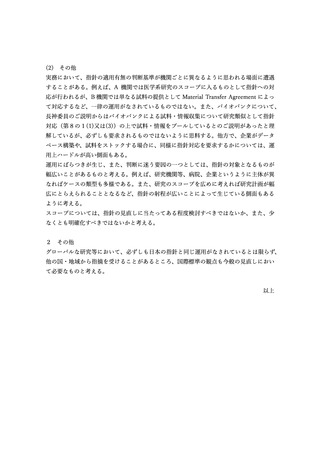よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2-1 : 第4回合同会議後の委員の追加意見 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63268.html |
| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第13回 9/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(別紙1:吉田委員)
「倫理審査の合理化と審査免除の導入に関する提言」
1. 倫理審査委員会の「指針該当性判断」の問題点
倫理審査委員会に関する見直しの方向性(案)については、一括審査等の課題を整理してい
ただいたが、この見直しでは解決しない倫理審査委員会の「指針該当性判断」の問題点につい
て意見を申し上げたい。
生命科学・医学系倫理審査委員会において、「指針該当性判断」は実務上の悩みの種となっ
ている。たとえば、臨床現場で行われる調査や業務改善活動の一貫として実施される研究が
「医学研究」として倫理指針の枠組みか、また医学教育の分野での実践的な教育手法の検証や
行動観察型研究についても対象の判断やその審査に時間を要してよいものか、倫理審査委員
会内部でも判断が割れるなど問題視している。現場の倫理審査委員会には、本来審査不要と
迷う案件も数多く付議され、結果として審査負担が増大している。
このような境界領域の研究においては、審査の視点もいわゆる臨床研究とは異なるため、
研究者への指摘とそれに対する回答が噛み合わないことで研究実施が進まないことや、指針
非該当と倫理審査委員会で認めた場合であっても、判断を迷われた学会や学術誌が研究者に
要請して倫理審査委員会での審査を受けることを求めてくることもある。
現在の指針とガイダンスのままであると全国では依然として倫理審査委員会の「指針該当性
判断」に関する混乱と負担が継続していく。この現状に対して、制度として明確な対応策が必
要ではないかと感じている。
2. 審査免除規定の必要性と国際的な流れ
このような現場の問題点に対する対応策の一つとして、いわゆる米国のコモンルールにおけ
る「審査免除(exempt)」など国際的な流れを参考に倫理指針に明文化し、倫理審査委員会の
「指針該当性判断」を明確化することを提案する。
米国のコモンルール(Common Rule)では、被験者リスクが極めて低い 8 つの研究類型
(例:教育現場での通常授業の調査や教材評価、既存の匿名化データ利用、公共事業調査、行
動観察、特定の公的プログラムの評価等)について、人を対象とする研究の適用となる場合
に、倫理審査の対象外(Exempt)とする規定を設けている。
今回の倫理審査委員会に関する見直しの方向性(案)で言えば、新規研究においてもこれら
を例に報告事項のカテゴリーとするようなことはできないか。
また、国際共同研究や多施設共同プロジェクトが増加する中、我が国の倫理審査制度が国際
標準と異なる場合、研究活動の遅延や不均一な審査対応が生じ、結果的に我が国の研究が国
際的に不利となる恐れもある。審査免除の研究類型は、こうしたグローバルな枠組みとの整合
性を高め、国際的な信頼性と競争力を維持・向上させるうえでも重要ではないか。日本でもこ
うした「リスクベース」の視点から、教育的調査、非介入的行動観察、既存公開情報の分析など
を、規制強化とならぬよう、審査免除の研究類型で判断できるよう、指針本文やガイダンスに
「倫理審査の合理化と審査免除の導入に関する提言」
1. 倫理審査委員会の「指針該当性判断」の問題点
倫理審査委員会に関する見直しの方向性(案)については、一括審査等の課題を整理してい
ただいたが、この見直しでは解決しない倫理審査委員会の「指針該当性判断」の問題点につい
て意見を申し上げたい。
生命科学・医学系倫理審査委員会において、「指針該当性判断」は実務上の悩みの種となっ
ている。たとえば、臨床現場で行われる調査や業務改善活動の一貫として実施される研究が
「医学研究」として倫理指針の枠組みか、また医学教育の分野での実践的な教育手法の検証や
行動観察型研究についても対象の判断やその審査に時間を要してよいものか、倫理審査委員
会内部でも判断が割れるなど問題視している。現場の倫理審査委員会には、本来審査不要と
迷う案件も数多く付議され、結果として審査負担が増大している。
このような境界領域の研究においては、審査の視点もいわゆる臨床研究とは異なるため、
研究者への指摘とそれに対する回答が噛み合わないことで研究実施が進まないことや、指針
非該当と倫理審査委員会で認めた場合であっても、判断を迷われた学会や学術誌が研究者に
要請して倫理審査委員会での審査を受けることを求めてくることもある。
現在の指針とガイダンスのままであると全国では依然として倫理審査委員会の「指針該当性
判断」に関する混乱と負担が継続していく。この現状に対して、制度として明確な対応策が必
要ではないかと感じている。
2. 審査免除規定の必要性と国際的な流れ
このような現場の問題点に対する対応策の一つとして、いわゆる米国のコモンルールにおけ
る「審査免除(exempt)」など国際的な流れを参考に倫理指針に明文化し、倫理審査委員会の
「指針該当性判断」を明確化することを提案する。
米国のコモンルール(Common Rule)では、被験者リスクが極めて低い 8 つの研究類型
(例:教育現場での通常授業の調査や教材評価、既存の匿名化データ利用、公共事業調査、行
動観察、特定の公的プログラムの評価等)について、人を対象とする研究の適用となる場合
に、倫理審査の対象外(Exempt)とする規定を設けている。
今回の倫理審査委員会に関する見直しの方向性(案)で言えば、新規研究においてもこれら
を例に報告事項のカテゴリーとするようなことはできないか。
また、国際共同研究や多施設共同プロジェクトが増加する中、我が国の倫理審査制度が国際
標準と異なる場合、研究活動の遅延や不均一な審査対応が生じ、結果的に我が国の研究が国
際的に不利となる恐れもある。審査免除の研究類型は、こうしたグローバルな枠組みとの整合
性を高め、国際的な信頼性と競争力を維持・向上させるうえでも重要ではないか。日本でもこ
うした「リスクベース」の視点から、教育的調査、非介入的行動観察、既存公開情報の分析など
を、規制強化とならぬよう、審査免除の研究類型で判断できるよう、指針本文やガイダンスに