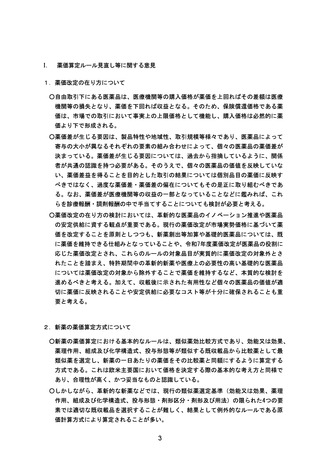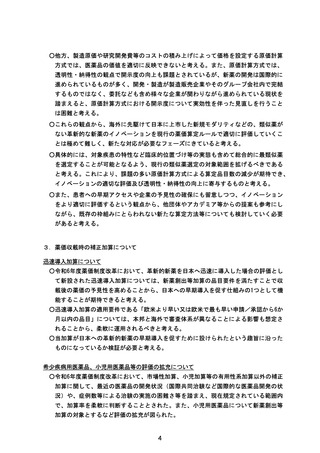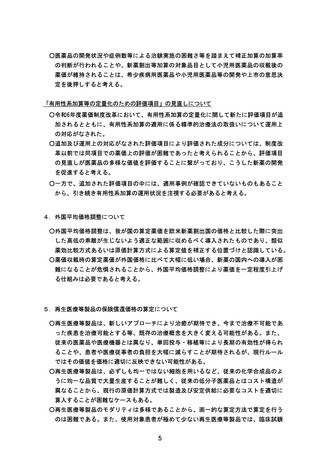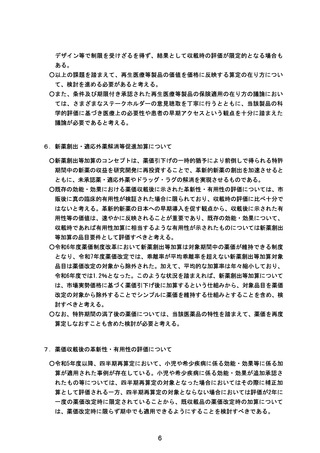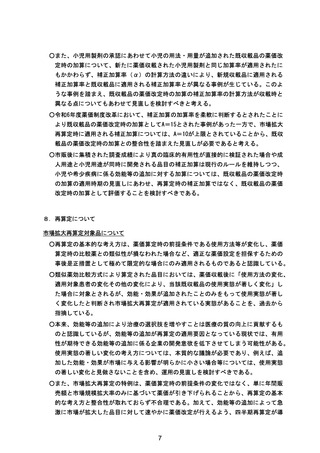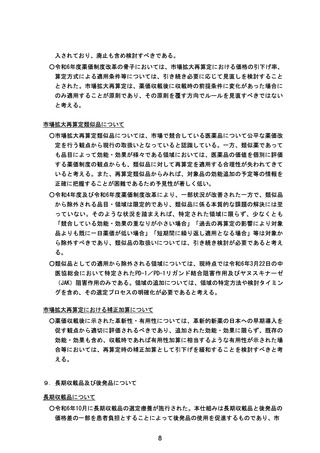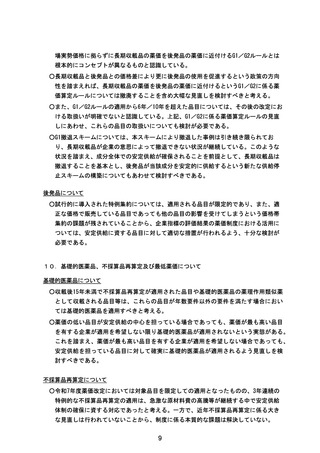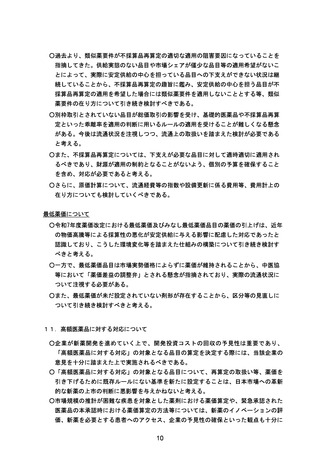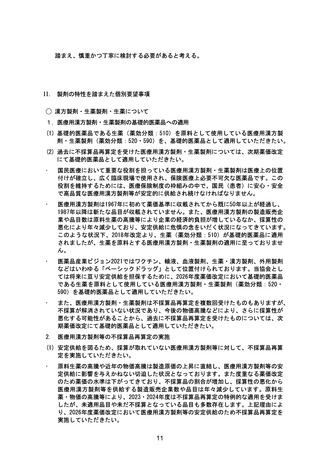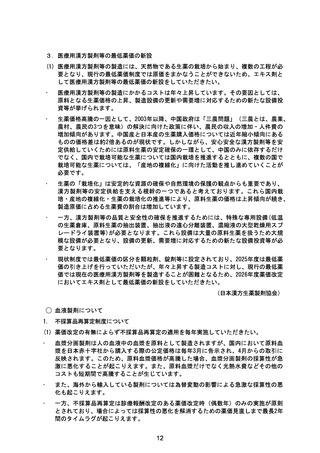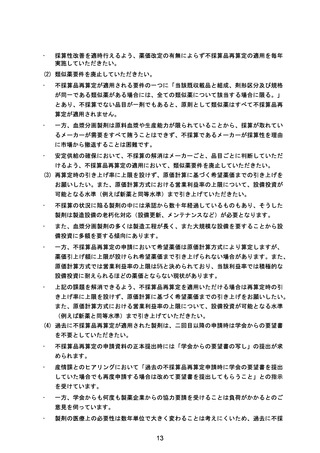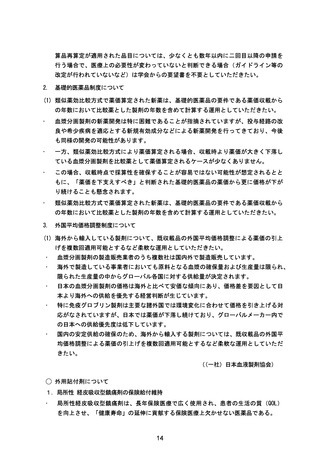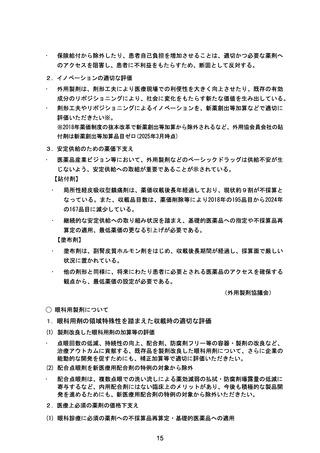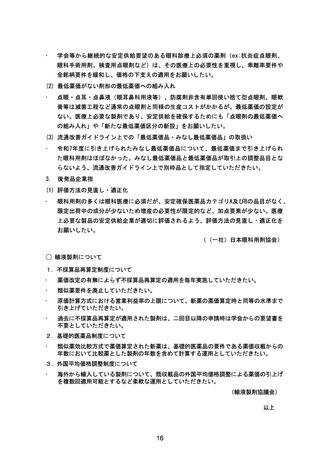よむ、つかう、まなぶ。
薬-1別添[404KB] (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59378.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第236回 7/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3.医療用漢方製剤等の最低薬価の新設
(1) 医療用漢方製剤等の製造には、天然物である生薬の栽培から始まり、複数の工程が必
要となり、現行の最低薬価制度では原価をまかなうことができないため、エキス剤と
して医療用漢方製剤等の最低薬価の新設をしていただきたい。
医療用漢方製剤等の製造にかかるコストは年々上昇しています。その要因としては、
原料となる生薬価格の上昇、製造設備の更新や需要増に対応するための新たな設備投
資等が挙げられます。
生薬価格高騰の一因として、2003年以降、中国政府は「三農問題」(三農とは、農業、
農村、農民の3つを意味)の解決に向けた政策に伴い、農民の収入の増加・人件費の
増加傾向があります。中国産と日本産の生薬購入価格については近年縮小傾向にある
ものの価格差は約2倍あるのが現状です。しかしながら、安心安全な漢方製剤等を安
定供給していくためには原料生薬の安定確保の一環として、中国のみに依存するだけ
でなく、国内で栽培可能な生薬については国内栽培を推進するとともに、複数の国で
栽培可能な生薬については、「産地の複線化」に向けた活動を推し進めていくことが
必要です。
生薬の「栽培化」は安定的な資源の確保や自然環境の保護の観点からも重要であり、
漢方製剤等の安定供給を支える根幹の一つであると考えております。これら国内栽
培・産地の複線化・生薬の栽培化の推進等により、原料生薬の価格は上昇傾向が続き、
製造原価に占める生薬費の割合は増加しています。
一方、漢方製剤等の品質と安全性の確保を推進するためには、特殊な専用設備(低温
の生薬倉庫、原料生薬の抽出装置、抽出液の遠心分離装置、濃縮液の大型乾燥用スプ
レードライ装置等)が必要となります。これら設備は大量の原料生薬を扱うため大規
模な設備が必要となり、設備の更新、需要増に対応するための新たな設備投資等が必
要となります。
現状制度では最低薬価の区分を顆粒剤、錠剤等に設定されており、2025年度は最低薬
価の引き上げを行っていただいたが、年々上昇する製造コストに対し、現行の最低薬
価では現在の医療用漢方製剤等を製造することが困難となるため、2026年度薬価改定
においてエキス剤として最低薬価の新設をしていただきたい。
(日本漢方生薬製剤協会)
◯ 血液製剤について
1. 不採算品再算定制度について
(1) 薬価改定の有無によらず不採算品再算定の適用を毎年実施していただきたい。
血漿分画製剤は人の血液中の血漿を原料として製造されますが、国内において原料血
漿を日本赤十字社から購入する際の公定価格は毎年3月に告示され、4月からの取引に
反映されます。このため、原料血漿価格が高騰した場合、血漿分画製剤の採算性が急
激に悪化することが起こりえます。また、原料血漿だけでなく光熱水費などその他の
コストも短期間で高騰することが生じています。
また、海外から輸入している製剤については為替変動の影響による急激な採算性の悪
化も起こりえます。
一方、不採算品再算定は診療報酬改定のある薬価改定時(偶数年)のみの実施が原則
とされており、場合によっては採算性の悪化を解消するための薬価見直しまで最長2年
間のタイムラグが起こりえます。
12
(1) 医療用漢方製剤等の製造には、天然物である生薬の栽培から始まり、複数の工程が必
要となり、現行の最低薬価制度では原価をまかなうことができないため、エキス剤と
して医療用漢方製剤等の最低薬価の新設をしていただきたい。
医療用漢方製剤等の製造にかかるコストは年々上昇しています。その要因としては、
原料となる生薬価格の上昇、製造設備の更新や需要増に対応するための新たな設備投
資等が挙げられます。
生薬価格高騰の一因として、2003年以降、中国政府は「三農問題」(三農とは、農業、
農村、農民の3つを意味)の解決に向けた政策に伴い、農民の収入の増加・人件費の
増加傾向があります。中国産と日本産の生薬購入価格については近年縮小傾向にある
ものの価格差は約2倍あるのが現状です。しかしながら、安心安全な漢方製剤等を安
定供給していくためには原料生薬の安定確保の一環として、中国のみに依存するだけ
でなく、国内で栽培可能な生薬については国内栽培を推進するとともに、複数の国で
栽培可能な生薬については、「産地の複線化」に向けた活動を推し進めていくことが
必要です。
生薬の「栽培化」は安定的な資源の確保や自然環境の保護の観点からも重要であり、
漢方製剤等の安定供給を支える根幹の一つであると考えております。これら国内栽
培・産地の複線化・生薬の栽培化の推進等により、原料生薬の価格は上昇傾向が続き、
製造原価に占める生薬費の割合は増加しています。
一方、漢方製剤等の品質と安全性の確保を推進するためには、特殊な専用設備(低温
の生薬倉庫、原料生薬の抽出装置、抽出液の遠心分離装置、濃縮液の大型乾燥用スプ
レードライ装置等)が必要となります。これら設備は大量の原料生薬を扱うため大規
模な設備が必要となり、設備の更新、需要増に対応するための新たな設備投資等が必
要となります。
現状制度では最低薬価の区分を顆粒剤、錠剤等に設定されており、2025年度は最低薬
価の引き上げを行っていただいたが、年々上昇する製造コストに対し、現行の最低薬
価では現在の医療用漢方製剤等を製造することが困難となるため、2026年度薬価改定
においてエキス剤として最低薬価の新設をしていただきたい。
(日本漢方生薬製剤協会)
◯ 血液製剤について
1. 不採算品再算定制度について
(1) 薬価改定の有無によらず不採算品再算定の適用を毎年実施していただきたい。
血漿分画製剤は人の血液中の血漿を原料として製造されますが、国内において原料血
漿を日本赤十字社から購入する際の公定価格は毎年3月に告示され、4月からの取引に
反映されます。このため、原料血漿価格が高騰した場合、血漿分画製剤の採算性が急
激に悪化することが起こりえます。また、原料血漿だけでなく光熱水費などその他の
コストも短期間で高騰することが生じています。
また、海外から輸入している製剤については為替変動の影響による急激な採算性の悪
化も起こりえます。
一方、不採算品再算定は診療報酬改定のある薬価改定時(偶数年)のみの実施が原則
とされており、場合によっては採算性の悪化を解消するための薬価見直しまで最長2年
間のタイムラグが起こりえます。
12