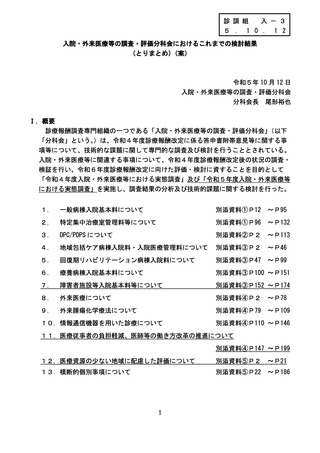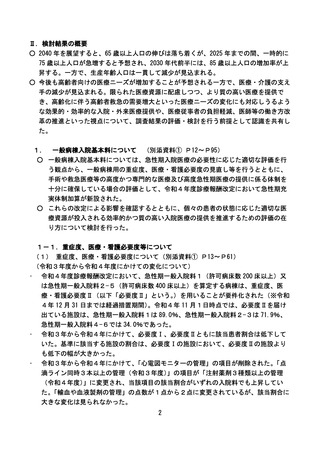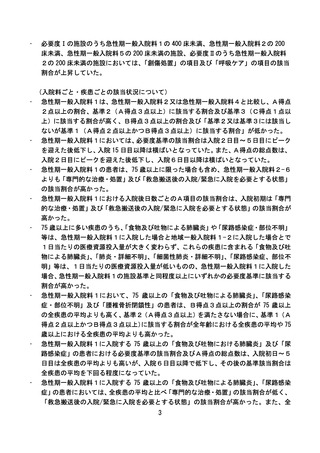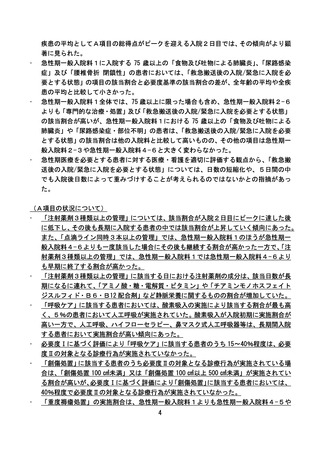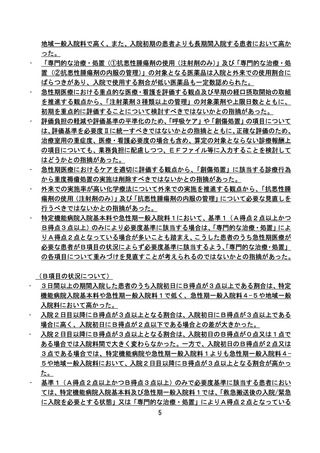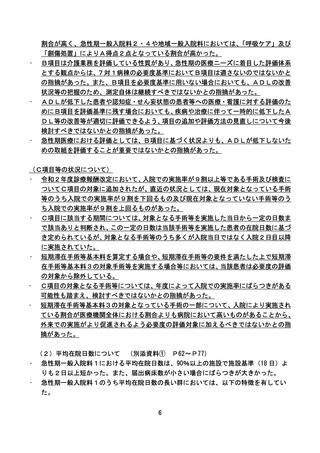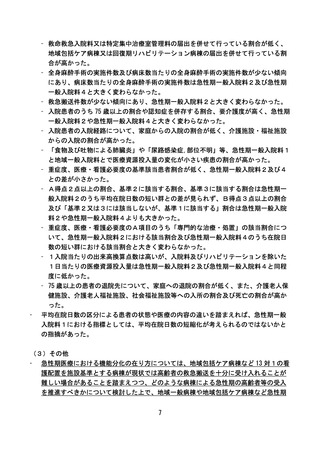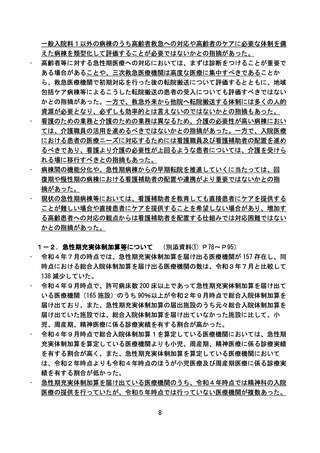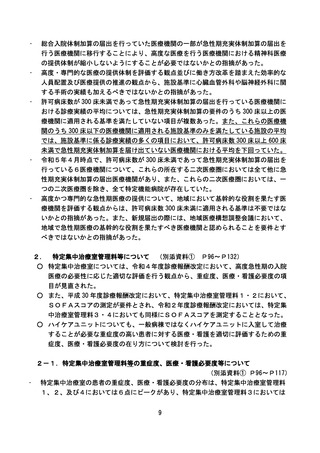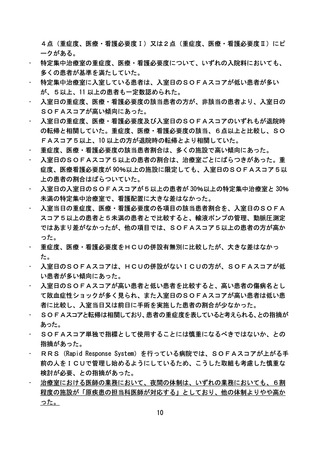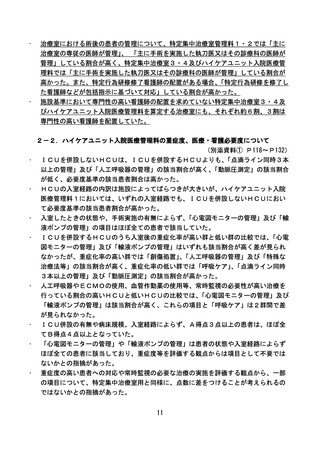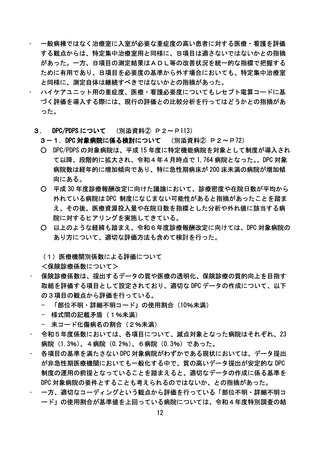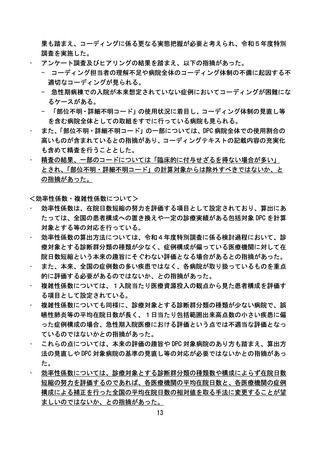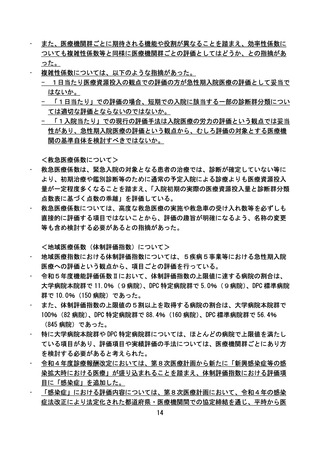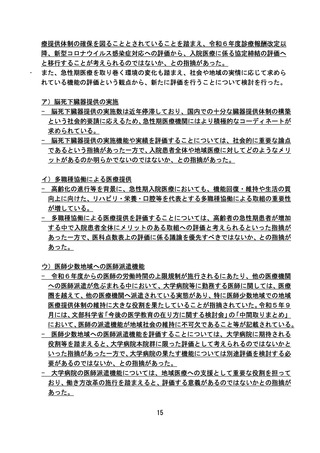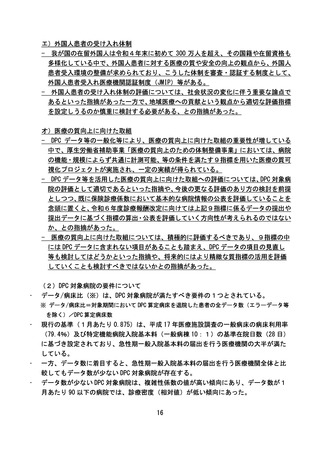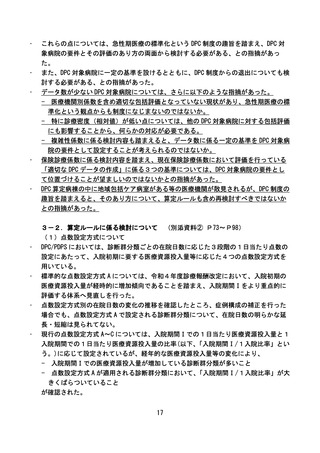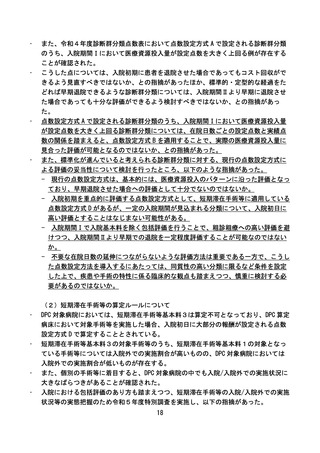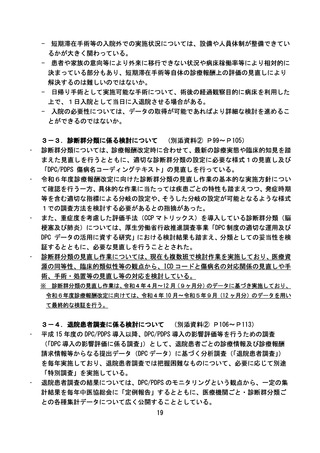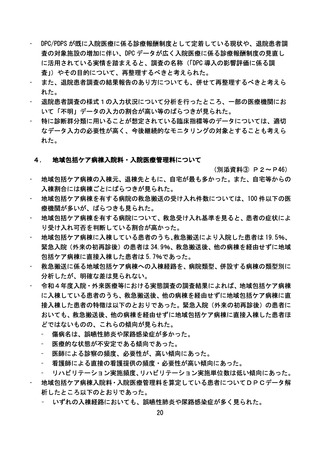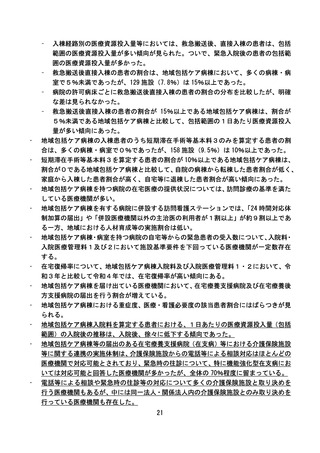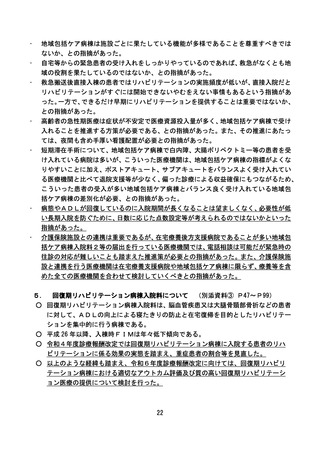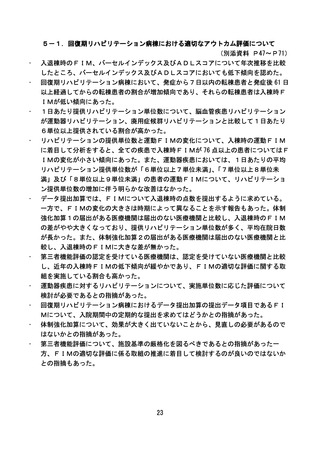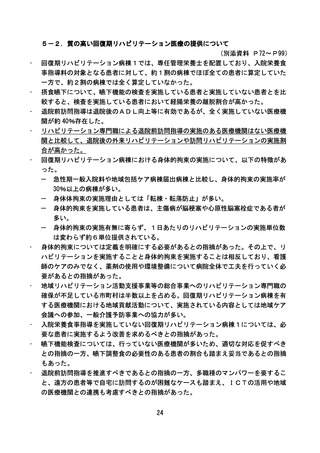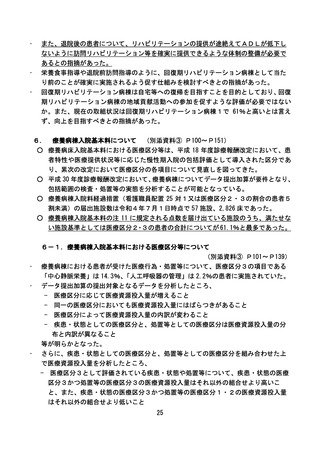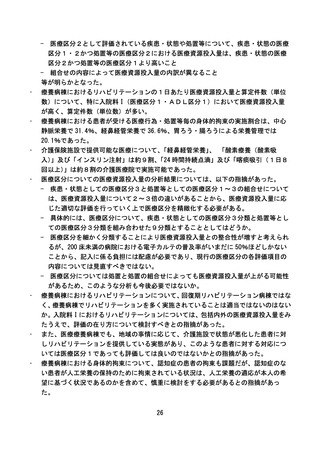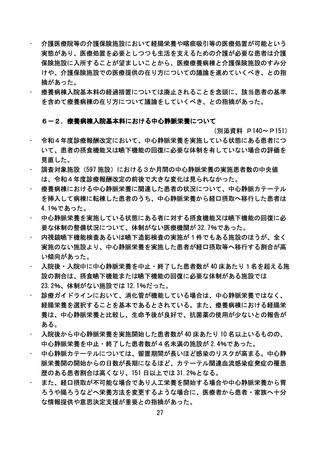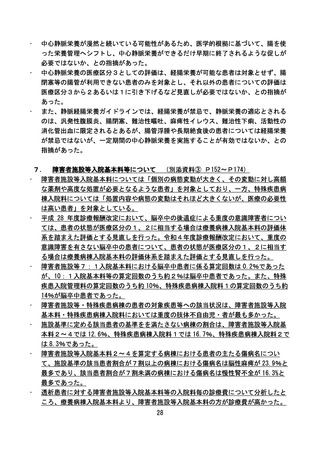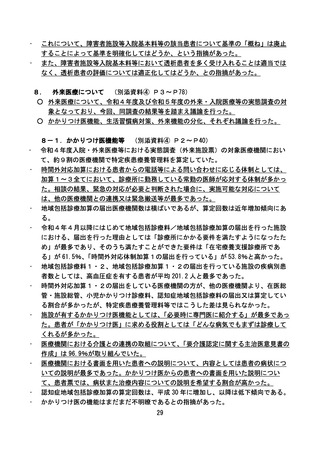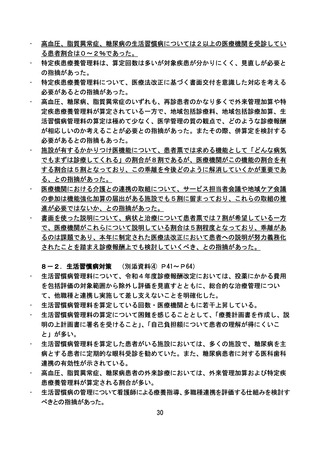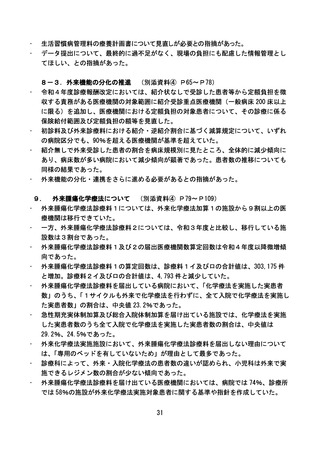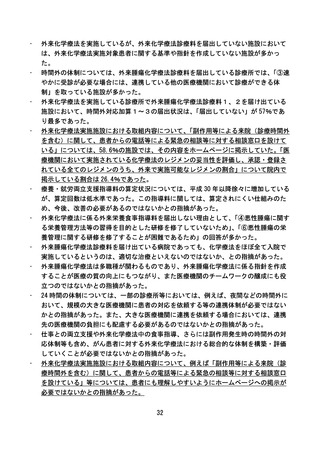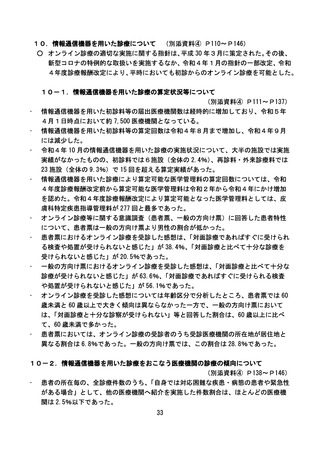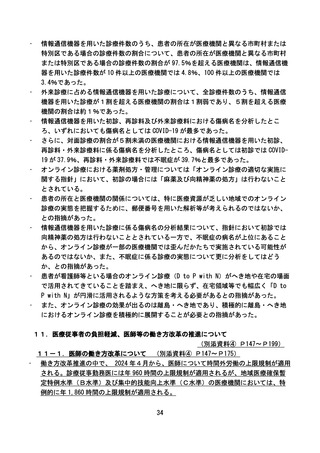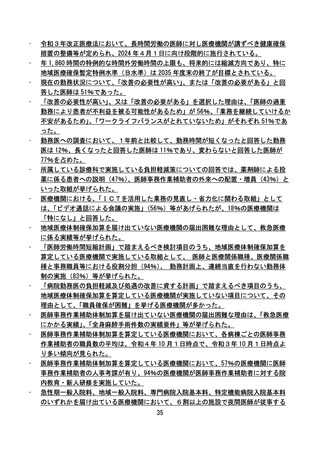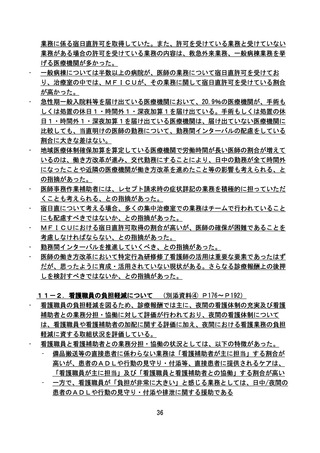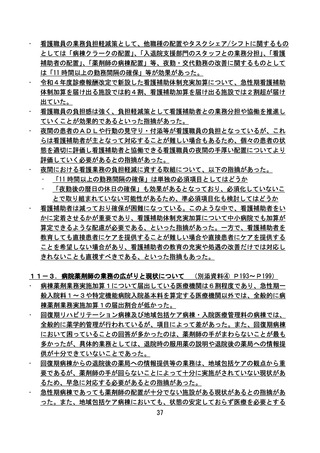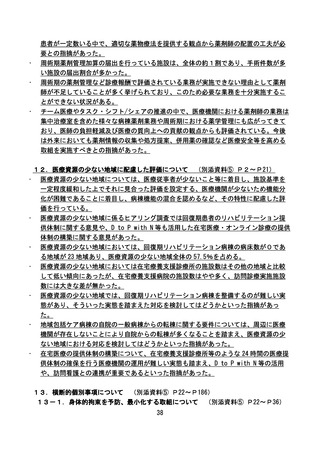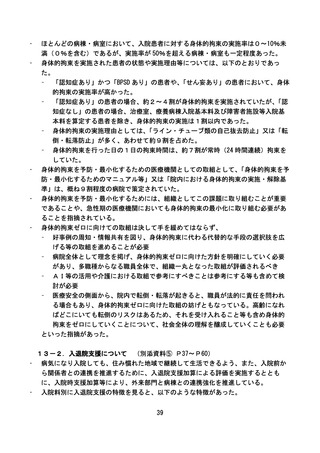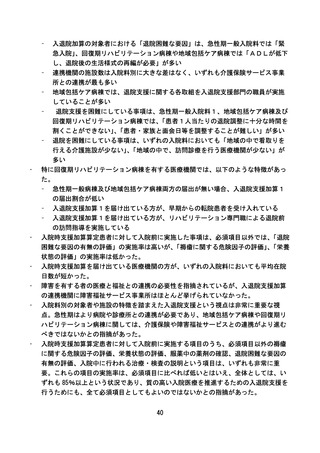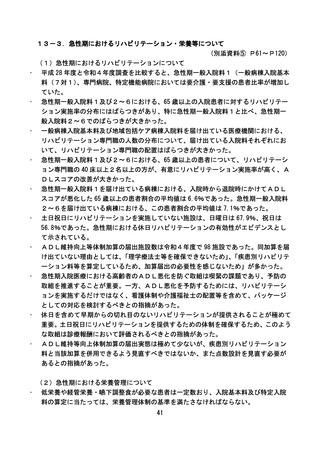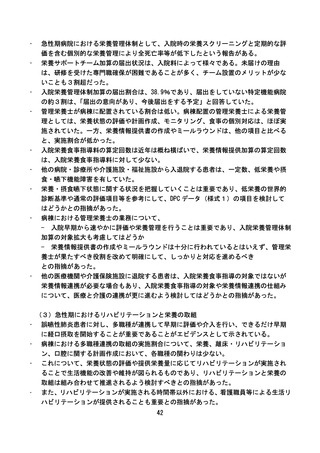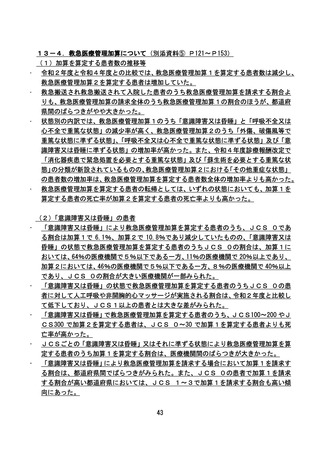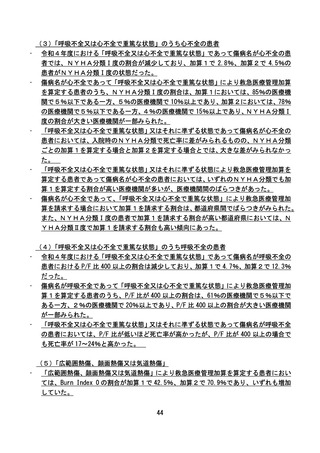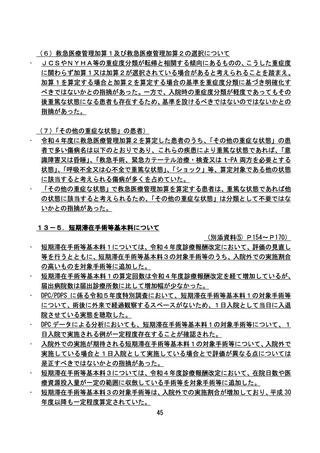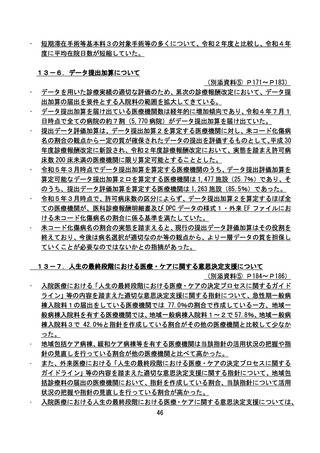よむ、つかう、まなぶ。
入-3入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討結果(とりまとめ)(案) (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00217.html |
| 出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第10回 10/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ほとんどの病棟・病室において、入院患者に対する身体的拘束の実施率は0~10%未
満(0%を含む)であるが、実施率が 50%を超える病棟・病室も一定程度あった。
身体的拘束を実施された患者の状態や実施理由等については、以下のとおりであっ
た。
– 「認知症あり」かつ「BPSD あり」の患者や、「せん妄あり」の患者において、身体
的拘束の実施率が高かった。
– 「認知症あり」の患者の場合、約2~4割が身体的拘束を実施されていたが、「認
知症なし」の患者の場合、治療室、療養病棟入院基本料及び障害者施設等入院基
本料を算定する患者を除き、身体的拘束の実施は1割以内であった。
– 身体的拘束の実施理由としては、「ライン・チューブ類の自己抜去防止」又は「転
倒・転落防止」が多く、あわせて約9割を占めた。
–
身体的拘束を行った日の1日の拘束時間は、約7割が常時(24 時間連続)拘束を
していた。
身体的拘束を予防・最小化するための医療機関としての取組として、「身体的拘束を予
防・最小化するためのマニュアル等」又は「院内における身体的拘束の実施・解除基
準」は、概ね9割程度の病院で策定されていた。
身体的拘束を予防・最小化するためには、組織としてこの課題に取り組むことが重要
であることや、急性期の医療機関においても身体的拘束の最小化に取り組む必要があ
ることを指摘されている。
身体的拘束ゼロに向けての取組は決して手を緩めてはならず、
– 好事例の周知・情報共有を図り、身体的拘束に代わる代替的な手段の選択肢を広
げる等の取組を進めることが必要
– 病院全体として理念を掲げ、身体的拘束ゼロに向けた方針を明確にしていく必要
があり、多職種からなる職員全体で、組織一丸となった取組が評価されるべき
– AI等の活用や介護における取組で参考にすべきことは参考にする等も含めて検
討が必要
– 医療安全の側面から、院内で転倒・転落が起きると、職員が法的に責任を問われ
る場合もあり、身体的拘束ゼロに向けた取組の妨げともなっている。高齢になれ
ばどこにいても転倒のリスクはあるため、それを受け入れること等も含め身体的
拘束をゼロにしていくことについて、社会全体の理解を醸成していくことも必要
といった指摘があった。
13-2.入退院支援について (別添資料⑤ P37~P60)
病気になり入院しても、住み慣れた地域で継続して生活できるよう、また、入院前か
ら関係者との連携を推進するために、入退院支援加算による評価を実施するととも
に、入院時支援加算等により、外来部門と病棟との連携強化を推進している。
入院料別に入退院支援の特徴を見ると、以下のような特徴があった。
39
ほとんどの病棟・病室において、入院患者に対する身体的拘束の実施率は0~10%未
満(0%を含む)であるが、実施率が 50%を超える病棟・病室も一定程度あった。
身体的拘束を実施された患者の状態や実施理由等については、以下のとおりであっ
た。
– 「認知症あり」かつ「BPSD あり」の患者や、「せん妄あり」の患者において、身体
的拘束の実施率が高かった。
– 「認知症あり」の患者の場合、約2~4割が身体的拘束を実施されていたが、「認
知症なし」の患者の場合、治療室、療養病棟入院基本料及び障害者施設等入院基
本料を算定する患者を除き、身体的拘束の実施は1割以内であった。
– 身体的拘束の実施理由としては、「ライン・チューブ類の自己抜去防止」又は「転
倒・転落防止」が多く、あわせて約9割を占めた。
–
身体的拘束を行った日の1日の拘束時間は、約7割が常時(24 時間連続)拘束を
していた。
身体的拘束を予防・最小化するための医療機関としての取組として、「身体的拘束を予
防・最小化するためのマニュアル等」又は「院内における身体的拘束の実施・解除基
準」は、概ね9割程度の病院で策定されていた。
身体的拘束を予防・最小化するためには、組織としてこの課題に取り組むことが重要
であることや、急性期の医療機関においても身体的拘束の最小化に取り組む必要があ
ることを指摘されている。
身体的拘束ゼロに向けての取組は決して手を緩めてはならず、
– 好事例の周知・情報共有を図り、身体的拘束に代わる代替的な手段の選択肢を広
げる等の取組を進めることが必要
– 病院全体として理念を掲げ、身体的拘束ゼロに向けた方針を明確にしていく必要
があり、多職種からなる職員全体で、組織一丸となった取組が評価されるべき
– AI等の活用や介護における取組で参考にすべきことは参考にする等も含めて検
討が必要
– 医療安全の側面から、院内で転倒・転落が起きると、職員が法的に責任を問われ
る場合もあり、身体的拘束ゼロに向けた取組の妨げともなっている。高齢になれ
ばどこにいても転倒のリスクはあるため、それを受け入れること等も含め身体的
拘束をゼロにしていくことについて、社会全体の理解を醸成していくことも必要
といった指摘があった。
13-2.入退院支援について (別添資料⑤ P37~P60)
病気になり入院しても、住み慣れた地域で継続して生活できるよう、また、入院前か
ら関係者との連携を推進するために、入退院支援加算による評価を実施するととも
に、入院時支援加算等により、外来部門と病棟との連携強化を推進している。
入院料別に入退院支援の特徴を見ると、以下のような特徴があった。
39