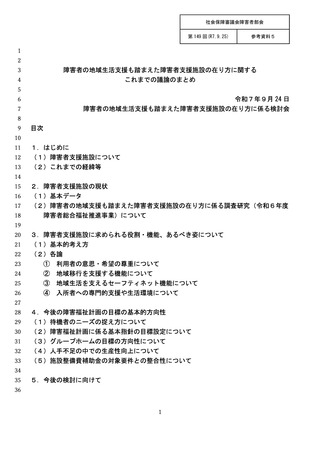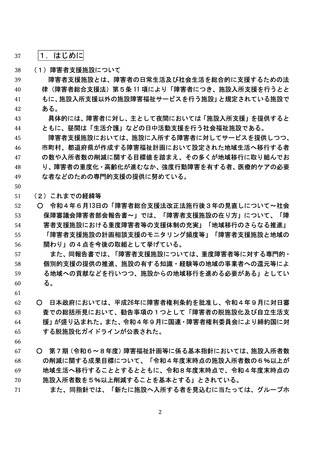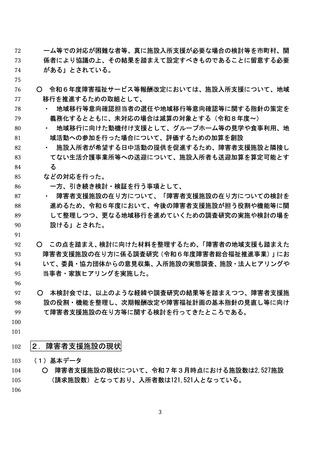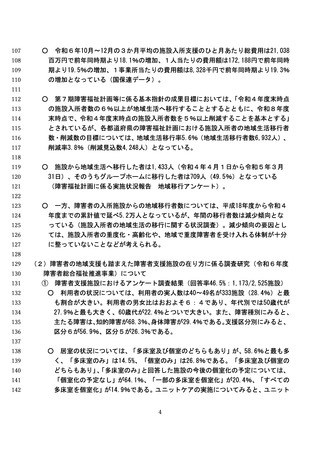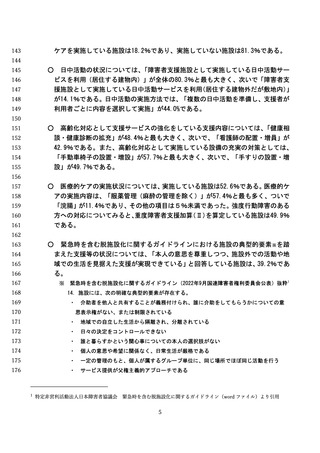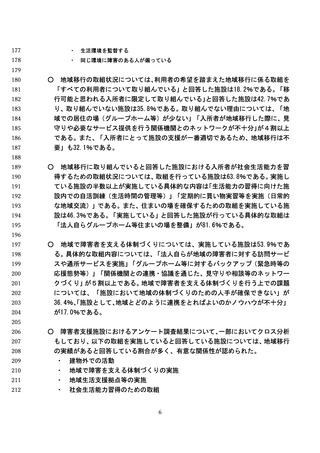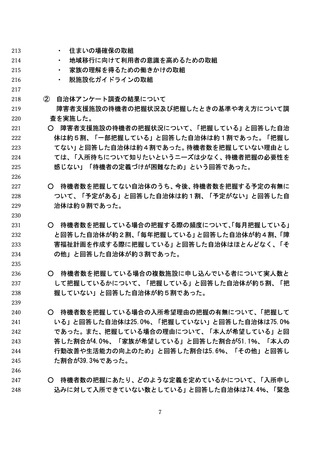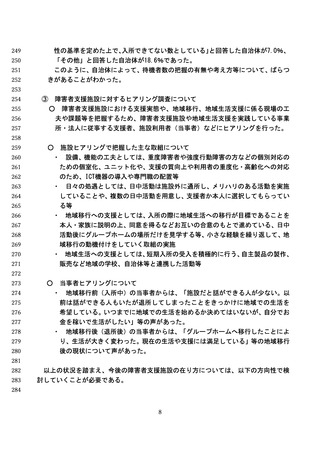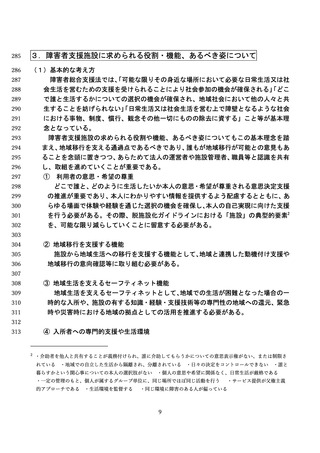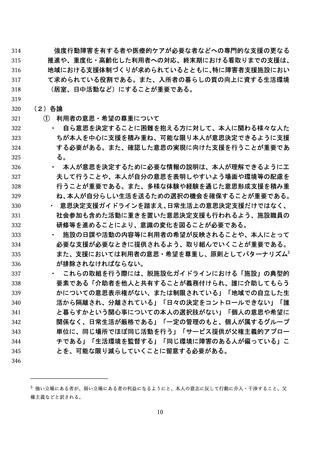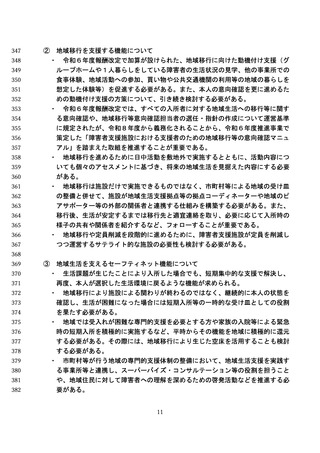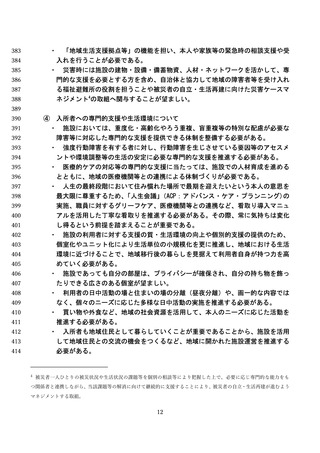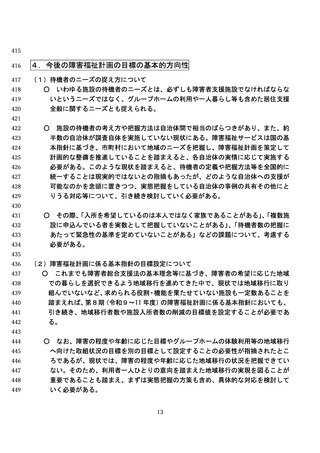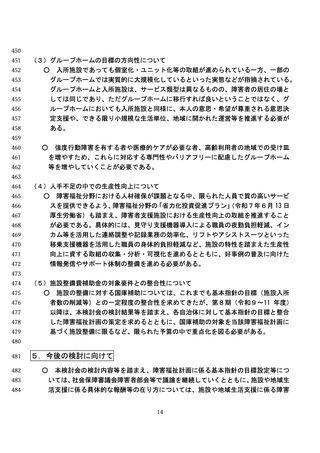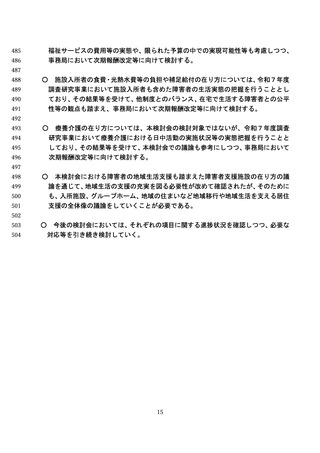よむ、つかう、まなぶ。
参考資料5 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関するこれまでの議論のまとめ (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
② 地域移行を支援する機能について
・ 令和6年度報酬改定で加算が設けられた、地域移行に向けた動機付け支援(グ
ループホームや1人暮らしをしている障害者の生活状況の見学、他の事業所での
食事体験、地域活動への参加、買い物や公共交通機関の利用等の地域の暮らしを
想定した体験等)を促進する必要がある。また、本人の意向確認を更に進めるた
めの動機付け支援の方策について、引き続き検討する必要がある。
・ 令和6年度報酬改定では、すべての入所者に対する地域生活への移行等に関す
る意向確認や、地域移行等意向確認担当者の選任・指針の作成について運営基準
に規定されたが、令和8年度から義務化されることから、令和6年度推進事業で
策定した「障害者支援施設における支援者のための地域移行等の意向確認マニュ
アル」を踏まえた取組を推進することが重要である。
・ 地域移行を進めるために日中活動を敷地外で実施するとともに、活動内容につ
いても個々のアセスメントに基づき、将来の地域生活を見据えた内容にする必要
がある。
・ 地域移行は施設だけで実施できるものではなく、市町村等による地域の受け皿
の整備と併せて、施設が地域生活支援拠点等の拠点コーディネーターや地域のピ
アサポーター等の外部の関係者と連携する仕組みを構築する必要がある。また、
移行後、生活が安定するまでは移行先と適宜連絡を取り、必要に応じて入所時の
様子の共有や関係者を紹介するなど、フォローすることが重要である。
・ 地域移行や定員削減を段階的に進めるために、障害者支援施設が定員を削減し
つつ運営するサテライト的な施設の必要性も検討する必要がある。
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
③ 地域生活を支えるセーフティネット機能について
・ 生活課題が生じたことにより入所した場合でも、短期集中的な支援で解決し、
再度、本人が選択した生活環境に戻るような機能が求められる。
・ 地域移行により施設による関わりが終わるのではなく、継続的に本人の状態を
確認し、生活が困難になった場合には短期入所等の一時的な受け皿としての役割
を果たす必要がある。
・ 地域では受入れが困難な専門的支援を必要とする方や家族の入院等による緊急
時の短期入所を積極的に実施するなど、平時からその機能を地域に積極的に還元
する必要がある。その際には、地域移行により生じた空床を活用することも検討
する必要がある。
・ 市町村等が行う地域の専門的支援体制の整備において、地域生活支援を実践す
る事業所等と連携し、スーパーバイズ・コンサルテーション等の役割を担うこと
や、地域住民に対して障害者への理解を深めるための啓発活動などを推進する必
要がある。
11
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
② 地域移行を支援する機能について
・ 令和6年度報酬改定で加算が設けられた、地域移行に向けた動機付け支援(グ
ループホームや1人暮らしをしている障害者の生活状況の見学、他の事業所での
食事体験、地域活動への参加、買い物や公共交通機関の利用等の地域の暮らしを
想定した体験等)を促進する必要がある。また、本人の意向確認を更に進めるた
めの動機付け支援の方策について、引き続き検討する必要がある。
・ 令和6年度報酬改定では、すべての入所者に対する地域生活への移行等に関す
る意向確認や、地域移行等意向確認担当者の選任・指針の作成について運営基準
に規定されたが、令和8年度から義務化されることから、令和6年度推進事業で
策定した「障害者支援施設における支援者のための地域移行等の意向確認マニュ
アル」を踏まえた取組を推進することが重要である。
・ 地域移行を進めるために日中活動を敷地外で実施するとともに、活動内容につ
いても個々のアセスメントに基づき、将来の地域生活を見据えた内容にする必要
がある。
・ 地域移行は施設だけで実施できるものではなく、市町村等による地域の受け皿
の整備と併せて、施設が地域生活支援拠点等の拠点コーディネーターや地域のピ
アサポーター等の外部の関係者と連携する仕組みを構築する必要がある。また、
移行後、生活が安定するまでは移行先と適宜連絡を取り、必要に応じて入所時の
様子の共有や関係者を紹介するなど、フォローすることが重要である。
・ 地域移行や定員削減を段階的に進めるために、障害者支援施設が定員を削減し
つつ運営するサテライト的な施設の必要性も検討する必要がある。
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
③ 地域生活を支えるセーフティネット機能について
・ 生活課題が生じたことにより入所した場合でも、短期集中的な支援で解決し、
再度、本人が選択した生活環境に戻るような機能が求められる。
・ 地域移行により施設による関わりが終わるのではなく、継続的に本人の状態を
確認し、生活が困難になった場合には短期入所等の一時的な受け皿としての役割
を果たす必要がある。
・ 地域では受入れが困難な専門的支援を必要とする方や家族の入院等による緊急
時の短期入所を積極的に実施するなど、平時からその機能を地域に積極的に還元
する必要がある。その際には、地域移行により生じた空床を活用することも検討
する必要がある。
・ 市町村等が行う地域の専門的支援体制の整備において、地域生活支援を実践す
る事業所等と連携し、スーパーバイズ・コンサルテーション等の役割を担うこと
や、地域住民に対して障害者への理解を深めるための啓発活動などを推進する必
要がある。
11