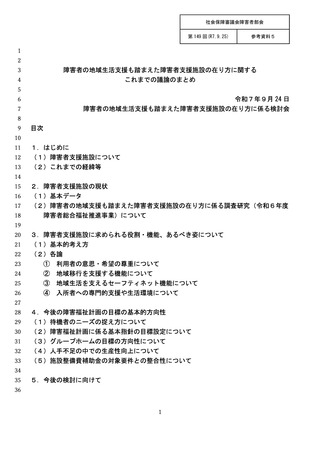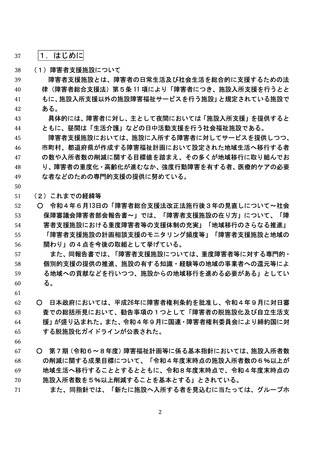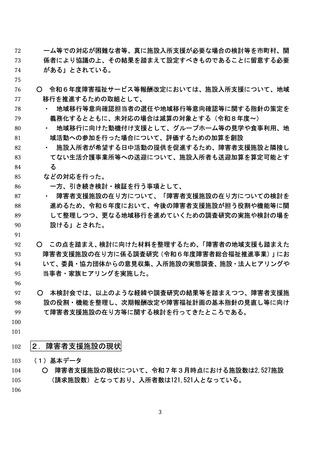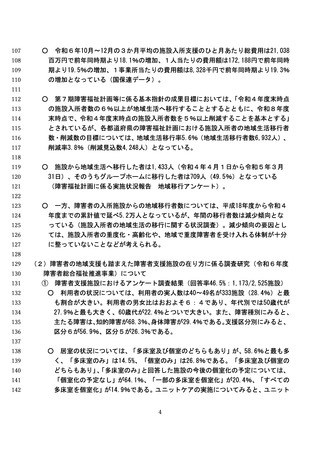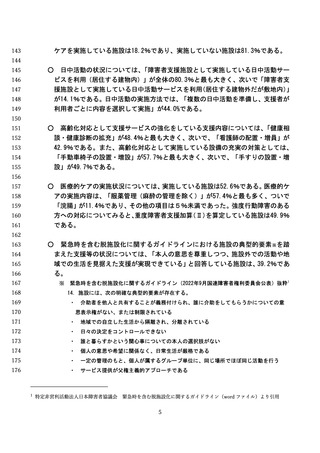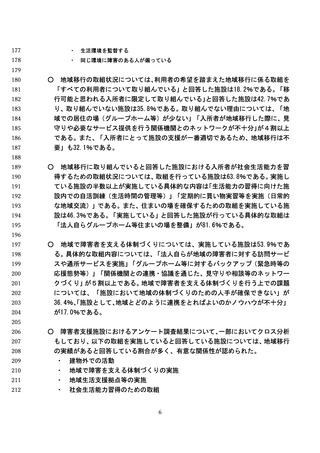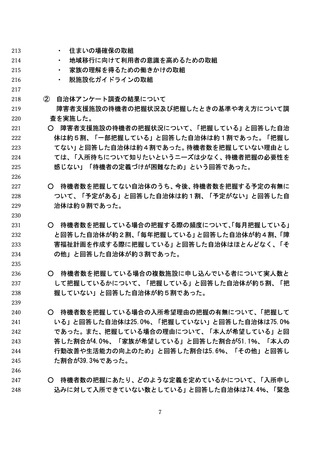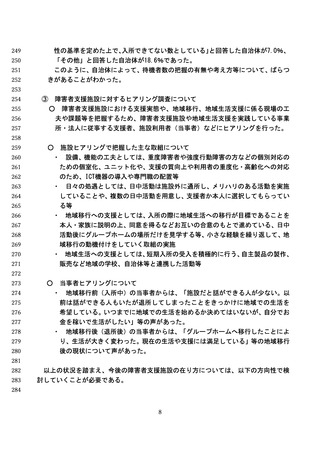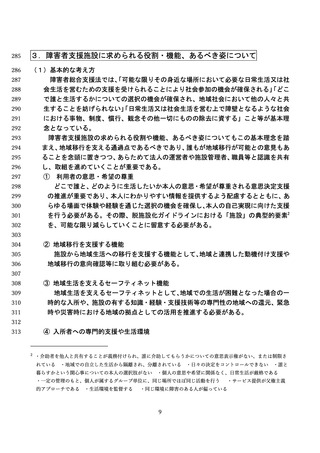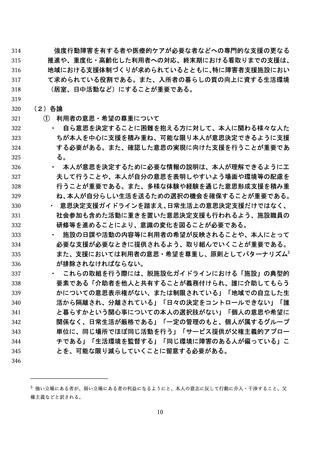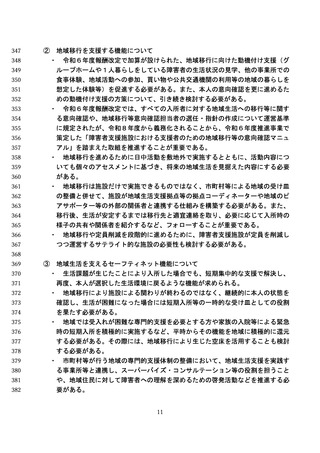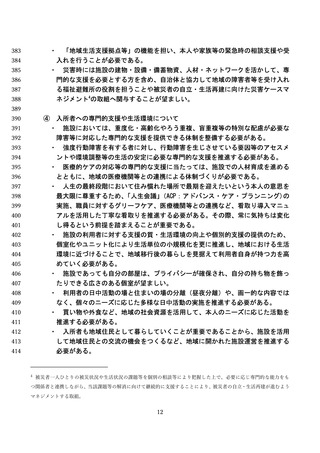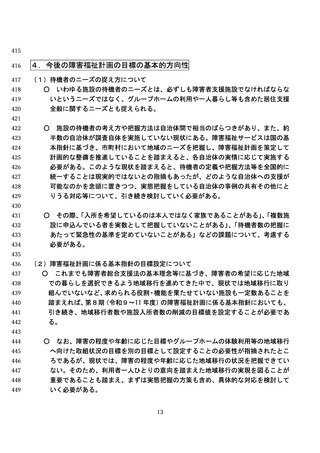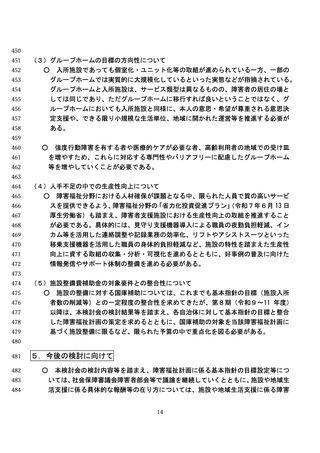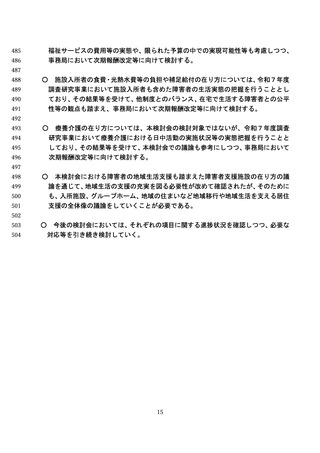よむ、つかう、まなぶ。
参考資料5 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関するこれまでの議論のまとめ (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者などへの専門的な支援の更なる
推進や、重度化・高齢化した利用者への対応、終末期における看取りまでの支援は、
地域における支援体制づくりが求められているとともに、特に障害者支援施設におい
て求められている役割である。また、入所者の暮らしの質の向上に資する生活環境
(居室、日中活動など)にすることが重要である。
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
(2)各論
① 利用者の意思・希望の尊重について
・ 自ら意思を決定することに困難を抱える方に対して、本人に関わる様々な人た
ちが本人を中心に支援を積み重ね、可能な限り本人が意思決定できるように支援
する必要がある。また、確認した意思の実現に向けた支援を行うことが重要であ
る。
・ 本人が意思を決定するために必要な情報の説明は、本人が理解できるように工
324
325
326
夫して行うことや、本人が自分の意思を表明しやすいよう場面や環境等の配慮を
行うことが重要である。また、多様な体験や経験を通じた意思形成支援を積み重
ね、本人が自分らしい生活を送るための選択の機会を確保することが重要である。
・ 意思決定支援ガイドラインを踏まえ、日常生活上の意思決定支援だけではなく、
社会参加も含めた活動に重きを置いた意思決定支援も行われるよう、施設職員の
研修等を進めることにより、意識の変化を図ることが必要である。
・ 施設の日課や活動の内容等に利用者の希望が反映されることや、本人にとって
327
328
329
330
331
332
333
必要な支援が必要なときに提供されるよう、取り組んでいくことが重要である。
また、支援においては利用者の意思・希望を尊重し、原則としてパターナリズム3
が排除されなければならない。
・ これらの取組を行う際には、脱施設化ガイドラインにおける「施設」の典型的
要素である「介助者を他人と共有することが義務付けられ、誰に介助してもらう
かについての意思表示権がない、または制限されている」「地域での自立した生
活から隔離され、分離されている」「日々の決定をコントロールできない」「誰
と暮らすかという関心事についての本人の選択肢がない」「個人の意思や希望に
関係なく、日常生活が厳格である」「一定の管理のもと、個人が属するグループ
単位に、同じ場所でほぼ同じ活動を行う」「サービス提供が父権主義的アプロー
チである」「生活環境を監督する」「同じ環境に障害のある人が偏っている」こ
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
とを、可能な限り減らしていくことに留意する必要がある。
345
346
3
強い立場にある者が、弱い立場にある者の利益になるようにと、本人の意志に反して行動に介入・干渉すること。父
権主義などと訳される。
10
推進や、重度化・高齢化した利用者への対応、終末期における看取りまでの支援は、
地域における支援体制づくりが求められているとともに、特に障害者支援施設におい
て求められている役割である。また、入所者の暮らしの質の向上に資する生活環境
(居室、日中活動など)にすることが重要である。
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
(2)各論
① 利用者の意思・希望の尊重について
・ 自ら意思を決定することに困難を抱える方に対して、本人に関わる様々な人た
ちが本人を中心に支援を積み重ね、可能な限り本人が意思決定できるように支援
する必要がある。また、確認した意思の実現に向けた支援を行うことが重要であ
る。
・ 本人が意思を決定するために必要な情報の説明は、本人が理解できるように工
324
325
326
夫して行うことや、本人が自分の意思を表明しやすいよう場面や環境等の配慮を
行うことが重要である。また、多様な体験や経験を通じた意思形成支援を積み重
ね、本人が自分らしい生活を送るための選択の機会を確保することが重要である。
・ 意思決定支援ガイドラインを踏まえ、日常生活上の意思決定支援だけではなく、
社会参加も含めた活動に重きを置いた意思決定支援も行われるよう、施設職員の
研修等を進めることにより、意識の変化を図ることが必要である。
・ 施設の日課や活動の内容等に利用者の希望が反映されることや、本人にとって
327
328
329
330
331
332
333
必要な支援が必要なときに提供されるよう、取り組んでいくことが重要である。
また、支援においては利用者の意思・希望を尊重し、原則としてパターナリズム3
が排除されなければならない。
・ これらの取組を行う際には、脱施設化ガイドラインにおける「施設」の典型的
要素である「介助者を他人と共有することが義務付けられ、誰に介助してもらう
かについての意思表示権がない、または制限されている」「地域での自立した生
活から隔離され、分離されている」「日々の決定をコントロールできない」「誰
と暮らすかという関心事についての本人の選択肢がない」「個人の意思や希望に
関係なく、日常生活が厳格である」「一定の管理のもと、個人が属するグループ
単位に、同じ場所でほぼ同じ活動を行う」「サービス提供が父権主義的アプロー
チである」「生活環境を監督する」「同じ環境に障害のある人が偏っている」こ
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
とを、可能な限り減らしていくことに留意する必要がある。
345
346
3
強い立場にある者が、弱い立場にある者の利益になるようにと、本人の意志に反して行動に介入・干渉すること。父
権主義などと訳される。
10