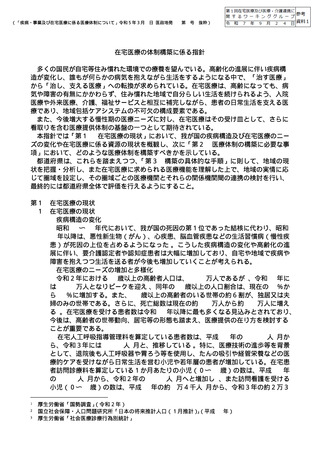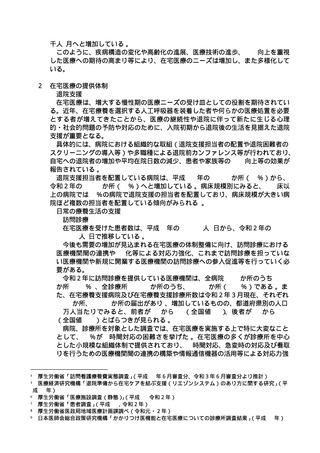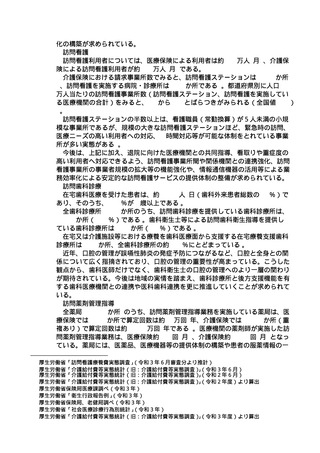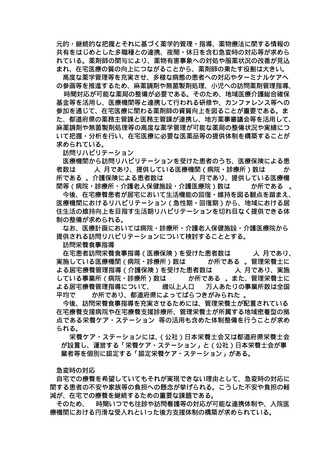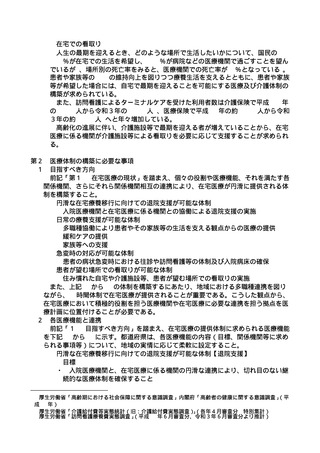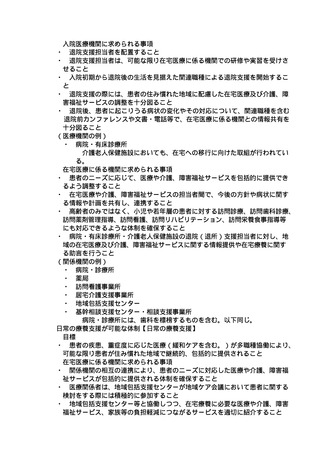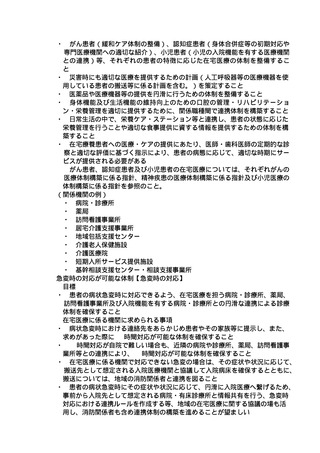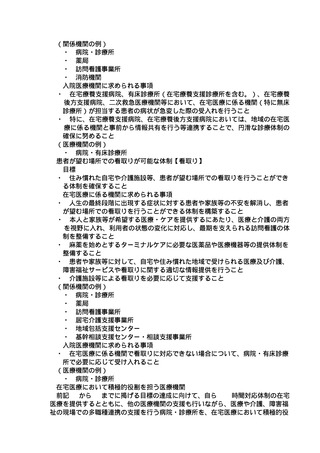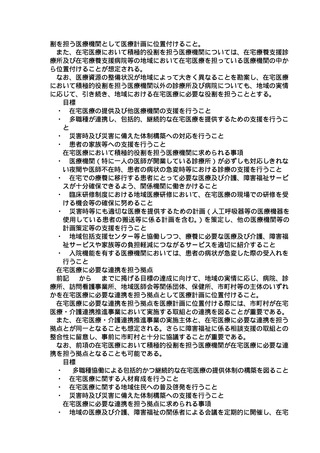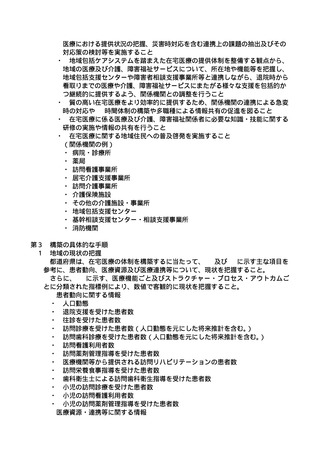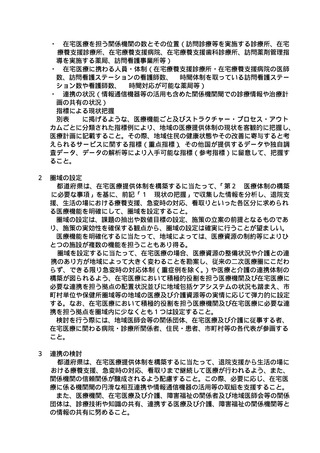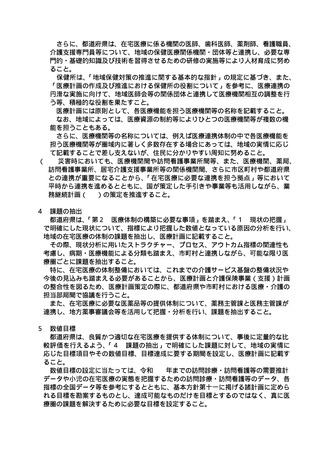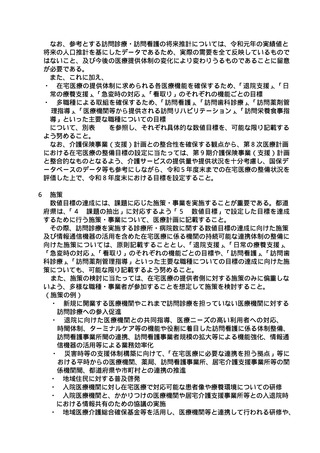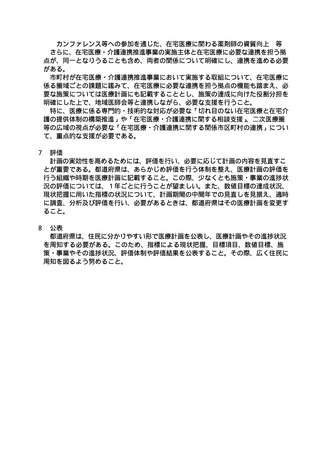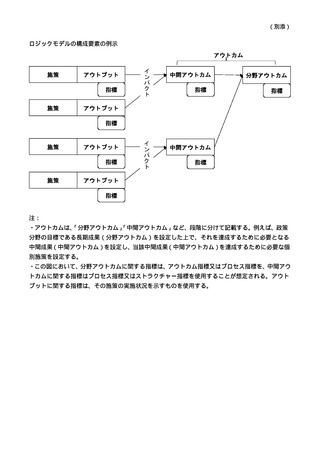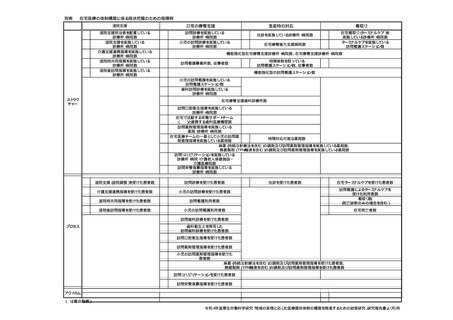よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 在宅医療の体制構築に係る指針 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63687.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第1回 9/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導、薬物療法に関する情報の
共有をはじめとした多職種との連携、夜間・休日を含む急変時の対応等が求めら
れている。薬剤師の関与により、薬物有害事象への対処や服薬状況の改善が見込
まれ、在宅医療の質の向上につながることから、薬剤師の果たす役割は大きい。
高度な薬学管理等を充実させ、多様な病態の患者への対応やターミナルケアへ
の参画等を推進するため、麻薬調剤や無菌製剤処理、小児への訪問薬剤管理指導、
24 時間対応が可能な薬局の整備が必要である。そのため、地域医療介護総合確保
基金等を活用し、医療機関等と連携して行われる研修や、カンファレンス等への
参加を通じて、在宅医療に関わる薬剤師の資質向上を図ることが重要である。ま
た、都道府県の薬務主管課と医務主管課が連携し、地方薬事審議会等を活用して、
麻薬調剤や無菌製剤処理等の高度な薬学管理が可能な薬局の整備状況や実績につ
いて把握・分析を行い、在宅医療に必要な医薬品等の提供体制を構築することが
求められている。
⑤ 訪問リハビリテーション
医療機関から訪問リハビリテーションを受けた患者のうち、医療保険による患
者数は 2,326 人/月であり、提供している医療機関(病院・診療所)数は 1,472 か
所である 8。介護保険による患者数は 135,700 人/月であり、提供している医療機
関等(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)数は 4,950 か所である 11。
今後、在宅療養患者が居宅において生活機能の回復・維持を図る観点を踏まえ、
医療機関におけるリハビリテーション(急性期・回復期)から、地域における居
住生活の維持向上を目指す生活期リハビリテーションを切れ目なく提供できる体
制の整備が求められる。
なお、医療計画においては病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院から
提供される訪問リハビリテーションについて検討することとする。
⑥ 訪問栄養食事指導
在宅患者訪問栄養食事指導(医療保険)を受けた患者数は 142.5 人/月であり、
実施している医療機関(病院・診療所)数は 114.7 か所である 8。管理栄養士に
よる居宅療養管理指導(介護保険)を受けた患者数は 4,960 人/月であり、実施
している事業所(病院・診療所)数は 1,116 か所である 8。また、管理栄養士に
よる居宅療養管理指導について、65 歳以上人口 10 万人あたりの事業所数は全国
平均で 31.4 か所であり、都道府県によってばらつきがみられた 8。
今後、訪問栄養食事指導を充実させるためには、管理栄養士が配置されている
在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、管理栄養士が所属する地域密着型の拠
点である栄養ケア・ステーション※等の活用も含めた体制整備を行うことが求め
られる。
※ 栄養ケア・ステーションには、(公社)日本栄養士会又は都道府県栄養士会
が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」と(公社)日本栄養士会が事
業者等を個別に認定する「認定栄養ケア・ステーション」がある。
(3)
急変時の対応
自宅での療養を希望していてもそれが実現できない理由として、急変時の対応に
関する患者の不安や家族等の負担への懸念が挙げられる。こうした不安や負担の軽
減が、在宅での療養を継続するための重要な課題である。
そのため、24 時間いつでも往診や訪問看護等の対応が可能な連携体制や、入院医
療機関における円滑な受入れといった後方支援体制の構築が求められている。
170
共有をはじめとした多職種との連携、夜間・休日を含む急変時の対応等が求めら
れている。薬剤師の関与により、薬物有害事象への対処や服薬状況の改善が見込
まれ、在宅医療の質の向上につながることから、薬剤師の果たす役割は大きい。
高度な薬学管理等を充実させ、多様な病態の患者への対応やターミナルケアへ
の参画等を推進するため、麻薬調剤や無菌製剤処理、小児への訪問薬剤管理指導、
24 時間対応が可能な薬局の整備が必要である。そのため、地域医療介護総合確保
基金等を活用し、医療機関等と連携して行われる研修や、カンファレンス等への
参加を通じて、在宅医療に関わる薬剤師の資質向上を図ることが重要である。ま
た、都道府県の薬務主管課と医務主管課が連携し、地方薬事審議会等を活用して、
麻薬調剤や無菌製剤処理等の高度な薬学管理が可能な薬局の整備状況や実績につ
いて把握・分析を行い、在宅医療に必要な医薬品等の提供体制を構築することが
求められている。
⑤ 訪問リハビリテーション
医療機関から訪問リハビリテーションを受けた患者のうち、医療保険による患
者数は 2,326 人/月であり、提供している医療機関(病院・診療所)数は 1,472 か
所である 8。介護保険による患者数は 135,700 人/月であり、提供している医療機
関等(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)数は 4,950 か所である 11。
今後、在宅療養患者が居宅において生活機能の回復・維持を図る観点を踏まえ、
医療機関におけるリハビリテーション(急性期・回復期)から、地域における居
住生活の維持向上を目指す生活期リハビリテーションを切れ目なく提供できる体
制の整備が求められる。
なお、医療計画においては病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院から
提供される訪問リハビリテーションについて検討することとする。
⑥ 訪問栄養食事指導
在宅患者訪問栄養食事指導(医療保険)を受けた患者数は 142.5 人/月であり、
実施している医療機関(病院・診療所)数は 114.7 か所である 8。管理栄養士に
よる居宅療養管理指導(介護保険)を受けた患者数は 4,960 人/月であり、実施
している事業所(病院・診療所)数は 1,116 か所である 8。また、管理栄養士に
よる居宅療養管理指導について、65 歳以上人口 10 万人あたりの事業所数は全国
平均で 31.4 か所であり、都道府県によってばらつきがみられた 8。
今後、訪問栄養食事指導を充実させるためには、管理栄養士が配置されている
在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、管理栄養士が所属する地域密着型の拠
点である栄養ケア・ステーション※等の活用も含めた体制整備を行うことが求め
られる。
※ 栄養ケア・ステーションには、(公社)日本栄養士会又は都道府県栄養士会
が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」と(公社)日本栄養士会が事
業者等を個別に認定する「認定栄養ケア・ステーション」がある。
(3)
急変時の対応
自宅での療養を希望していてもそれが実現できない理由として、急変時の対応に
関する患者の不安や家族等の負担への懸念が挙げられる。こうした不安や負担の軽
減が、在宅での療養を継続するための重要な課題である。
そのため、24 時間いつでも往診や訪問看護等の対応が可能な連携体制や、入院医
療機関における円滑な受入れといった後方支援体制の構築が求められている。
170