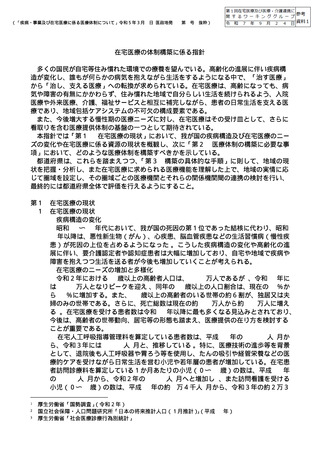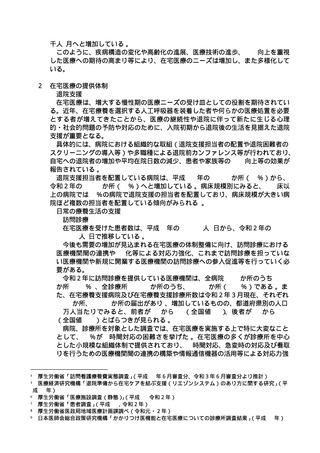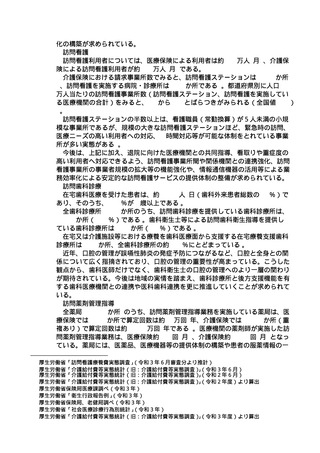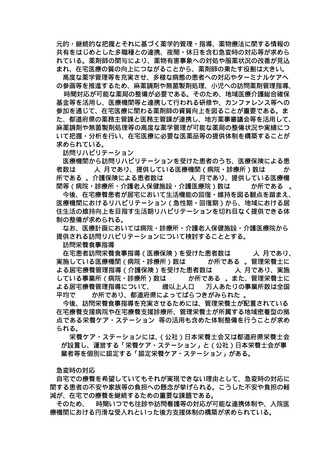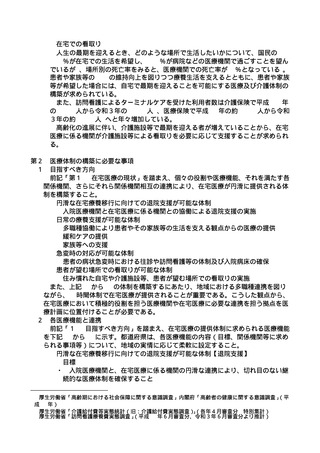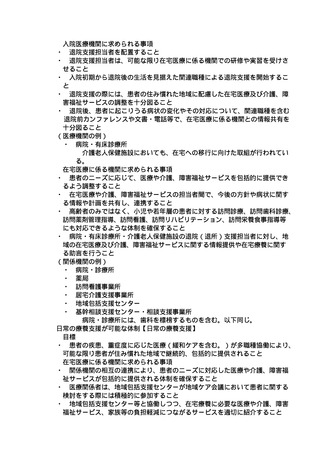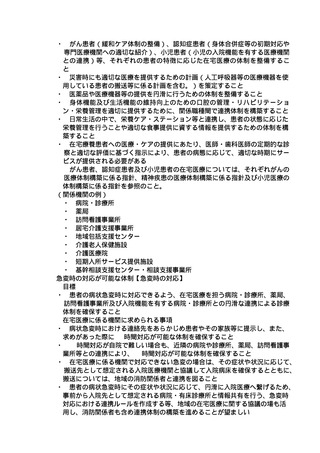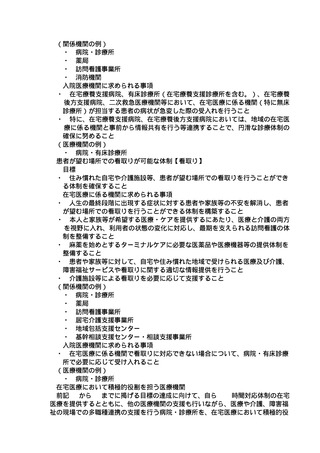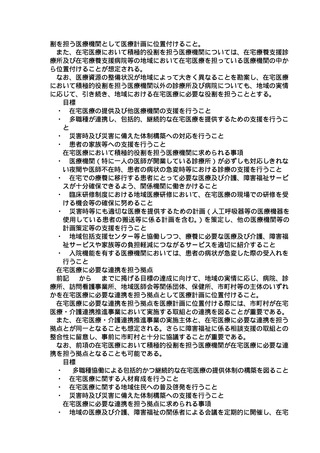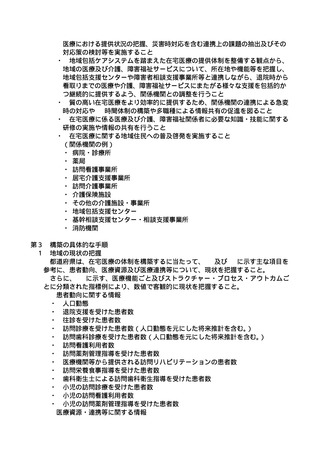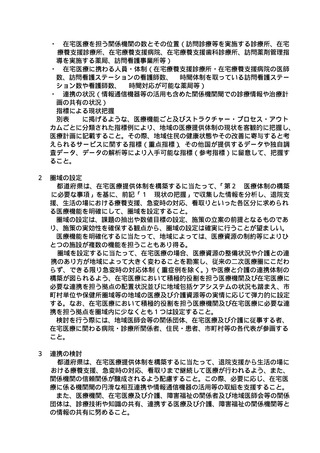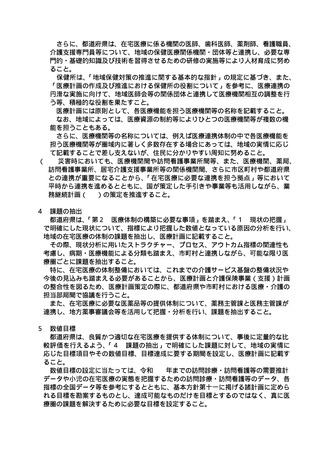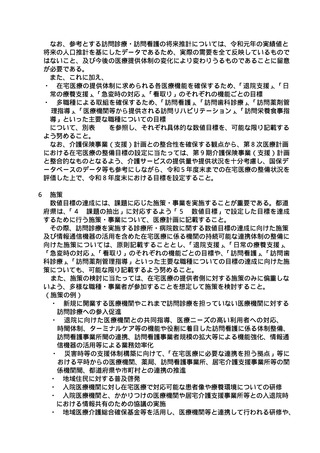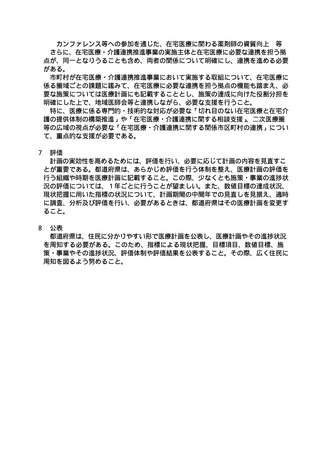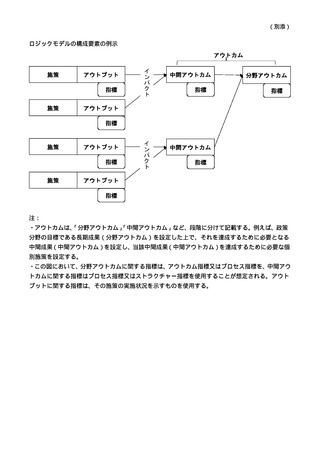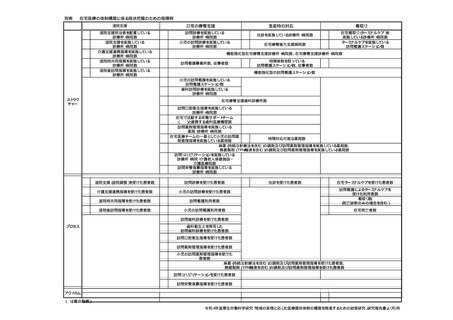よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 在宅医療の体制構築に係る指針 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63687.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第1回 9/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」令和5年3月31日 医政地発0331第14号
抜粋)
在宅医療の体制構築に係る指針
多くの国民が自宅等住み慣れた環境での療養を望んでいる。高齢化の進展に伴い疾病構
造が変化し、誰もが何らかの病気を抱えながら生活をするようになる中で、「治す医療」
から「治し、支える医療」への転換が求められている。在宅医療は、高齢になっても、病
気や障害の有無にかかわらず、住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう、入院
医療や外来医療、介護、福祉サービスと相互に補完しながら、患者の日常生活を支える医
療であり、地域包括ケアシステムの不可欠の構成要素である。
また、今後増大する慢性期の医療ニーズに対し、在宅医療はその受け皿として、さらに
看取りを含む医療提供体制の基盤の一つとして期待されている。
本指針では「第1
在宅医療の現状」において、我が国の疾病構造及び在宅医療のニー
ズの変化や在宅医療に係る資源の現状を概観し、次に「第2 医療体制の構築に必要な事
項」において、どのような医療体制を構築すべきかを示している。
都道府県は、これらを踏まえつつ、「第3 構築の具体的な手順」に則して、地域の現
状を把握・分析し、また在宅医療に求められる医療機能を理解した上で、地域の実情に応
じて圏域を設定し、その圏域ごとの医療機関とそれらの関係機関間の連携の検討を行い、
最終的には都道府県全体で評価を行えるようにすること。
第1 在宅医療の現状
1 在宅医療の現状
(1) 疾病構造の変化
昭和 10〜20 年代において、我が国の死因の第1位であった結核に代わり、昭和
33 年以降は、悪性新生物(がん)、心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病(慢性疾
患)が死因の上位を占めるようになった1。こうした疾病構造の変化や高齢化の進
展に伴い、要介護認定者や認知症患者は大幅に増加しており、自宅や地域で疾病や
障害を抱えつつ生活を送る者が今後も増加していくことが考えられる。
(2) 在宅医療のニーズの増加と多様化
令和2年における 65 歳以上の高齢者人口は、3,534 万人であるが 1、令和 24 年に
は 3,935 万人となりピークを迎え2、同年の 75 歳以上の人口割合は、現在の 14%か
ら 20%に増加する。また、65 歳以上の高齢者のいる世帯の約6割が、独居又は夫
婦のみの世帯である。さらに、死亡総数は現在の約 136 万人から約 167 万人に増え
る 2。在宅医療を受ける患者数は令和 22 年以降に最も多くなる見込みとされており、
今後は、高齢者の世帯動向、居宅等の形態も踏まえ、医療提供の在り方を検討する
ことが重要である。
在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者数は、平成 30 年の 18,257 人/月か
ら、令和3年には 19,536 人/月と、推移している3。特に、医療技術の進歩等を背景
として、退院後も人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医
療的ケアを受けながら日常生活を営む小児や若年層の患者が増加している。在宅患
者訪問診療料を算定している1か月あたりの小児(0〜14 歳)の数は、平成 30 年
の 2,085 人/月から、令和2年の 2,935 人/月へと増加し 3、また訪問看護を受ける
小児(0〜14 歳)の数は、平成 29 年の約 1 万4千人/月から、令和3年の約2万3
1
2
3
厚生労働省「国勢調査」(令和2年)
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(1月推計)
」(平成 29 年)
厚生労働省「社会医療診療行為別統計」
167
抜粋)
在宅医療の体制構築に係る指針
多くの国民が自宅等住み慣れた環境での療養を望んでいる。高齢化の進展に伴い疾病構
造が変化し、誰もが何らかの病気を抱えながら生活をするようになる中で、「治す医療」
から「治し、支える医療」への転換が求められている。在宅医療は、高齢になっても、病
気や障害の有無にかかわらず、住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう、入院
医療や外来医療、介護、福祉サービスと相互に補完しながら、患者の日常生活を支える医
療であり、地域包括ケアシステムの不可欠の構成要素である。
また、今後増大する慢性期の医療ニーズに対し、在宅医療はその受け皿として、さらに
看取りを含む医療提供体制の基盤の一つとして期待されている。
本指針では「第1
在宅医療の現状」において、我が国の疾病構造及び在宅医療のニー
ズの変化や在宅医療に係る資源の現状を概観し、次に「第2 医療体制の構築に必要な事
項」において、どのような医療体制を構築すべきかを示している。
都道府県は、これらを踏まえつつ、「第3 構築の具体的な手順」に則して、地域の現
状を把握・分析し、また在宅医療に求められる医療機能を理解した上で、地域の実情に応
じて圏域を設定し、その圏域ごとの医療機関とそれらの関係機関間の連携の検討を行い、
最終的には都道府県全体で評価を行えるようにすること。
第1 在宅医療の現状
1 在宅医療の現状
(1) 疾病構造の変化
昭和 10〜20 年代において、我が国の死因の第1位であった結核に代わり、昭和
33 年以降は、悪性新生物(がん)、心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病(慢性疾
患)が死因の上位を占めるようになった1。こうした疾病構造の変化や高齢化の進
展に伴い、要介護認定者や認知症患者は大幅に増加しており、自宅や地域で疾病や
障害を抱えつつ生活を送る者が今後も増加していくことが考えられる。
(2) 在宅医療のニーズの増加と多様化
令和2年における 65 歳以上の高齢者人口は、3,534 万人であるが 1、令和 24 年に
は 3,935 万人となりピークを迎え2、同年の 75 歳以上の人口割合は、現在の 14%か
ら 20%に増加する。また、65 歳以上の高齢者のいる世帯の約6割が、独居又は夫
婦のみの世帯である。さらに、死亡総数は現在の約 136 万人から約 167 万人に増え
る 2。在宅医療を受ける患者数は令和 22 年以降に最も多くなる見込みとされており、
今後は、高齢者の世帯動向、居宅等の形態も踏まえ、医療提供の在り方を検討する
ことが重要である。
在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者数は、平成 30 年の 18,257 人/月か
ら、令和3年には 19,536 人/月と、推移している3。特に、医療技術の進歩等を背景
として、退院後も人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医
療的ケアを受けながら日常生活を営む小児や若年層の患者が増加している。在宅患
者訪問診療料を算定している1か月あたりの小児(0〜14 歳)の数は、平成 30 年
の 2,085 人/月から、令和2年の 2,935 人/月へと増加し 3、また訪問看護を受ける
小児(0〜14 歳)の数は、平成 29 年の約 1 万4千人/月から、令和3年の約2万3
1
2
3
厚生労働省「国勢調査」(令和2年)
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(1月推計)
」(平成 29 年)
厚生労働省「社会医療診療行為別統計」
167