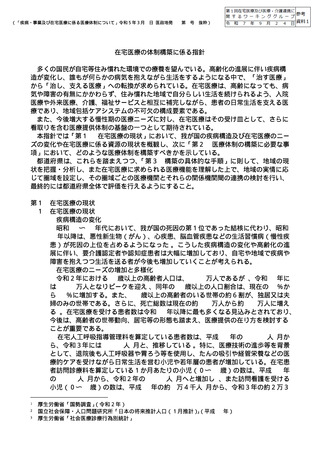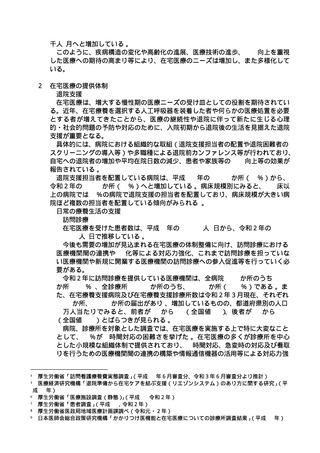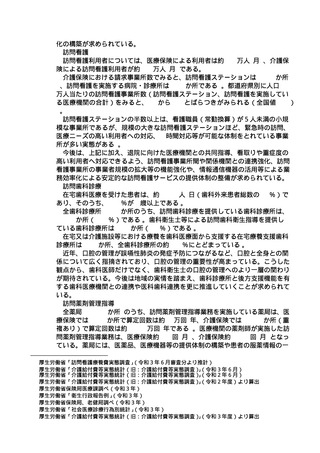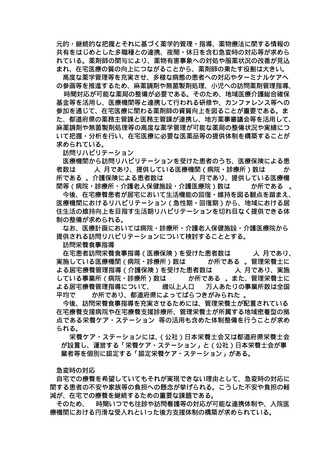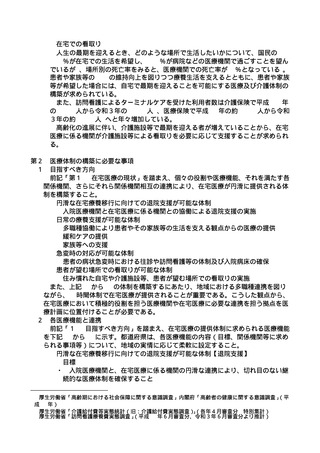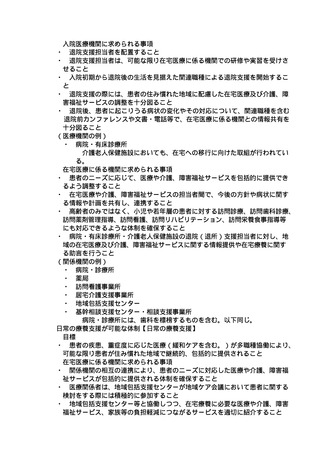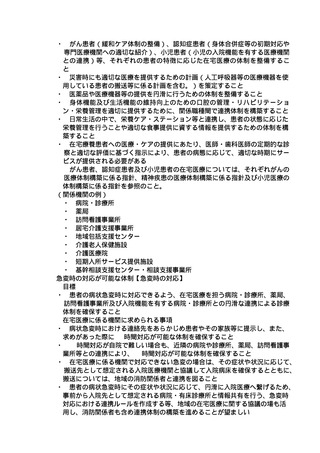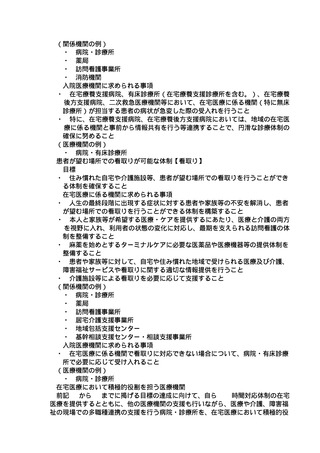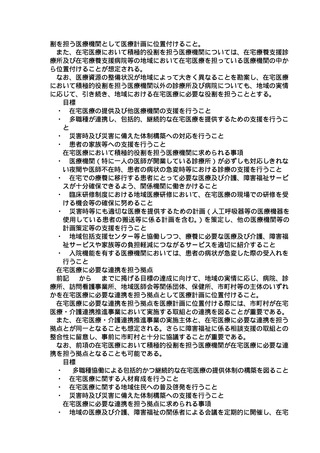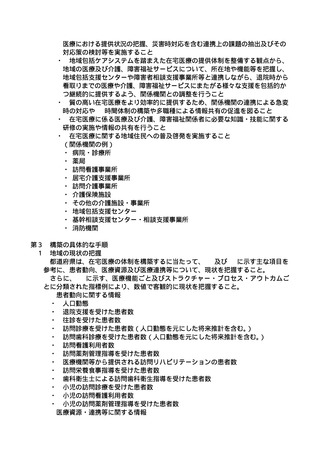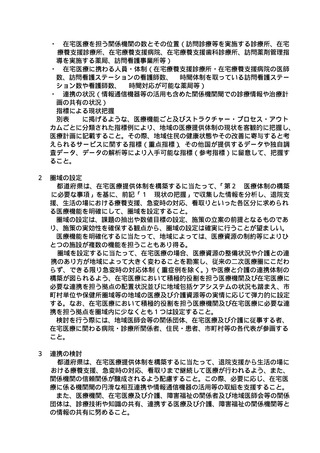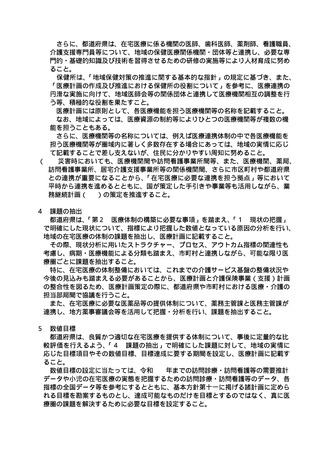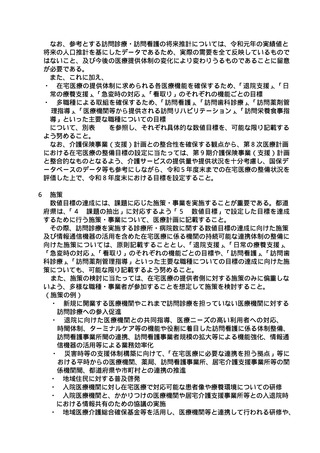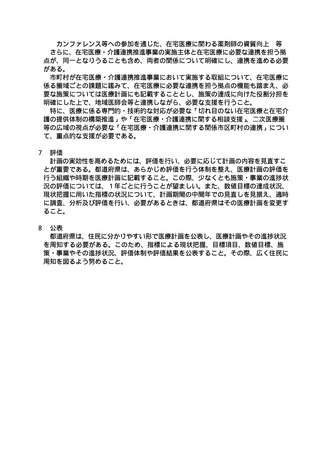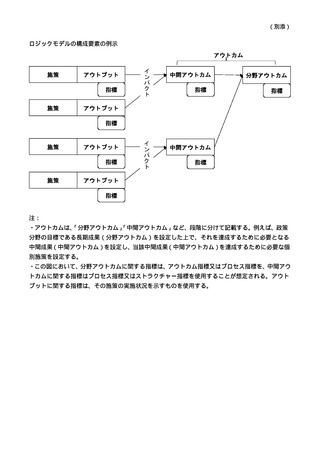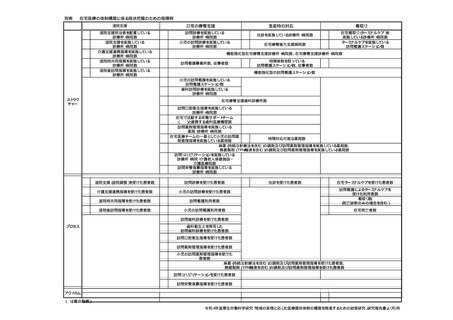よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 在宅医療の体制構築に係る指針 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63687.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第1回 9/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
千人/月へと増加している4。
このように、疾病構造の変化や高齢化の進展、医療技術の進歩、QOL 向上を重視
した医療への期待の高まり等により、在宅医療のニーズは増加し、また多様化して
いる。
2 在宅医療の提供体制
(1) 退院支援
在宅医療は、増大する慢性期の医療ニーズの受け皿としての役割を期待されてい
る。近年、在宅療養を選択する人工呼吸器を装着した者や何らかの医療処置を必要
とする者が増えてきたことから、医療の継続性や退院に伴って新たに生じる心理
的・社会的問題の予防や対応のために、入院初期から退院後の生活を見据えた退院
支援が重要となる。
具体的には、病院における組織的な取組(退院支援担当者の配置や退院困難者の
スクリーニングの導入等)や多職種による退院前カンファレンス等が行われており、
自宅への退院者の増加や平均在院日数の減少、患者や家族等の QOL 向上等の効果が
報告されている5。
退院支援担当者を配置している病院は、平成 20 年の 2,450 か所(28%)から、
令和2年の 4,147 か所(50%)へと増加している6。病床規模別にみると、300 床以
上の病院では 74%の病院で退院支援の担当者を配置しており、病床規模が大きい病
院ほど複数の担当者を配置している傾向がみられる 6。
(2) 日常の療養生活の支援
① 訪問診療
在宅医療を受けた患者数は、平成29 年の160,600 人/ 日から、令和2年の
158,400人/日で推移している7。
今後も需要の増加が見込まれる在宅医療の体制整備に向け、訪問診療における
医療機関間の連携やICT化等による対応力強化、これまで訪問診療を担っていな
い医療機関や新規に開業する医療機関の訪問診療への参入促進等を行っていく必
要がある。
令和2年に訪問診療を提供している医療機関は、全病院8,238か所のうち2,973
か所(36.1%)、全診療所102,612か所のうち、20,187か所(19.7%)である6。ま
た、在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所数は令和2年3月現在、それぞれ
1,493か所、14,401か所の届出があり8、増加しているものの、都道府県別の人口
10万人当たりでみると、前者が0.4から5.4(全国値1.2)、後者が5.5から21.4
(全国値11.6)とばらつきが見られる7。
病院、診療所を対象とした調査では、在宅医療を実施する上で特に大変なこと
として、74%が24時間対応の困難さを挙げた9。在宅医療の多くが診療所を中心
とした小規模な組織体制で提供されており、24時間対応、急変時の対応及び看取
りを行うための医療機関間の連携の構築や情報通信機器の活用等による対応力強
4
厚生労働省「訪問看護療養費実態調査」(平成 29 年6月審査分、令和3年6月審査分より推計)
医療経済研究機構「退院準備から在宅ケアを結ぶ支援(リエゾンシステム)のあり方に関する研究」
(平
成 19 年)
6
厚生労働省「医療施設調査(静態)」
(平成 20,令和2年)
7
厚生労働省「患者調査」(平成 29,令和2年)
8
厚生労働省医政局地域医療計画課調べ(令和元・2年)
9
日本医師会総合政策研究機構「かかりつけ医機能と在宅医療についての診療所調査結果」
(平成 29 年)
5
168
このように、疾病構造の変化や高齢化の進展、医療技術の進歩、QOL 向上を重視
した医療への期待の高まり等により、在宅医療のニーズは増加し、また多様化して
いる。
2 在宅医療の提供体制
(1) 退院支援
在宅医療は、増大する慢性期の医療ニーズの受け皿としての役割を期待されてい
る。近年、在宅療養を選択する人工呼吸器を装着した者や何らかの医療処置を必要
とする者が増えてきたことから、医療の継続性や退院に伴って新たに生じる心理
的・社会的問題の予防や対応のために、入院初期から退院後の生活を見据えた退院
支援が重要となる。
具体的には、病院における組織的な取組(退院支援担当者の配置や退院困難者の
スクリーニングの導入等)や多職種による退院前カンファレンス等が行われており、
自宅への退院者の増加や平均在院日数の減少、患者や家族等の QOL 向上等の効果が
報告されている5。
退院支援担当者を配置している病院は、平成 20 年の 2,450 か所(28%)から、
令和2年の 4,147 か所(50%)へと増加している6。病床規模別にみると、300 床以
上の病院では 74%の病院で退院支援の担当者を配置しており、病床規模が大きい病
院ほど複数の担当者を配置している傾向がみられる 6。
(2) 日常の療養生活の支援
① 訪問診療
在宅医療を受けた患者数は、平成29 年の160,600 人/ 日から、令和2年の
158,400人/日で推移している7。
今後も需要の増加が見込まれる在宅医療の体制整備に向け、訪問診療における
医療機関間の連携やICT化等による対応力強化、これまで訪問診療を担っていな
い医療機関や新規に開業する医療機関の訪問診療への参入促進等を行っていく必
要がある。
令和2年に訪問診療を提供している医療機関は、全病院8,238か所のうち2,973
か所(36.1%)、全診療所102,612か所のうち、20,187か所(19.7%)である6。ま
た、在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所数は令和2年3月現在、それぞれ
1,493か所、14,401か所の届出があり8、増加しているものの、都道府県別の人口
10万人当たりでみると、前者が0.4から5.4(全国値1.2)、後者が5.5から21.4
(全国値11.6)とばらつきが見られる7。
病院、診療所を対象とした調査では、在宅医療を実施する上で特に大変なこと
として、74%が24時間対応の困難さを挙げた9。在宅医療の多くが診療所を中心
とした小規模な組織体制で提供されており、24時間対応、急変時の対応及び看取
りを行うための医療機関間の連携の構築や情報通信機器の活用等による対応力強
4
厚生労働省「訪問看護療養費実態調査」(平成 29 年6月審査分、令和3年6月審査分より推計)
医療経済研究機構「退院準備から在宅ケアを結ぶ支援(リエゾンシステム)のあり方に関する研究」
(平
成 19 年)
6
厚生労働省「医療施設調査(静態)」
(平成 20,令和2年)
7
厚生労働省「患者調査」(平成 29,令和2年)
8
厚生労働省医政局地域医療計画課調べ(令和元・2年)
9
日本医師会総合政策研究機構「かかりつけ医機能と在宅医療についての診療所調査結果」
(平成 29 年)
5
168