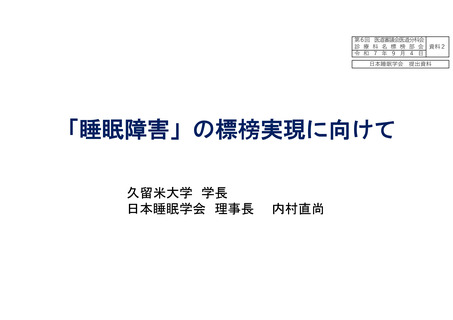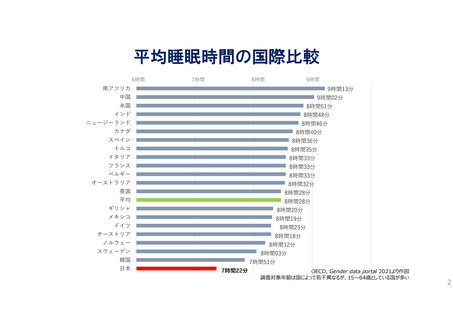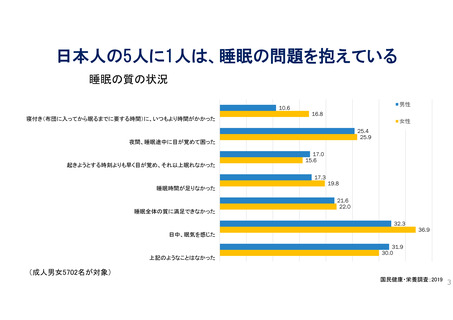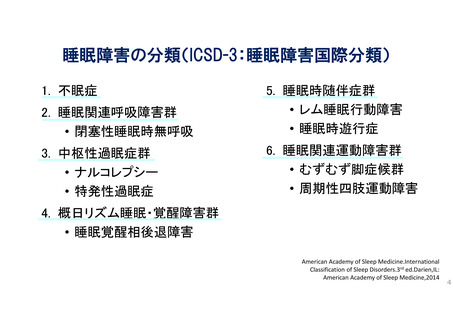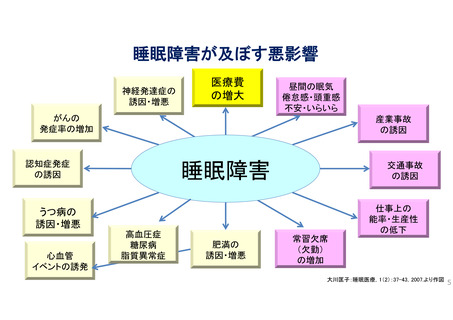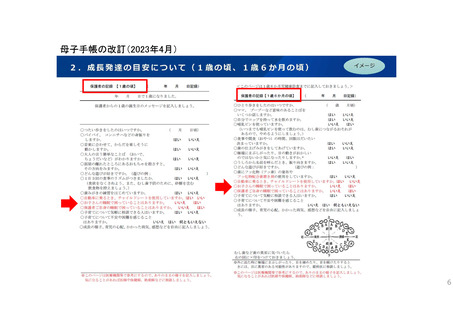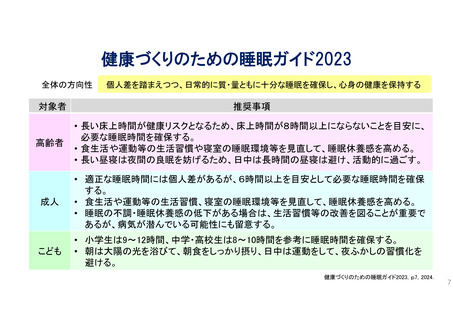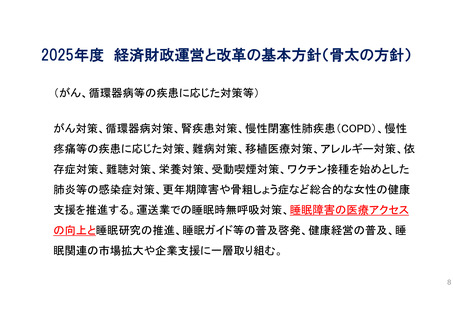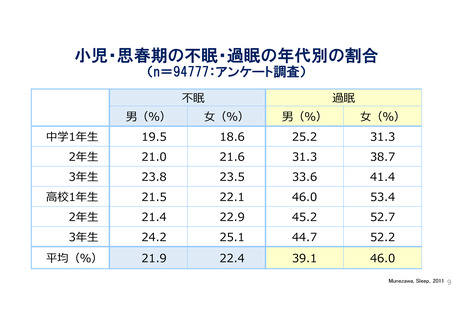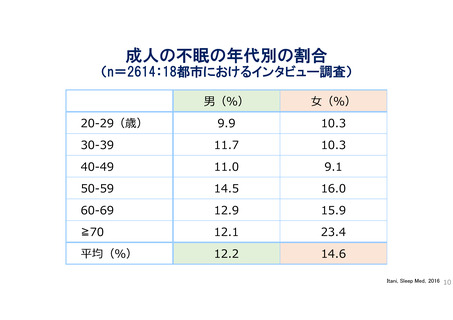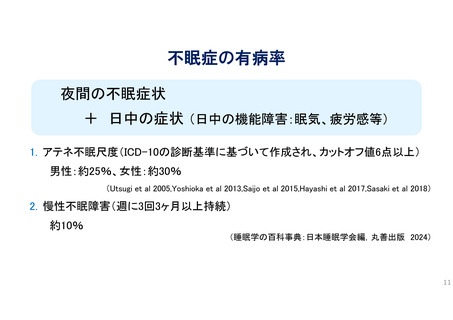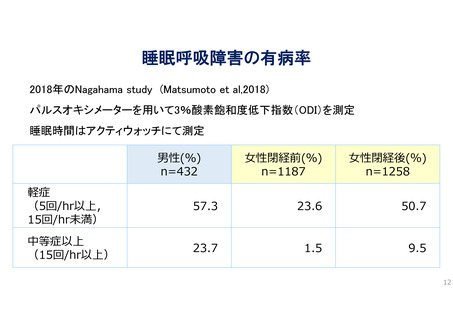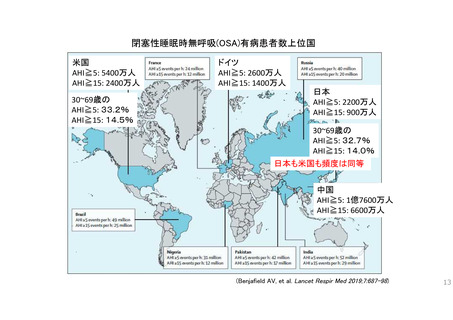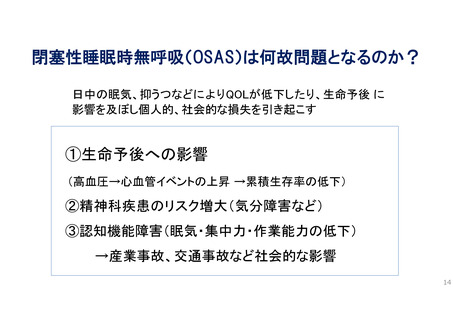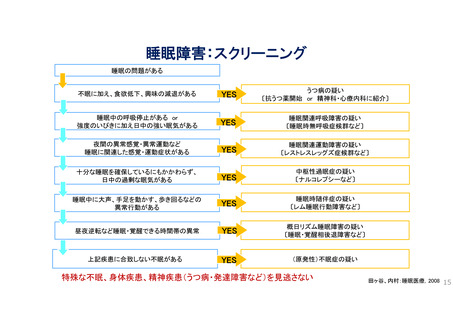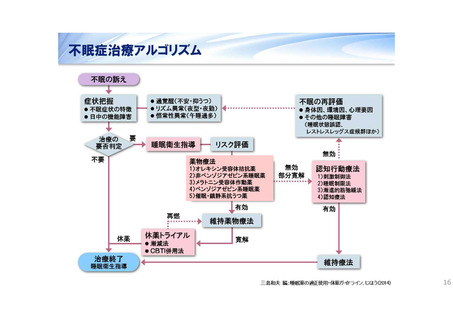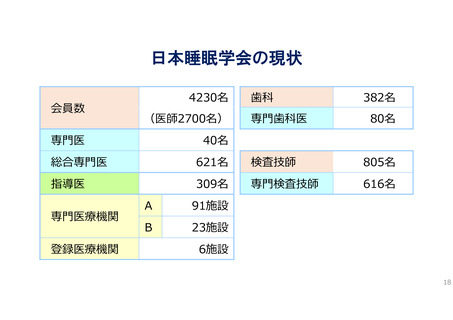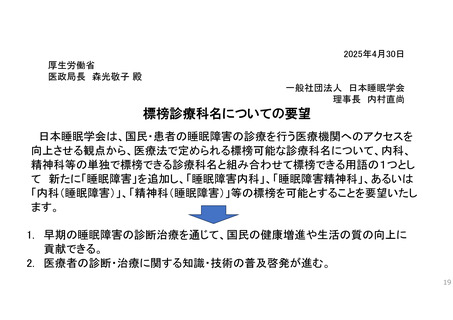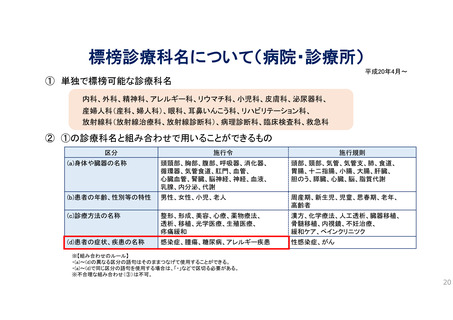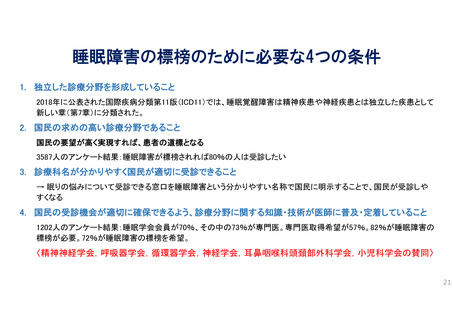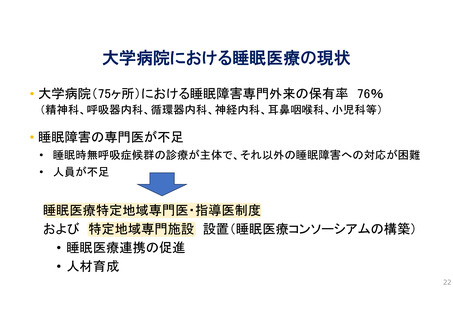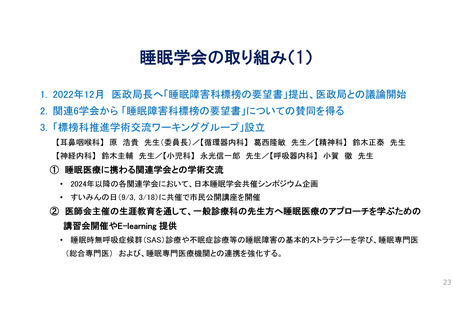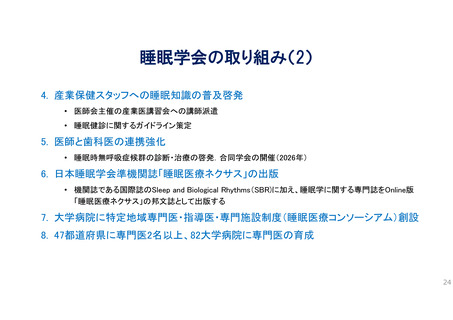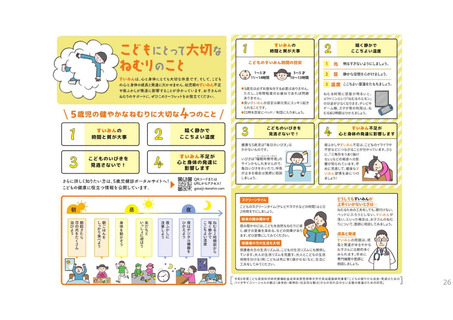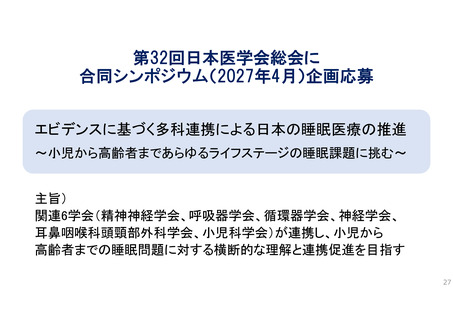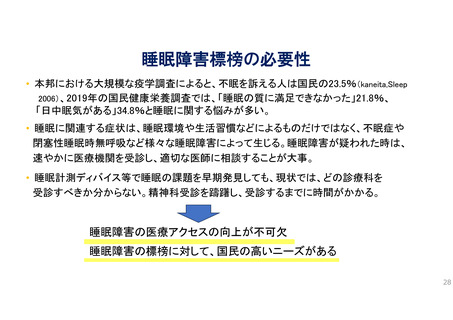よむ、つかう、まなぶ。
資料2「睡眠障害」の標榜実現に向けて(一般社団法人日本睡眠学会 提出資料) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62906.html |
| 出典情報 | 医道審議会 医道分科会 診療科名標榜部会(第6回 9/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
健康づくりのための睡眠ガイド2023
全体の方向性
個人差を踏まえつつ、日常的に質・量ともに十分な睡眠を確保し、心身の健康を保持する
対象者
推奨事項
高齢者
• 長い床上時間が健康リスクとなるため、床上時間が8時間以上にならないことを目安に、
必要な睡眠時間を確保する。
• 食生活や運動等の生活習慣や寝室の睡眠環境等を見直して、睡眠休養感を高める。
• 長い昼寝は夜間の良眠を妨げるため、日中は長時間の昼寝は避け、活動的に過ごす。
成人
• 適正な睡眠時間には個人差があるが、6時間以上を目安として必要な睡眠時間を確保
する。
• 食生活や運動等の生活習慣、寝室の睡眠環境等を見直して、睡眠休養感を高める。
• 睡眠の不調・睡眠休養感の低下がある場合は、生活習慣等の改善を図ることが重要で
あるが、病気が潜んでいる可能性にも留意する。
こども
• 小学生は9~12時間、中学・高校生は8~10時間を参考に睡眠時間を確保する。
• 朝は大陽の光を浴びて、朝食をしっかり摂り、日中は運動をして、夜ふかしの習慣化を
避ける。
健康づくりのための睡眠ガイド2023,p7,2024.
7
全体の方向性
個人差を踏まえつつ、日常的に質・量ともに十分な睡眠を確保し、心身の健康を保持する
対象者
推奨事項
高齢者
• 長い床上時間が健康リスクとなるため、床上時間が8時間以上にならないことを目安に、
必要な睡眠時間を確保する。
• 食生活や運動等の生活習慣や寝室の睡眠環境等を見直して、睡眠休養感を高める。
• 長い昼寝は夜間の良眠を妨げるため、日中は長時間の昼寝は避け、活動的に過ごす。
成人
• 適正な睡眠時間には個人差があるが、6時間以上を目安として必要な睡眠時間を確保
する。
• 食生活や運動等の生活習慣、寝室の睡眠環境等を見直して、睡眠休養感を高める。
• 睡眠の不調・睡眠休養感の低下がある場合は、生活習慣等の改善を図ることが重要で
あるが、病気が潜んでいる可能性にも留意する。
こども
• 小学生は9~12時間、中学・高校生は8~10時間を参考に睡眠時間を確保する。
• 朝は大陽の光を浴びて、朝食をしっかり摂り、日中は運動をして、夜ふかしの習慣化を
避ける。
健康づくりのための睡眠ガイド2023,p7,2024.
7