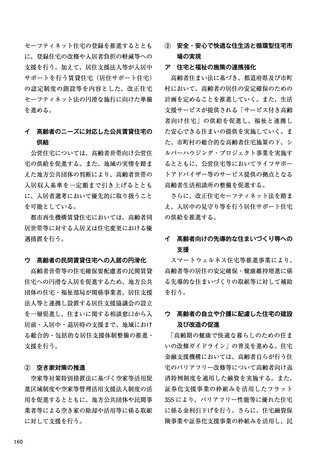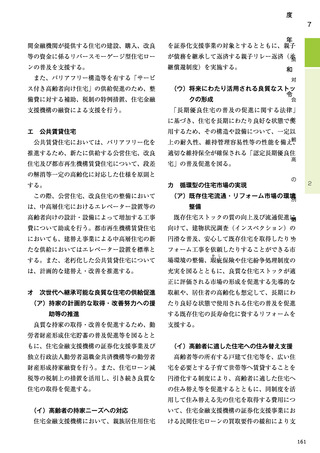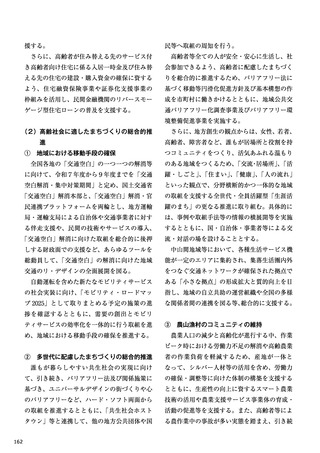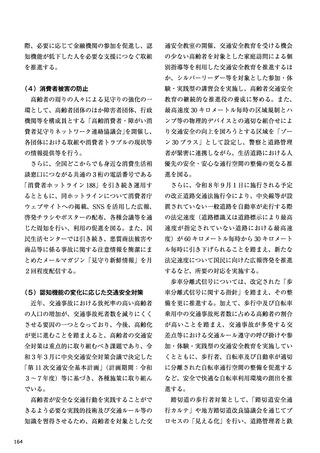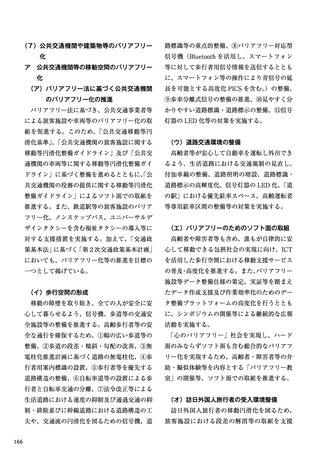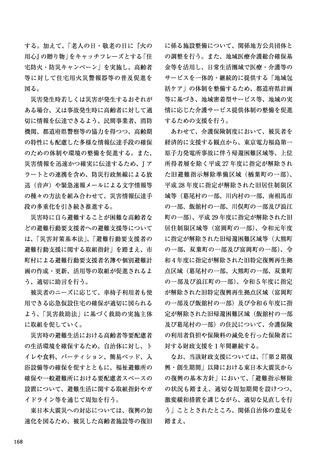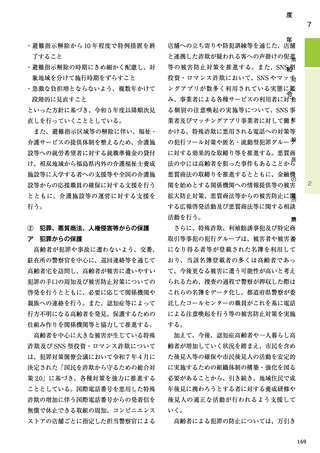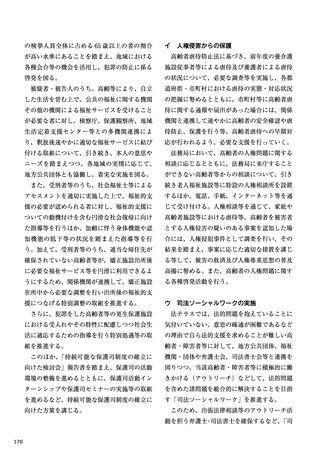よむ、つかう、まなぶ。
4 生活環境 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html |
| 出典情報 | 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
際、必要に応じて金融機関の参加を促進し、認
通安全教室の開催、交通安全教育を受ける機会
知機能が低下した人を必要な支援につなぐ取組
の少ない高齢者を対象とした家庭訪問による個
を推進する。
別指導等を利用した交通安全教育を推進するほ
か、シルバーリーダー等を対象とした参加・体
(4)消費者被害の防止
験・実践型の講習会を実施し、高齢者交通安全
高齢者の周りの人々による見守りの強化の一
教育の継続的な推進役の養成に努める。また、
環として、高齢者団体のほか障害者団体、行政
最高速度 30 キロメートル毎時の区域規制とハ
機関等を構成員とする「高齢消費者・障がい消
ンプ等の物理的デバイスとの適切な組合せによ
費者見守りネットワーク連絡協議会」を開催し、
り交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾー
各団体における取組や消費者トラブルの現状等
ン 30 プラス」として設定し、警察と道路管理
の情報提供等を行う。
者が緊密に連携しながら、生活道路における人
さらに、全国どこからでも身近な消費生活相
談窓口につながる共通の3桁の電話番号である
優先の安全・安心な通行空間の整備の更なる推
進を図る。
「消費者ホットライン 188」を引き続き運用す
さらに、令和8年9月1日に施行される予定
るとともに、同ホットラインについて消費者庁
の改正道路交通法施行令により、中央線等が設
ウェブサイトへの掲載、SNS を活用した広報、
置されていない一般道路を自動車が走行する際
啓発チラシやポスターの配布、各種会議等を通
の法定速度(道路標識又は道路標示により最高
じた周知を行い、利用の促進を図る。また、国
速度が指定されていない道路における最高速
民生活センターでは引き続き、悪質商法被害や
度)が 60 キロメートル毎時から 30 キロメート
商品等に係る事故に関する注意情報を簡潔にま
ル毎時に引き下げられることを踏まえ、新たな
とめたメールマガジン「見守り新鮮情報」を月
法定速度について国民に向けた広報啓発を推進
2回程度配信する。
するなど、所要の対応を実施する。
歩車分離式信号については、改定された「歩
(5)認知機能の変化に応じた交通安全対策
車分離式信号に関する指針」を踏まえ、その整
近年、交通事故における致死率の高い高齢者
備を更に推進する。加えて、歩行中及び自転車
の人口の増加が、交通事故死者数を減りにくく
乗用中の交通事故死者数に占める高齢者の割合
させる要因の一つとなっており、今後、高齢化
が高いことを踏まえ、交通事故が多発する交
が更に進むことを踏まえると、高齢者の交通安
差点等における交通ルール遵守の呼び掛けや参
全対策は重点的に取り組むべき課題であり、令
加・体験・実践型の交通安全教育を実施してい
和3年3月に中央交通安全対策会議で決定した
くとともに、歩行者、自転車及び自動車が適切
「第 11 次交通安全基本計画」(計画期間:令和
に分離された自転車通行空間の整備を促進する
3~7年度)等に基づき、各種施策に取り組ん
など、安全で快適な自転車利用環境の創出を推
でいる。
進する。
164
高齢者が安全な交通行動を実践することがで
踏切道の歩行者対策として、
「踏切道安全通
きるよう必要な実践的技術及び交通ルール等の
行カルテ」や地方踏切道改良協議会を通じてプ
知識を習得させるため、高齢者を対象とした交
ロセスの「見える化」を行い、道路管理者と鉄
通安全教室の開催、交通安全教育を受ける機会
知機能が低下した人を必要な支援につなぐ取組
の少ない高齢者を対象とした家庭訪問による個
を推進する。
別指導等を利用した交通安全教育を推進するほ
か、シルバーリーダー等を対象とした参加・体
(4)消費者被害の防止
験・実践型の講習会を実施し、高齢者交通安全
高齢者の周りの人々による見守りの強化の一
教育の継続的な推進役の養成に努める。また、
環として、高齢者団体のほか障害者団体、行政
最高速度 30 キロメートル毎時の区域規制とハ
機関等を構成員とする「高齢消費者・障がい消
ンプ等の物理的デバイスとの適切な組合せによ
費者見守りネットワーク連絡協議会」を開催し、
り交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾー
各団体における取組や消費者トラブルの現状等
ン 30 プラス」として設定し、警察と道路管理
の情報提供等を行う。
者が緊密に連携しながら、生活道路における人
さらに、全国どこからでも身近な消費生活相
談窓口につながる共通の3桁の電話番号である
優先の安全・安心な通行空間の整備の更なる推
進を図る。
「消費者ホットライン 188」を引き続き運用す
さらに、令和8年9月1日に施行される予定
るとともに、同ホットラインについて消費者庁
の改正道路交通法施行令により、中央線等が設
ウェブサイトへの掲載、SNS を活用した広報、
置されていない一般道路を自動車が走行する際
啓発チラシやポスターの配布、各種会議等を通
の法定速度(道路標識又は道路標示により最高
じた周知を行い、利用の促進を図る。また、国
速度が指定されていない道路における最高速
民生活センターでは引き続き、悪質商法被害や
度)が 60 キロメートル毎時から 30 キロメート
商品等に係る事故に関する注意情報を簡潔にま
ル毎時に引き下げられることを踏まえ、新たな
とめたメールマガジン「見守り新鮮情報」を月
法定速度について国民に向けた広報啓発を推進
2回程度配信する。
するなど、所要の対応を実施する。
歩車分離式信号については、改定された「歩
(5)認知機能の変化に応じた交通安全対策
車分離式信号に関する指針」を踏まえ、その整
近年、交通事故における致死率の高い高齢者
備を更に推進する。加えて、歩行中及び自転車
の人口の増加が、交通事故死者数を減りにくく
乗用中の交通事故死者数に占める高齢者の割合
させる要因の一つとなっており、今後、高齢化
が高いことを踏まえ、交通事故が多発する交
が更に進むことを踏まえると、高齢者の交通安
差点等における交通ルール遵守の呼び掛けや参
全対策は重点的に取り組むべき課題であり、令
加・体験・実践型の交通安全教育を実施してい
和3年3月に中央交通安全対策会議で決定した
くとともに、歩行者、自転車及び自動車が適切
「第 11 次交通安全基本計画」(計画期間:令和
に分離された自転車通行空間の整備を促進する
3~7年度)等に基づき、各種施策に取り組ん
など、安全で快適な自転車利用環境の創出を推
でいる。
進する。
164
高齢者が安全な交通行動を実践することがで
踏切道の歩行者対策として、
「踏切道安全通
きるよう必要な実践的技術及び交通ルール等の
行カルテ」や地方踏切道改良協議会を通じてプ
知識を習得させるため、高齢者を対象とした交
ロセスの「見える化」を行い、道路管理者と鉄