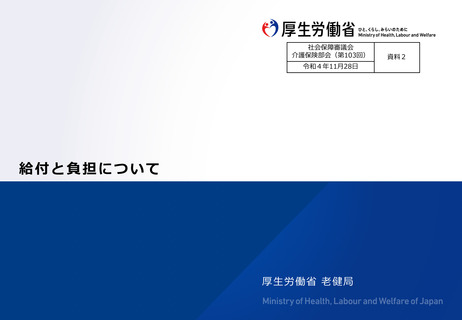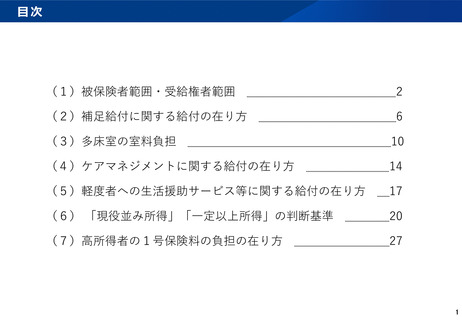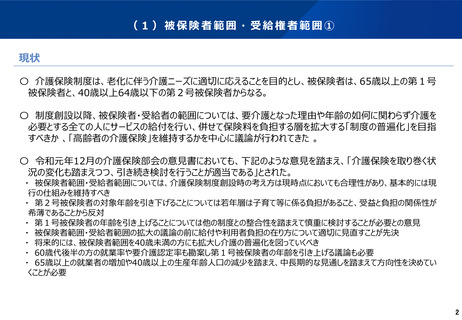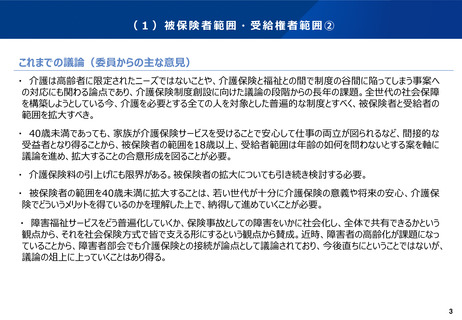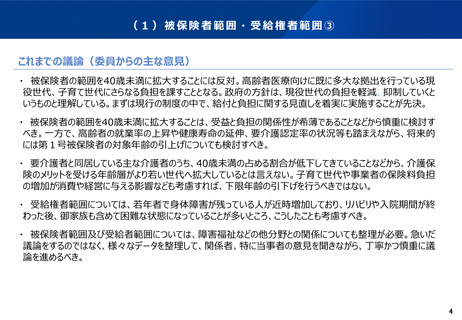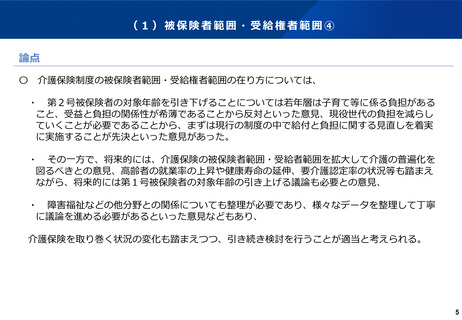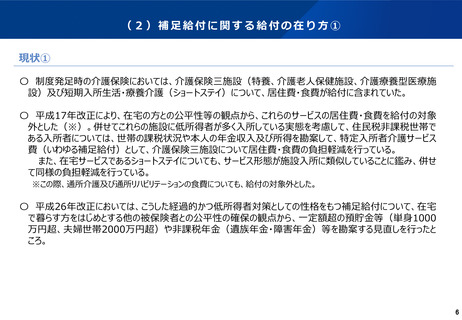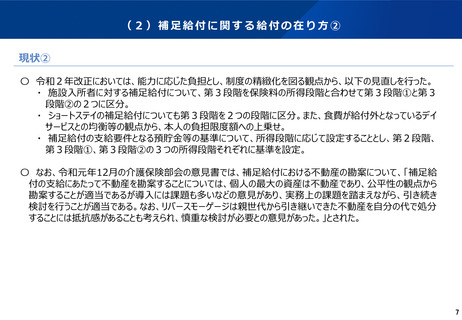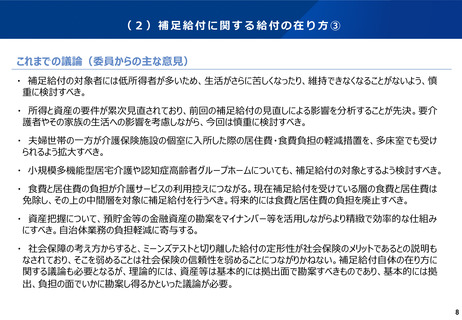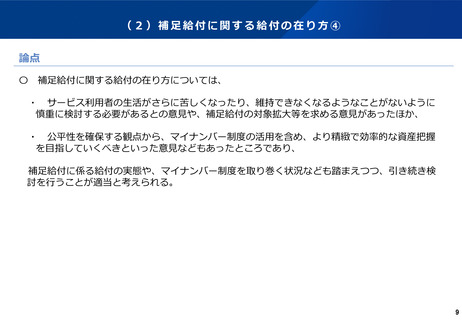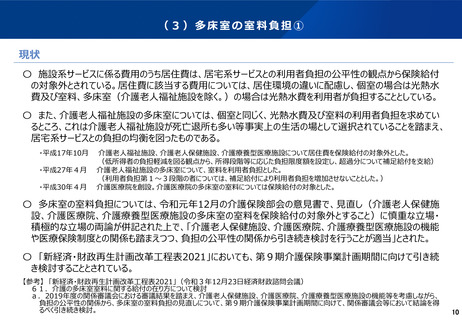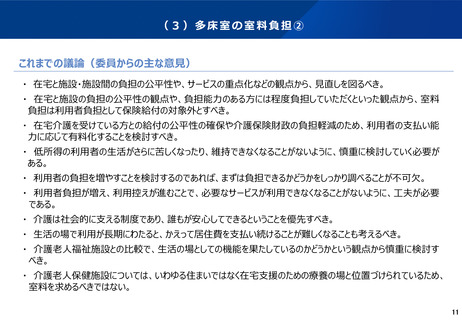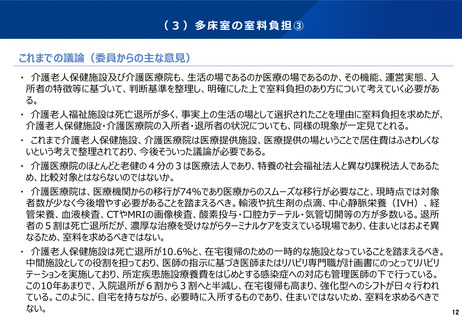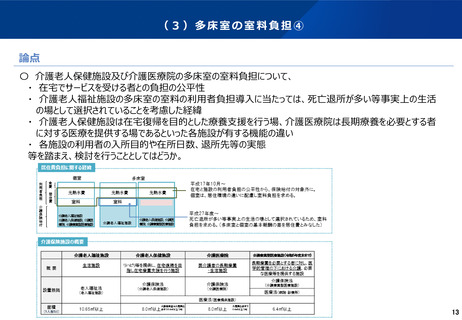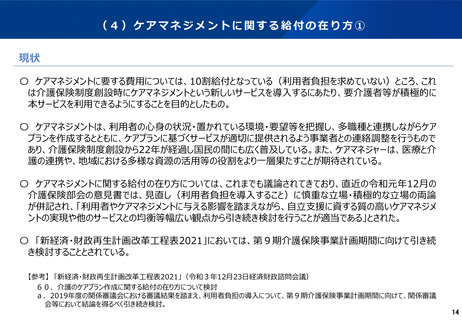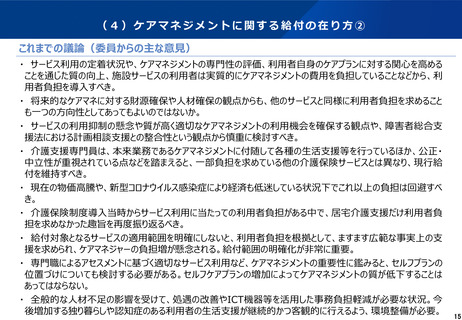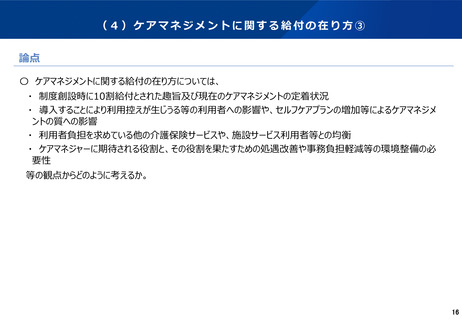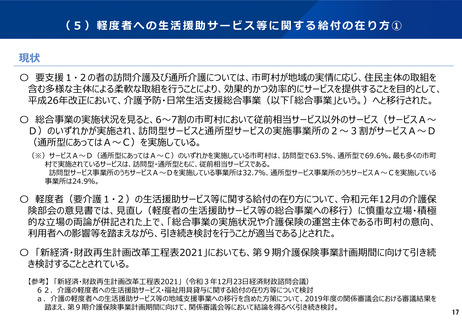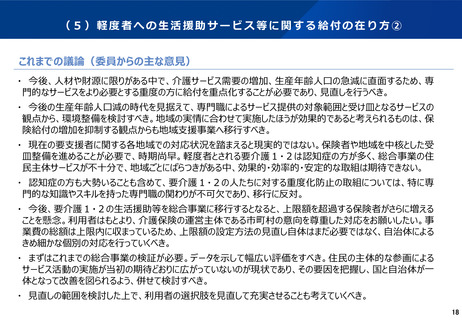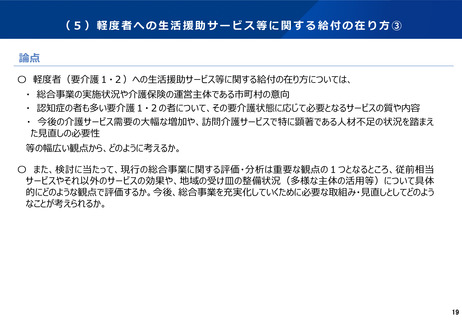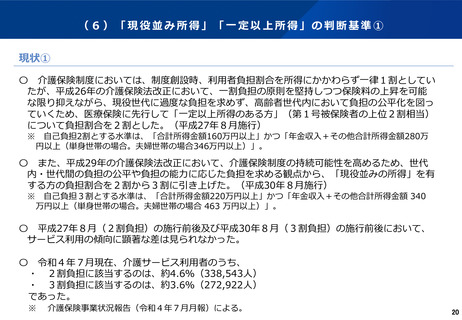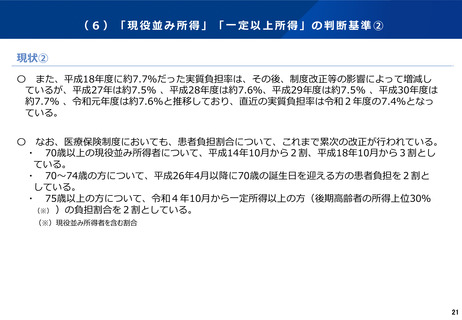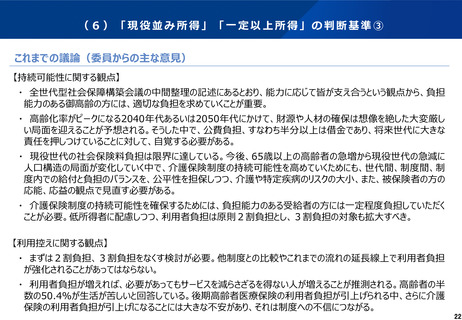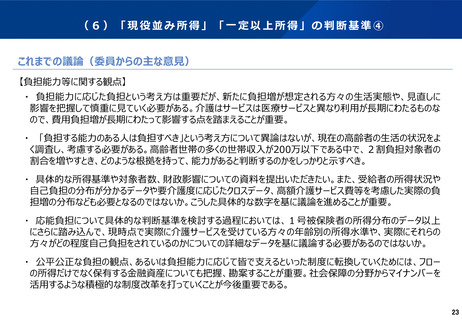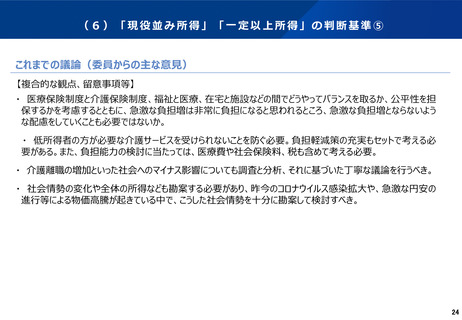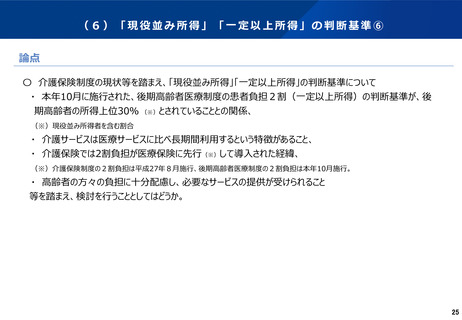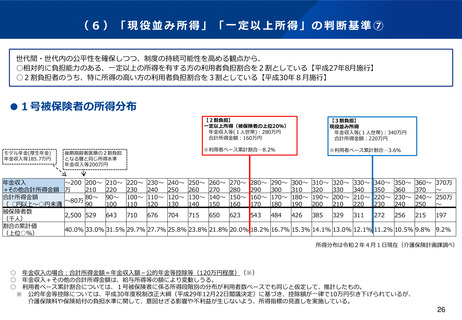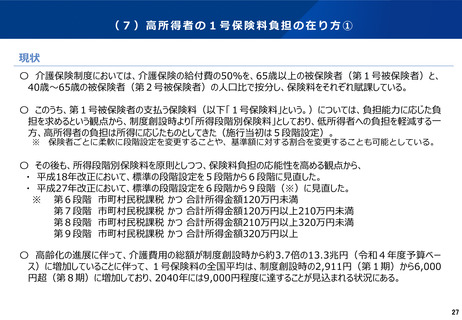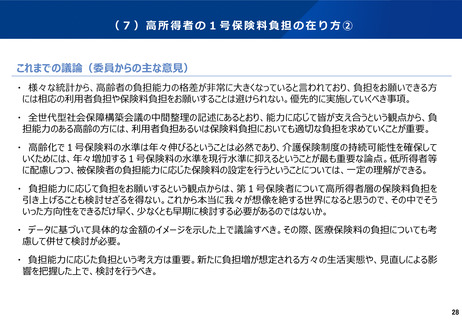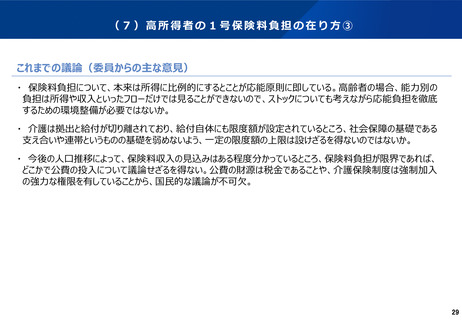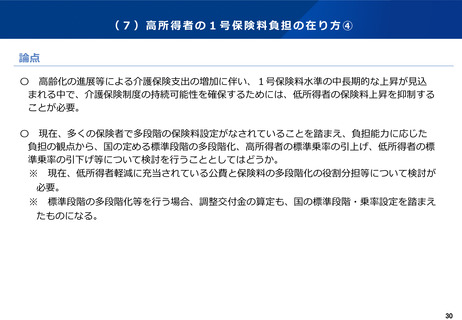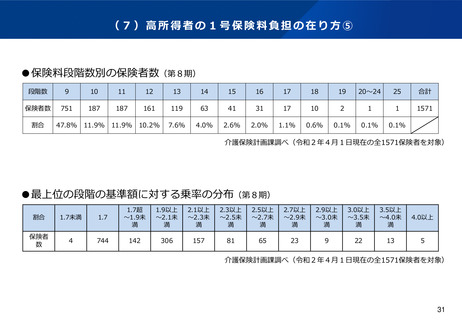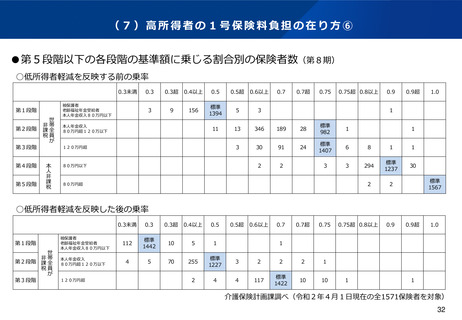よむ、つかう、まなぶ。
資料2 給付と負担について (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29318.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第103回 11/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(5)軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方②
これまでの議論(委員からの主な意見)
・ 今後、人材や財源に限りがある中で、介護サービス需要の増加、生産年齢人口の急減に直面するため、専
門的なサービスをより必要とする重度の方に給付を重点化することが必要であり、見直しを行うべき。
・ 今後の生産年齢人口減の時代を見据えて、専門職によるサービス提供の対象範囲と受け皿となるサービスの
観点から、環境整備を検討すべき。地域の実情に合わせて実施したほうが効果的であると考えられるものは、保
険給付の増加を抑制する観点からも地域支援事業へ移行すべき。
・ 現在の要支援者に関する各地域での対応状況を踏まえると現実的ではない。保険者や地域を中核とした受
皿整備を進めることが必要で、時期尚早。軽度者とされる要介護1・2は認知症の方が多く、総合事業の住
民主体サービスが不十分で、地域ごとにばらつきがある中、効果的・効率的・安定的な取組は期待できない。
・ 認知症の方も大勢いることも含めて、要介護1・2の人たちに対する重度化防止の取組については、特に専
門的な知識やスキルを持った専門職の関わりが不可欠であり、移行に反対。
・ 今後、要介護1・2の生活援助等を総合事業に移行するとなると、上限額を超過する保険者がさらに増える
ことを懸念。利用者はもとより、介護保険の運営主体である市町村の意向を尊重した対応をお願いしたい。事
業費の総額は上限内に収まっているため、上限額の設定方法の見直し自体はまだ必要ではなく、自治体による
きめ細かな個別の対応を行っていくべき。
・ まずはこれまでの総合事業の検証が必要。データを示して幅広い評価をすべき。住民の主体的な参画による
サービス活動の実施が当初の期待どおりに広がっていないのが現状であり、その要因を把握し、国と自治体が一
体となって改善を図られるよう、併せて検討すべき。
・ 見直しの範囲を検討した上で、利用者の選択肢を見直して充実させることも考えていくべき。
18
これまでの議論(委員からの主な意見)
・ 今後、人材や財源に限りがある中で、介護サービス需要の増加、生産年齢人口の急減に直面するため、専
門的なサービスをより必要とする重度の方に給付を重点化することが必要であり、見直しを行うべき。
・ 今後の生産年齢人口減の時代を見据えて、専門職によるサービス提供の対象範囲と受け皿となるサービスの
観点から、環境整備を検討すべき。地域の実情に合わせて実施したほうが効果的であると考えられるものは、保
険給付の増加を抑制する観点からも地域支援事業へ移行すべき。
・ 現在の要支援者に関する各地域での対応状況を踏まえると現実的ではない。保険者や地域を中核とした受
皿整備を進めることが必要で、時期尚早。軽度者とされる要介護1・2は認知症の方が多く、総合事業の住
民主体サービスが不十分で、地域ごとにばらつきがある中、効果的・効率的・安定的な取組は期待できない。
・ 認知症の方も大勢いることも含めて、要介護1・2の人たちに対する重度化防止の取組については、特に専
門的な知識やスキルを持った専門職の関わりが不可欠であり、移行に反対。
・ 今後、要介護1・2の生活援助等を総合事業に移行するとなると、上限額を超過する保険者がさらに増える
ことを懸念。利用者はもとより、介護保険の運営主体である市町村の意向を尊重した対応をお願いしたい。事
業費の総額は上限内に収まっているため、上限額の設定方法の見直し自体はまだ必要ではなく、自治体による
きめ細かな個別の対応を行っていくべき。
・ まずはこれまでの総合事業の検証が必要。データを示して幅広い評価をすべき。住民の主体的な参画による
サービス活動の実施が当初の期待どおりに広がっていないのが現状であり、その要因を把握し、国と自治体が一
体となって改善を図られるよう、併せて検討すべき。
・ 見直しの範囲を検討した上で、利用者の選択肢を見直して充実させることも考えていくべき。
18