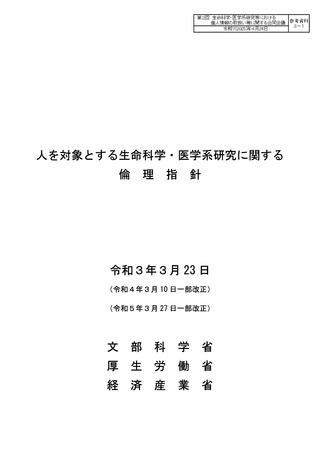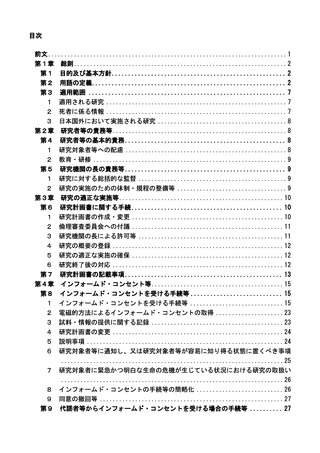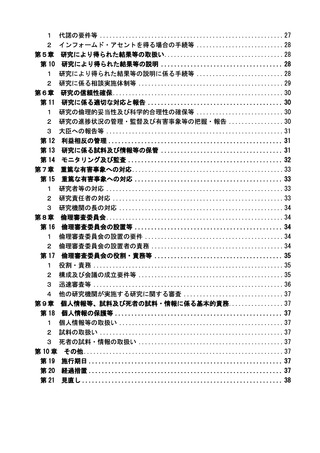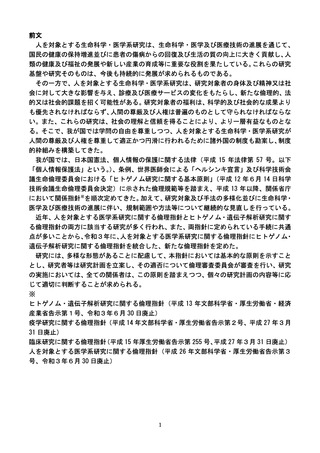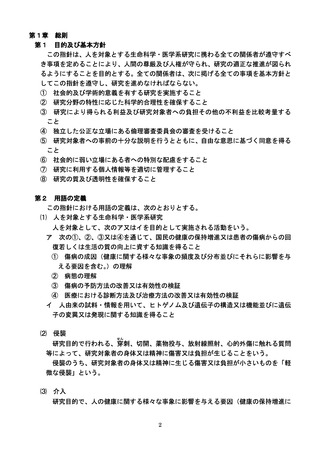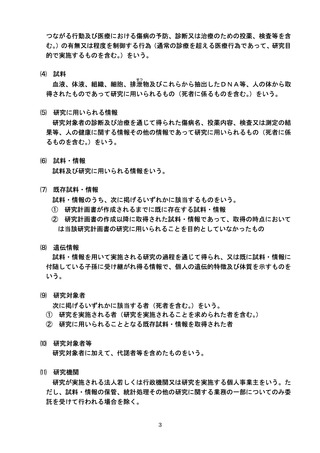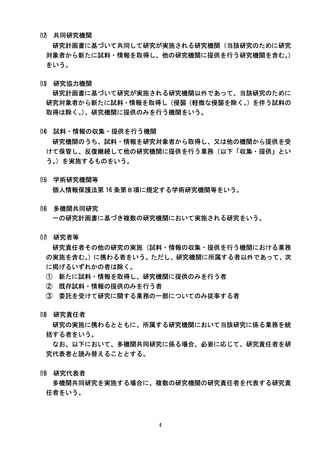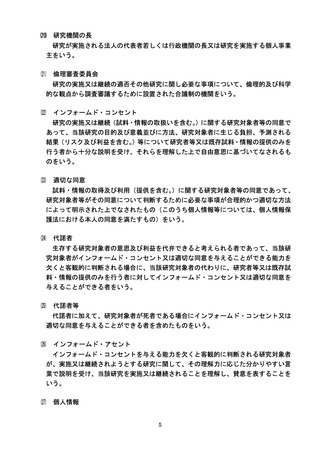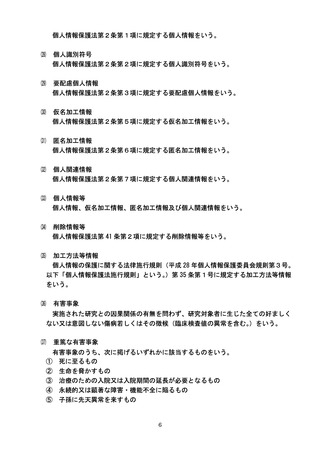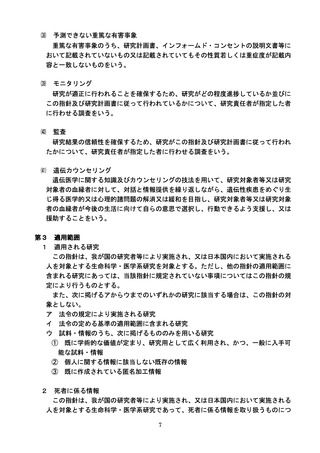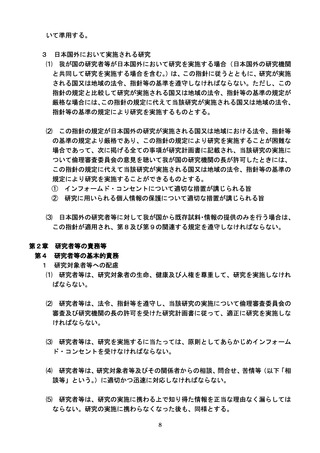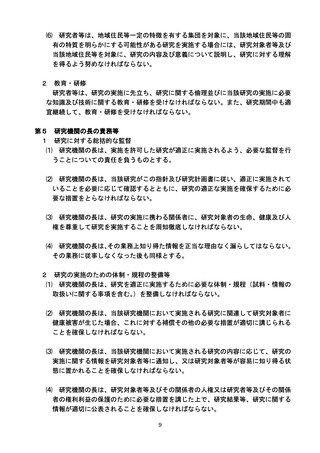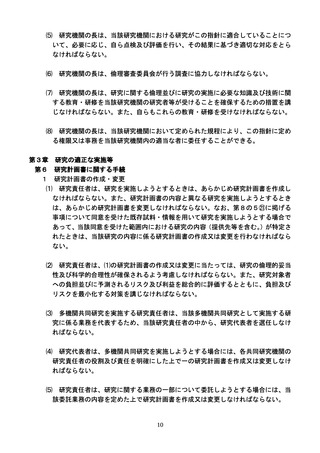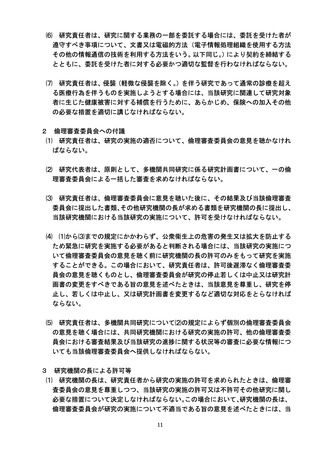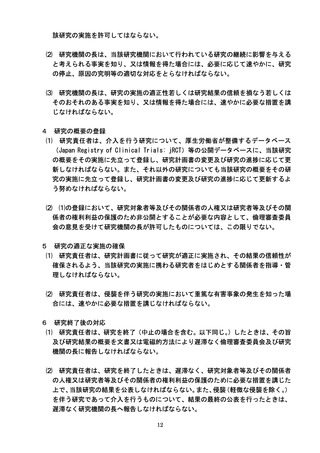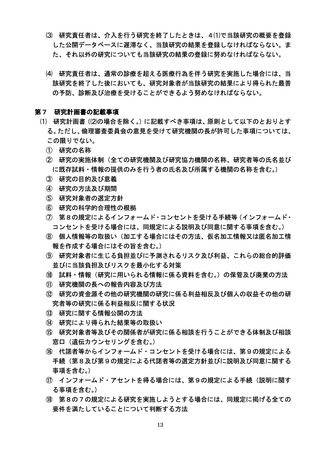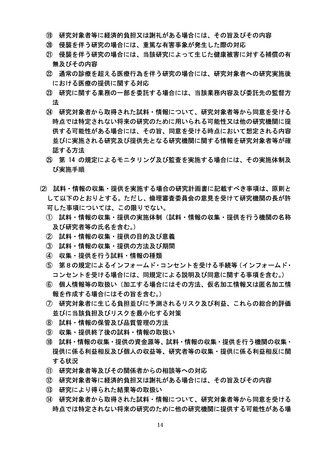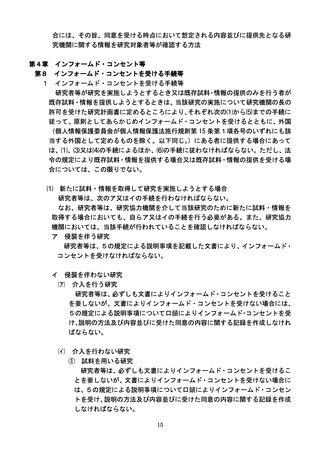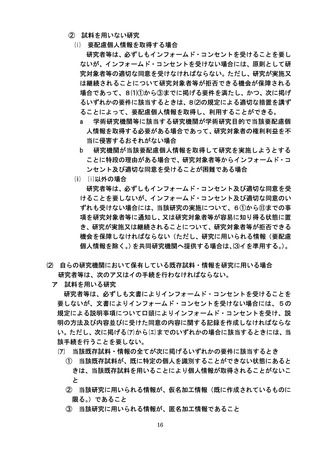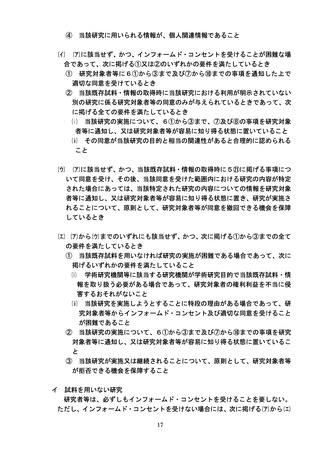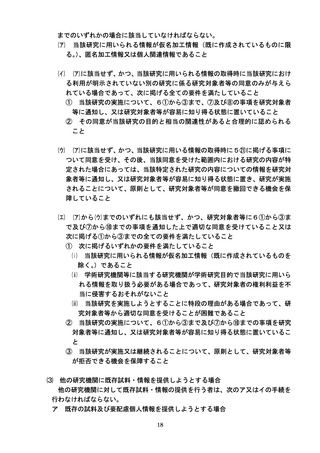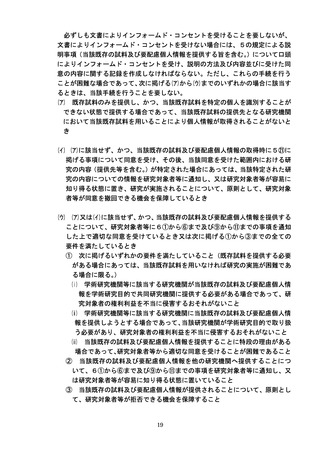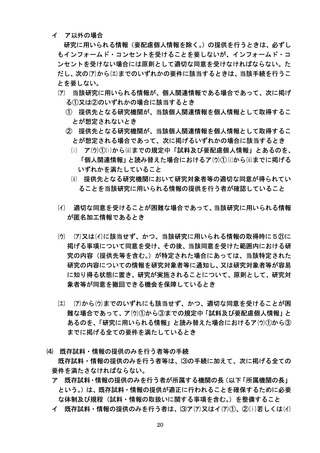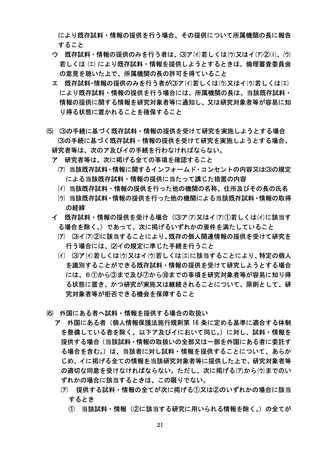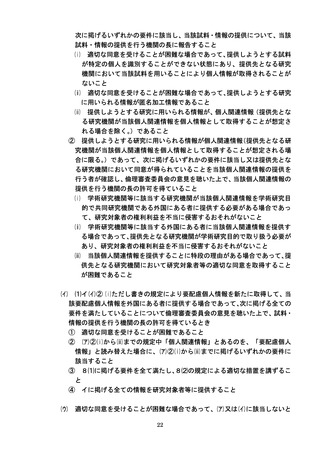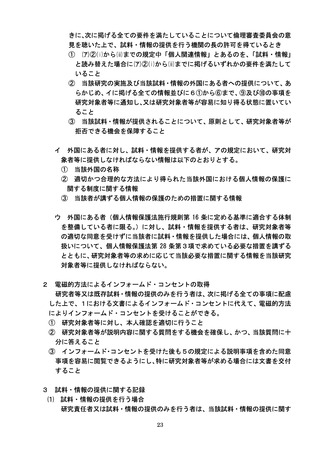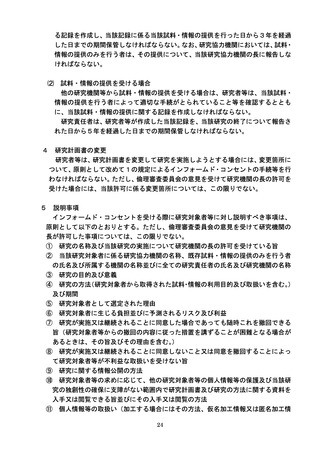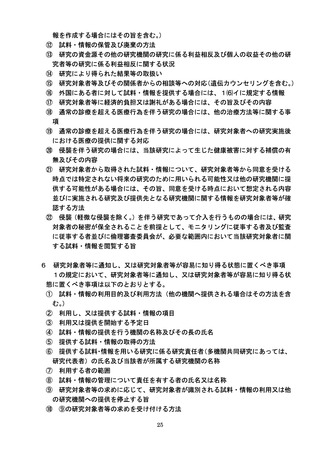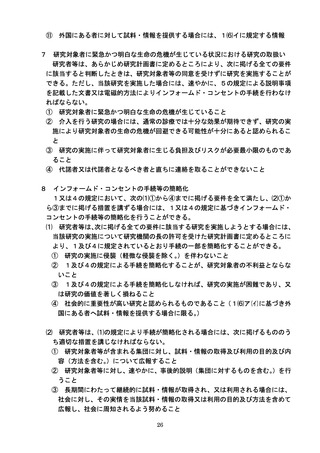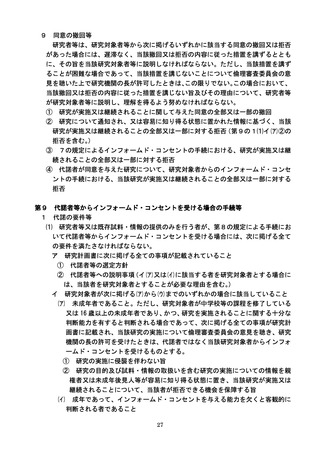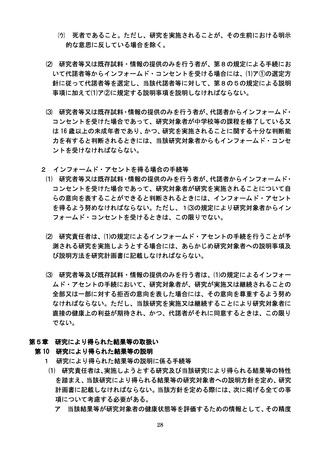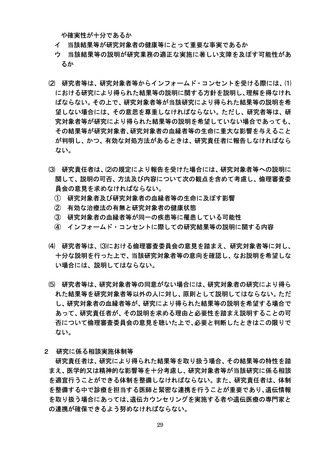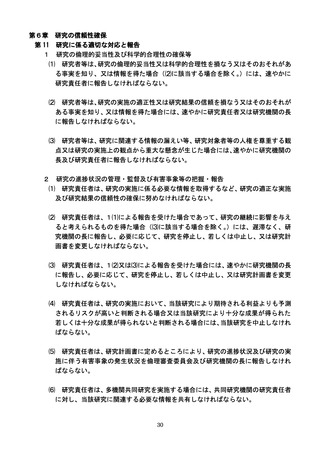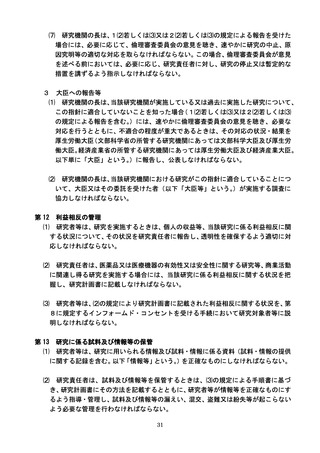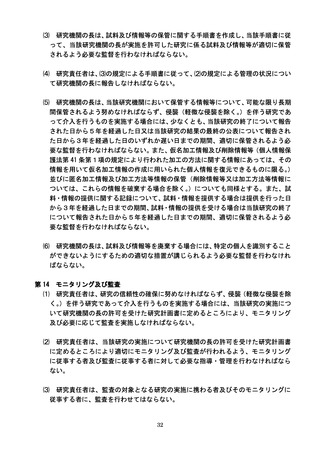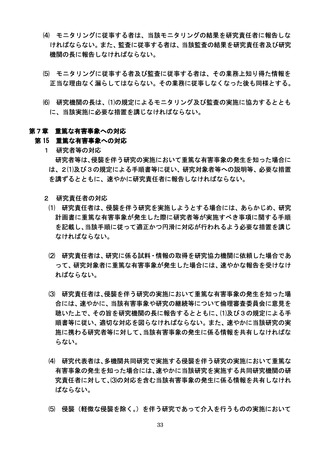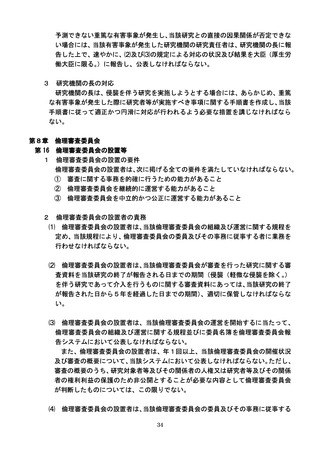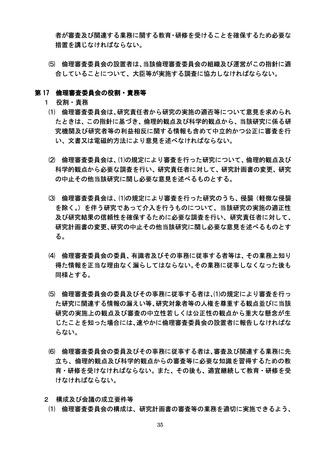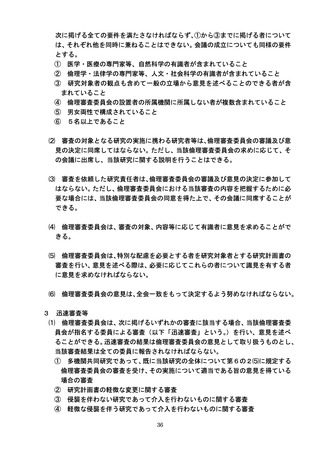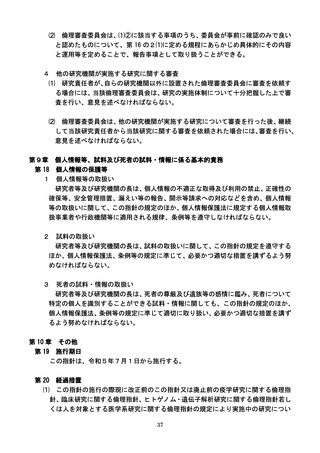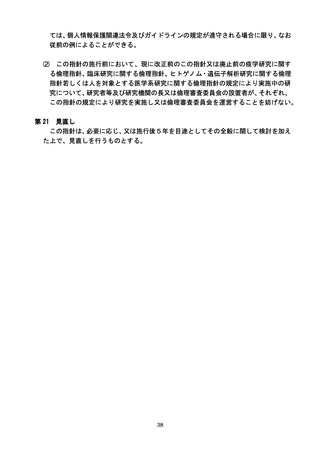よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3-1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57354.html |
| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第10回 4/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
⑸ 研究機関の長は、当該研究機関における研究がこの指針に適合していることにつ
いて、必要に応じ、自ら点検及び評価を行い、その結果に基づき適切な対応をとら
なければならない。
⑹ 研究機関の長は、倫理審査委員会が行う調査に協力しなければならない。
⑺ 研究機関の長は、研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知識及び技術に関
する教育・研修を当該研究機関の研究者等が受けることを確保するための措置を講
じなければならない。また、自らもこれらの教育・研修を受けなければならない。
⑻ 研究機関の長は、当該研究機関において定められた規程により、この指針に定め
る権限又は事務を当該研究機関内の適当な者に委任することができる。
第3章 研究の適正な実施等
第6 研究計画書に関する手続
1 研究計画書の作成・変更
⑴ 研究責任者は、研究を実施しようとするときは、あらかじめ研究計画書を作成し
なければならない。また、研究計画書の内容と異なる研究を実施しようとするとき
は、あらかじめ研究計画書を変更しなければならない。なお、第8の5㉑に掲げる
事項について同意を受けた既存試料・情報を用いて研究を実施しようとする場合で
あって、当該同意を受けた範囲内における研究の内容(提供先等を含む。)が特定さ
れたときは、当該研究の内容に係る研究計画書の作成又は変更を行わなければなら
ない。
⑵ 研究責任者は、⑴の研究計画書の作成又は変更に当たっては、研究の倫理的妥当
性及び科学的合理性が確保されるよう考慮しなければならない。また、研究対象者
への負担並びに予測されるリスク及び利益を総合的に評価するとともに、負担及び
リスクを最小化する対策を講じなければならない。
⑶ 多機関共同研究を実施する研究責任者は、当該多機関共同研究として実施する研
究に係る業務を代表するため、当該研究責任者の中から、研究代表者を選任しなけ
ればならない。
⑷ 研究代表者は、多機関共同研究を実施しようとする場合には、各共同研究機関の
研究責任者の役割及び責任を明確にした上で一の研究計画書を作成又は変更しなけ
ればならない。
⑸ 研究責任者は、研究に関する業務の一部について委託しようとする場合には、当
該委託業務の内容を定めた上で研究計画書を作成又は変更しなければならない。
10
いて、必要に応じ、自ら点検及び評価を行い、その結果に基づき適切な対応をとら
なければならない。
⑹ 研究機関の長は、倫理審査委員会が行う調査に協力しなければならない。
⑺ 研究機関の長は、研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知識及び技術に関
する教育・研修を当該研究機関の研究者等が受けることを確保するための措置を講
じなければならない。また、自らもこれらの教育・研修を受けなければならない。
⑻ 研究機関の長は、当該研究機関において定められた規程により、この指針に定め
る権限又は事務を当該研究機関内の適当な者に委任することができる。
第3章 研究の適正な実施等
第6 研究計画書に関する手続
1 研究計画書の作成・変更
⑴ 研究責任者は、研究を実施しようとするときは、あらかじめ研究計画書を作成し
なければならない。また、研究計画書の内容と異なる研究を実施しようとするとき
は、あらかじめ研究計画書を変更しなければならない。なお、第8の5㉑に掲げる
事項について同意を受けた既存試料・情報を用いて研究を実施しようとする場合で
あって、当該同意を受けた範囲内における研究の内容(提供先等を含む。)が特定さ
れたときは、当該研究の内容に係る研究計画書の作成又は変更を行わなければなら
ない。
⑵ 研究責任者は、⑴の研究計画書の作成又は変更に当たっては、研究の倫理的妥当
性及び科学的合理性が確保されるよう考慮しなければならない。また、研究対象者
への負担並びに予測されるリスク及び利益を総合的に評価するとともに、負担及び
リスクを最小化する対策を講じなければならない。
⑶ 多機関共同研究を実施する研究責任者は、当該多機関共同研究として実施する研
究に係る業務を代表するため、当該研究責任者の中から、研究代表者を選任しなけ
ればならない。
⑷ 研究代表者は、多機関共同研究を実施しようとする場合には、各共同研究機関の
研究責任者の役割及び責任を明確にした上で一の研究計画書を作成又は変更しなけ
ればならない。
⑸ 研究責任者は、研究に関する業務の一部について委託しようとする場合には、当
該委託業務の内容を定めた上で研究計画書を作成又は変更しなければならない。
10