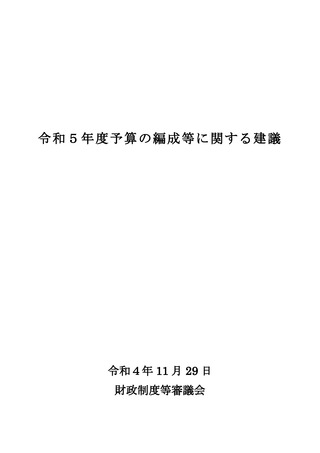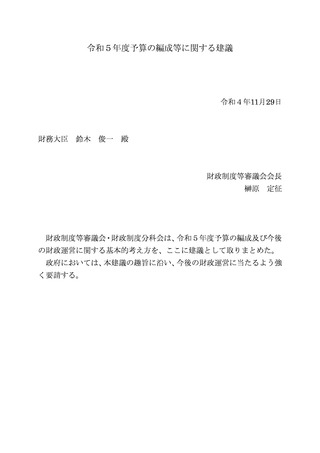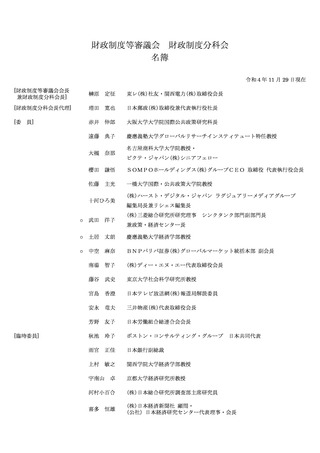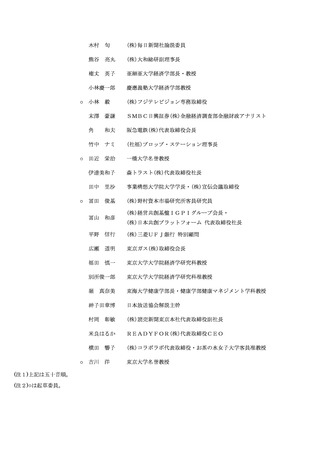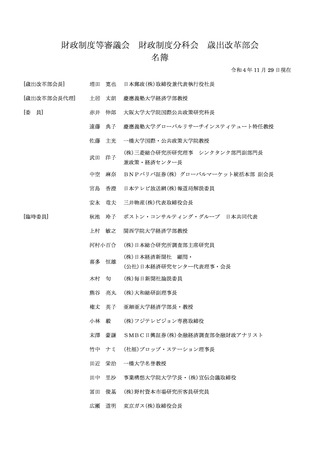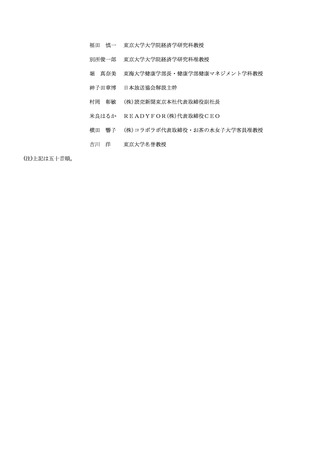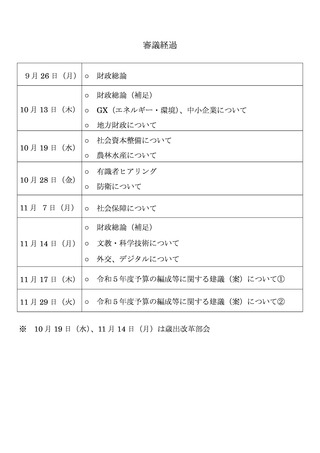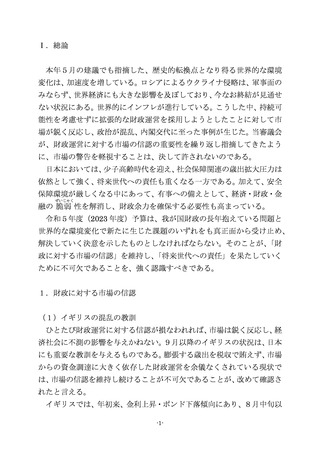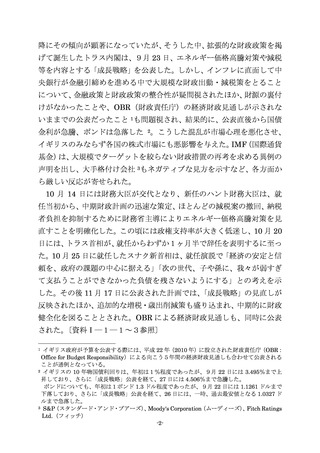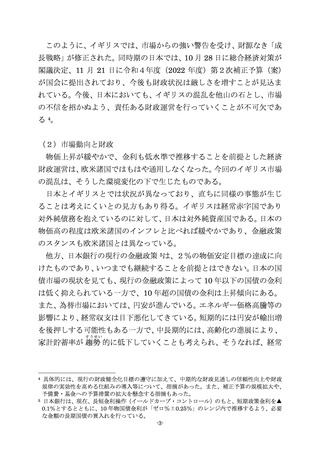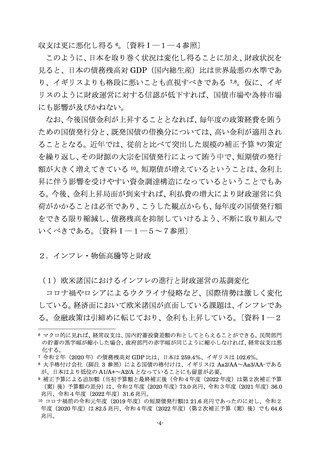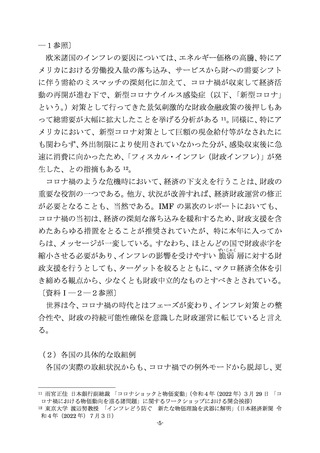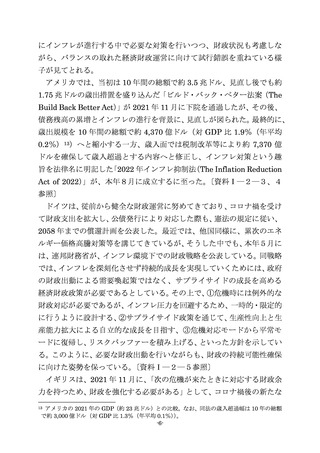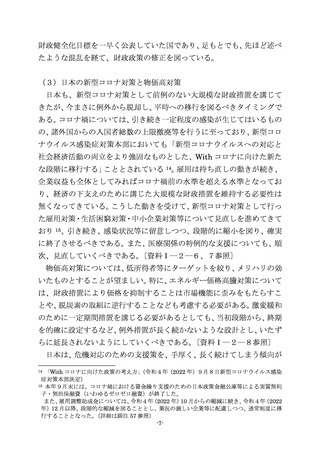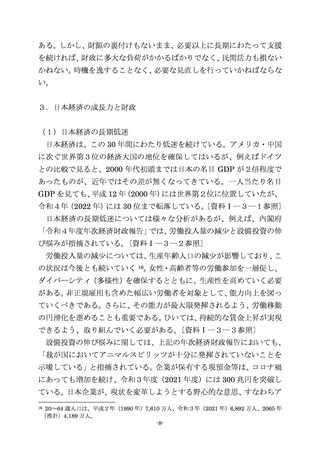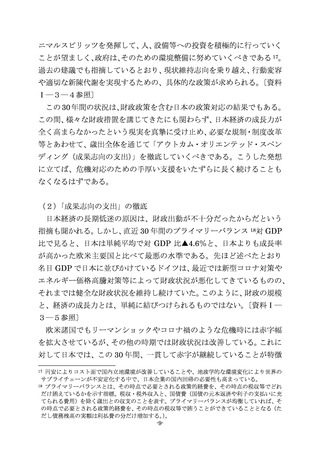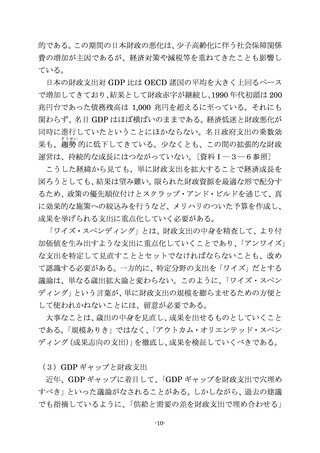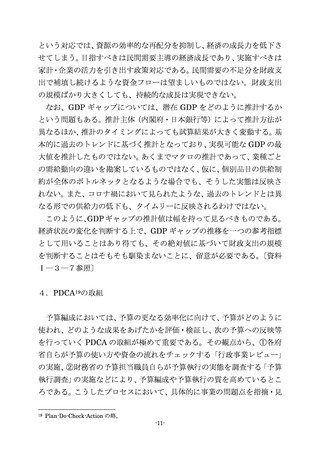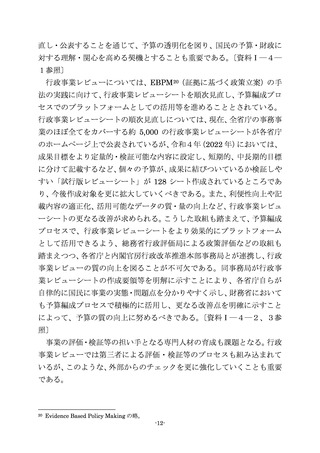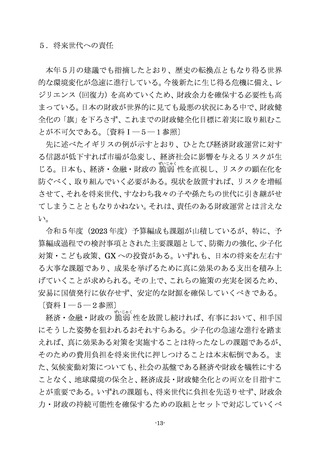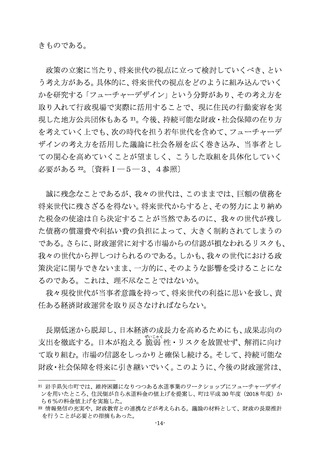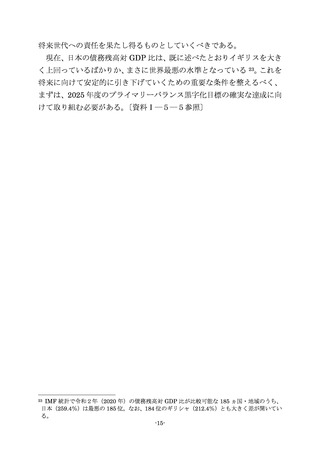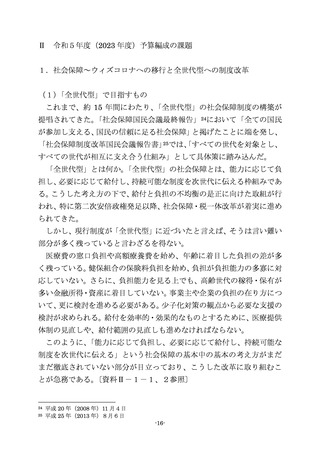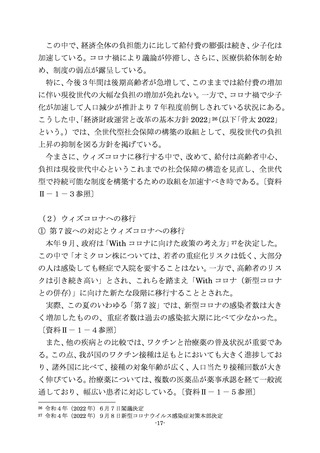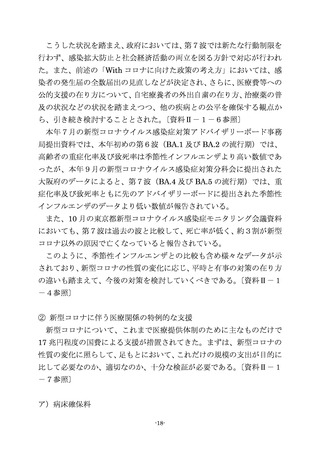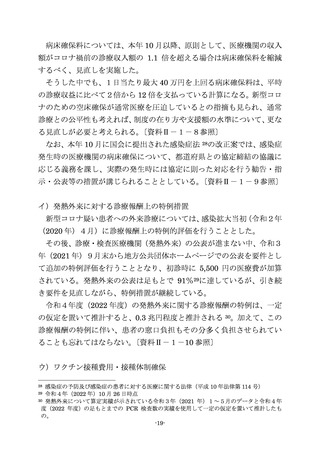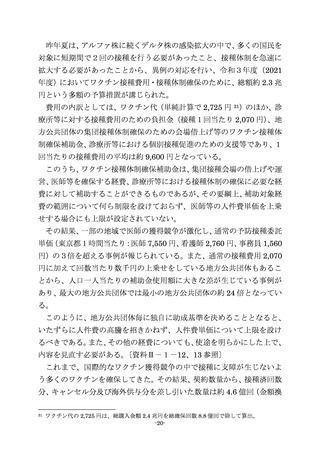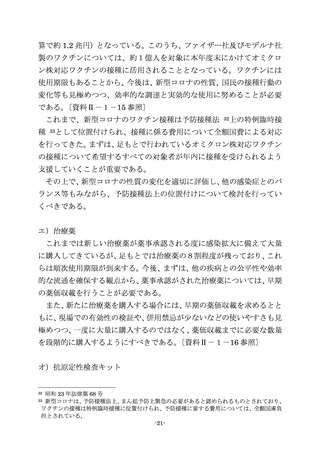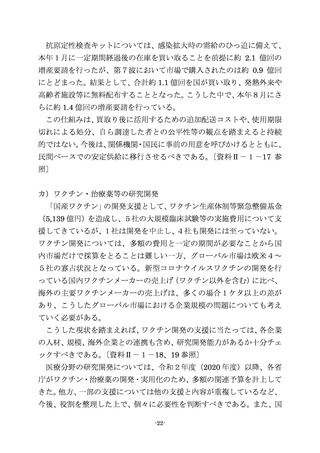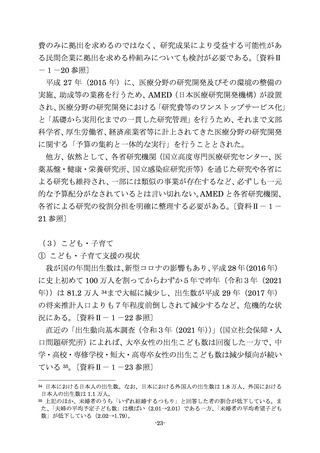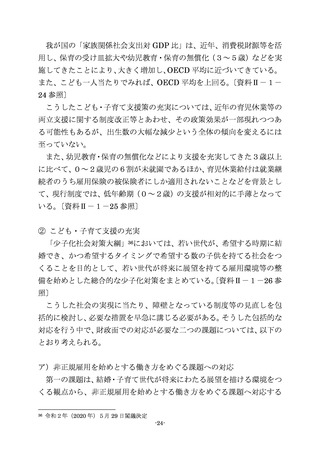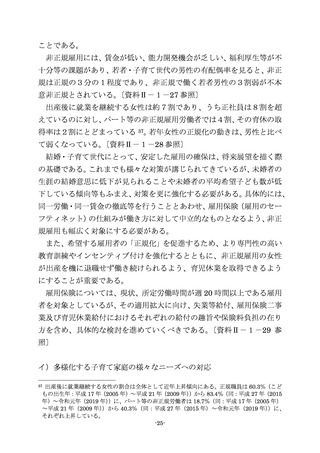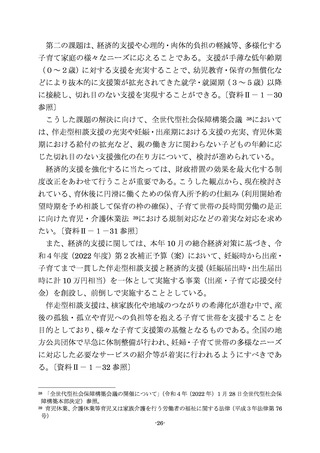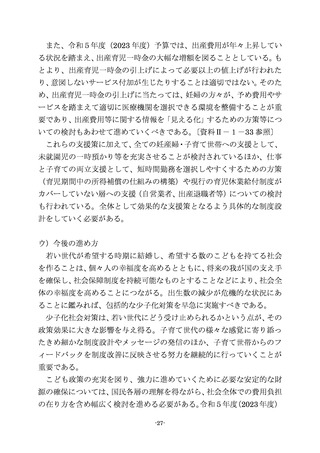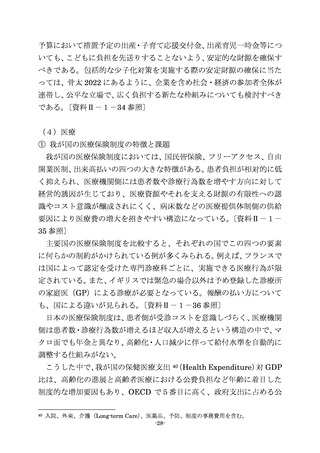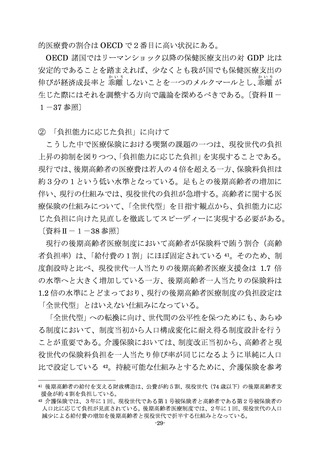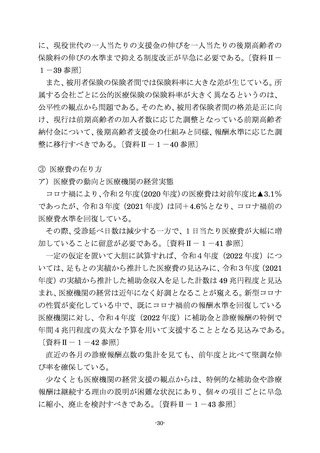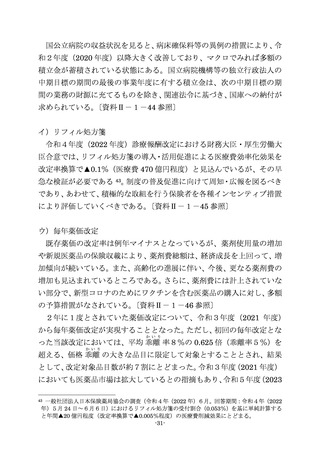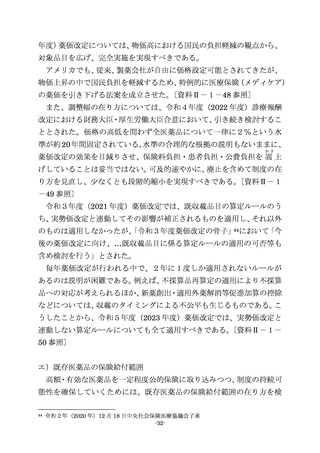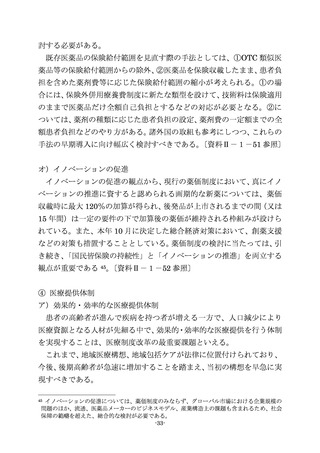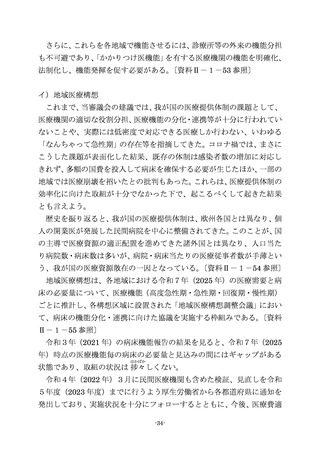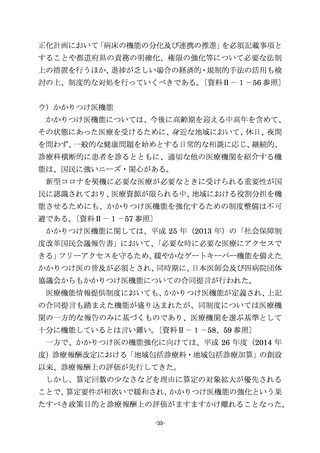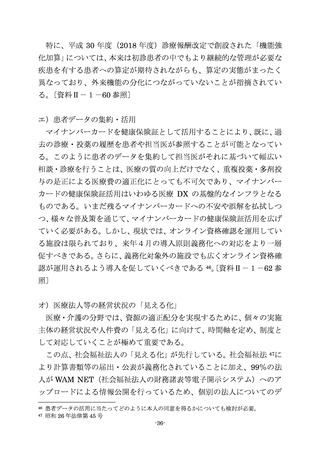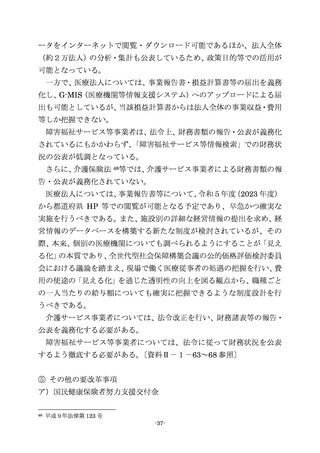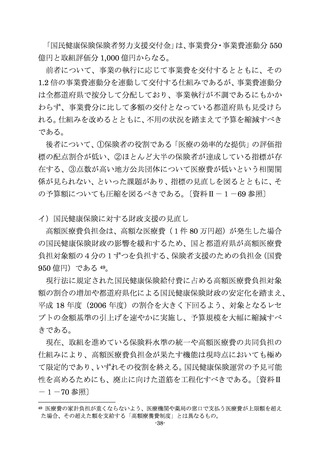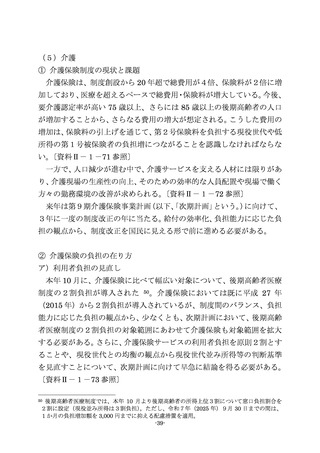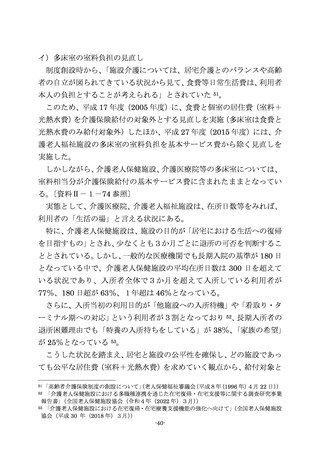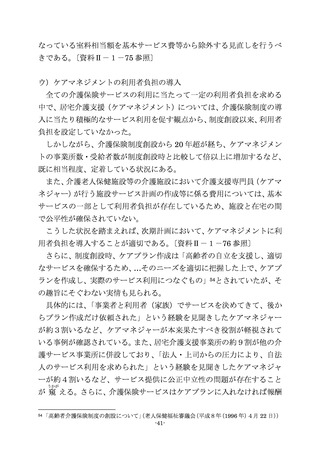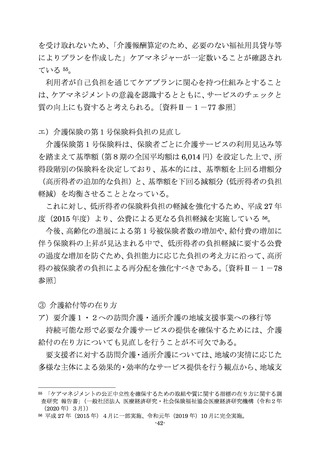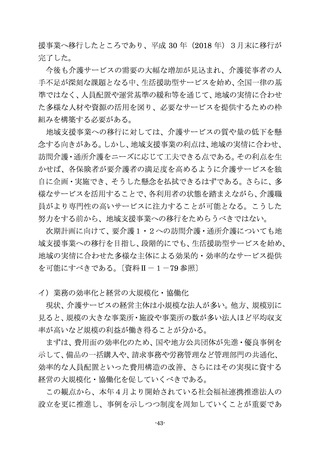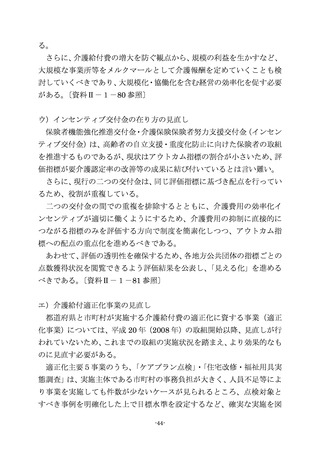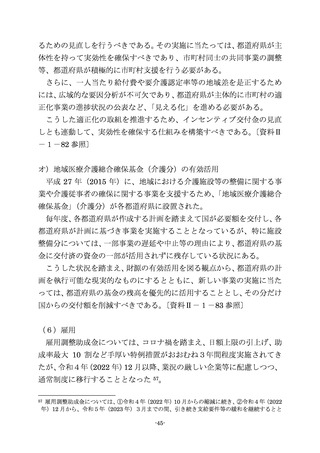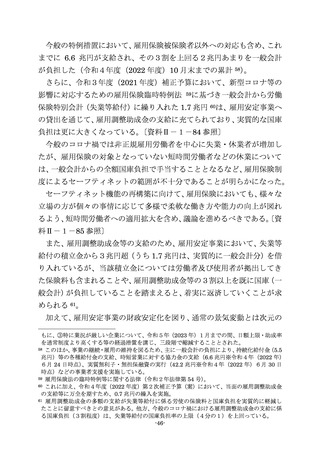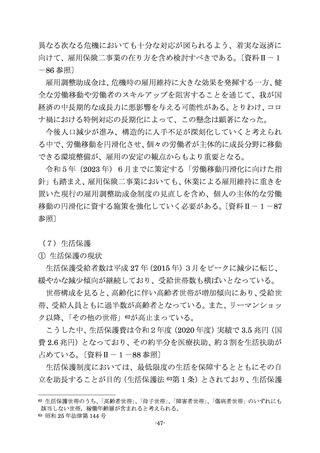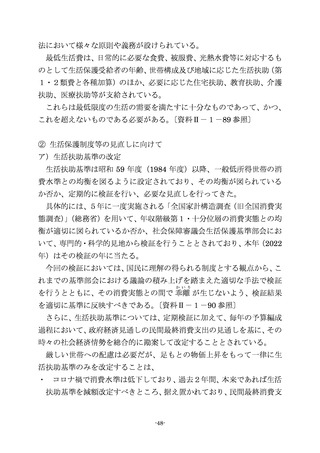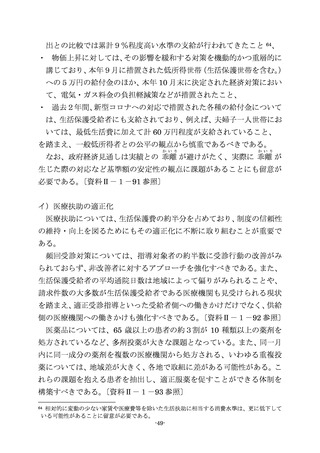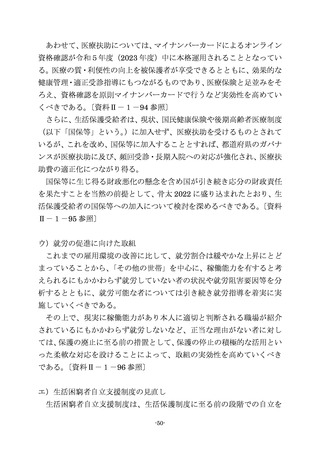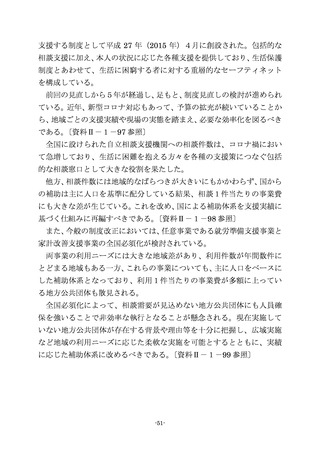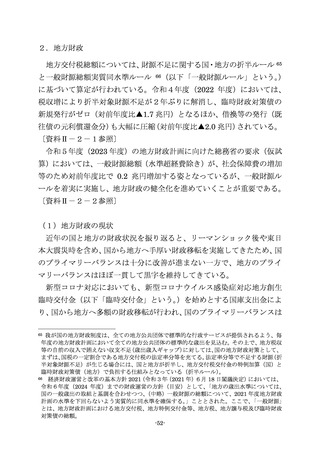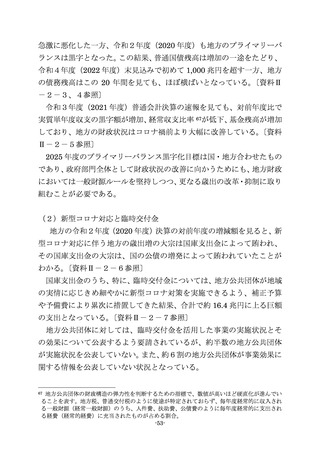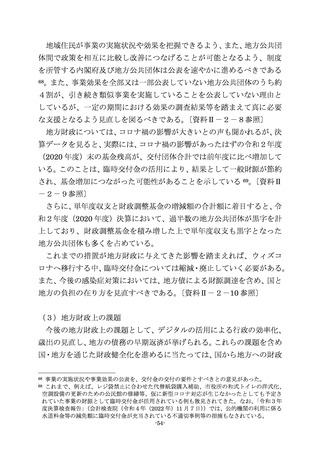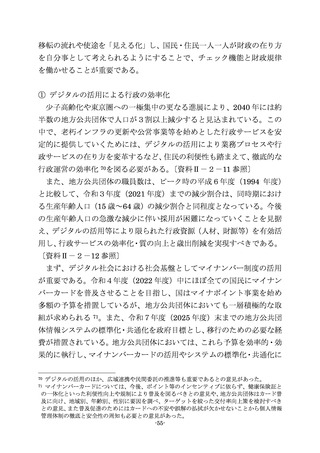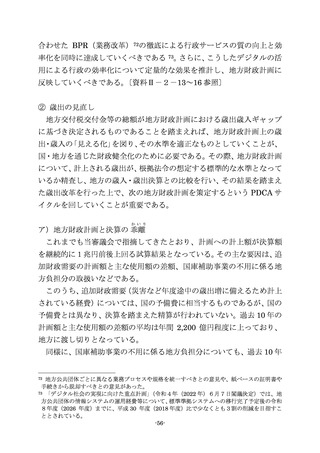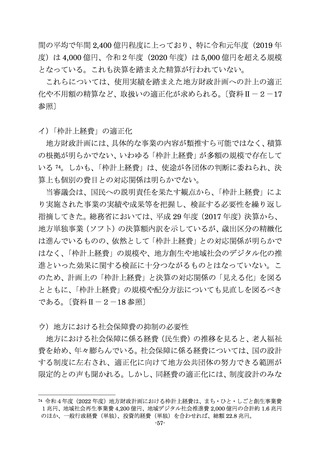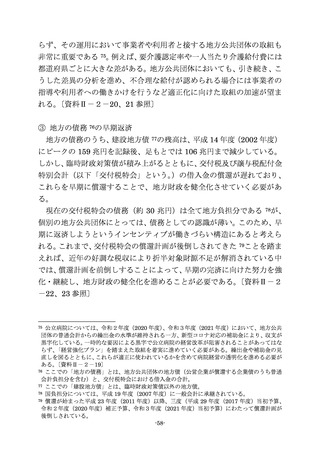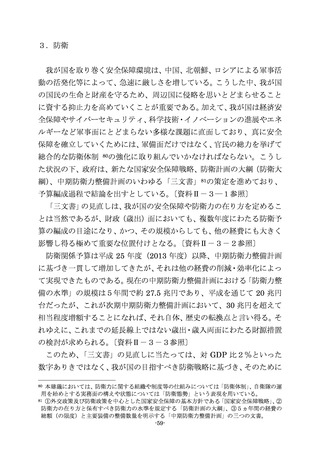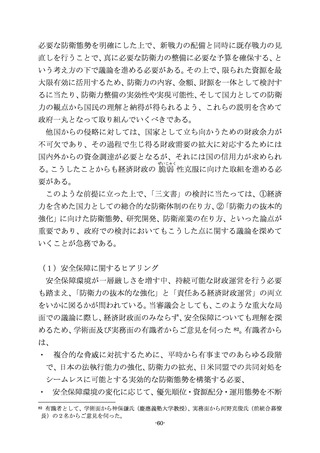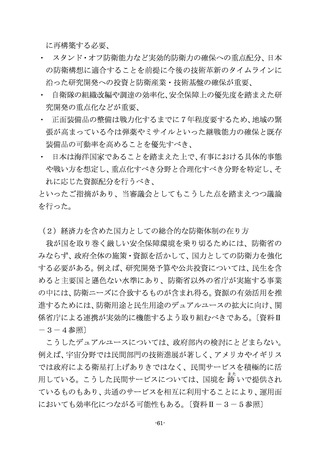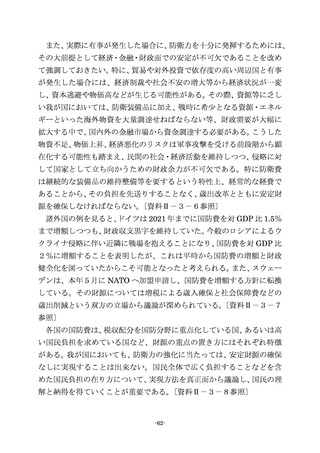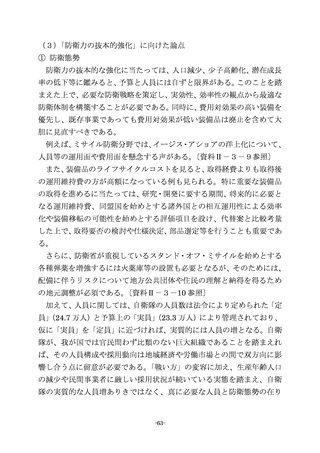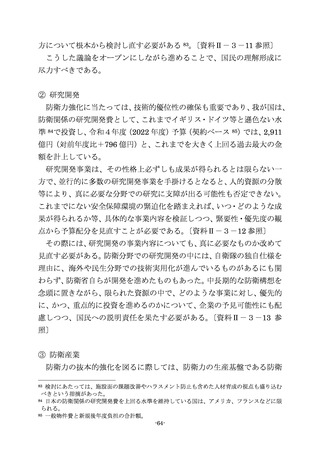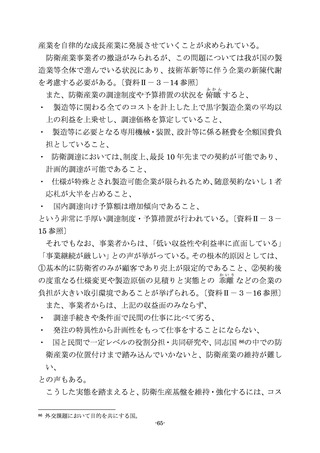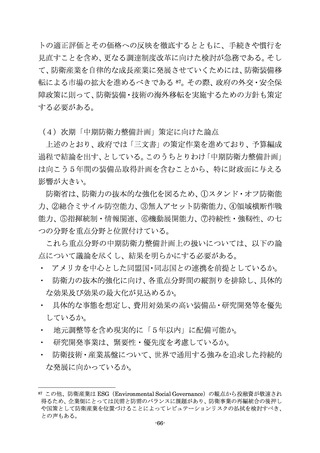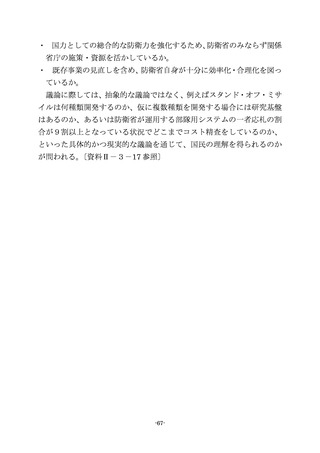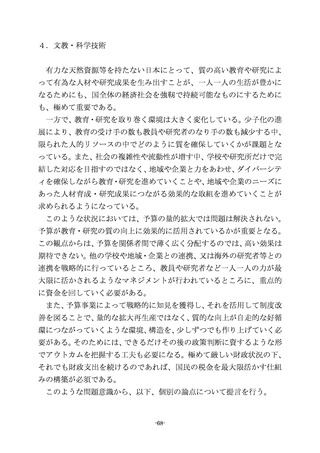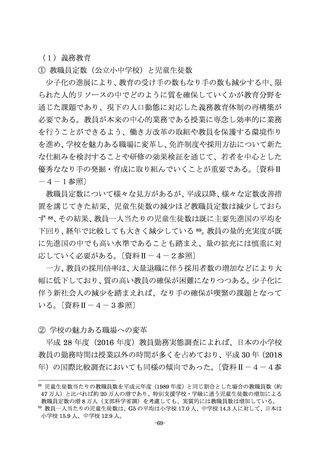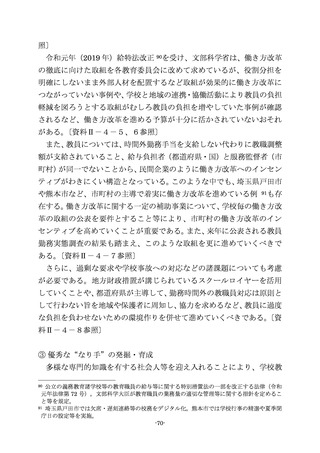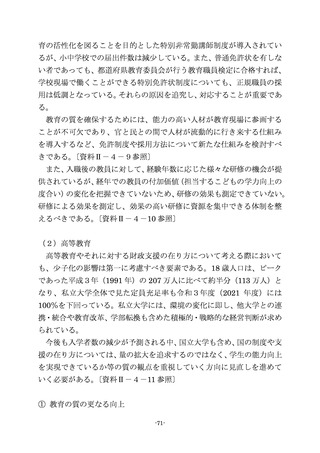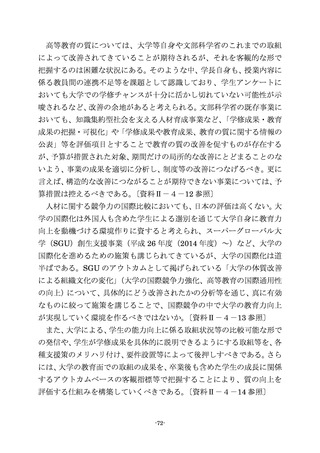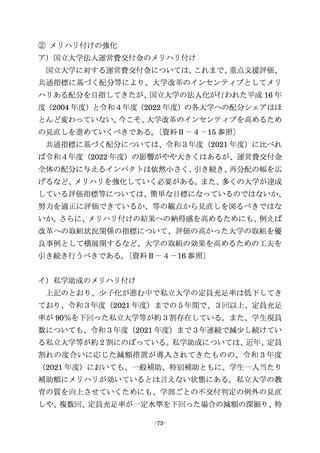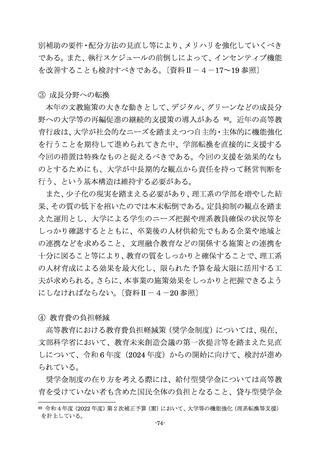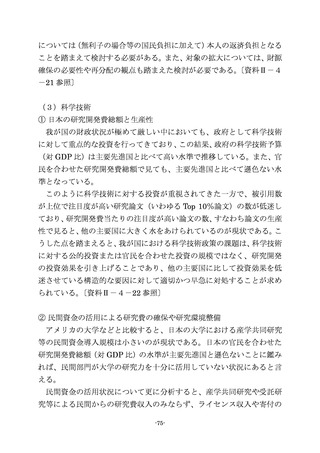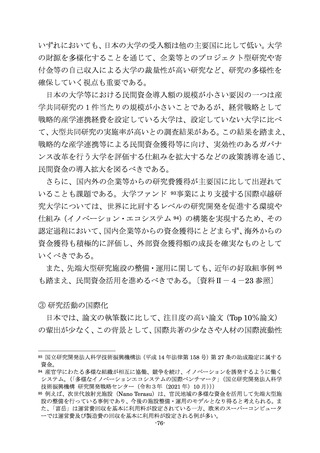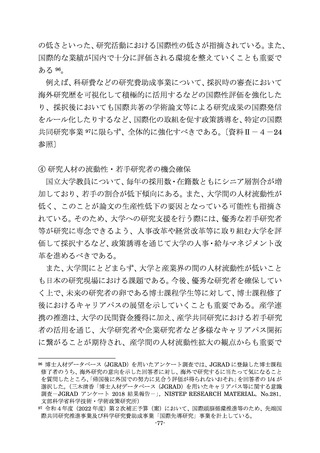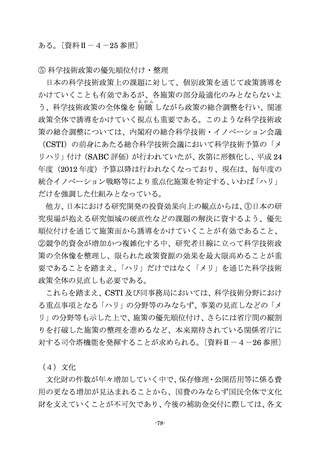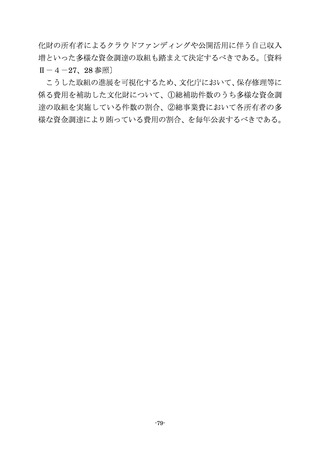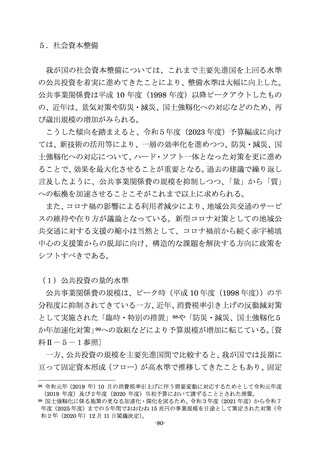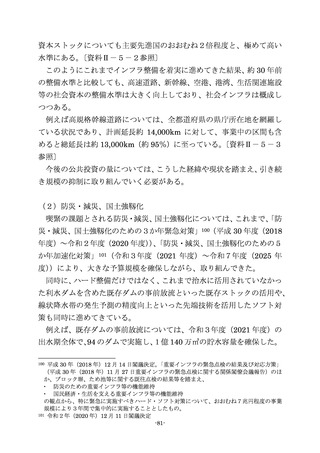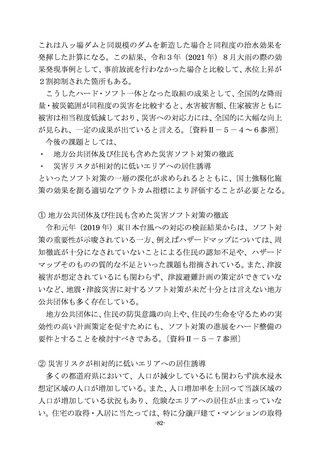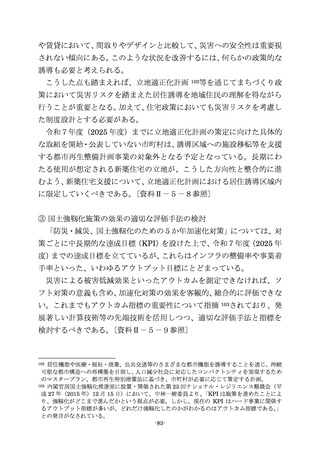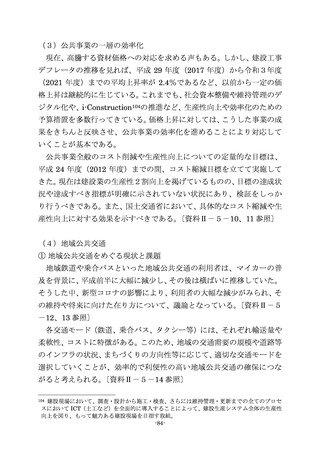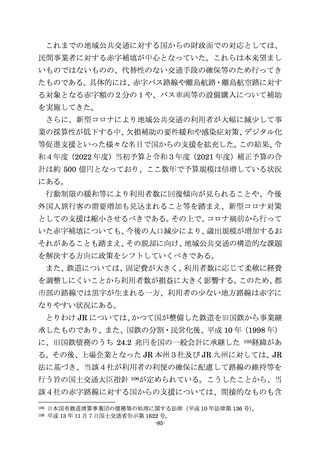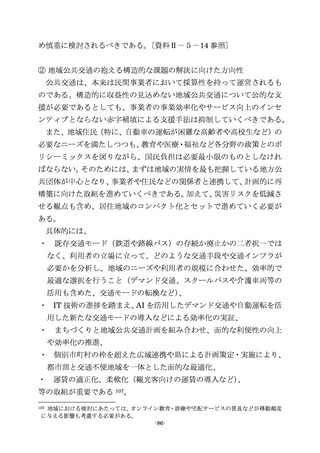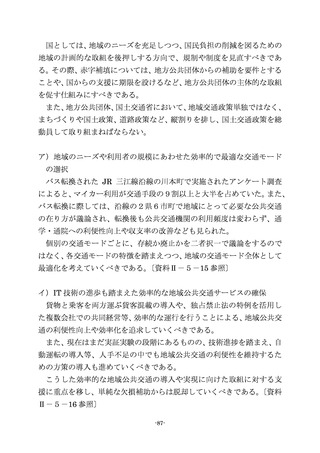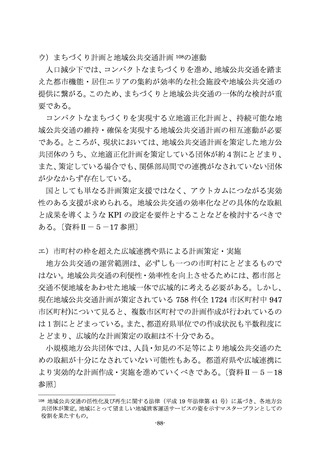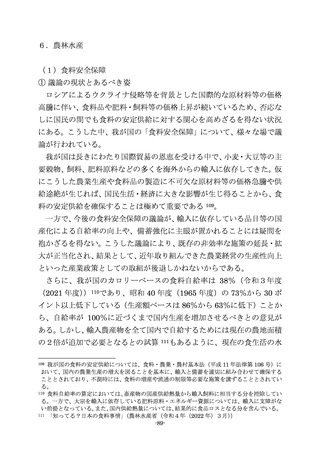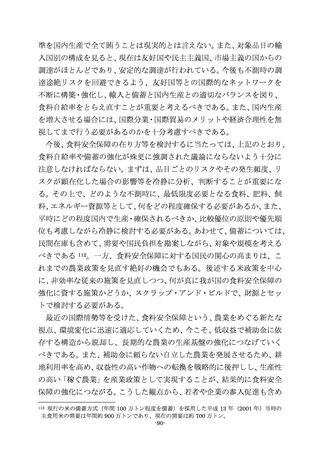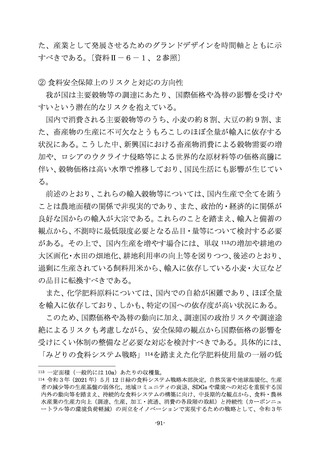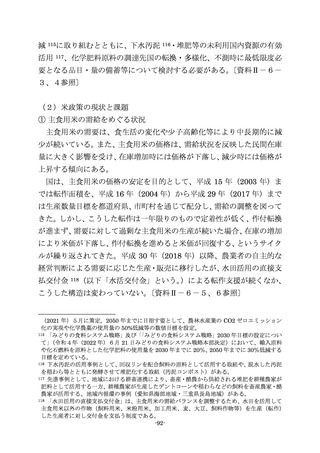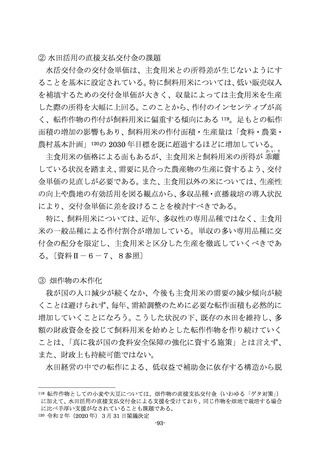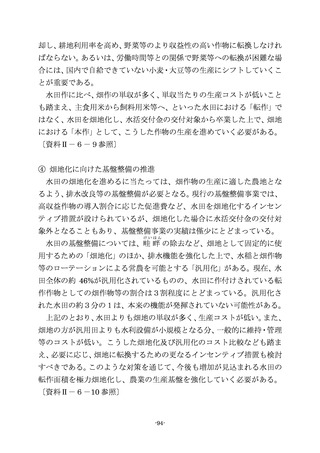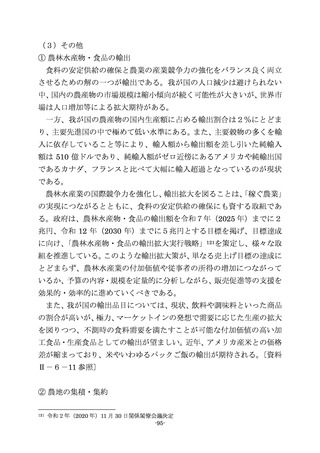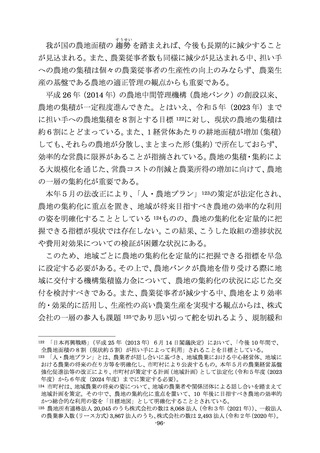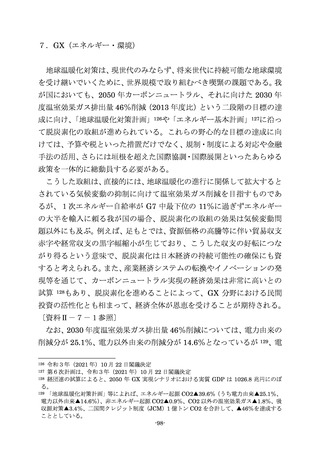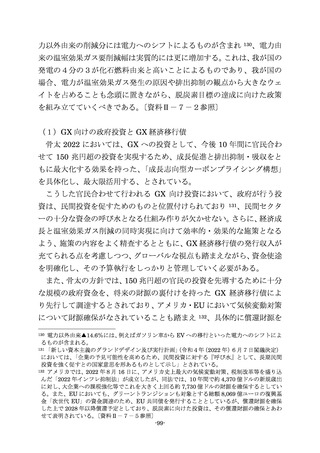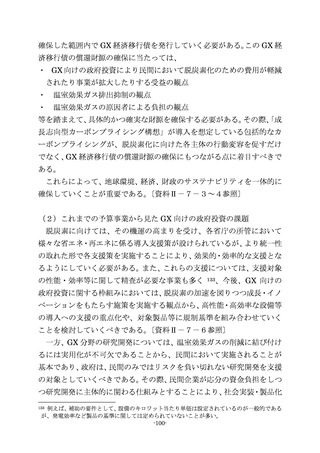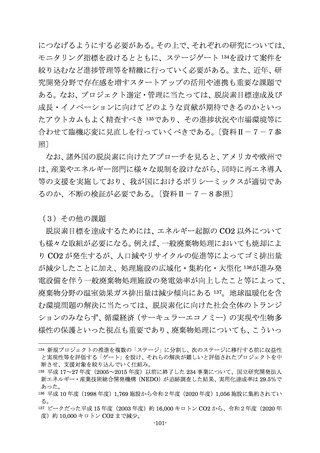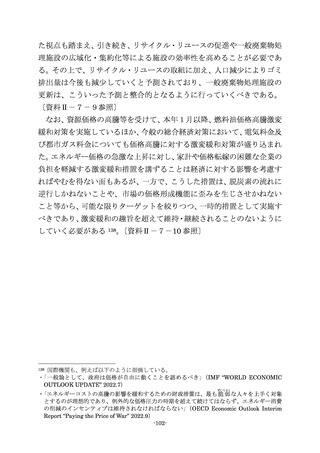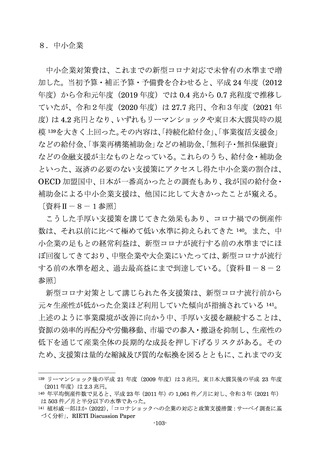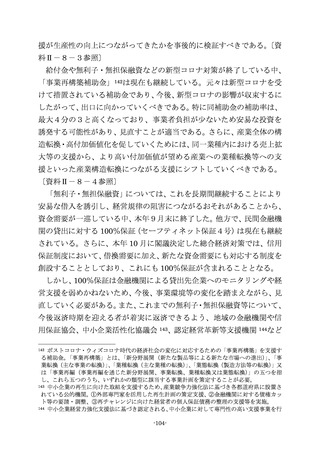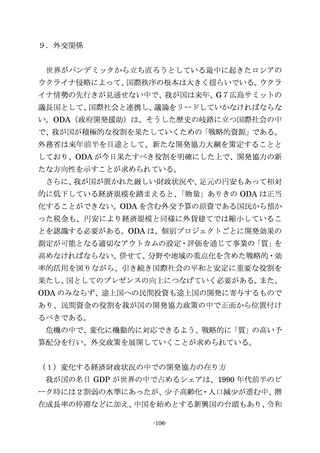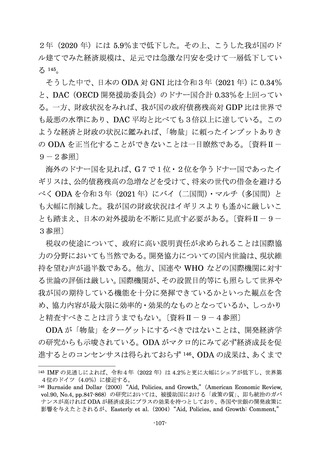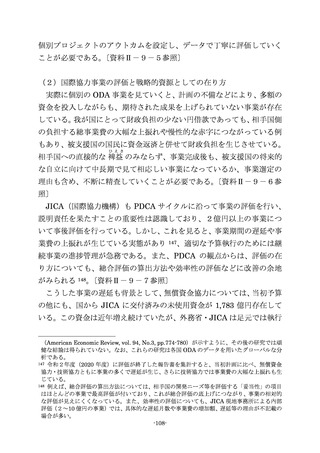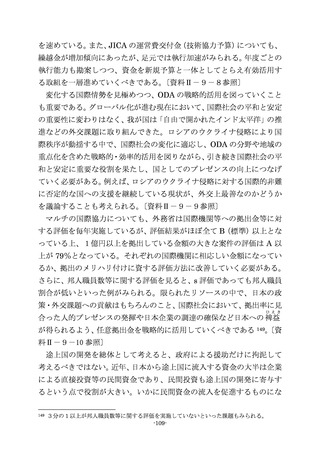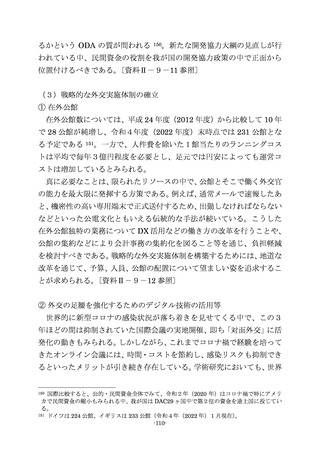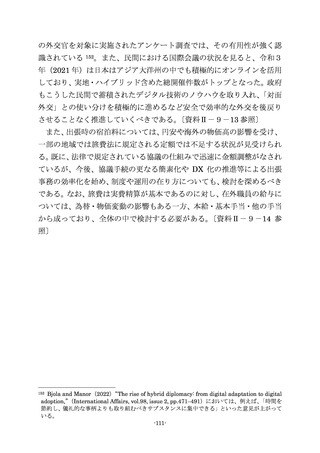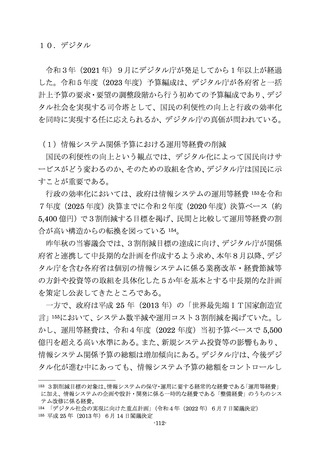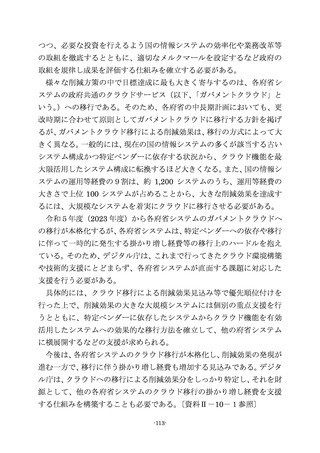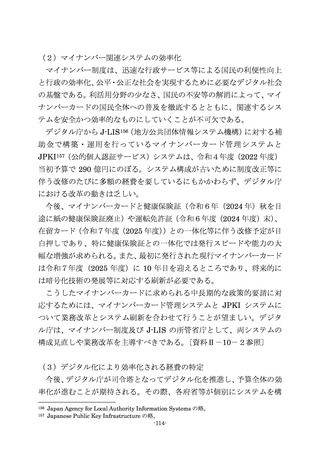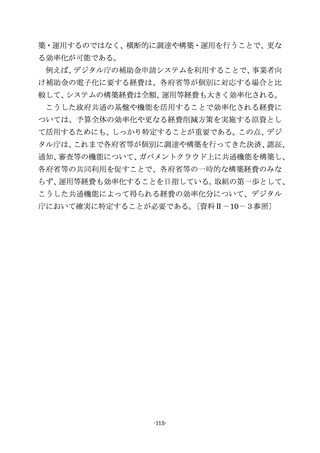令和5年度予算の編成等に関する建議 (101 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html |
| 出典情報 | 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
入国別の構成を見ると、現在は友好国や民主主義国、市場主義の国からの
調達がほとんどであり、安定的な調達が行われている。今後も不測時の調
達途絶リスクを回避できるよう、友好国等との国際的なネットワークを
不断に構築・強化し、輸入と備蓄と国内生産との適切なバランスを図り、
食料自給率をとらえ直すことが重要と考えるべきである。また、国内生産
を増大させる場合には、国際分業・国際貿易のメリットや経済合理性を無
視してまで行う必要があるのかを十分考慮すべきである。
今後、食料安全保障の在り方等を検討するに当たっては、上記のとおり、
食料自給率や備蓄の強化が殊更に強調された議論にならないよう十分に
注意しなければならない。まずは、品目ごとのリスクやその発生頻度、リ
スクが顕在化した場合の影響等を冷静に分析、判断することが重要にな
る。その上で、どのような不測時に、最低限度必要となる食料、肥料、飼
料、エネルギー資源等として、何をどの程度確保する必要があるか、また、
平時にどの程度国内で生産・確保されるべきか、比較優位の原則や優先順
位も考慮しながら冷静に検討する必要がある。あわせて、備蓄については、
民間在庫も含めて、需要や国民負担を勘案しながら、対象や規模を考える
べきである
112。一方、食料安全保障に対する国民の関心の高まりは、こ
れまでの農業政策を見直す絶好の機会でもある。後述する米政策を中心
に、非効率な従来の施策を見直しつつ、何が真に我が国の食料安全保障の
強化に資する施策かどうか、スクラップ・アンド・ビルドで、財源とセッ
トで検討する必要がある。
最近の国際情勢等を受けた、食料安全保障という、農業をめぐる新たな
視点、環境変化に迅速に適応していくため、今こそ、低収益で補助金に依
存する構造から脱却し、長期的な農業の生産基盤の強化につなげていく
べきである。また、補助金に頼らない自立した農業を発展させるため、耕
地利用率を高め、収益性の高い作物への転換を戦略的に後押しし、生産性
の高い「稼ぐ農業」を産業政策として実現することが、結果的に食料安全
保障の強化につながる。こうした観点から、若者や企業の参入促進も含め
現行の米の備蓄方式(年間 100 万トン程度を備蓄)を採用した平成 13 年(2001 年)当時の
主食用米の需要は年間約 900 万トンであり、現在の需要は約 700 万トン。
-90-
112