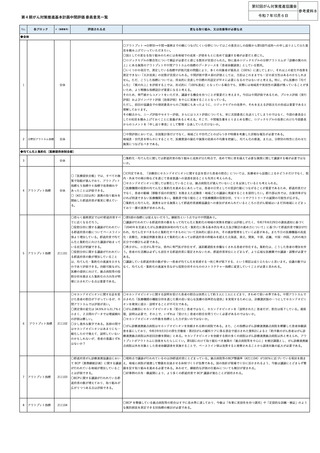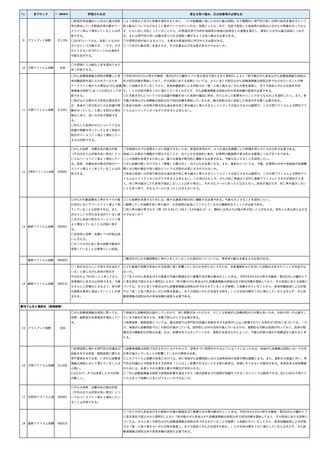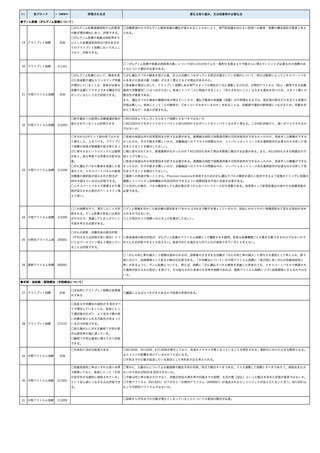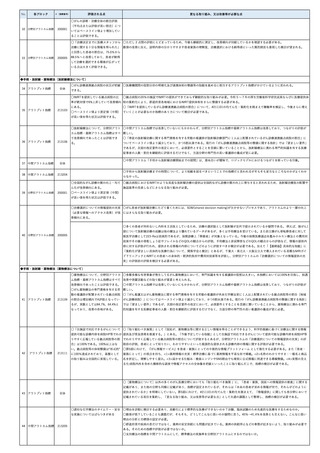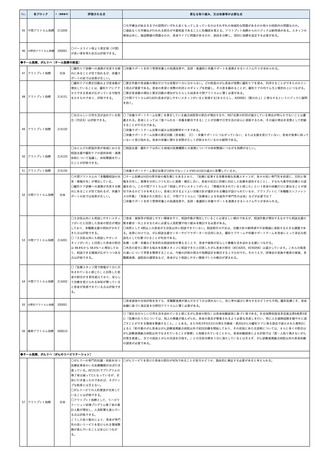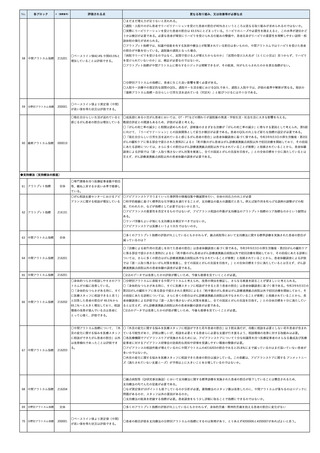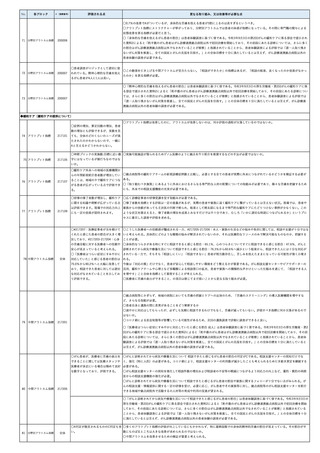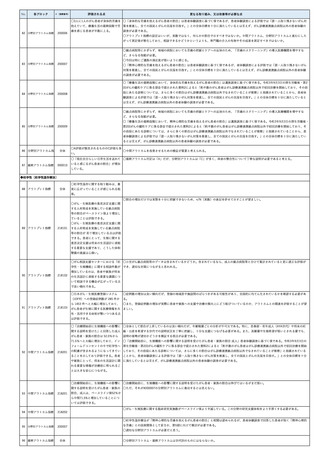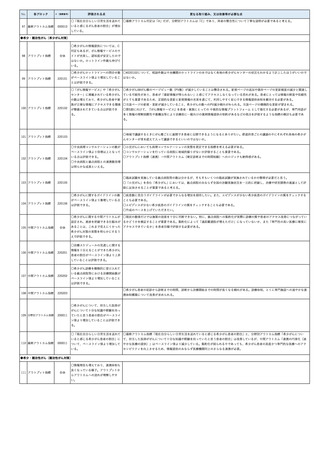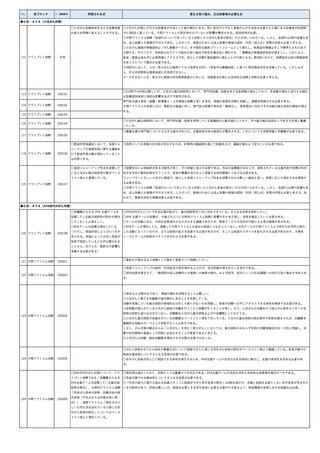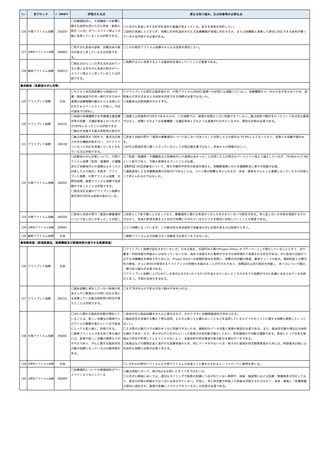よむ、つかう、まなぶ。
参考資料8 第4期がん対策推進基本計画中間評価 委員意見一覧 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64289.html |
| 出典情報 | がん対策推進協議会(第92回 10/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
No.
各ブロック
評価される点
#(指標番号)
更なる取り組み、又は改善等が必要な点
○0.7%の改善でAがついているが、身体的な苦痛を抱える患者が3割に上るのは高すぎるというべき。
○アウトプット指標にストラクチャーが挙がっており、分野別アウトカムでは患者の体感が指標になっている。その間に専門職の関与による
状態改善を測る指標が必要だと思う。
71 分野別アウトカム指標
○「身体的な苦痛を抱えるがん患者の割合」は患者体験調査に基づく値である。令和3年9月3日の第2回がんの緩和ケアに係る部会で提示され
200006
た資料2によると「約半数のがん患者はがん診療連携拠点病院以外で初回治療を開始しており、その前段にあたる診断については、さらに多く
の割合はがん診療連携拠点病院以外でなされていることが推察」と指摘されていることから、患者体験調査による評価では「誰一人取り残さ
ないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」との全体目標を十分に満たしているとは言えず、がん診療連携拠点病院以外の
患者体験の調査が必要である。
○患者調査がロジックとして適切に使
72 分野別アウトカム指標
200007
われている。精神心理的な苦痛を抱え
るがん患者が4人に1人は高い。
○この数値を引き上げる中間アウトカムが見当たらない。「相談ができたか」の指標はあるが、「相談の結果、良くなったのか効果がなかっ
たのか」を測る指標が必要。
○「精神心理的な苦痛を抱えるがん患者の割合」は患者体験調査に基づく値である。令和3年9月3日の厚生労働省・第2回がんの緩和ケアに係
る部会で提示された資料2によると「約半数のがん患者はがん診療連携拠点病院以外で初回治療を開始しており、その前段にあたる診断につい
73 分野別アウトカム指標
ては、さらに多くの割合はがん診療連携拠点病院以外でなされていることが推察」と指摘されていることから、患者体験調査による評価では
200007
「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」との全体目標を十分に満たしているとは言えず、がん診療連
携拠点病院以外の患者体験の調査が必要である。
◆緩和ケア〔緩和ケアの提供について〕
○症例の増加、算定回数の増加、患者
○アウトプット指標は改善したのに、アウトカムが改善しないのは、何か評価の過程が欠落しているのではないか。
数の増加とも評価できるが、実数を見
74 アウトプット指標
217101
ても、全体のどのくらいのニーズが満
たされたのかわからないので、一概に
Aと言えるかどうかわからない。
○神経ブロックの実施数:目標に近い数 ○実施可能施設が限られるためゲノム医療のように拠点を作り紹介を推奨するなどの手法が必要ではないか。
75 アウトプット指標
217105
字にはなっているが頭打ちなのではな
いか。
○緩和ケア外来への地域の医療機関か
76 アウトプット指標
217107
らの年間新規紹介患者数が増加してい ○拠点病院等の緩和ケアチームの新規診療症例数と比較し、必要とする全ての患者が実際に外来につながれているかどうかを検証する必要が
ることは、地域の中で緩和ケアにつな ある。
がる患者が広がっている点で評価でき ○「取り組むべき施策」にあるように外来におけるさらなる専門的な人材の配置についての取組みが必要であり、様々な苦痛を把握するため
にも、外来での相談支援機能の充実が必要である。
る。
○研修の修了者数が増加し、緩和ケア ○広く診療従事者の研修受講を促す取組みが必要である。
に関する知識や理解が広がっている点 ○修了者数を指標とする評価は一定の意義があるが、実際の患者や家族に届く緩和ケアに繋がっているとは言えない状況。現場では、患者や
77 アウトプット指標
217109
は評価できます。現場での対応力向上 家族からの依頼があっても主治医の判断で断られ、結果として終末期になるまで専門的な緩和ケアにたどりつけない事例が少なくない。この
にも一定の効果が期待されます。
ような状況を踏まえると、修了者数の増加を成果とみなすだけでは不十分であり、むしろ「いかに適切な時期につなげられるか」というプロ
セスに着目した調査や評価を求める。
○#217207:医療従事者が耳を傾けて ○こうした医療者への信頼感が醸成される一方、#217205-217206:本人・家族の生活などの悩みや負担に関しては、相談や支援が十分ではな
くれたと感じた患者の割合が大きく増 いと考えられる。具体的にどのような種類の悩みが解消されていないのか、それは医療的なリソースのみで解決可能なものなのか、把握する
加しており、#217203-217204:心身
ことが必要。
の苦痛全般に対する医療者への信頼や ○身体的なつらさがある時にすぐに相談できると感じる割合:65.1%、心のつらさについてすぐに相談できると感じる割合:47.6%、がんと
安心が高まっていると考えられる。
診断されてから病気や療養生活について相談できたと感じる割合:76.3%から60.6%へ減少という結果から、相談できた人には十分な対応が
○「医療者はつらい症状にすみやかに されている一方で、そもそも「相談しにくい」「相談できない」患者が相当数存在し、苦しみを抱えたままになっている可能性が強く示唆さ
78 中間アウトカム指標
全体
対応していた」と感じる患者の割合は れる。
75.0%から90.2%へと大幅に改善して
今後は「対応の質」だけでなく、患者が安心して相談しやすい環境をどう整えるかが重要である。がん相談支援センターやピアサポーターの
おり、相談できた患者に対しては適切 活用、緩和ケアチームや心理士など多職種による相談窓口の拡充、患者や家族への積極的な声かけといった仕組みを通じて、「相談できる人
な対応がなされていることを示してお
を増やす」こと自体を指標として重視することが考えられる。
り評価できる。
○医療者に苦痛の表出ができること、の項目は総じてまだ低いことから更なる取り組みが必要。
○拠点病院等にかぎらず、地域の病院においても苦痛の把握とケアへの反映のため、「苦痛のスクリーニング」の導入医療機関を増やすな
ど、さらなる取組が必要。
○患者自身と遺族の間に差異があることをどう解釈するか
○速やかに対応はしてもらったが、必ずしも気軽に相談できるわけでもなく、苦痛が減ってもいない。評価すべき指標に何か欠落があるので
はないか。
79 中間アウトカム指標
○コロナ禍による面会制限等が影響している可能性があるため、次回の遺族調査で詳細に調査ができると良い。
217201
○「医療者はつらい症状にすみやかに対応していたと感じる割合 成人」は患者体験調査に基づく値である。令和3年9月3日の厚生労働省・第2
回がんの緩和ケアに係る部会で提示された資料2によると「約半数のがん患者はがん診療連携拠点病院以外で初回治療を開始しており、その前
段にあたる診断については、さらに多くの割合はがん診療連携拠点病院以外でなされていることが推察」と指摘されていることから、患者体
験調査による評価では「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」との全体目標を十分に満たしていると
は言えず、がん診療連携拠点病院以外の患者体験の調査が必要である。
○がん患者が、医療者に苦痛の表出を ○がんと診断されてから病気や療養生活について 相談できたと感じるがん患者の割合の判定がCである。相談支援センターの周知だけでな
できることに関しては医療スタッフや く、強化(特に人的)の必要がある。コロナ禍により、相談支援センターの利用数が減少したことも考えられるため引き続き測定を継続する
医療者が身近にいる場合は極めて良好 必要がある。
な数字となっており、評価できる。
○がん相談支援センターの周知を強化して相談件数の増加および相談者の不安等の軽減につながるよう対応力の向上など、量的・質的の両側
面からの相談支援機能の強化が必要。
○がんと診断されてから病気や療養生活について相談できたと感じるがん患者の割会や家族に関するフォローが十分でない点がみられる。が
80 中間アウトカム指標
んの相談支援・情報提供に関する一定の研修を受け、必要に応じ、がん患者やその家族等に対し、拠点病院等のがん相談支援センターを紹介
217205
できる地域や拠点病院外で活動するの人材等の育成や利用の促進が望まれる。
○「がんと診断されてから病気や療養生活について相談できたと感じるがん患者の割合」は患者体験調査に基づく値である。令和3年9月3日の
厚生労働省・第2回がんの緩和ケアに係る部会で提示された資料2によると「約半数のがん患者はがん診療連携拠点病院以外で初回治療を開始
しており、その前段にあたる診断については、さらに多くの割合はがん診療連携拠点病院以外でなされていることが推察」と指摘されている
ことから、患者体験調査による評価では「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」との全体目標を十分
に満たしているとは言えず、がん診療連携拠点病院以外の患者体験の調査が必要である。
○A判定が散見されるもののC判定も多 ○多くのアウトプット指標の評価が向上しているにもかかわらず、特に最終段階での身体的精神的苦痛の割合が高まっている。その割合が半
81 分野別アウトカム指標
全体
い。
数にものぼるところは大きな改善が求められるのではないか。
○中間アウトカムを改善させるための検証が重要と考えられる。
各ブロック
評価される点
#(指標番号)
更なる取り組み、又は改善等が必要な点
○0.7%の改善でAがついているが、身体的な苦痛を抱える患者が3割に上るのは高すぎるというべき。
○アウトプット指標にストラクチャーが挙がっており、分野別アウトカムでは患者の体感が指標になっている。その間に専門職の関与による
状態改善を測る指標が必要だと思う。
71 分野別アウトカム指標
○「身体的な苦痛を抱えるがん患者の割合」は患者体験調査に基づく値である。令和3年9月3日の第2回がんの緩和ケアに係る部会で提示され
200006
た資料2によると「約半数のがん患者はがん診療連携拠点病院以外で初回治療を開始しており、その前段にあたる診断については、さらに多く
の割合はがん診療連携拠点病院以外でなされていることが推察」と指摘されていることから、患者体験調査による評価では「誰一人取り残さ
ないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」との全体目標を十分に満たしているとは言えず、がん診療連携拠点病院以外の
患者体験の調査が必要である。
○患者調査がロジックとして適切に使
72 分野別アウトカム指標
200007
われている。精神心理的な苦痛を抱え
るがん患者が4人に1人は高い。
○この数値を引き上げる中間アウトカムが見当たらない。「相談ができたか」の指標はあるが、「相談の結果、良くなったのか効果がなかっ
たのか」を測る指標が必要。
○「精神心理的な苦痛を抱えるがん患者の割合」は患者体験調査に基づく値である。令和3年9月3日の厚生労働省・第2回がんの緩和ケアに係
る部会で提示された資料2によると「約半数のがん患者はがん診療連携拠点病院以外で初回治療を開始しており、その前段にあたる診断につい
73 分野別アウトカム指標
ては、さらに多くの割合はがん診療連携拠点病院以外でなされていることが推察」と指摘されていることから、患者体験調査による評価では
200007
「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」との全体目標を十分に満たしているとは言えず、がん診療連
携拠点病院以外の患者体験の調査が必要である。
◆緩和ケア〔緩和ケアの提供について〕
○症例の増加、算定回数の増加、患者
○アウトプット指標は改善したのに、アウトカムが改善しないのは、何か評価の過程が欠落しているのではないか。
数の増加とも評価できるが、実数を見
74 アウトプット指標
217101
ても、全体のどのくらいのニーズが満
たされたのかわからないので、一概に
Aと言えるかどうかわからない。
○神経ブロックの実施数:目標に近い数 ○実施可能施設が限られるためゲノム医療のように拠点を作り紹介を推奨するなどの手法が必要ではないか。
75 アウトプット指標
217105
字にはなっているが頭打ちなのではな
いか。
○緩和ケア外来への地域の医療機関か
76 アウトプット指標
217107
らの年間新規紹介患者数が増加してい ○拠点病院等の緩和ケアチームの新規診療症例数と比較し、必要とする全ての患者が実際に外来につながれているかどうかを検証する必要が
ることは、地域の中で緩和ケアにつな ある。
がる患者が広がっている点で評価でき ○「取り組むべき施策」にあるように外来におけるさらなる専門的な人材の配置についての取組みが必要であり、様々な苦痛を把握するため
にも、外来での相談支援機能の充実が必要である。
る。
○研修の修了者数が増加し、緩和ケア ○広く診療従事者の研修受講を促す取組みが必要である。
に関する知識や理解が広がっている点 ○修了者数を指標とする評価は一定の意義があるが、実際の患者や家族に届く緩和ケアに繋がっているとは言えない状況。現場では、患者や
77 アウトプット指標
217109
は評価できます。現場での対応力向上 家族からの依頼があっても主治医の判断で断られ、結果として終末期になるまで専門的な緩和ケアにたどりつけない事例が少なくない。この
にも一定の効果が期待されます。
ような状況を踏まえると、修了者数の増加を成果とみなすだけでは不十分であり、むしろ「いかに適切な時期につなげられるか」というプロ
セスに着目した調査や評価を求める。
○#217207:医療従事者が耳を傾けて ○こうした医療者への信頼感が醸成される一方、#217205-217206:本人・家族の生活などの悩みや負担に関しては、相談や支援が十分ではな
くれたと感じた患者の割合が大きく増 いと考えられる。具体的にどのような種類の悩みが解消されていないのか、それは医療的なリソースのみで解決可能なものなのか、把握する
加しており、#217203-217204:心身
ことが必要。
の苦痛全般に対する医療者への信頼や ○身体的なつらさがある時にすぐに相談できると感じる割合:65.1%、心のつらさについてすぐに相談できると感じる割合:47.6%、がんと
安心が高まっていると考えられる。
診断されてから病気や療養生活について相談できたと感じる割合:76.3%から60.6%へ減少という結果から、相談できた人には十分な対応が
○「医療者はつらい症状にすみやかに されている一方で、そもそも「相談しにくい」「相談できない」患者が相当数存在し、苦しみを抱えたままになっている可能性が強く示唆さ
78 中間アウトカム指標
全体
対応していた」と感じる患者の割合は れる。
75.0%から90.2%へと大幅に改善して
今後は「対応の質」だけでなく、患者が安心して相談しやすい環境をどう整えるかが重要である。がん相談支援センターやピアサポーターの
おり、相談できた患者に対しては適切 活用、緩和ケアチームや心理士など多職種による相談窓口の拡充、患者や家族への積極的な声かけといった仕組みを通じて、「相談できる人
な対応がなされていることを示してお
を増やす」こと自体を指標として重視することが考えられる。
り評価できる。
○医療者に苦痛の表出ができること、の項目は総じてまだ低いことから更なる取り組みが必要。
○拠点病院等にかぎらず、地域の病院においても苦痛の把握とケアへの反映のため、「苦痛のスクリーニング」の導入医療機関を増やすな
ど、さらなる取組が必要。
○患者自身と遺族の間に差異があることをどう解釈するか
○速やかに対応はしてもらったが、必ずしも気軽に相談できるわけでもなく、苦痛が減ってもいない。評価すべき指標に何か欠落があるので
はないか。
79 中間アウトカム指標
○コロナ禍による面会制限等が影響している可能性があるため、次回の遺族調査で詳細に調査ができると良い。
217201
○「医療者はつらい症状にすみやかに対応していたと感じる割合 成人」は患者体験調査に基づく値である。令和3年9月3日の厚生労働省・第2
回がんの緩和ケアに係る部会で提示された資料2によると「約半数のがん患者はがん診療連携拠点病院以外で初回治療を開始しており、その前
段にあたる診断については、さらに多くの割合はがん診療連携拠点病院以外でなされていることが推察」と指摘されていることから、患者体
験調査による評価では「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」との全体目標を十分に満たしていると
は言えず、がん診療連携拠点病院以外の患者体験の調査が必要である。
○がん患者が、医療者に苦痛の表出を ○がんと診断されてから病気や療養生活について 相談できたと感じるがん患者の割合の判定がCである。相談支援センターの周知だけでな
できることに関しては医療スタッフや く、強化(特に人的)の必要がある。コロナ禍により、相談支援センターの利用数が減少したことも考えられるため引き続き測定を継続する
医療者が身近にいる場合は極めて良好 必要がある。
な数字となっており、評価できる。
○がん相談支援センターの周知を強化して相談件数の増加および相談者の不安等の軽減につながるよう対応力の向上など、量的・質的の両側
面からの相談支援機能の強化が必要。
○がんと診断されてから病気や療養生活について相談できたと感じるがん患者の割会や家族に関するフォローが十分でない点がみられる。が
80 中間アウトカム指標
んの相談支援・情報提供に関する一定の研修を受け、必要に応じ、がん患者やその家族等に対し、拠点病院等のがん相談支援センターを紹介
217205
できる地域や拠点病院外で活動するの人材等の育成や利用の促進が望まれる。
○「がんと診断されてから病気や療養生活について相談できたと感じるがん患者の割合」は患者体験調査に基づく値である。令和3年9月3日の
厚生労働省・第2回がんの緩和ケアに係る部会で提示された資料2によると「約半数のがん患者はがん診療連携拠点病院以外で初回治療を開始
しており、その前段にあたる診断については、さらに多くの割合はがん診療連携拠点病院以外でなされていることが推察」と指摘されている
ことから、患者体験調査による評価では「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」との全体目標を十分
に満たしているとは言えず、がん診療連携拠点病院以外の患者体験の調査が必要である。
○A判定が散見されるもののC判定も多 ○多くのアウトプット指標の評価が向上しているにもかかわらず、特に最終段階での身体的精神的苦痛の割合が高まっている。その割合が半
81 分野別アウトカム指標
全体
い。
数にものぼるところは大きな改善が求められるのではないか。
○中間アウトカムを改善させるための検証が重要と考えられる。