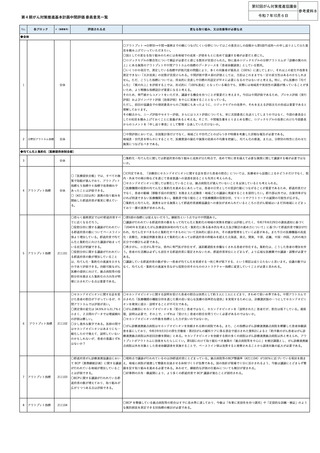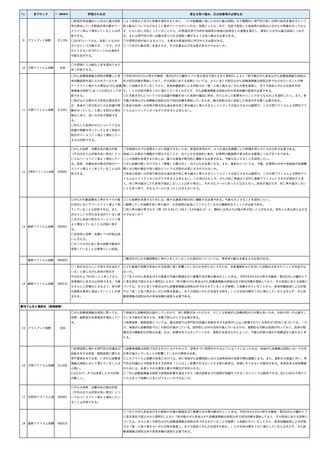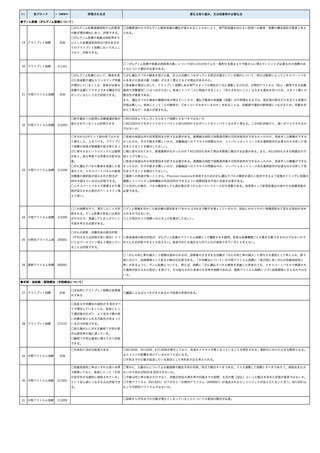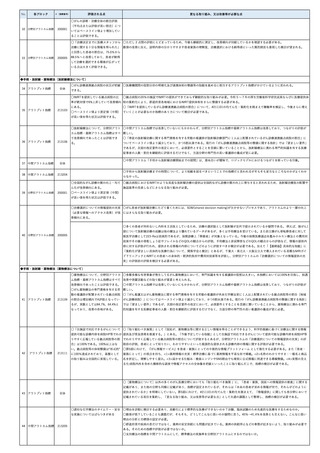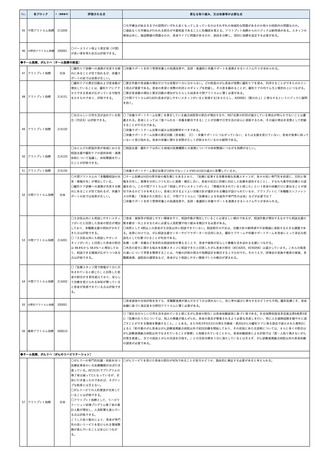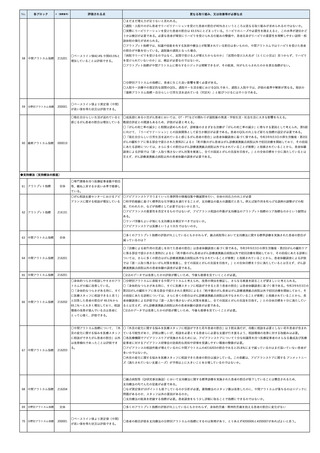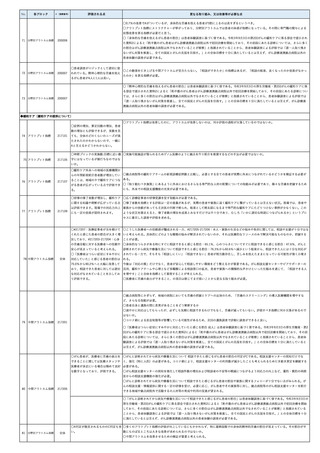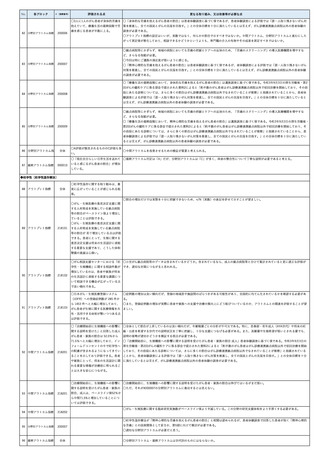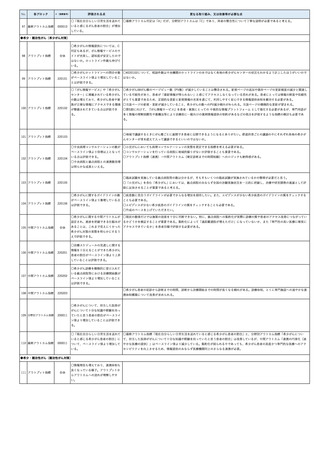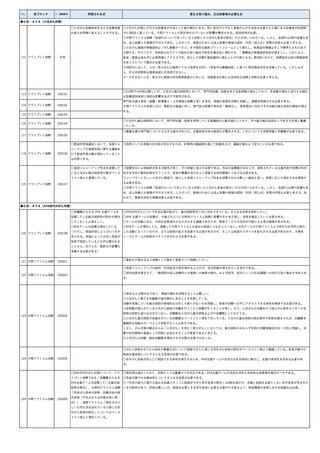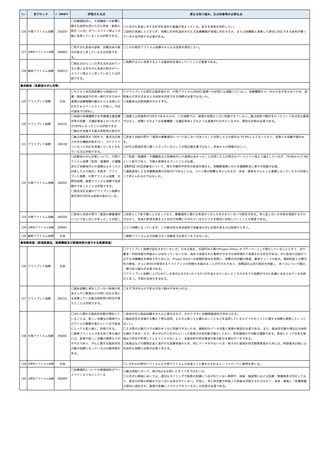よむ、つかう、まなぶ。
参考資料8 第4期がん対策推進基本計画中間評価 委員意見一覧 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64289.html |
| 出典情報 | がん対策推進協議会(第92回 10/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
No.
各ブロック
評価される点
#(指標番号)
更なる取り組み、又は改善等が必要な点
○化学療法が始まるまでの期間がいずれも長くなってしまっているのはそれぞれの地域的な問題があるのか個々の病院内の問題なのか。
45 中間アウトカム指標
213206
○遅延なく化学療法が行われる割合が半数程度であることに危機感を覚える。アウトプット指標からのロジックは納得感がある。スタッフの
確保以外に、施設整備の問題なのか、患者サイドに問題があるのか、原因を分解し、個別に指標を設定する必要がある。
46 分野別アウトカム指標
200001
○ベースライン値より測定値(中間)
が高い値を得た状況は評価できる。
◆チーム医療、がんリハ〔チーム医療の推進〕
○緩和ケア診療への連携が充実する傾 ○栄養サポートを担う管理栄養士の処遇改善や、医師・看護師と栄養サポートを連携させるシステム作りが求められる。
47 アウトプット指標
全体
向にあることが見て取れるが、栄養サ
ポートの面では改善が乏しい。
○緩和ケアの算定回数および患者数が ○算定件数や患者数の増加だけでは実態が十分に分からない。どの程度のがん患者が実際に緩和ケアを望み、利用することができたのかとい
増加していることは、緩和ケアにアク う視点が重要である。患者の希望と実際の利用とのギャップを把握し、その差を縮めることが、緩和ケアの均てん化と質的向上につながる。
48 アウトプット指標
214101
セスできる患者が広がっている可能性 ○算定患者数の増加と算定回数の増加がもたらした成果を中間アウトカムに置く必要がある。
を示すものであり、評価できる。
○中間アウトカム#214201患者が話しやすいスタッフがいると実感する)をもたらし、#200001(質の向上)に寄与するというロジックに疑問
を抱く。
○自分らしい日常生活が送れている割 ○「栄養サポートチーム加算」を算定している拠点病院等の割合が増加する中、NST加算の利用が減少している理由が明らかでないことは憂
合(判定A)は評価できる。
慮される。患者にとっては「食べられる・栄養を維持できる」ことが治療や日常生活の安心に直結するため、その減少理由を実態として把握
することが不可欠である。
49 アウトプット指標
214102
○栄養サポートチーム加算の減少は原因解明すべきである。
○栄養サポートチーム加算の算定回数(患者数)(C):栄養サポートにつながっていない、または支援を受けていない、患者が食事に困って
いないと受け取れる。患者の栄養に関する実態が正しく評価されているのか疑問である。
○ほとんどの都道府県が地域における ○相談支援・緩和ケア以外にも地域の医療機関との連携についての体制整備につながる指標がほしい。
50 アウトプット指標
214103
相談支援や緩和ケアの提供体制・連携
体制について協議し、体制整備を行っ
たことが評価できる。
51 アウトプット指標
214105
○栄養サポートチーム算定加算が100%でないことが#214102の減少に影響しているか。
○中間アウトカムの「多職種相談の充 ○チーム医療はH22の厚労省の報告書にもあるとおり、「医療に従事する多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門性を前提に、目的と情
実・情報共有」が増加している。
報を共有し、業務を分担しつつも互いに連携・補完し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提供すること」、すなわち集学的治療との認
○緩和ケア診療への連携が充実する傾 識を持つ。この中間アウトカムが「相談しやすいスタッフがいた」「情報共有されていると感じた」という患者の体験だけに委ねることが適
52 中間アウトカム指標
全体
向にあることが見て取れるが、栄養サ 切であるかどうかを考えたい。患者に対するよりよい治療方針が選択される機会が設けられているか、アウトプットに「多職種カンファレン
ポートの面では改善が乏しい。
スの件数」「実施された割合」など、中間アウトカムに「医療者による有益性や専門性の反映」などが必要では?
○栄養サポートを担う管理栄養士の処遇改善や、医師・看護師と栄養サポートを連携させるシステム作りが求められる。
○主治医以外にも相談しやすいスタッ ○患者・家族等が相談しやすい環境を作り、相談件数が増加していることは望ましい傾向であるが、相談件数が増加するなかでも相談支援の
フがいたと回答した患者の割合が増加 質を維持・向上させるために必要な人員配置や取り組みを検討する必要がある。
53 中間アウトカム指標
214201
しており、多職種支援の周知がされて
○依然として 4割以上の患者が主治医以外に相談できていない。相談相手の不足は、治療方針の納得感や不安軽減に直結する大きな課題であ
きた点は評価できる。
る。改善に向けては、がん相談支援センターやピアサポーターの活用に加え、緩和ケアチームや栄養サポートチームを患者にとって身近な相
○「主治医以外にも相談しやすいス
談先として位置づけることが有効である。
タッフがいた」と回答した患者の割合 医療・心理・栄養など多面的な相談体制を整えることで、患者や家族が安心して療養生活を送れる支援につながる。
は 48.8%から 58.4%へと増加してお
○外見の変化に関する悩みを医療スタッフに相談できたと回答したがん患者の割合(#216203、#230206)は減少しています。これらの結果
り、相談できる環境が広がりつつある の違いについて背景を整理することは、今後の評価の視点や指標設定を検討する上で大切です。そのうえで、研修会の実施や教育の推進、多
点は評価できる。
職種連携、退院前の講習会など、患者がより相談しやすい環境づくりの検討が望まれる。
○「医療スタッフ間で情報が十分に共
有されていると感じた」と回答した患
者の割合が 8 割を超えており、安心し
54 中間アウトカム指標
214202
て治療を受けられる体制が整っている
と患者が実感できている点は評価でき
る。
○患者調査の全体評価を見ても、多職種連携が進んだかどうかは測れないし、死亡率の減少に寄与するかどうかも不明。緩和医療こそ、患者
55 分野別アウトカム指標
200001
体験に基づく満足度を分野別アウトカムに置く必要がある。
○「現在自分らしい日常生活を送れていると感じるがん患者の割合」は患者体験調査に基づく値である。社会保障制度改革促進法第6条第3項
に「医療の在り方については、個人の尊厳が重んぜられ、患者の意思が尊重されるよう必要な見直しを行い、特に人生最終段階を穏やかに過
ごすことができる環境を整備すること。」とある。また令和3年9月3日の厚生労働省・第2回がんの緩和ケアに係る部会で提示された資料2に
56 最終アウトカム指標
よると「約半数のがん患者はがん診療連携拠点病院以外で初回治療を開始しており、その前段にあたる診断については、さらに多くの割合は
000010
がん診療連携拠点病院以外でなされていることが推察」と指摘されていることから、患者体験調査による評価では「誰一人取り残さないがん
対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」との全体目標を十分に満たしているとは言えず、がん診療連携拠点病院以外の患者体験
の調査が必要である。
◆チーム医療、がんリハ〔がんのリハビリテーション〕
○がんリハの専門的知識・技能を持つ ○がんリハビリを受けた患者の割合が42%であることが妥当かどうか、臨床的に検証する必要があると考えられる。
医療従事者のいる医療機関がほぼ行き
渡っている。#215101でプログラムの
修了者は減ってCとなっているが、全
体に行き渡ったのであれば、ネガティ
ブな結果とは言えない。
○がんリハビリの人的資源が充実して
いることは評価できる。
57 アウトプット指標
全体
○アウトプット指標として、リハビリ
テーション研修プログラム修了者の累
計人数が増加し、人員配置も進んでい
る点は評価できる。
こうした取り組みにより、患者が専門
性の高いリハビリを受けられる環境整
備が進んでいることは安心につなが
る。
各ブロック
評価される点
#(指標番号)
更なる取り組み、又は改善等が必要な点
○化学療法が始まるまでの期間がいずれも長くなってしまっているのはそれぞれの地域的な問題があるのか個々の病院内の問題なのか。
45 中間アウトカム指標
213206
○遅延なく化学療法が行われる割合が半数程度であることに危機感を覚える。アウトプット指標からのロジックは納得感がある。スタッフの
確保以外に、施設整備の問題なのか、患者サイドに問題があるのか、原因を分解し、個別に指標を設定する必要がある。
46 分野別アウトカム指標
200001
○ベースライン値より測定値(中間)
が高い値を得た状況は評価できる。
◆チーム医療、がんリハ〔チーム医療の推進〕
○緩和ケア診療への連携が充実する傾 ○栄養サポートを担う管理栄養士の処遇改善や、医師・看護師と栄養サポートを連携させるシステム作りが求められる。
47 アウトプット指標
全体
向にあることが見て取れるが、栄養サ
ポートの面では改善が乏しい。
○緩和ケアの算定回数および患者数が ○算定件数や患者数の増加だけでは実態が十分に分からない。どの程度のがん患者が実際に緩和ケアを望み、利用することができたのかとい
増加していることは、緩和ケアにアク う視点が重要である。患者の希望と実際の利用とのギャップを把握し、その差を縮めることが、緩和ケアの均てん化と質的向上につながる。
48 アウトプット指標
214101
セスできる患者が広がっている可能性 ○算定患者数の増加と算定回数の増加がもたらした成果を中間アウトカムに置く必要がある。
を示すものであり、評価できる。
○中間アウトカム#214201患者が話しやすいスタッフがいると実感する)をもたらし、#200001(質の向上)に寄与するというロジックに疑問
を抱く。
○自分らしい日常生活が送れている割 ○「栄養サポートチーム加算」を算定している拠点病院等の割合が増加する中、NST加算の利用が減少している理由が明らかでないことは憂
合(判定A)は評価できる。
慮される。患者にとっては「食べられる・栄養を維持できる」ことが治療や日常生活の安心に直結するため、その減少理由を実態として把握
することが不可欠である。
49 アウトプット指標
214102
○栄養サポートチーム加算の減少は原因解明すべきである。
○栄養サポートチーム加算の算定回数(患者数)(C):栄養サポートにつながっていない、または支援を受けていない、患者が食事に困って
いないと受け取れる。患者の栄養に関する実態が正しく評価されているのか疑問である。
○ほとんどの都道府県が地域における ○相談支援・緩和ケア以外にも地域の医療機関との連携についての体制整備につながる指標がほしい。
50 アウトプット指標
214103
相談支援や緩和ケアの提供体制・連携
体制について協議し、体制整備を行っ
たことが評価できる。
51 アウトプット指標
214105
○栄養サポートチーム算定加算が100%でないことが#214102の減少に影響しているか。
○中間アウトカムの「多職種相談の充 ○チーム医療はH22の厚労省の報告書にもあるとおり、「医療に従事する多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門性を前提に、目的と情
実・情報共有」が増加している。
報を共有し、業務を分担しつつも互いに連携・補完し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提供すること」、すなわち集学的治療との認
○緩和ケア診療への連携が充実する傾 識を持つ。この中間アウトカムが「相談しやすいスタッフがいた」「情報共有されていると感じた」という患者の体験だけに委ねることが適
52 中間アウトカム指標
全体
向にあることが見て取れるが、栄養サ 切であるかどうかを考えたい。患者に対するよりよい治療方針が選択される機会が設けられているか、アウトプットに「多職種カンファレン
ポートの面では改善が乏しい。
スの件数」「実施された割合」など、中間アウトカムに「医療者による有益性や専門性の反映」などが必要では?
○栄養サポートを担う管理栄養士の処遇改善や、医師・看護師と栄養サポートを連携させるシステム作りが求められる。
○主治医以外にも相談しやすいスタッ ○患者・家族等が相談しやすい環境を作り、相談件数が増加していることは望ましい傾向であるが、相談件数が増加するなかでも相談支援の
フがいたと回答した患者の割合が増加 質を維持・向上させるために必要な人員配置や取り組みを検討する必要がある。
53 中間アウトカム指標
214201
しており、多職種支援の周知がされて
○依然として 4割以上の患者が主治医以外に相談できていない。相談相手の不足は、治療方針の納得感や不安軽減に直結する大きな課題であ
きた点は評価できる。
る。改善に向けては、がん相談支援センターやピアサポーターの活用に加え、緩和ケアチームや栄養サポートチームを患者にとって身近な相
○「主治医以外にも相談しやすいス
談先として位置づけることが有効である。
タッフがいた」と回答した患者の割合 医療・心理・栄養など多面的な相談体制を整えることで、患者や家族が安心して療養生活を送れる支援につながる。
は 48.8%から 58.4%へと増加してお
○外見の変化に関する悩みを医療スタッフに相談できたと回答したがん患者の割合(#216203、#230206)は減少しています。これらの結果
り、相談できる環境が広がりつつある の違いについて背景を整理することは、今後の評価の視点や指標設定を検討する上で大切です。そのうえで、研修会の実施や教育の推進、多
点は評価できる。
職種連携、退院前の講習会など、患者がより相談しやすい環境づくりの検討が望まれる。
○「医療スタッフ間で情報が十分に共
有されていると感じた」と回答した患
者の割合が 8 割を超えており、安心し
54 中間アウトカム指標
214202
て治療を受けられる体制が整っている
と患者が実感できている点は評価でき
る。
○患者調査の全体評価を見ても、多職種連携が進んだかどうかは測れないし、死亡率の減少に寄与するかどうかも不明。緩和医療こそ、患者
55 分野別アウトカム指標
200001
体験に基づく満足度を分野別アウトカムに置く必要がある。
○「現在自分らしい日常生活を送れていると感じるがん患者の割合」は患者体験調査に基づく値である。社会保障制度改革促進法第6条第3項
に「医療の在り方については、個人の尊厳が重んぜられ、患者の意思が尊重されるよう必要な見直しを行い、特に人生最終段階を穏やかに過
ごすことができる環境を整備すること。」とある。また令和3年9月3日の厚生労働省・第2回がんの緩和ケアに係る部会で提示された資料2に
56 最終アウトカム指標
よると「約半数のがん患者はがん診療連携拠点病院以外で初回治療を開始しており、その前段にあたる診断については、さらに多くの割合は
000010
がん診療連携拠点病院以外でなされていることが推察」と指摘されていることから、患者体験調査による評価では「誰一人取り残さないがん
対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」との全体目標を十分に満たしているとは言えず、がん診療連携拠点病院以外の患者体験
の調査が必要である。
◆チーム医療、がんリハ〔がんのリハビリテーション〕
○がんリハの専門的知識・技能を持つ ○がんリハビリを受けた患者の割合が42%であることが妥当かどうか、臨床的に検証する必要があると考えられる。
医療従事者のいる医療機関がほぼ行き
渡っている。#215101でプログラムの
修了者は減ってCとなっているが、全
体に行き渡ったのであれば、ネガティ
ブな結果とは言えない。
○がんリハビリの人的資源が充実して
いることは評価できる。
57 アウトプット指標
全体
○アウトプット指標として、リハビリ
テーション研修プログラム修了者の累
計人数が増加し、人員配置も進んでい
る点は評価できる。
こうした取り組みにより、患者が専門
性の高いリハビリを受けられる環境整
備が進んでいることは安心につなが
る。