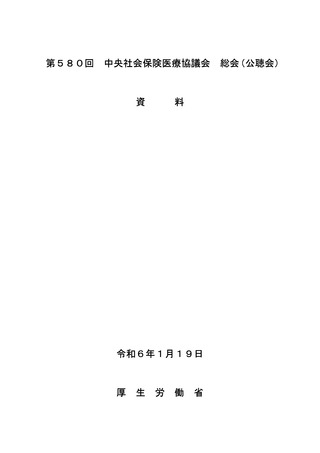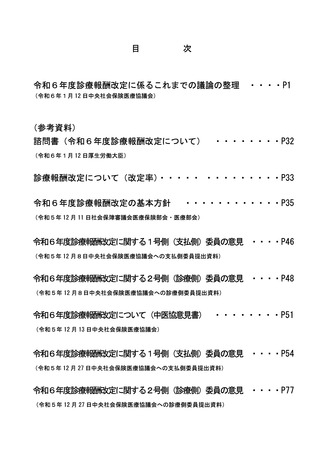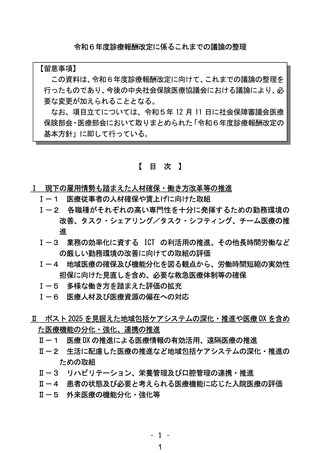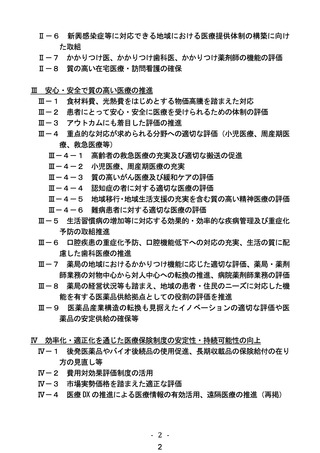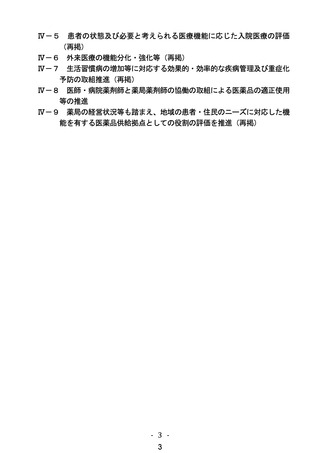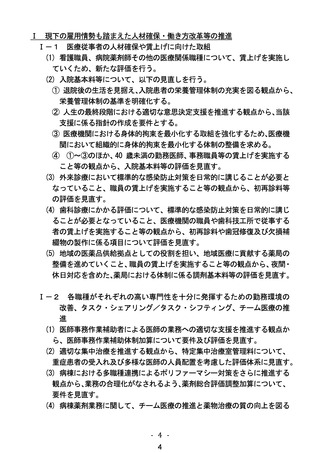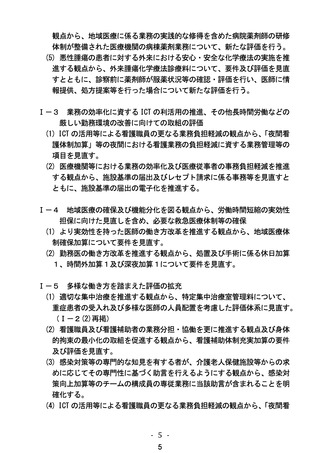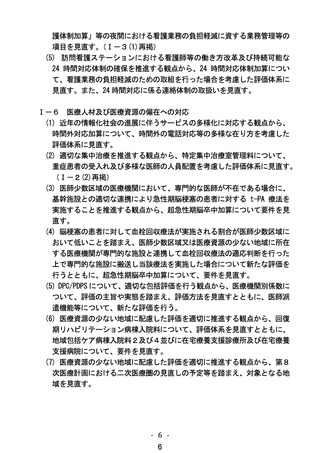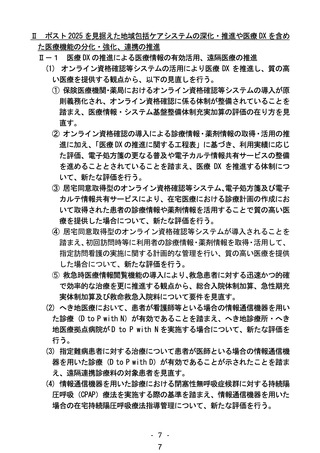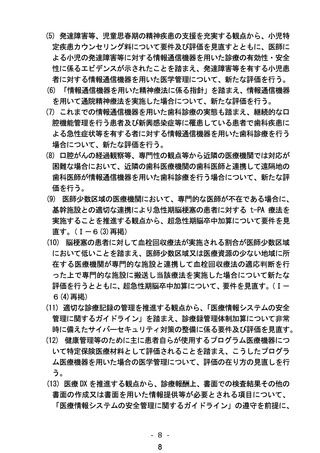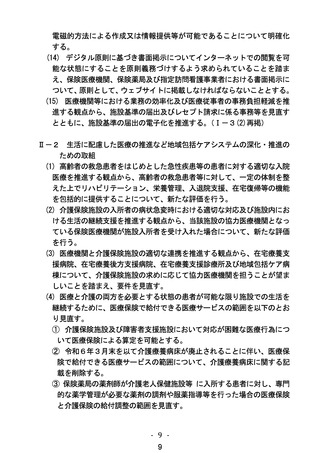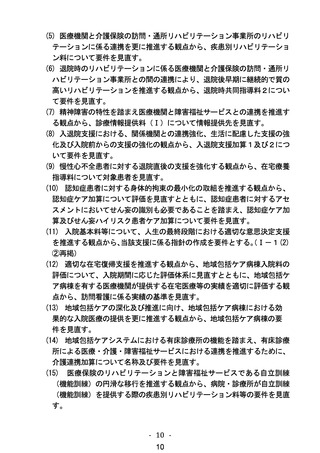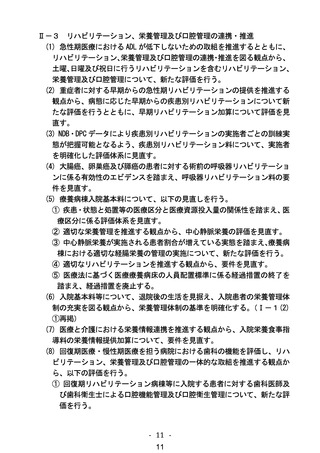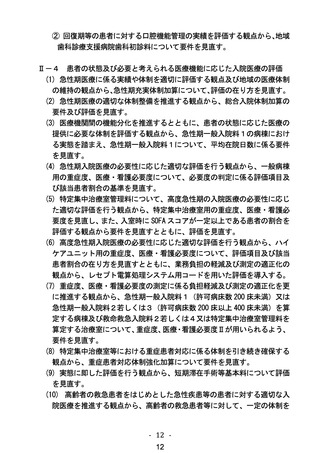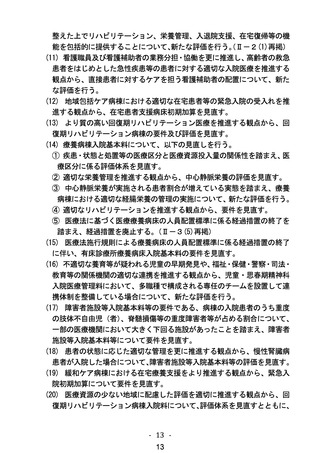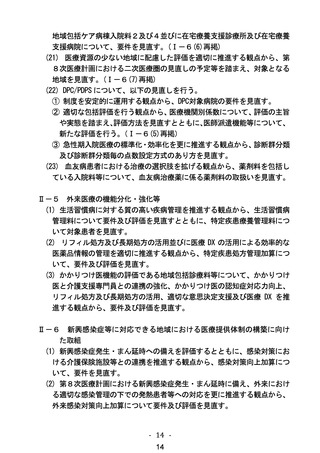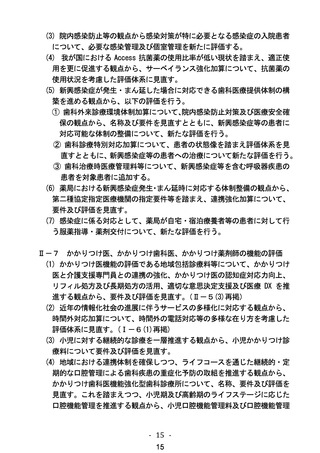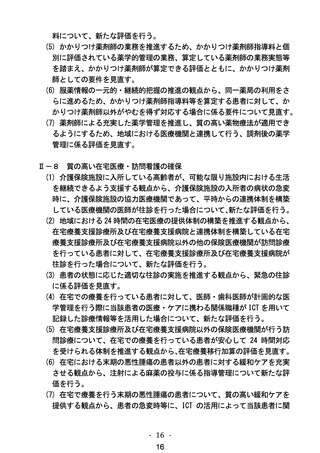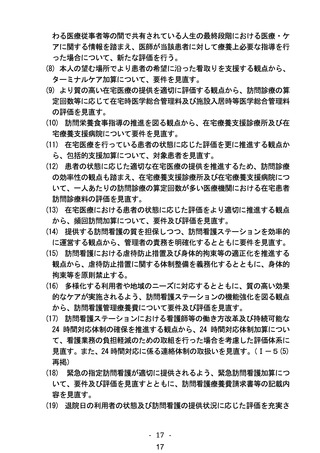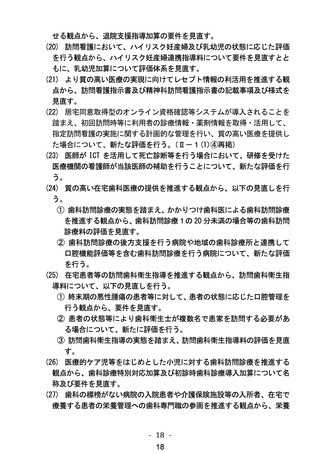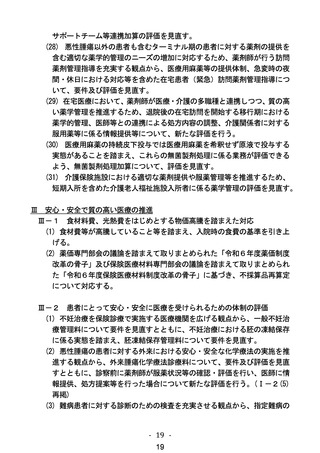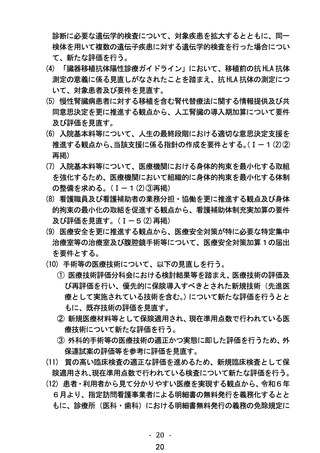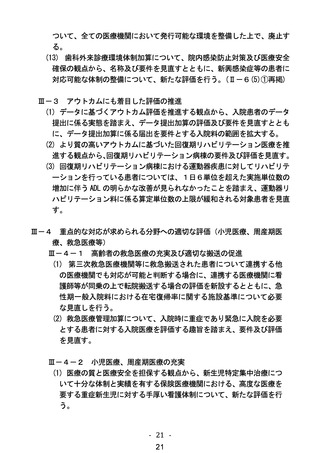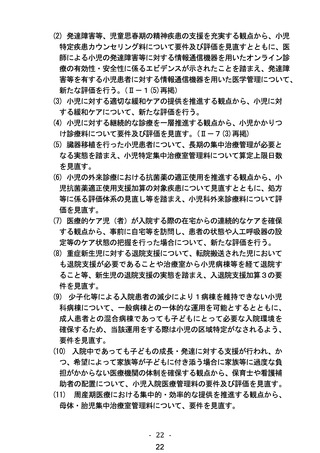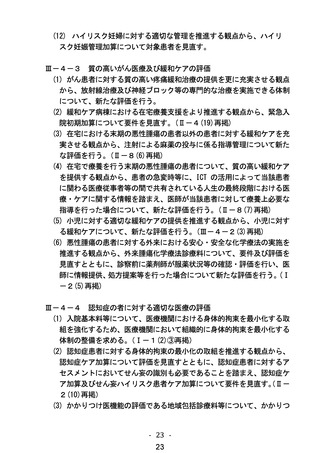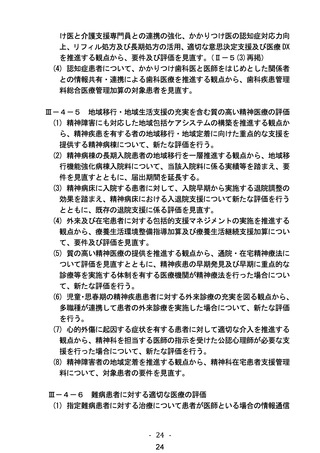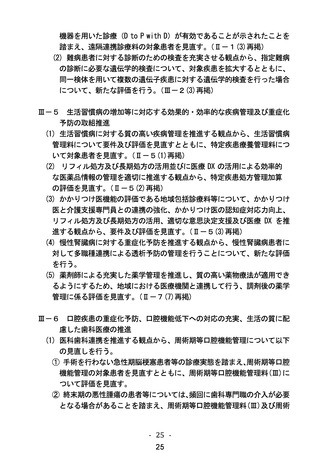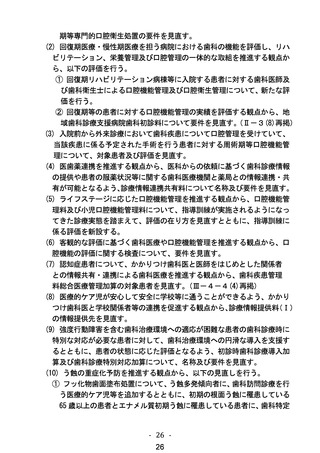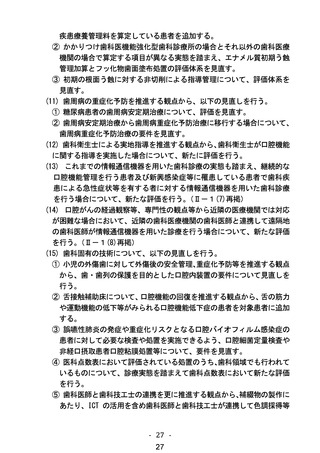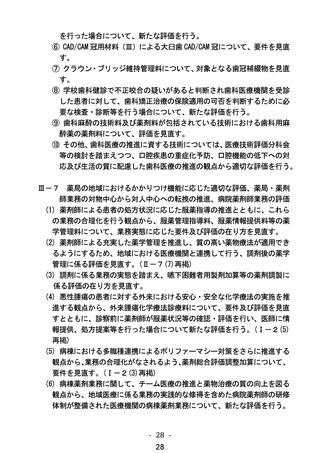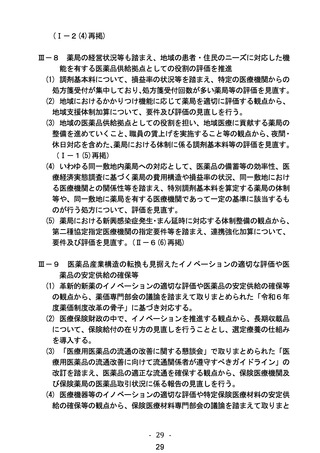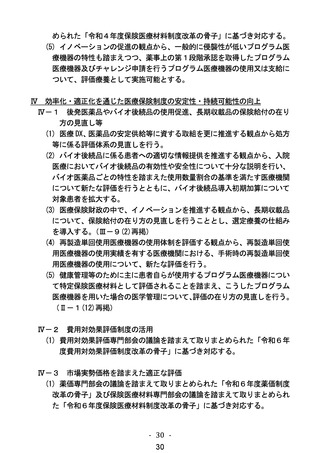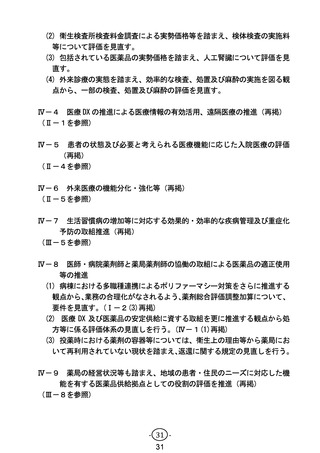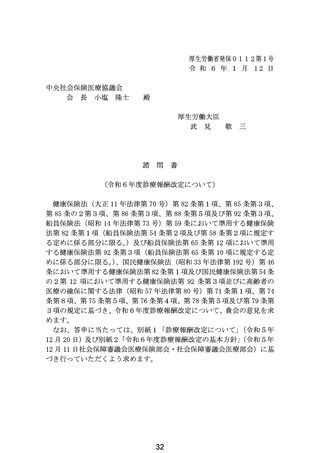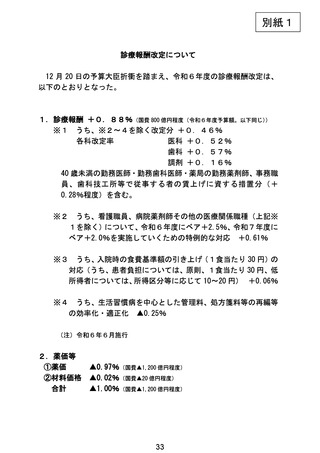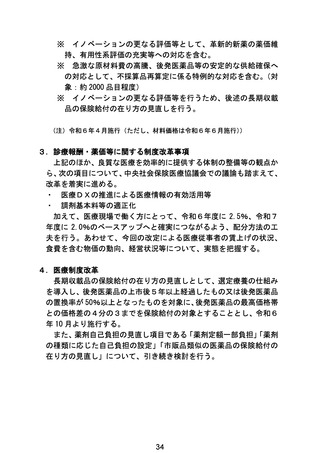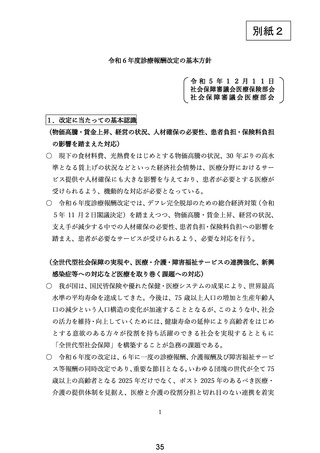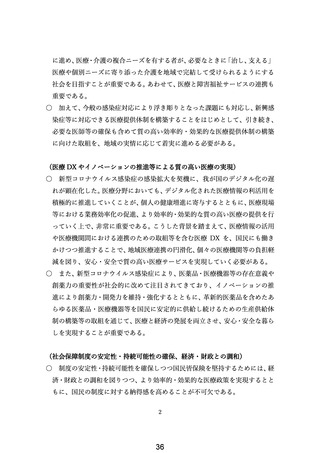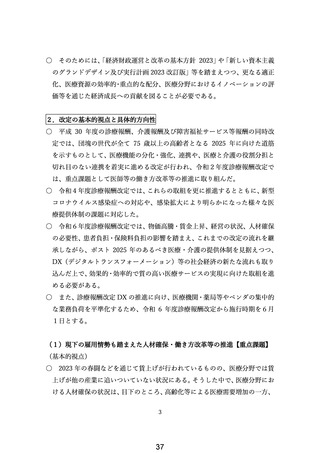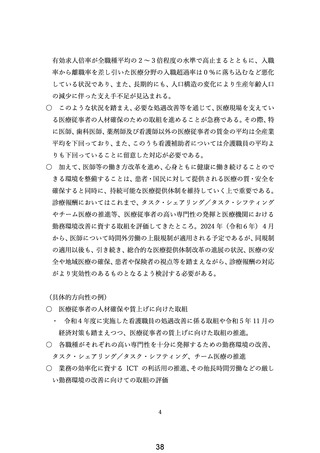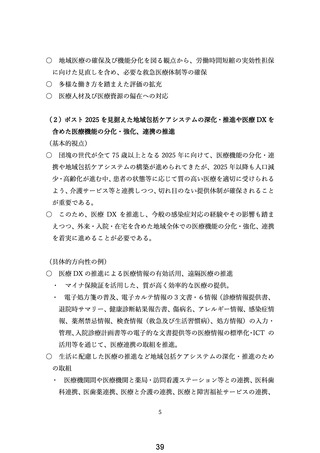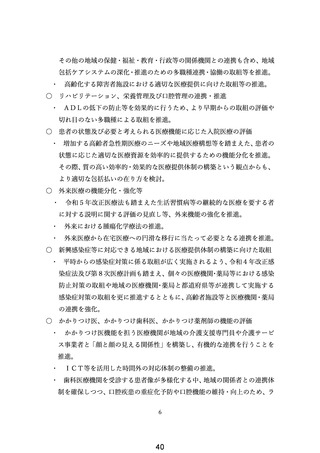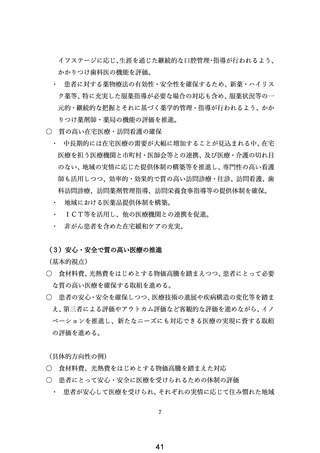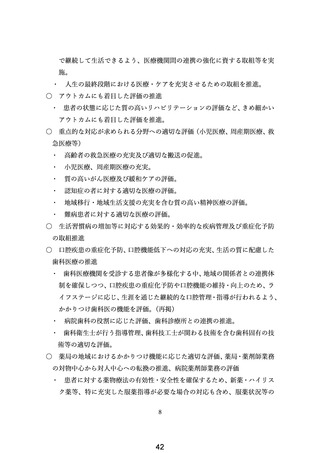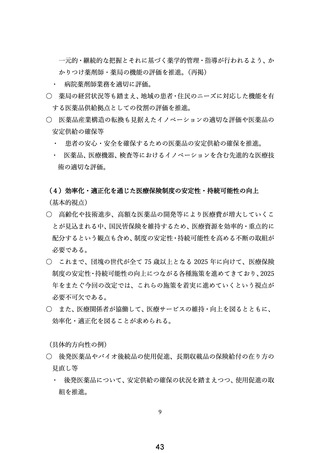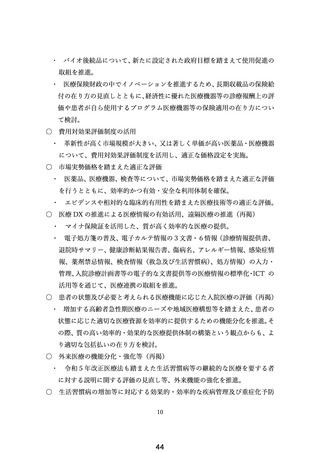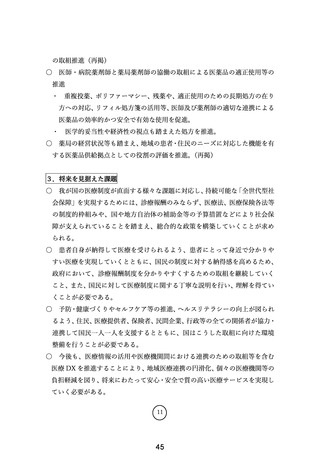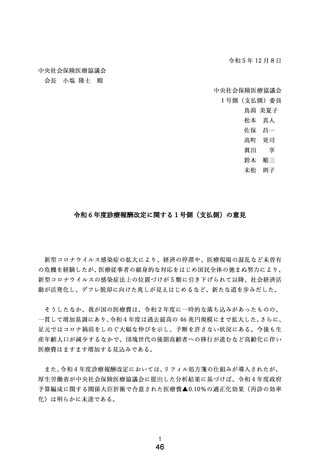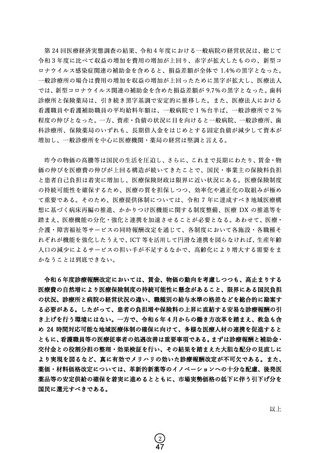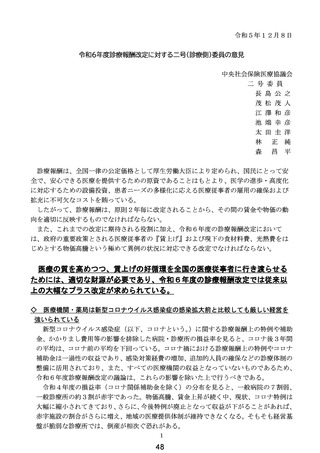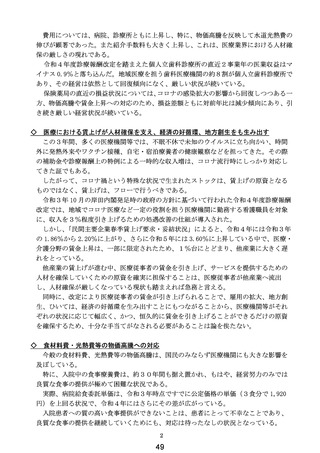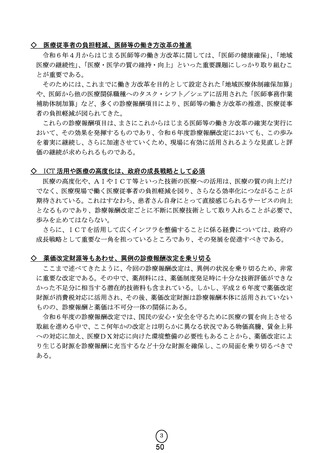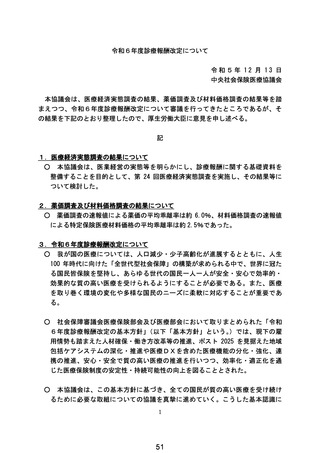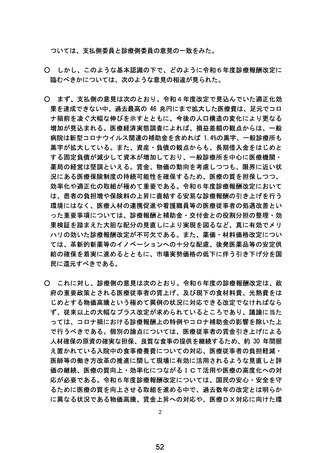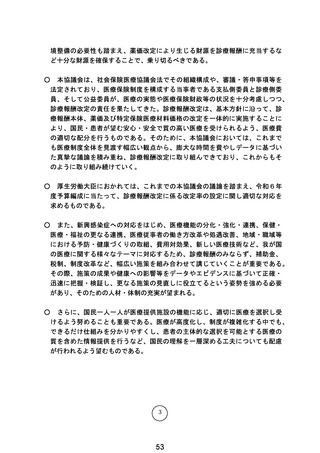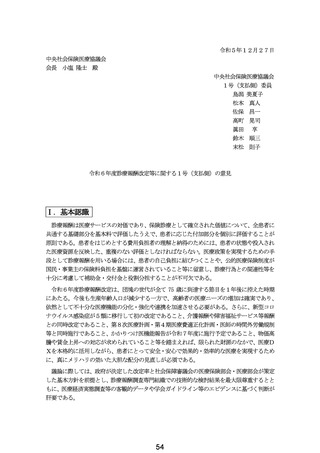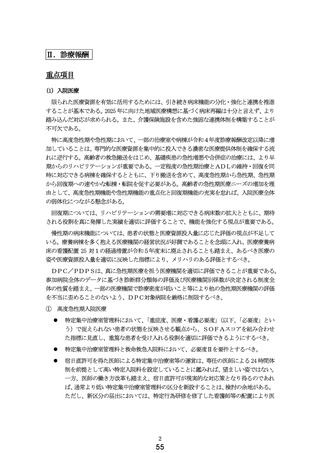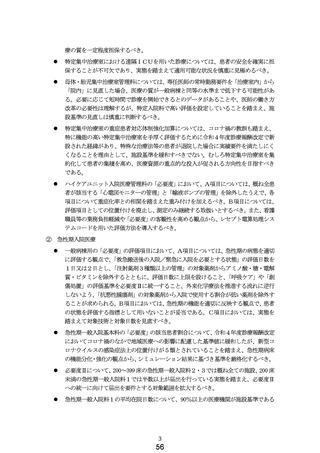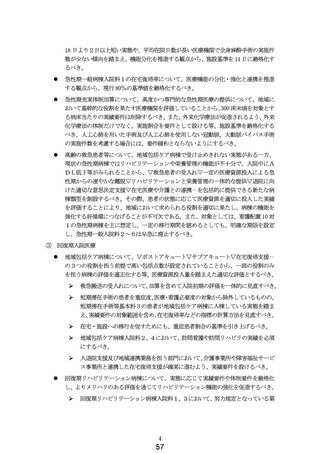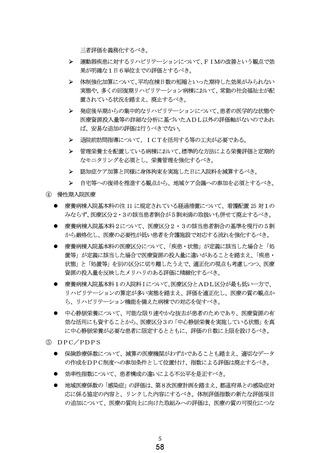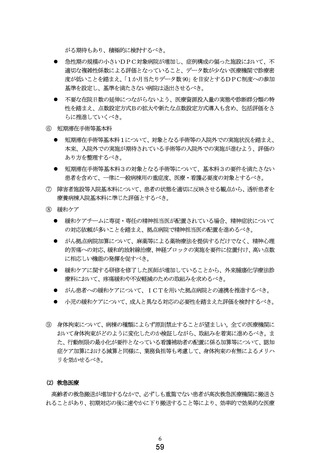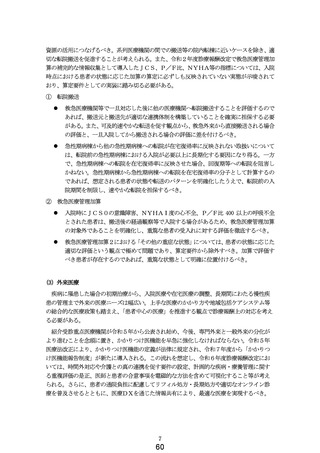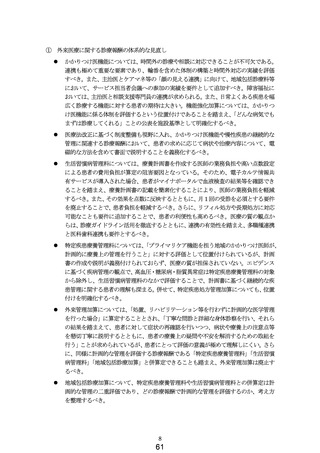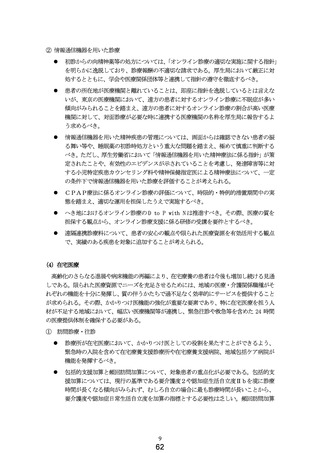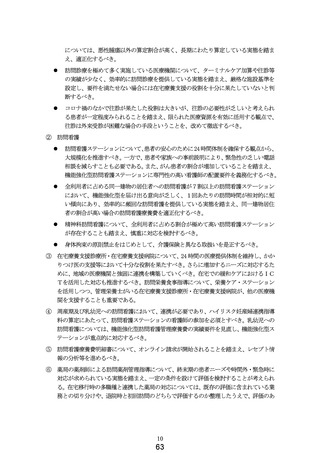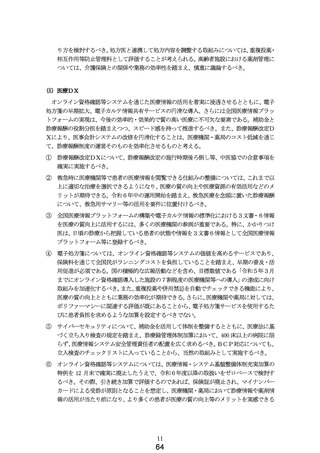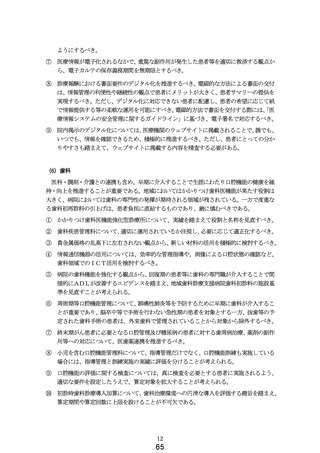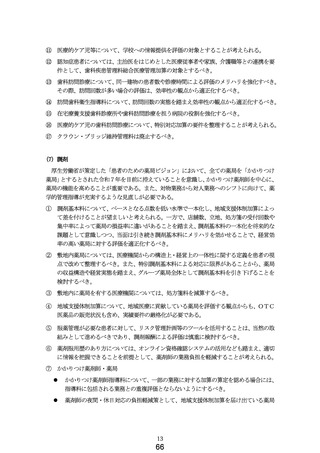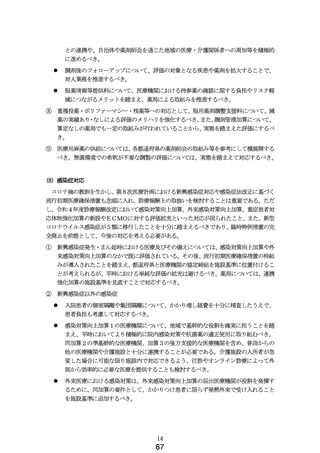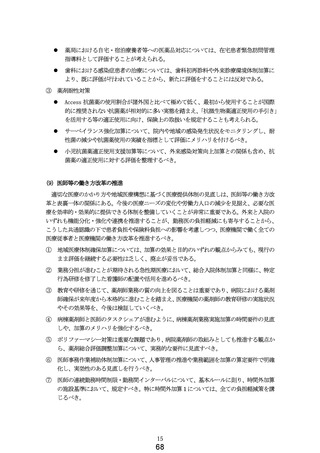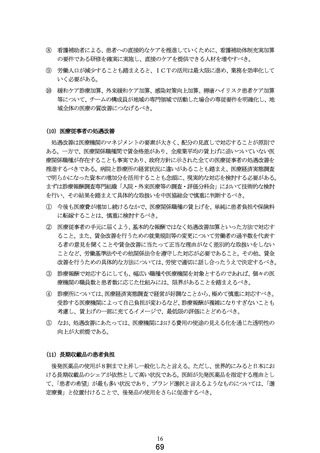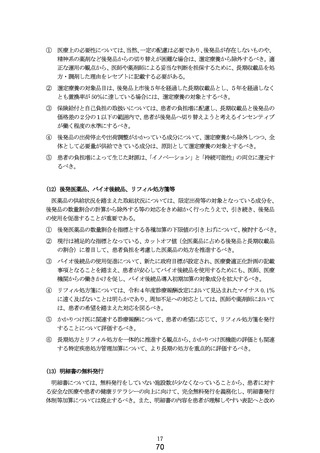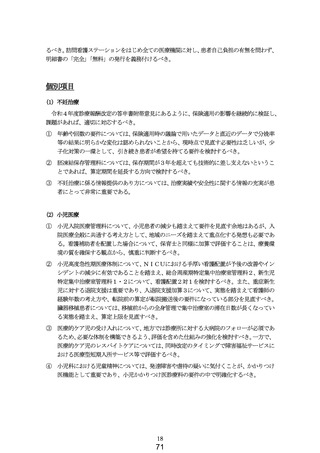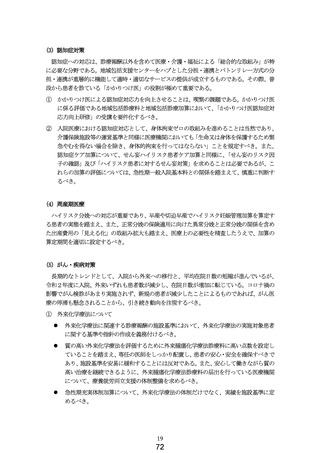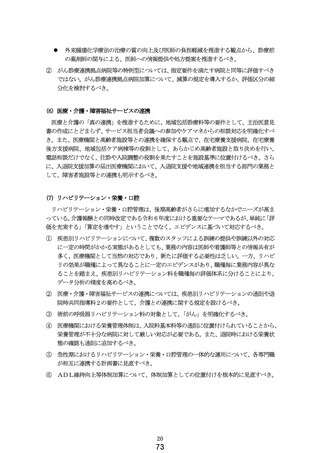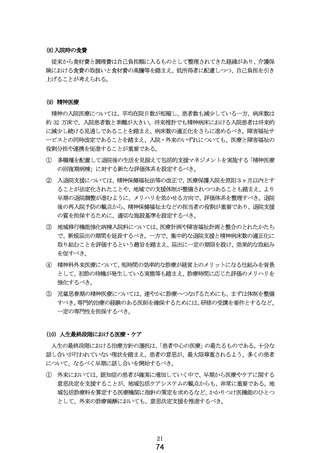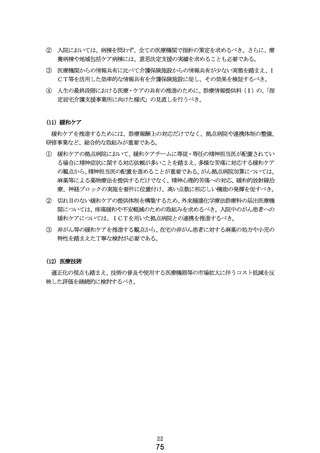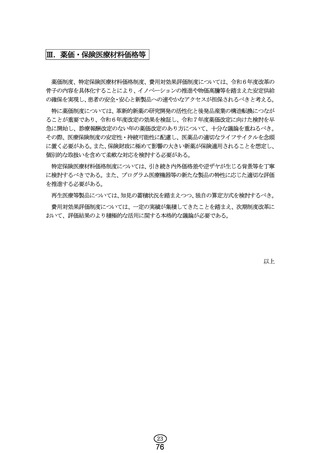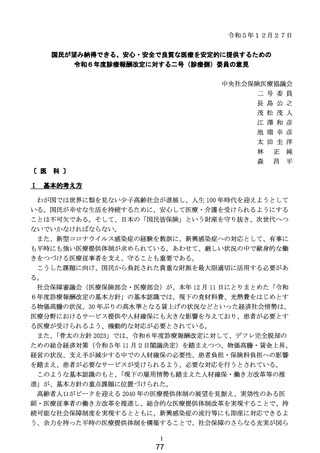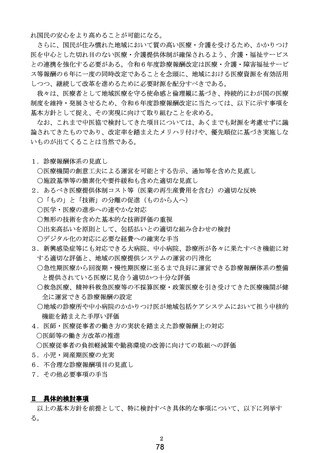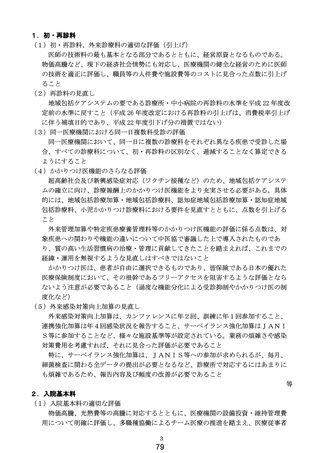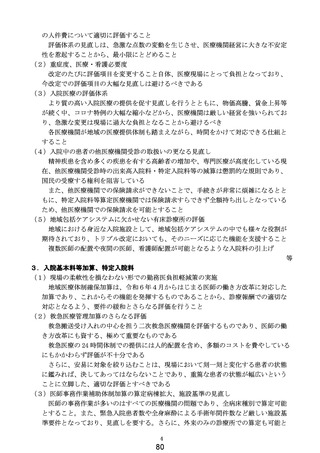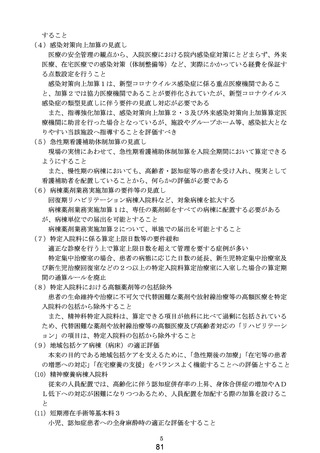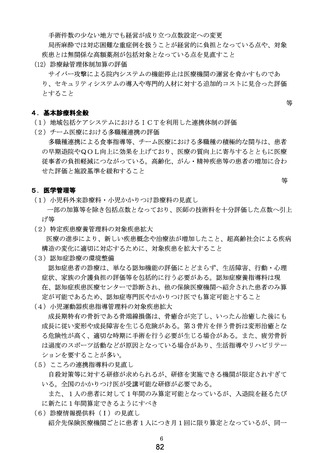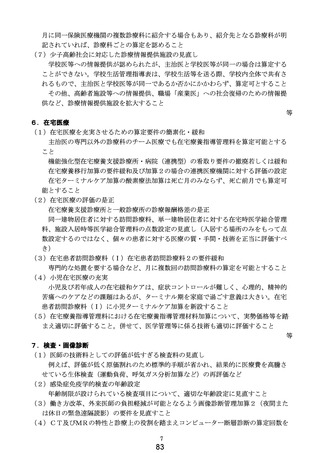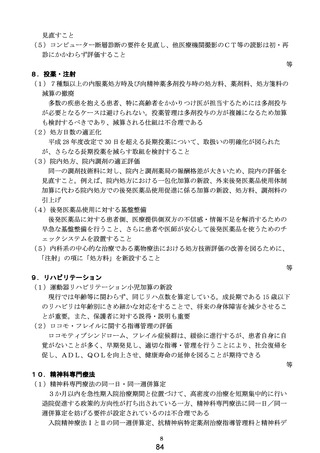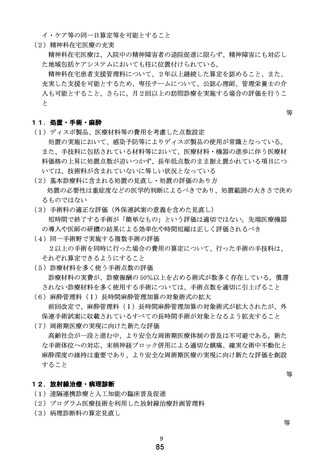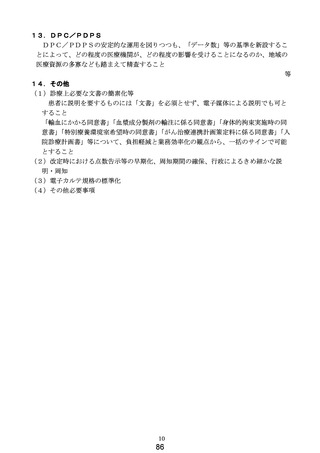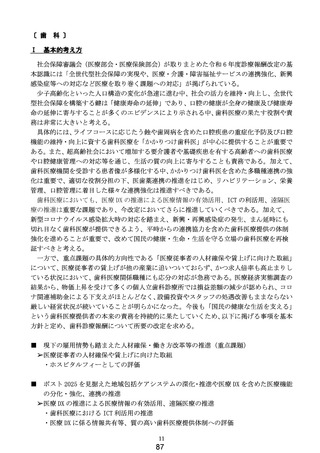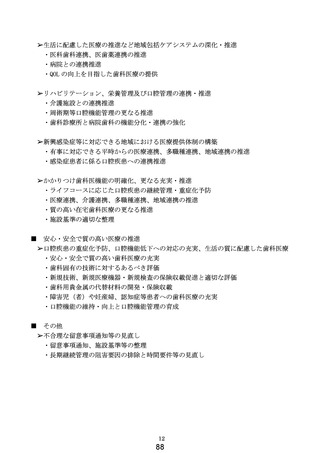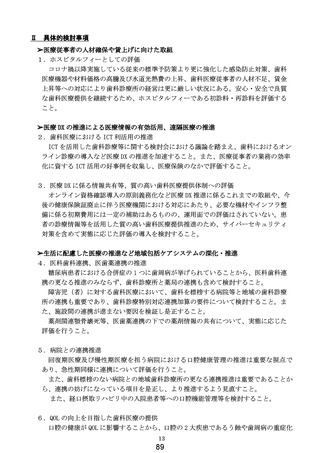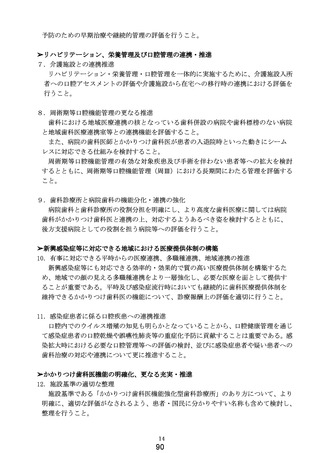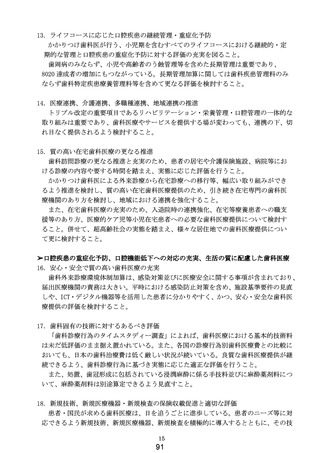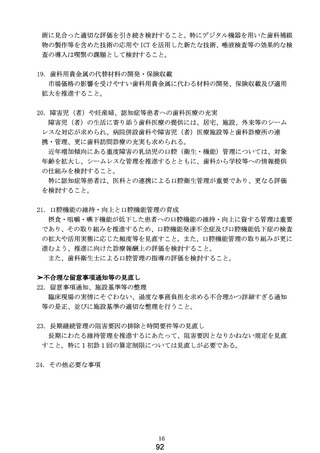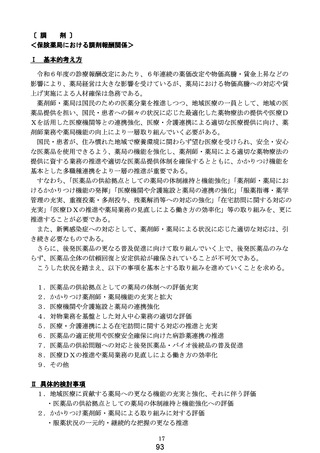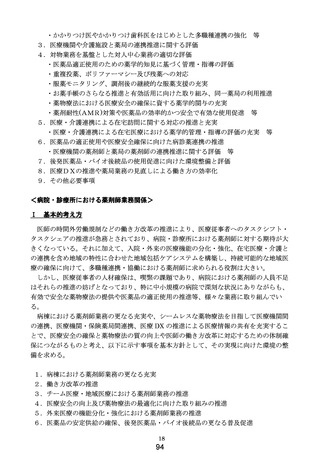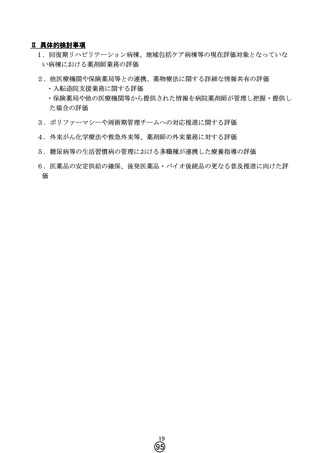よむ、つかう、まなぶ。
資料○令和6年度診療報酬改定に係る検討状況について (58 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00241.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第580回 1/19)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
療の質を一定程度担保するべき。
特定集中治療室における遠隔ICUを用いた診療については、患者の安全を確実に担
保することが不可欠であり、実態を踏まえて適用可能な状況を慎重に見極めるべき。
母体・胎児集中治療室管理料については、専任医師の常時勤務要件を「治療室内」から
「院内」に見直した場合、医療の質が一般病棟と同等の水準まで低下する可能性があ
る。必要に応じて短時間で診療を開始できるとのデータがあることや、医師の働き方
改革の必要性は理解するが、特定入院料で高い評価を設定していることを踏まえ、施
設基準の見直しは慎重に判断するべき。
特定集中治療室の重症患者対応体制強化加算については、コロナ禍の教訓も踏まえ、
特に機能の高い特定集中治療室を手厚く評価するために令和4年度診療報酬改定で新
設された経緯があり、特殊な治療法等の患者が退院した場合に実績要件を満たしにく
くなることを理由として、施設基準を緩和すべきでない。むしろ特定集中治療室を集
約化して患者の集積を高め、医療資源の重点的な投入が促される方向性を目指すべき
である。
ハイケアユニット入院医療管理料の「必要度」において、A項目については、概ね全患
者が該当する「心電図モニターの管理」と「輸液ポンプの管理」を除外したうえで、各
項目について重症化率との相関を踏まえた重み付けを加えるべき。B項目については、
評価項目としての位置付けを廃止し、測定のみ継続する取扱いとするべき。また、看護
職員等の業務負担軽減や「必要度」の客観性を高める観点から、レセプト電算処理シス
テムコードを用いた評価方法を導入するべき。
② 急性期入院医療
一般病棟用の「必要度」の評価項目において、A項目については、急性期の病態を適切
に評価する観点で、
「救急搬送後の入院/緊急に入院を必要とする状態」の評価日数を
1日又は2日とし、
「注射薬剤3種類以上の管理」の対象薬剤からアミノ酸・糖・電解
質・ビタミンを除外するとともに、評価日数に上限を設けること、
「呼吸ケア」や「創
傷処置」の評価基準を必要度Ⅱに統一すること、外来化学療法を推進する流れに逆行
しないよう、
「抗悪性腫瘍剤」の対象薬剤から入院で使用する割合が低い薬剤を除外す
ることが求められる。B項目においては、急性期の機能を適切に反映する観点で、患者
の状態を評価する指標として用いないことが妥当である。C項目においては、実態を
踏まえて対象技術と対象日数を見直すべき。
急性期一般入院基本料の「必要度」の該当患者割合について、令和4年度診療報酬改定
においてコロナ禍のなかで地域医療への影響に配慮した基準値に緩和したが、新型コ
ロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類とされていることを踏まえ、急性期病床
の機能分化・強化の観点から、シミュレーション結果に基づき基準を厳格化するべき。
必要度Ⅱについて、200~399 床の急性期一般入院料2・3では概ね全ての施設、200 床
未満の急性期一般入院料1では半数以上が届出を行っている実態を踏まえ、必要度Ⅱ
への統一に向けて届出を要件とする対象範囲を拡大するべき。
急性期一般入院料1の平均在院日数について、90%以上の医療機関が施設基準である
3
56
特定集中治療室における遠隔ICUを用いた診療については、患者の安全を確実に担
保することが不可欠であり、実態を踏まえて適用可能な状況を慎重に見極めるべき。
母体・胎児集中治療室管理料については、専任医師の常時勤務要件を「治療室内」から
「院内」に見直した場合、医療の質が一般病棟と同等の水準まで低下する可能性があ
る。必要に応じて短時間で診療を開始できるとのデータがあることや、医師の働き方
改革の必要性は理解するが、特定入院料で高い評価を設定していることを踏まえ、施
設基準の見直しは慎重に判断するべき。
特定集中治療室の重症患者対応体制強化加算については、コロナ禍の教訓も踏まえ、
特に機能の高い特定集中治療室を手厚く評価するために令和4年度診療報酬改定で新
設された経緯があり、特殊な治療法等の患者が退院した場合に実績要件を満たしにく
くなることを理由として、施設基準を緩和すべきでない。むしろ特定集中治療室を集
約化して患者の集積を高め、医療資源の重点的な投入が促される方向性を目指すべき
である。
ハイケアユニット入院医療管理料の「必要度」において、A項目については、概ね全患
者が該当する「心電図モニターの管理」と「輸液ポンプの管理」を除外したうえで、各
項目について重症化率との相関を踏まえた重み付けを加えるべき。B項目については、
評価項目としての位置付けを廃止し、測定のみ継続する取扱いとするべき。また、看護
職員等の業務負担軽減や「必要度」の客観性を高める観点から、レセプト電算処理シス
テムコードを用いた評価方法を導入するべき。
② 急性期入院医療
一般病棟用の「必要度」の評価項目において、A項目については、急性期の病態を適切
に評価する観点で、
「救急搬送後の入院/緊急に入院を必要とする状態」の評価日数を
1日又は2日とし、
「注射薬剤3種類以上の管理」の対象薬剤からアミノ酸・糖・電解
質・ビタミンを除外するとともに、評価日数に上限を設けること、
「呼吸ケア」や「創
傷処置」の評価基準を必要度Ⅱに統一すること、外来化学療法を推進する流れに逆行
しないよう、
「抗悪性腫瘍剤」の対象薬剤から入院で使用する割合が低い薬剤を除外す
ることが求められる。B項目においては、急性期の機能を適切に反映する観点で、患者
の状態を評価する指標として用いないことが妥当である。C項目においては、実態を
踏まえて対象技術と対象日数を見直すべき。
急性期一般入院基本料の「必要度」の該当患者割合について、令和4年度診療報酬改定
においてコロナ禍のなかで地域医療への影響に配慮した基準値に緩和したが、新型コ
ロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類とされていることを踏まえ、急性期病床
の機能分化・強化の観点から、シミュレーション結果に基づき基準を厳格化するべき。
必要度Ⅱについて、200~399 床の急性期一般入院料2・3では概ね全ての施設、200 床
未満の急性期一般入院料1では半数以上が届出を行っている実態を踏まえ、必要度Ⅱ
への統一に向けて届出を要件とする対象範囲を拡大するべき。
急性期一般入院料1の平均在院日数について、90%以上の医療機関が施設基準である
3
56