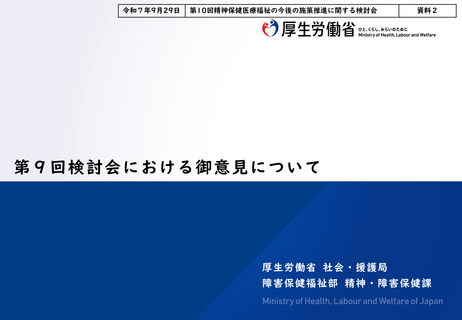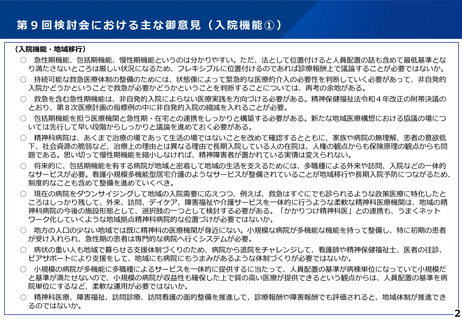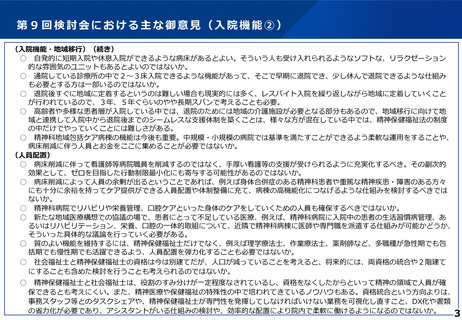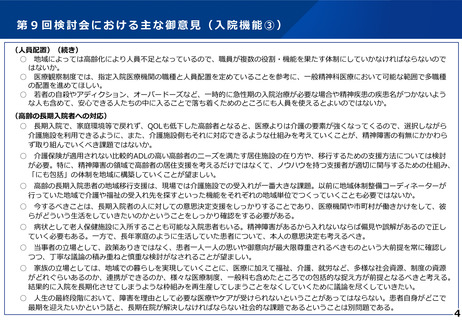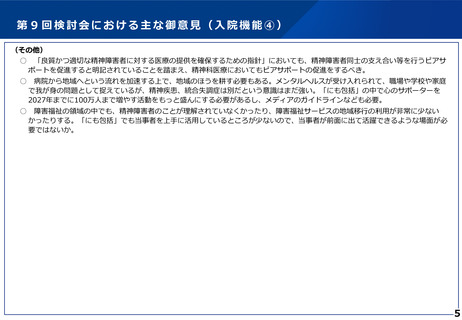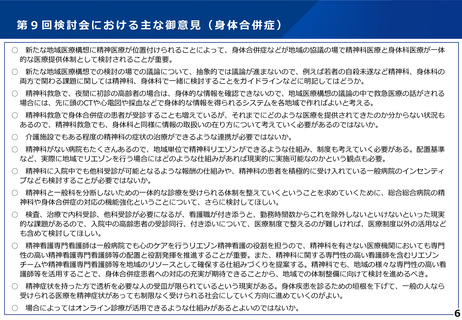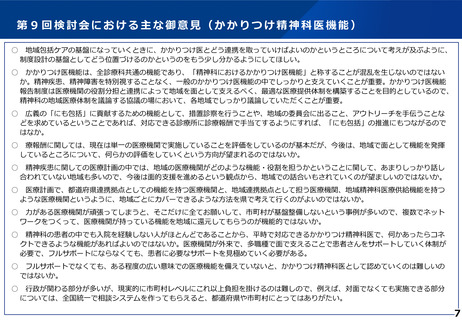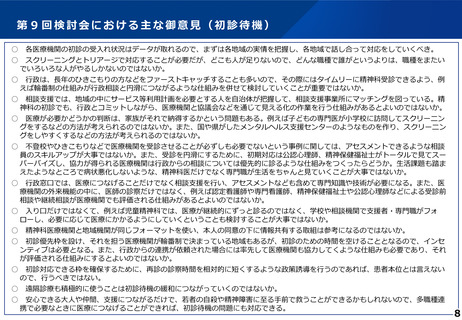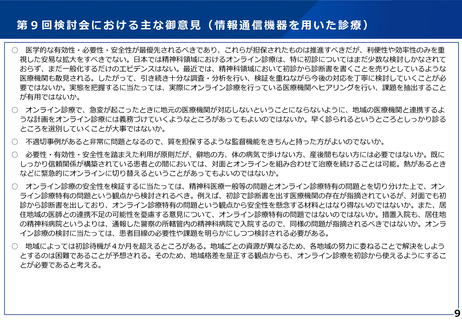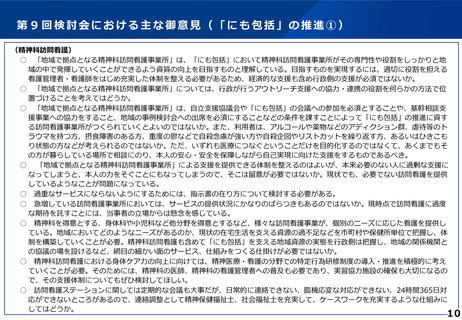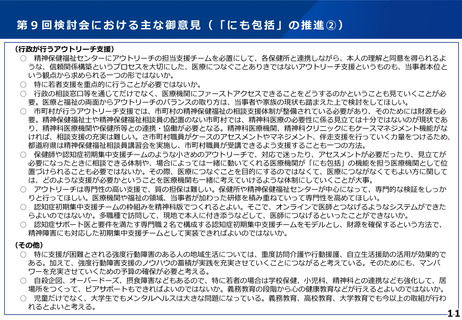よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】第9回検討会における主な御意見について (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64009.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第10回 9/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第9回検討会における主な御意見(初診待機)
○
各医療機関の初診の受入れ状況はデータが取れるので、まずは各地域の実情を把握し、各地域で話し合って対応をしていくべき。
○
スクリーニングとトリアージで対応することが必要だが、どこも人が足りないので、どんな職種で誰がというよりは、職種をまたい
でいろいろな人がやるしかないのではないか。
○
行政は、長年のひきこもりの方などをファーストキャッチすることも多いので、その際にはタイムリーに精神科受診できるよう、例
えば輪番制の仕組みが行政相談と円滑につながるような仕組みを併せて検討していくことが重要ではないか。
○
相談支援では、地域の中にサービス等利用計画を必要とする人を自治体が把握して、相談支援事業所にマッチングを図っている。精
神科の初診でも、行政とコミットしながら、医療機関と協議会などを通じて見える化の作業を行う仕組みがあるとよいのではないか。
○ 医療が必要かどうかの判断は、家族がそれで納得するかという問題もある。例えば子どもの専門医が小学校に訪問してスクリーニン
グをするなどの方法が考えられるのではないか。また、国や県がしたメンタルヘルス支援センターのようなものを作り、スクリーニン
グをしやすくするなどの方法が考えられるのではないか。
○
不登校やひきこもりなどで医療機関を受診させることが必ずしも必要でないという事例に関しては、アセスメントできるような相談
員のスキルアップが大事ではないか。また、受診を円滑にするために、初期対応は公認心理師、精神保健福祉士がトータルで見てスー
パーバイズし、協力が得られる医療機関は行政からの相談については優先的に診るような仕組みをつくったらどうか。生活課題も踏ま
えたようなところで病状悪化しないような、精神科医だけでなく専門職が生活をちゃんと見ていくことが大事ではないか。
○ 行政窓口では、医療につなげることだけでなく相談支援を行い、アセスメントなども含めて専門知識や技術が必要になる。また、医
療機関の外来機能の中に、医師の診察だけではなく、例えば認定看護師や専門看護師、精神保健福祉士や公認心理師などによる受診前
相談や継続相談が医療機関でも評価される仕組みがあるとよいのではないか。
○
○
入り口だけではなくて、例えば児童精神科では、医療が継続的にずっと診るのではなく、学校や相談機関で支援者・専門職がフォ
ローし、必要に応じて医療にかかるようにしていくということも検討することが大事ではないか。
精神科医療機関と地域機関が同じフォーマットを使い、本人の同意の下に情報共有する取組は参考になるのではないか。
○ 初診優先枠を設け、それを担う医療機関が輪番制で決まっている地域もあるが、初診のための時間を空けることとなるので、インセ
ンティブは必要となる。また、行政からの連携が依頼された場合には率先して医療機関も協力してくような仕組みも必要であり、それ
が評価される仕組みにするとよいのではないか。
○
○
○
初診対応できる枠を確保するために、再診の診察時間を相対的に短くするような政策誘導を行うのであれば、患者本位とは言えない
ので、行うべきではない。
遠隔診療も積極的に使うことは初診待機の緩和につながっていくのではないか。
安心できる大人や仲間、支援につながるだけで、若者の自殺や精神障害に至る手前で救うことができるかもしれないので、多職種連
携で必要なときに医療につなげることができれば、初診待機の問題にも対応できる。
8
○
各医療機関の初診の受入れ状況はデータが取れるので、まずは各地域の実情を把握し、各地域で話し合って対応をしていくべき。
○
スクリーニングとトリアージで対応することが必要だが、どこも人が足りないので、どんな職種で誰がというよりは、職種をまたい
でいろいろな人がやるしかないのではないか。
○
行政は、長年のひきこもりの方などをファーストキャッチすることも多いので、その際にはタイムリーに精神科受診できるよう、例
えば輪番制の仕組みが行政相談と円滑につながるような仕組みを併せて検討していくことが重要ではないか。
○
相談支援では、地域の中にサービス等利用計画を必要とする人を自治体が把握して、相談支援事業所にマッチングを図っている。精
神科の初診でも、行政とコミットしながら、医療機関と協議会などを通じて見える化の作業を行う仕組みがあるとよいのではないか。
○ 医療が必要かどうかの判断は、家族がそれで納得するかという問題もある。例えば子どもの専門医が小学校に訪問してスクリーニン
グをするなどの方法が考えられるのではないか。また、国や県がしたメンタルヘルス支援センターのようなものを作り、スクリーニン
グをしやすくするなどの方法が考えられるのではないか。
○
不登校やひきこもりなどで医療機関を受診させることが必ずしも必要でないという事例に関しては、アセスメントできるような相談
員のスキルアップが大事ではないか。また、受診を円滑にするために、初期対応は公認心理師、精神保健福祉士がトータルで見てスー
パーバイズし、協力が得られる医療機関は行政からの相談については優先的に診るような仕組みをつくったらどうか。生活課題も踏ま
えたようなところで病状悪化しないような、精神科医だけでなく専門職が生活をちゃんと見ていくことが大事ではないか。
○ 行政窓口では、医療につなげることだけでなく相談支援を行い、アセスメントなども含めて専門知識や技術が必要になる。また、医
療機関の外来機能の中に、医師の診察だけではなく、例えば認定看護師や専門看護師、精神保健福祉士や公認心理師などによる受診前
相談や継続相談が医療機関でも評価される仕組みがあるとよいのではないか。
○
○
入り口だけではなくて、例えば児童精神科では、医療が継続的にずっと診るのではなく、学校や相談機関で支援者・専門職がフォ
ローし、必要に応じて医療にかかるようにしていくということも検討することが大事ではないか。
精神科医療機関と地域機関が同じフォーマットを使い、本人の同意の下に情報共有する取組は参考になるのではないか。
○ 初診優先枠を設け、それを担う医療機関が輪番制で決まっている地域もあるが、初診のための時間を空けることとなるので、インセ
ンティブは必要となる。また、行政からの連携が依頼された場合には率先して医療機関も協力してくような仕組みも必要であり、それ
が評価される仕組みにするとよいのではないか。
○
○
○
初診対応できる枠を確保するために、再診の診察時間を相対的に短くするような政策誘導を行うのであれば、患者本位とは言えない
ので、行うべきではない。
遠隔診療も積極的に使うことは初診待機の緩和につながっていくのではないか。
安心できる大人や仲間、支援につながるだけで、若者の自殺や精神障害に至る手前で救うことができるかもしれないので、多職種連
携で必要なときに医療につなげることができれば、初診待機の問題にも対応できる。
8