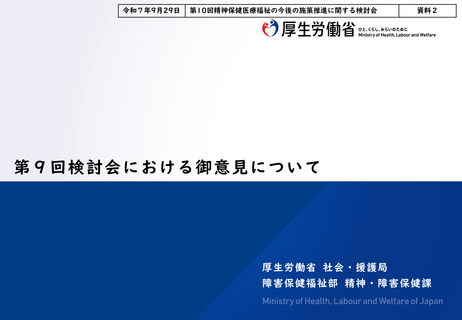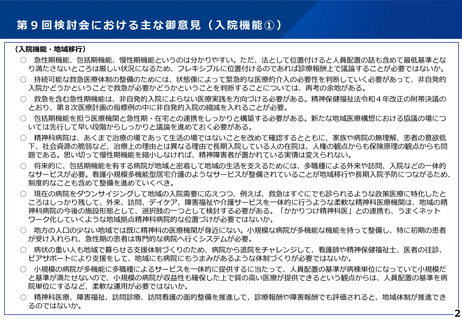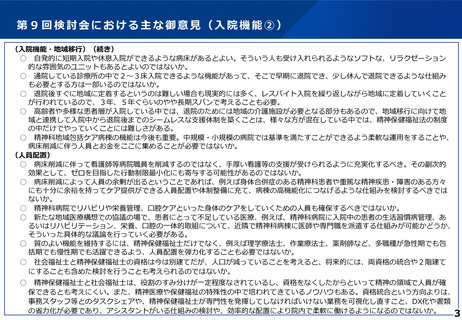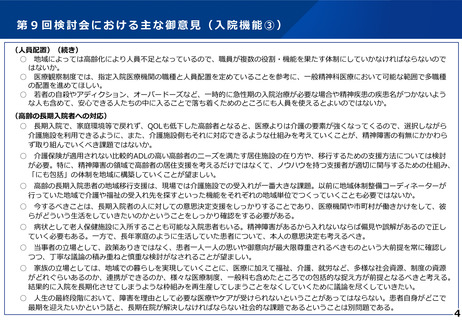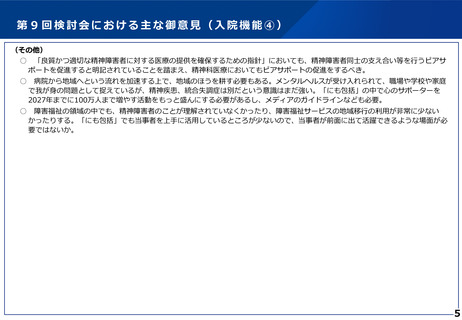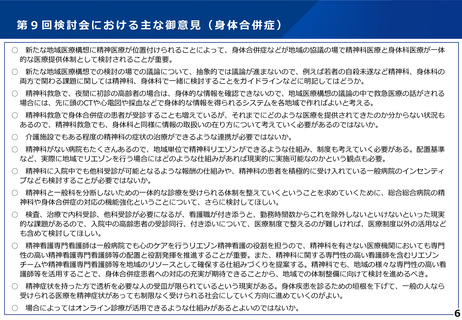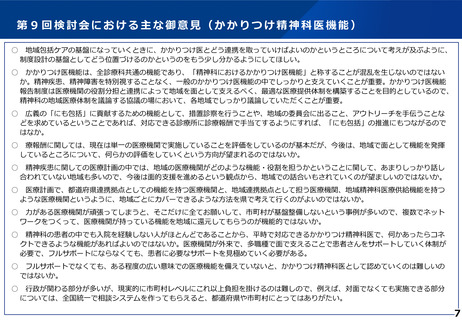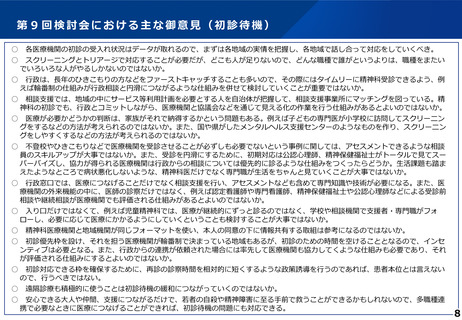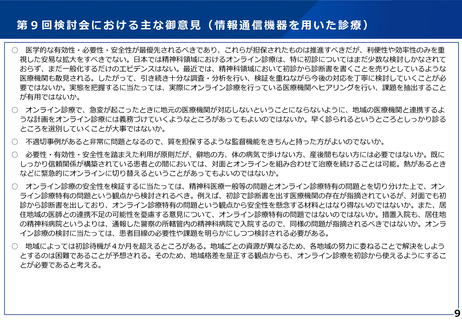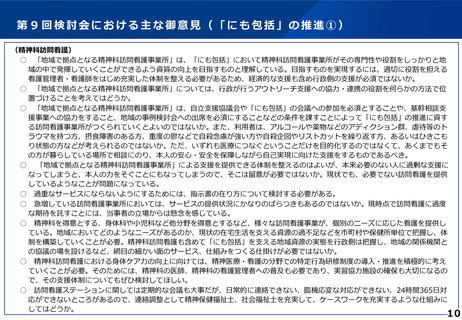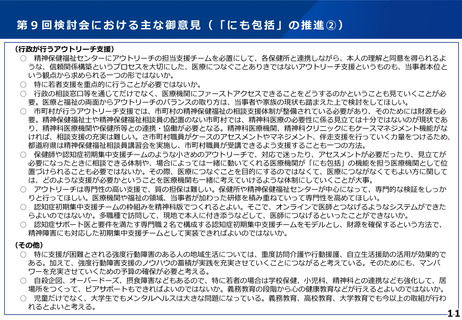よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】第9回検討会における主な御意見について (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64009.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第10回 9/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第9回検討会における主な御意見(「にも包括」の推進②)
(行政が行うアウトリーチ支援)
○ 精神保健福祉センターにアウトリーチの担当支援チームを必置にして、各保健所と連携しながら、本人の理解と同意を得られるよ
うな、信頼関係構築というプロセスを大切にした、医療につなぐことありきではないアウトリーチ支援というものも、当事者本位と
いう観点から求められる一つの形ではないか。
○ 特に若者支援を重点的に行うことが必要ではないか。
○ 行政の相談窓口等を通じてだけでなく、医療機関にファーストアクセスできることをどうするのかということも見ていくことが必
要。医療と福祉の両面からアウトリーチのバランスの取り方は、当事者や家族の現状も踏まえた上で検討をしてほしい。
○ 市町村が行うアウトリーチ支援では、市町村の精神保健福祉の相談支援体制が整備されている必要があり、そのためには財源も必
要。精神保健福祉士や精神保健福祉相談員の配置のない市町村では、精神科医療の必要性に係る見立ては十分ではないのが現状であ
り、精神科医療機関や保健所等との連携・協働が必要となる。精神科医療機関、精神科クリニックにもケースマネジメント機能がな
ければ、相談支援の充実は難しい。さ市町村職員がケースのアセスメントやマネジメント、伴走支援を行っていく力量をつけるため、
都道府県は精神保健福祉相談員講習会を実施し、市町村職員が受講できるよう支援することも一つの方法。
○ 保健師や認知症初期集中支援チームのような小さめのアウトリーチで、対応で迷ったり、アセスメントが必要だったり、見立てが
必要になったときに相談できる体制や、場合によっては一緒に動いてくれる医療機関が「にも包括」の機能を担う医療機関として位
置づけられることも必要ではないか。その際、医療につなぐことを目的にするのではなくて、医療につながなくてもよい方に関して
は、どのような支援が必要かということを医療機関も一緒に考えていけるような体制にしていくことが大事。
○ アウトリーチは専門性の高い支援で、質の担保は難しい。保健所や精神保健福祉センターが中心になって、専門的な検証をしっか
りと行ってほしい。医療機関や福祉の領域、当事者が加わった研修を積み重ねていって専門性を高めてほしい。
○ 認知症初期集中支援チームの枠組みを精神科版でつくれるとよい。そこで、オンラインで医師とつなげるようなシステムができた
らよいのではないか。多職種で訪問して、現地で本人に付き添うなどして、医師につなげるといったことができないか。
○ 認知症サポート医と要件を満たす専門職2名で構成する認知症初期集中支援チームをモデルとし、財源を確保するという方法で、
精神障害にも対応した初期集中支援チームとして実装できればよいのではないか。
(その他)
○ 特に支援が困難とされる強度行動障害のある人の地域生活については、重度訪問介護や行動援護、自立生活援助の活用が効果的で
ある。加えて、強度行動障害支援のノウハウの蓄積が実践を充実させていくことにつながると考えている。そのためにも、マンパ
ワーを充実させていくための予算の確保が必要と考える。
○ 自殺企図、オーバードーズ、摂食障害などもあるので、特に若者の場合は学校保健、小児科、精神科との連携なども強化して、居
場所をつくって、ピアサポートもできればよいのではないか。義務教育の段階から心の健康教育などが行えるとよいのではないか。
○ 児童だけでなく、大学生でもメンタルヘルスは大きな問題になっている。義務教育、高校教育、大学教育でも今以上の取組が行わ
れるとよいと考える。
11
(行政が行うアウトリーチ支援)
○ 精神保健福祉センターにアウトリーチの担当支援チームを必置にして、各保健所と連携しながら、本人の理解と同意を得られるよ
うな、信頼関係構築というプロセスを大切にした、医療につなぐことありきではないアウトリーチ支援というものも、当事者本位と
いう観点から求められる一つの形ではないか。
○ 特に若者支援を重点的に行うことが必要ではないか。
○ 行政の相談窓口等を通じてだけでなく、医療機関にファーストアクセスできることをどうするのかということも見ていくことが必
要。医療と福祉の両面からアウトリーチのバランスの取り方は、当事者や家族の現状も踏まえた上で検討をしてほしい。
○ 市町村が行うアウトリーチ支援では、市町村の精神保健福祉の相談支援体制が整備されている必要があり、そのためには財源も必
要。精神保健福祉士や精神保健福祉相談員の配置のない市町村では、精神科医療の必要性に係る見立ては十分ではないのが現状であ
り、精神科医療機関や保健所等との連携・協働が必要となる。精神科医療機関、精神科クリニックにもケースマネジメント機能がな
ければ、相談支援の充実は難しい。さ市町村職員がケースのアセスメントやマネジメント、伴走支援を行っていく力量をつけるため、
都道府県は精神保健福祉相談員講習会を実施し、市町村職員が受講できるよう支援することも一つの方法。
○ 保健師や認知症初期集中支援チームのような小さめのアウトリーチで、対応で迷ったり、アセスメントが必要だったり、見立てが
必要になったときに相談できる体制や、場合によっては一緒に動いてくれる医療機関が「にも包括」の機能を担う医療機関として位
置づけられることも必要ではないか。その際、医療につなぐことを目的にするのではなくて、医療につながなくてもよい方に関して
は、どのような支援が必要かということを医療機関も一緒に考えていけるような体制にしていくことが大事。
○ アウトリーチは専門性の高い支援で、質の担保は難しい。保健所や精神保健福祉センターが中心になって、専門的な検証をしっか
りと行ってほしい。医療機関や福祉の領域、当事者が加わった研修を積み重ねていって専門性を高めてほしい。
○ 認知症初期集中支援チームの枠組みを精神科版でつくれるとよい。そこで、オンラインで医師とつなげるようなシステムができた
らよいのではないか。多職種で訪問して、現地で本人に付き添うなどして、医師につなげるといったことができないか。
○ 認知症サポート医と要件を満たす専門職2名で構成する認知症初期集中支援チームをモデルとし、財源を確保するという方法で、
精神障害にも対応した初期集中支援チームとして実装できればよいのではないか。
(その他)
○ 特に支援が困難とされる強度行動障害のある人の地域生活については、重度訪問介護や行動援護、自立生活援助の活用が効果的で
ある。加えて、強度行動障害支援のノウハウの蓄積が実践を充実させていくことにつながると考えている。そのためにも、マンパ
ワーを充実させていくための予算の確保が必要と考える。
○ 自殺企図、オーバードーズ、摂食障害などもあるので、特に若者の場合は学校保健、小児科、精神科との連携なども強化して、居
場所をつくって、ピアサポートもできればよいのではないか。義務教育の段階から心の健康教育などが行えるとよいのではないか。
○ 児童だけでなく、大学生でもメンタルヘルスは大きな問題になっている。義務教育、高校教育、大学教育でも今以上の取組が行わ
れるとよいと考える。
11