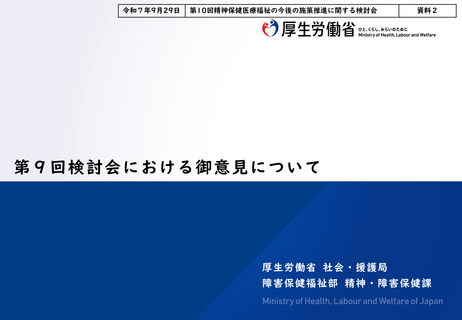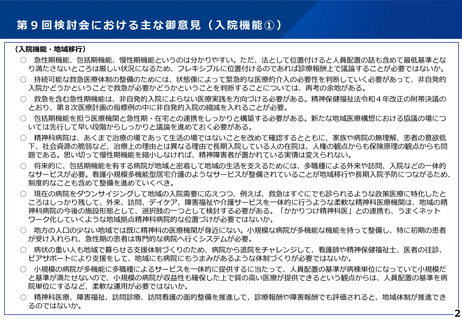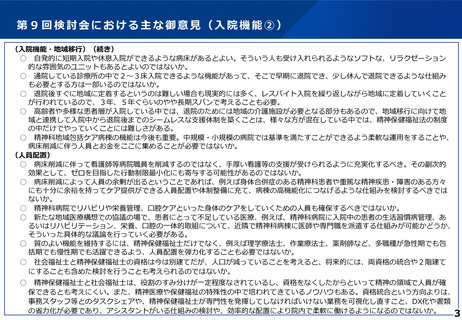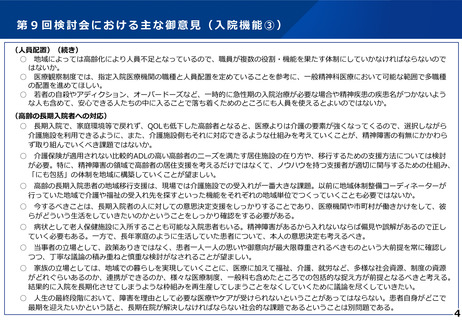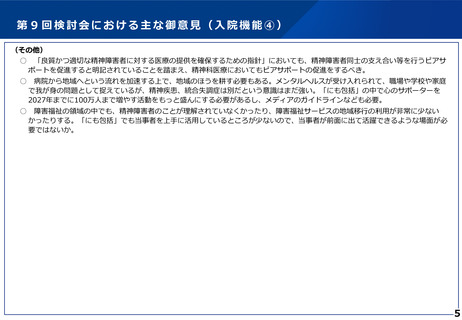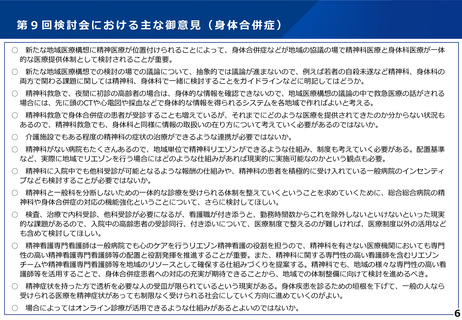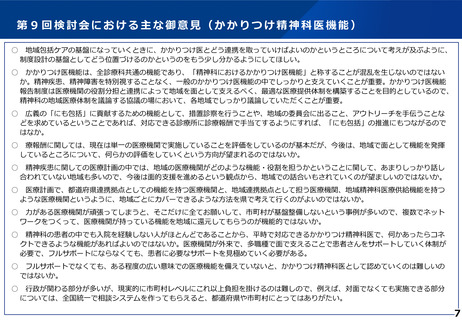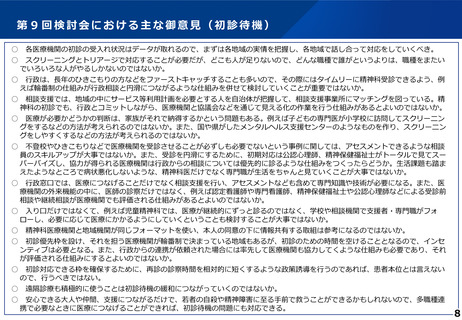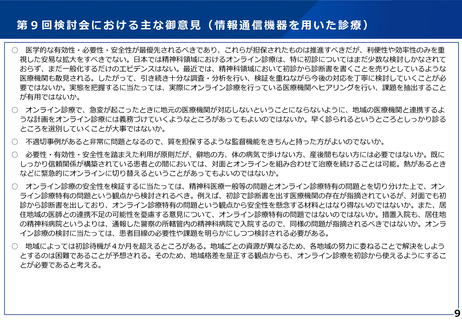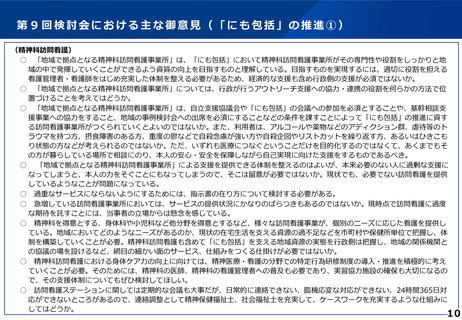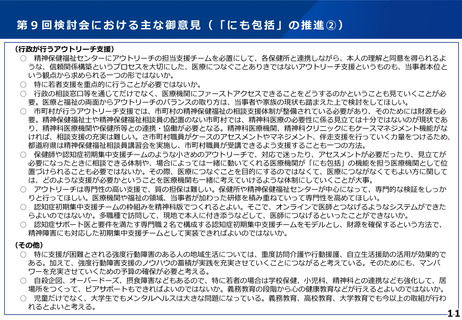よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】第9回検討会における主な御意見について (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64009.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第10回 9/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第9回検討会における主な御意見(入院機能②)
(入院機能・地域移行)(続き)
○ 自発的に短期入院や休息入院ができるような病床があるとよい。そういう人も受け入れられるようなソフトな、リラクゼーション
的な雰囲気のユニットもあるとよいのではないか。
○ 通院している診療所の中で2~3床入院できるような機能があって、そこで早期に退院でき、少し休んで退院できるような仕組み
も必要とする方は一部いるのではないか。
○ 退院後すぐに地域に定着するというのは難しい場合も現実的には多く、レスパイト入院を繰り返しながら地域に定着していくこと
が行われているので、3年、5年ぐらいのやや長期スパンで考えることも必要。
○ 高齢者や多様な患者層が入院している中では、退院のためには地域の介護施設が必要となる部分もあるので、地域移行に向けて地
域と連携して入院中から退院後までのシームレスな支援体制を築くことは、様々な方が混在している中では、精神保健福祉法の制度
の中だけでやっていくことには難しさがある。
○ 精神科地域包括ケア病棟の機能は今後も重要。中規模・小規模の病院では基準を満たすことができるよう柔軟な運用をすることや、
病床削減に伴う人員とお金をここに集めることが必要ではないか。
(人員配置)
○ 病床削減に伴って看護師等病院職員を削減するのではなく、手厚い看護等の支援が受けられるように充実化するべき。その副次的
効果として、ゼロを目指した行動制限最小化にも寄与する可能性があるのではないか。
○ 病床削減によって人員の余剰が出るということであれば、例えば身体合併症のある精神科患者や重篤な精神疾患・障害のある方々
にも十分に余裕を持ってケア提供ができる人員配置や体制整備に充て、病棟の高機能化につなげるような仕組みを検討するべきでは
ないか。
○ 精神科病院でリハビリや栄養管理、口腔ケアといった身体のケアをしていくための人員も確保するべきではないか。
○ 新たな地域医療構想での協議の場で、患者にとって不足している医療、例えば、精神科病院に入院中の患者の生活習慣病管理、あ
るいはリハビリテーション、栄養、口腔の一体的取組について、近隣で精神科病棟に医師や専門職を派遣する仕組みが可能かどうか、
そういった具体的な議論を行っていく必要がある。
○ 質のよい機能を維持するには、精神保健福祉士だけでなく、例えば理学療法士、作業療法士、薬剤師など、多職種が急性期でも包
括期でも慢性期でも活躍できるよう、人員配置を弾力化することも必要ではないか。
○ 社会福祉士と精神保健福祉士の資格は今は別建てだが、人口が減っていることを考えると、将来的には、両資格の統合や2階建て
にすることも含めた検討を行うことも考えられるのではないか。
○
精神保健福祉士と社会福祉士は、役割のすみ分けが一定程度なされているし、資格をなくしたからといって精神の領域で人員が確
保できるとも考えにくい。また、精神医療や保健福祉の特殊性の中で培われてきているノウハウもある。資格統合という方向よりは、
事務スタッフ等とのタスクシェアや、精神保健福祉士が専門性を発揮してしなければいけない業務を可視化し直すこと、DX化や書類
の省力化が必要であり、アシスタントがいる仕組みの検討や、効率的な配置により院内で柔軟に働けるようになるのではないか。
3
(入院機能・地域移行)(続き)
○ 自発的に短期入院や休息入院ができるような病床があるとよい。そういう人も受け入れられるようなソフトな、リラクゼーション
的な雰囲気のユニットもあるとよいのではないか。
○ 通院している診療所の中で2~3床入院できるような機能があって、そこで早期に退院でき、少し休んで退院できるような仕組み
も必要とする方は一部いるのではないか。
○ 退院後すぐに地域に定着するというのは難しい場合も現実的には多く、レスパイト入院を繰り返しながら地域に定着していくこと
が行われているので、3年、5年ぐらいのやや長期スパンで考えることも必要。
○ 高齢者や多様な患者層が入院している中では、退院のためには地域の介護施設が必要となる部分もあるので、地域移行に向けて地
域と連携して入院中から退院後までのシームレスな支援体制を築くことは、様々な方が混在している中では、精神保健福祉法の制度
の中だけでやっていくことには難しさがある。
○ 精神科地域包括ケア病棟の機能は今後も重要。中規模・小規模の病院では基準を満たすことができるよう柔軟な運用をすることや、
病床削減に伴う人員とお金をここに集めることが必要ではないか。
(人員配置)
○ 病床削減に伴って看護師等病院職員を削減するのではなく、手厚い看護等の支援が受けられるように充実化するべき。その副次的
効果として、ゼロを目指した行動制限最小化にも寄与する可能性があるのではないか。
○ 病床削減によって人員の余剰が出るということであれば、例えば身体合併症のある精神科患者や重篤な精神疾患・障害のある方々
にも十分に余裕を持ってケア提供ができる人員配置や体制整備に充て、病棟の高機能化につなげるような仕組みを検討するべきでは
ないか。
○ 精神科病院でリハビリや栄養管理、口腔ケアといった身体のケアをしていくための人員も確保するべきではないか。
○ 新たな地域医療構想での協議の場で、患者にとって不足している医療、例えば、精神科病院に入院中の患者の生活習慣病管理、あ
るいはリハビリテーション、栄養、口腔の一体的取組について、近隣で精神科病棟に医師や専門職を派遣する仕組みが可能かどうか、
そういった具体的な議論を行っていく必要がある。
○ 質のよい機能を維持するには、精神保健福祉士だけでなく、例えば理学療法士、作業療法士、薬剤師など、多職種が急性期でも包
括期でも慢性期でも活躍できるよう、人員配置を弾力化することも必要ではないか。
○ 社会福祉士と精神保健福祉士の資格は今は別建てだが、人口が減っていることを考えると、将来的には、両資格の統合や2階建て
にすることも含めた検討を行うことも考えられるのではないか。
○
精神保健福祉士と社会福祉士は、役割のすみ分けが一定程度なされているし、資格をなくしたからといって精神の領域で人員が確
保できるとも考えにくい。また、精神医療や保健福祉の特殊性の中で培われてきているノウハウもある。資格統合という方向よりは、
事務スタッフ等とのタスクシェアや、精神保健福祉士が専門性を発揮してしなければいけない業務を可視化し直すこと、DX化や書類
の省力化が必要であり、アシスタントがいる仕組みの検討や、効率的な配置により院内で柔軟に働けるようになるのではないか。
3