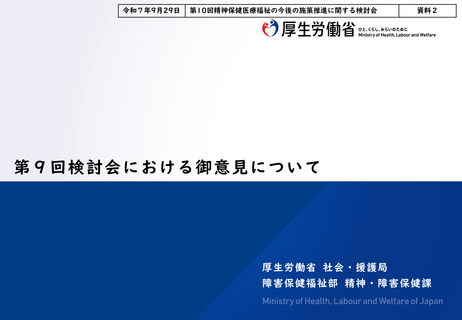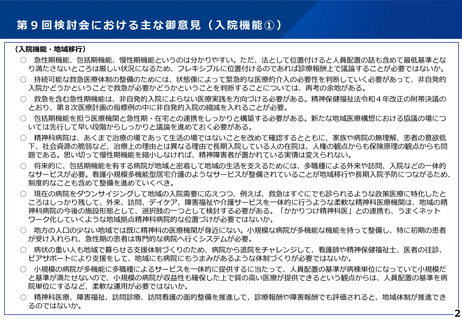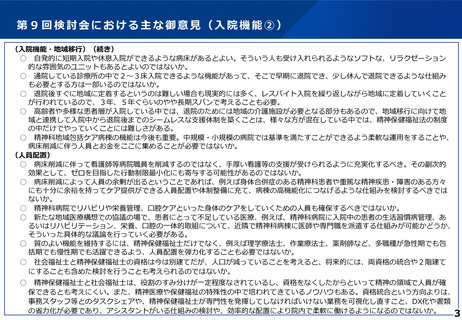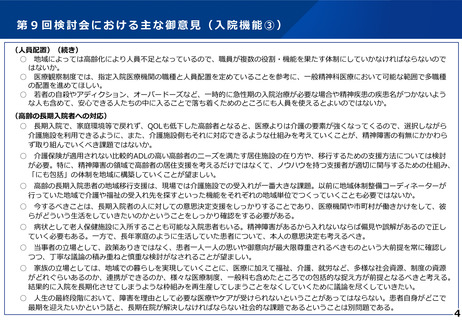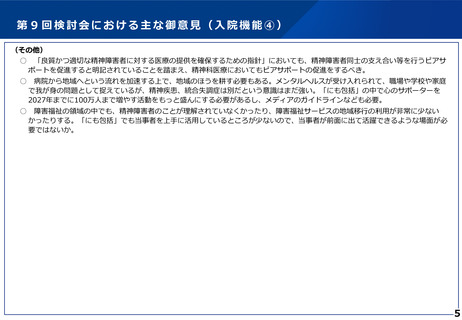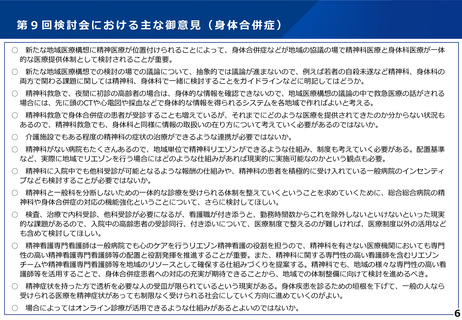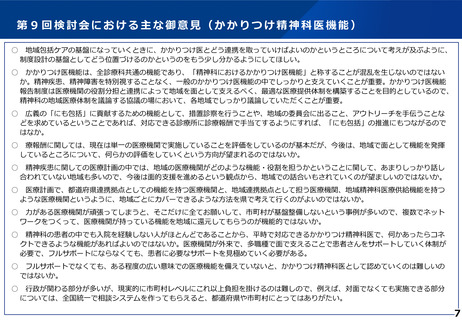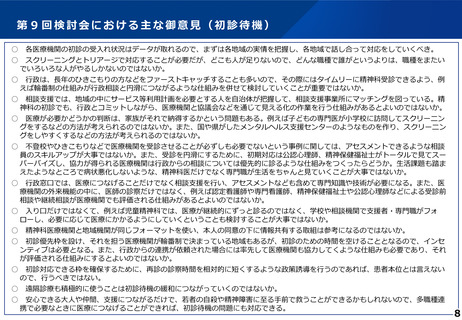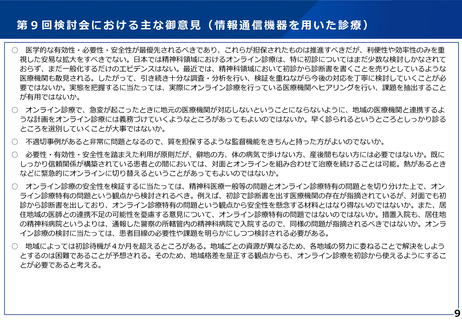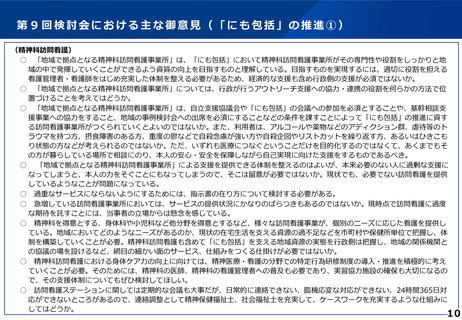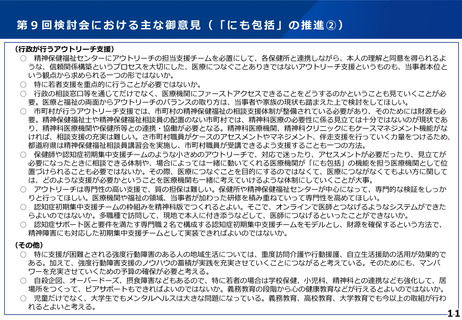よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】第9回検討会における主な御意見について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64009.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第10回 9/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第9回検討会における主な御意見(入院機能①)
(入院機能・地域移行)
○
急性期機能、包括期機能、慢性期機能というのは分かりやすい。ただ、法として位置付けると人員配置の話も含めて最低基準とな
り満たさないところは厳しい状況になるため、フレキシブルに位置付けるのであれば診療報酬上で議論することが必要ではないか。
○
持続可能な救急医療体制の整備のためには、状態像によって緊急的な医療的介入の必要性を判断していく必要があって、非自発的
入院かどうかということで救急が必要かどうかということを判断することについては、再考の余地がある。
○
救急を含む急性期機能は、非自発的入院によらない医療実践を方向づける必要がある。精神保健福祉法令和4年改正の附帯決議の
とおり、第8次医療計画の指標例の中に非自発的入院の縮減を入れることが必要。
○ 包括期機能を担う医療機関と急性期・在宅との連携をしっかりと構築する必要がある。新たな地域医療構想における協議の場につ
いては先行して早い段階からしっかりと議論を進めておく必要がある。
○
精神科病院は、あくまで治療の場であって生活の場ではないことを改めて確認するとともに、家族や病院の無理解、患者の意欲低
下、社会資源の脆弱など、治療上の理由とは異なる理由で長期入院している人の在院は、人権の観点からも保険原理の観点からも問
題である。思い切って慢性期機能を縮小しなければ、精神障害者が置かれている実情は変えられない。
○
将来的に、包括期機能を有する病院が地域と密着して地域の生活を支えるためには、多職種による外来や訪問、入院などの一体的
なサービスが必要。看護小規模多機能型居宅介護のようなサービスが整備されていることが地域移行や長期入院予防につながるため、
制度的なことも含めて整備を進めていくべき。
○
現在の病院をダウンサイジングして地域の入院需要に応えつつ、例えば、救急はすぐにでも診られるような政策医療に特化したと
ころはしっかり残して、外来、訪問、デイケア、障害福祉や介護サービスを一体的に行うような柔軟な精神科医療機関は、地域の精
神科病院の今後の施設形態として、選択肢の一つとして検討する必要がある。「かかりつけ精神科医」との連携も、うまくネット
ワーク化していくような地域拠点精神科病院的な位置づけが必要ではないか。
○
地方の人口の少ない地域では既に精神科の医療機関が身近にない。小規模な病院が多機能な機能を持って整備し、特に初期の患者
が受け入れられ、急性期の患者は専門的な病院へ行くシステムが必要。
○
病状の重い人も地域で暮らせる支援体制づくりのため、病院から退院をチャレンジして、看護師や精神保健福祉士、医者の往診、
ピアサポートにより支援をして、地域にも病院にもうまみがあるような体制づくりが必要ではないか。
○
小規模の病院が多機能に多職種によるサービスを一体的に提供するに当たって、人員配置の基準が病棟単位になっていて小規模だ
と基準が満たせないので、小規模の病院が収益性も確保した上で質の高い医療が提供できるという観点からは、人員配置の基準を病
院単位にするなど、柔軟な運用が必要ではないか。
○
精神科医療、障害福祉、訪問診療、訪問看護の面的整備を推進して、診療報酬や障害報酬でも評価されると、地域体制が推進でき
るのではないか。
2
(入院機能・地域移行)
○
急性期機能、包括期機能、慢性期機能というのは分かりやすい。ただ、法として位置付けると人員配置の話も含めて最低基準とな
り満たさないところは厳しい状況になるため、フレキシブルに位置付けるのであれば診療報酬上で議論することが必要ではないか。
○
持続可能な救急医療体制の整備のためには、状態像によって緊急的な医療的介入の必要性を判断していく必要があって、非自発的
入院かどうかということで救急が必要かどうかということを判断することについては、再考の余地がある。
○
救急を含む急性期機能は、非自発的入院によらない医療実践を方向づける必要がある。精神保健福祉法令和4年改正の附帯決議の
とおり、第8次医療計画の指標例の中に非自発的入院の縮減を入れることが必要。
○ 包括期機能を担う医療機関と急性期・在宅との連携をしっかりと構築する必要がある。新たな地域医療構想における協議の場につ
いては先行して早い段階からしっかりと議論を進めておく必要がある。
○
精神科病院は、あくまで治療の場であって生活の場ではないことを改めて確認するとともに、家族や病院の無理解、患者の意欲低
下、社会資源の脆弱など、治療上の理由とは異なる理由で長期入院している人の在院は、人権の観点からも保険原理の観点からも問
題である。思い切って慢性期機能を縮小しなければ、精神障害者が置かれている実情は変えられない。
○
将来的に、包括期機能を有する病院が地域と密着して地域の生活を支えるためには、多職種による外来や訪問、入院などの一体的
なサービスが必要。看護小規模多機能型居宅介護のようなサービスが整備されていることが地域移行や長期入院予防につながるため、
制度的なことも含めて整備を進めていくべき。
○
現在の病院をダウンサイジングして地域の入院需要に応えつつ、例えば、救急はすぐにでも診られるような政策医療に特化したと
ころはしっかり残して、外来、訪問、デイケア、障害福祉や介護サービスを一体的に行うような柔軟な精神科医療機関は、地域の精
神科病院の今後の施設形態として、選択肢の一つとして検討する必要がある。「かかりつけ精神科医」との連携も、うまくネット
ワーク化していくような地域拠点精神科病院的な位置づけが必要ではないか。
○
地方の人口の少ない地域では既に精神科の医療機関が身近にない。小規模な病院が多機能な機能を持って整備し、特に初期の患者
が受け入れられ、急性期の患者は専門的な病院へ行くシステムが必要。
○
病状の重い人も地域で暮らせる支援体制づくりのため、病院から退院をチャレンジして、看護師や精神保健福祉士、医者の往診、
ピアサポートにより支援をして、地域にも病院にもうまみがあるような体制づくりが必要ではないか。
○
小規模の病院が多機能に多職種によるサービスを一体的に提供するに当たって、人員配置の基準が病棟単位になっていて小規模だ
と基準が満たせないので、小規模の病院が収益性も確保した上で質の高い医療が提供できるという観点からは、人員配置の基準を病
院単位にするなど、柔軟な運用が必要ではないか。
○
精神科医療、障害福祉、訪問診療、訪問看護の面的整備を推進して、診療報酬や障害報酬でも評価されると、地域体制が推進でき
るのではないか。
2