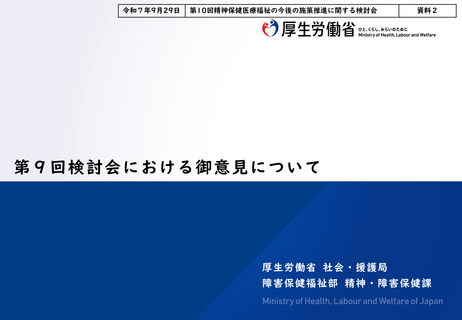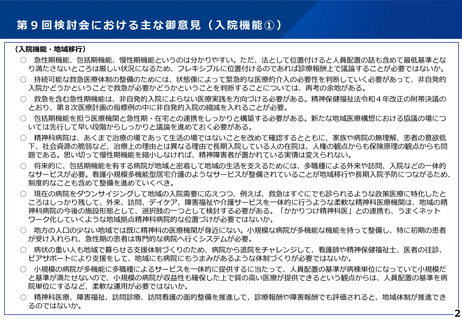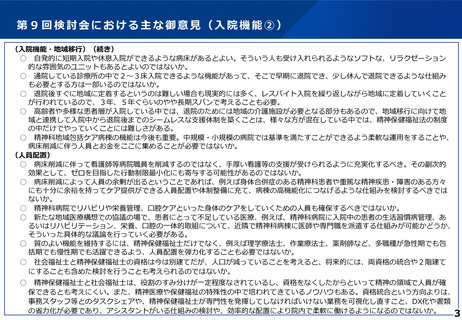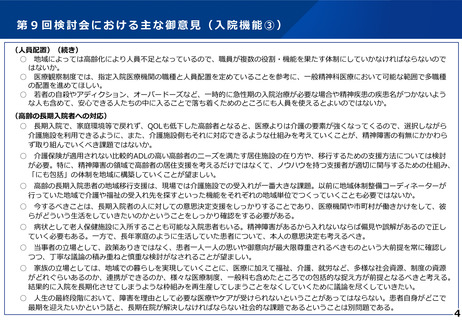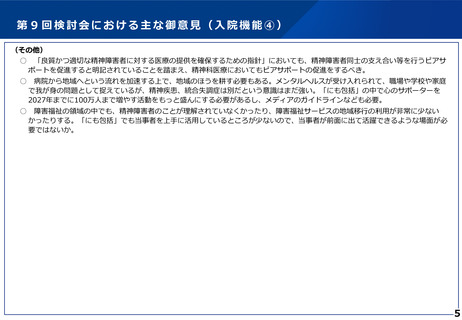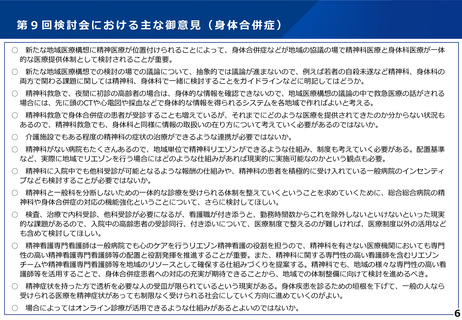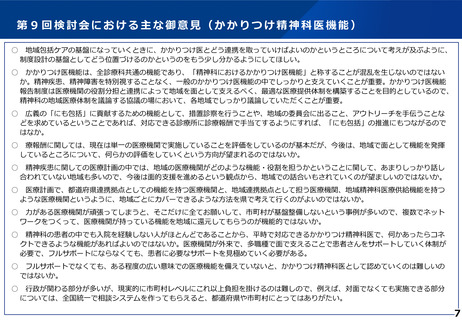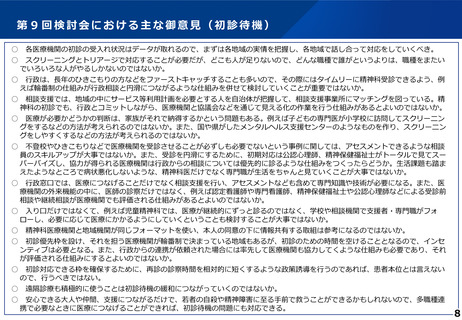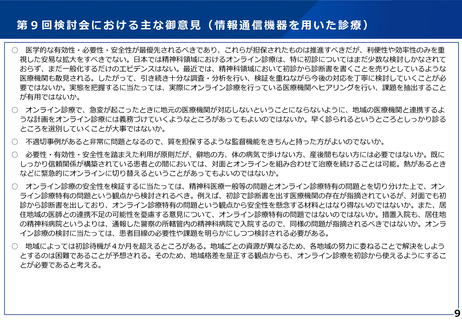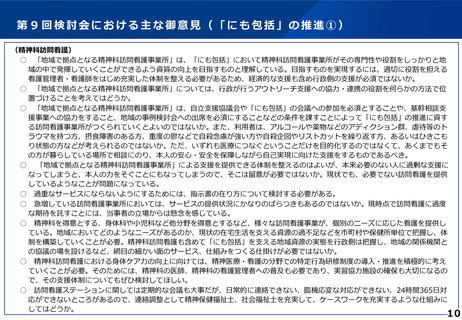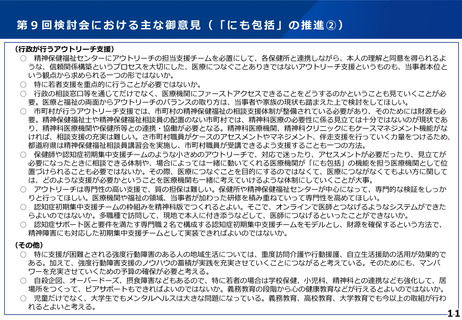よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】第9回検討会における主な御意見について (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64009.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第10回 9/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第9回検討会における主な御意見(入院機能③)
(人員配置)(続き)
○ 地域によっては高齢化により人員不足となっているので、職員が複数の役割・機能を果たす体制にしていかなければならないので
はないか。
○ 医療観察制度では、指定入院医療機関の職種と人員配置を定めていることを参考に、一般精神科医療において可能な範囲で多職種
の配置を進めてほしい。
○ 若者の自殺やアディクション、オーバードーズなど、一時的に急性期の入院治療が必要な場合や精神疾患の疾患名がつかないよう
な人も含めて、安心できる人たちの中に入ることで落ち着くためのところにも人員を使えるとよいのではないか。
(高齢の長期入院者への対応)
○ 長期入院で、家庭環境等で戻れず、QOLも低下した高齢者となると、医療よりは介護の要素が強くなってくるので、選択しながら
介護施設を利用できるように、また、介護施設側もそれに対応できるような仕組みを考えていくことが、精神障害の有無にかかわら
ず取り組んでいくべき課題ではないか。
○
介護保険が適用されない比較的ADLの高い高齢者のニーズを満たす居住施設の在り方や、移行するための支援方法については検討
が必要。特に、精神障害の領域で高齢者の居住支援を考えるだけではなくて、ノウハウを持つ支援者が適切に関与するための仕組み、
「にも包括」の体制を地域に構築していくことが望ましい。
○
高齢の長期入院患者の地域移行支援は、現場では介護施設での受入れが一番大きな課題。以前に地域体制整備コーディネーターが
行っていた地域で介護や福祉の受入れ先を探すといった機能をそれぞれの地域単位でつくっていくことも必要ではないか。
○
今するべきことは、長期入院者の人に対しての意思決定支援をしっかりすることであり、医療機関や市町村が働きかけをして、彼
らがどういう生活をしていきたいのかということをしっかり確認をする必要がある。
○
病状として老人保健施設に入所することも可能な入院患者もいる。精神障害があるから入れないならば偏見や誤解があるので正し
ていく必要もある。一方で、長年家庭のように生活していた患者について、本人の意思決定も考えるべき。
○
当事者の立場として、政策ありきではなく、患者一人一人の思いや御意向が最大限尊重されるべきものという大前提を常に確認し
つつ、丁寧な議論の積み重ねと慎重な検討がなされることが望ましい。
○
家族の立場としては、地域での暮らしを実現していくことに、医療に加えて福祉、介護、就労など、多様な社会資源、制度の資源
がどれぐらいあるのか、連携ができるのか、様々な医療制度、一般科も含めたところでの包括的な捉え方が前提となるべきと考える。
結果的に入院を長期化させてしまうような枠組みを再生産してしまうことをなくしていくために議論を尽くしていきたい。
○
人生の最終段階において、障害を理由として必要な医療やケアが受けられないということがあってはならない。患者自身がどこで
最期を迎えたいかという話と、長期在院が解決しなければならない社会的な課題であるということは別問題である。
4
(人員配置)(続き)
○ 地域によっては高齢化により人員不足となっているので、職員が複数の役割・機能を果たす体制にしていかなければならないので
はないか。
○ 医療観察制度では、指定入院医療機関の職種と人員配置を定めていることを参考に、一般精神科医療において可能な範囲で多職種
の配置を進めてほしい。
○ 若者の自殺やアディクション、オーバードーズなど、一時的に急性期の入院治療が必要な場合や精神疾患の疾患名がつかないよう
な人も含めて、安心できる人たちの中に入ることで落ち着くためのところにも人員を使えるとよいのではないか。
(高齢の長期入院者への対応)
○ 長期入院で、家庭環境等で戻れず、QOLも低下した高齢者となると、医療よりは介護の要素が強くなってくるので、選択しながら
介護施設を利用できるように、また、介護施設側もそれに対応できるような仕組みを考えていくことが、精神障害の有無にかかわら
ず取り組んでいくべき課題ではないか。
○
介護保険が適用されない比較的ADLの高い高齢者のニーズを満たす居住施設の在り方や、移行するための支援方法については検討
が必要。特に、精神障害の領域で高齢者の居住支援を考えるだけではなくて、ノウハウを持つ支援者が適切に関与するための仕組み、
「にも包括」の体制を地域に構築していくことが望ましい。
○
高齢の長期入院患者の地域移行支援は、現場では介護施設での受入れが一番大きな課題。以前に地域体制整備コーディネーターが
行っていた地域で介護や福祉の受入れ先を探すといった機能をそれぞれの地域単位でつくっていくことも必要ではないか。
○
今するべきことは、長期入院者の人に対しての意思決定支援をしっかりすることであり、医療機関や市町村が働きかけをして、彼
らがどういう生活をしていきたいのかということをしっかり確認をする必要がある。
○
病状として老人保健施設に入所することも可能な入院患者もいる。精神障害があるから入れないならば偏見や誤解があるので正し
ていく必要もある。一方で、長年家庭のように生活していた患者について、本人の意思決定も考えるべき。
○
当事者の立場として、政策ありきではなく、患者一人一人の思いや御意向が最大限尊重されるべきものという大前提を常に確認し
つつ、丁寧な議論の積み重ねと慎重な検討がなされることが望ましい。
○
家族の立場としては、地域での暮らしを実現していくことに、医療に加えて福祉、介護、就労など、多様な社会資源、制度の資源
がどれぐらいあるのか、連携ができるのか、様々な医療制度、一般科も含めたところでの包括的な捉え方が前提となるべきと考える。
結果的に入院を長期化させてしまうような枠組みを再生産してしまうことをなくしていくために議論を尽くしていきたい。
○
人生の最終段階において、障害を理由として必要な医療やケアが受けられないということがあってはならない。患者自身がどこで
最期を迎えたいかという話と、長期在院が解決しなければならない社会的な課題であるということは別問題である。
4