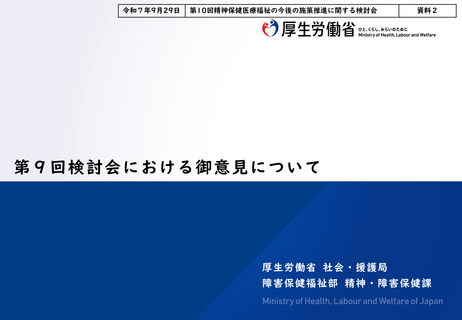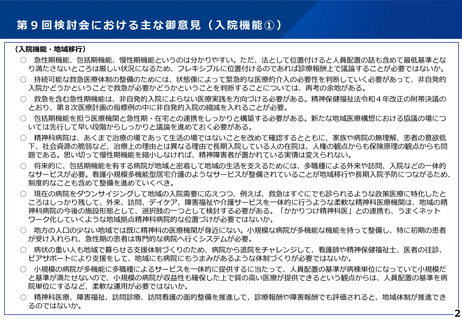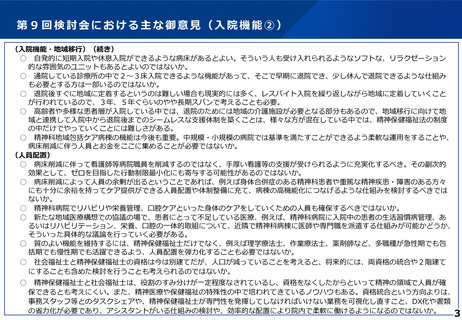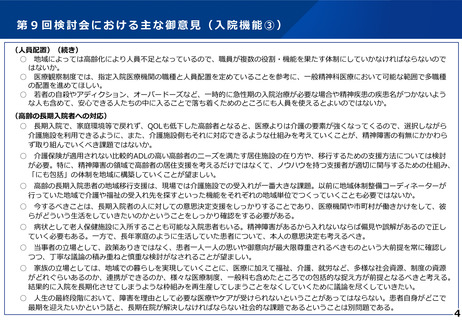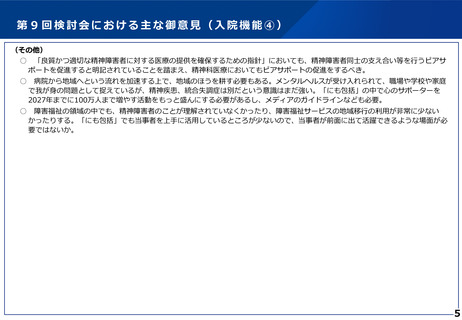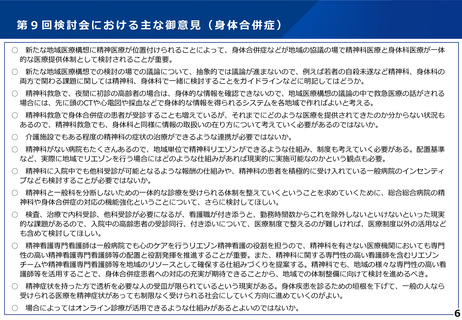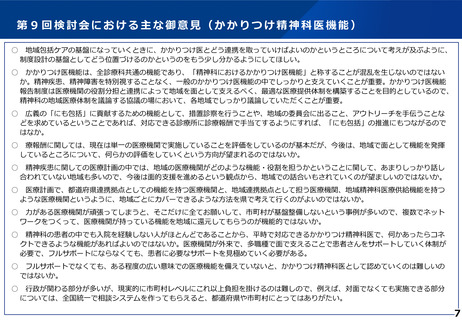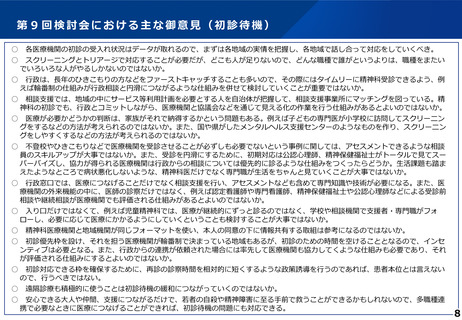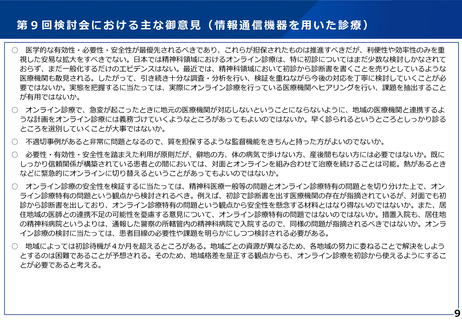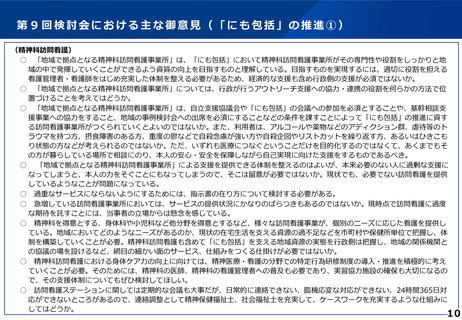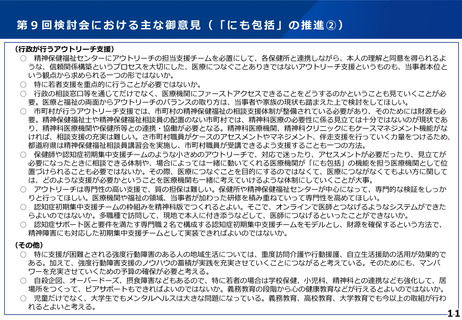よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】第9回検討会における主な御意見について (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64009.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第10回 9/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第9回検討会における主な御意見(「にも包括」の推進①)
(精神科訪問看護)
○ 「地域で拠点となる精神科訪問看護事業所」は、「にも包括」において精神科訪問看護事業所がその専門性や役割をしっかりと地
域の中で発揮していくことができるよう資質の向上を目指すものと理解している。目指すものを実現するには、適切に役割を担える
看護管理者・看護師をはじめ充実した体制を整える必要があるため、経済的な支援も含め行政側の支援が必須ではないか。
○ 「地域で拠点となる精神科訪問看護事業所」については、行政が行うアウトリーチ支援への協力・連携の役割を何らかの方法で位
置づけることを考えてはどうか。
○ 「地域で拠点となる精神科訪問看護事業所」は、自立支援協議会や「にも包括」の会議への参加を必須とすることや、基幹相談支
援事業への協力をすること、地域の事例検討会への出席を必須にすることなどの条件を課すことによって「にも包括」の推進に資す
る訪問看護事業所がつくられていくとよいのではないか。また、利用者は、アルコールや薬物などのアディクション群、虐待等のト
ラウマを持つ方、摂食障害のある方、重度の鬱などで自殺念慮が強い方や自殺企図やリストカットを繰り返す方、あるいはひきこも
り状態の方などが考えられるのではないか。ただ、いずれも医療につなぐということだけを目的化するのではなくて、あくまでもそ
の方が暮らしている場所で相談にのり、本人の安心・安全を保障しながら自己実現に向けた支援をするものであるべき。
○ 「地域で拠点となる精神科訪問看護事業所」による支援を提供できる体制を整えるのはよいが、本来必要のない人に過剰な支援に
なってしまうと、本人の力をそぐことにもなってしまうので、そこは留意が必要ではないか。現状でも、必要でない訪問看護を提供
しているようなことが問題になっている。
○ 過重なサービスにならないようにするためには、指示書の在り方について検討する必要がある。
○ 急増している訪問看護事業所においては、サービスの提供状況にかなりのばらつきもあるのではないか。現時点で訪問看護に過度
な期待を託すことには、当事者の立場からは懸念を感じている。
○ 精神科を得意とする、身体科や小児科など他分野を得意とするなど、様々な訪問看護事業が、個別のニーズに応じた看護を提供し
ている。地域においてどのようなニーズがあるのか、現状の在宅生活を支える資源の過不足などを市町村や保健所単位で把握し、体
制を構築していくことが必要。精神科訪問看護も含めて「にも包括」を支える地域資源の実態を行政側は把握し、地域の関係機関と
の協議の場を設けるなど、網目の細かい面のサービス、仕組みをつくる仕掛けが必要ではないか。
○ 精神科訪問看護における身体ケア力の向上に向けては、精神医療・看護の分野での特定行為研修制度の導入・推進を積極的に考え
ていくことが必要。そのためには、精神科の医師、精神科の看護管理者への普及も必要であり、実習協力施設の確保も大切になるの
で、その支援体制についてもぜひ検討してほしい。
○ 訪問看護ステーションに関しては定期的な会議も大事だが、日常的に連絡できない、臨機応変な対応ができない、24時間365日対
応ができないところがあるので、連絡調整として精神保健福祉士、社会福祉士を充実して、ケースワークを充実するような仕組みに
してはどうか。
10
(精神科訪問看護)
○ 「地域で拠点となる精神科訪問看護事業所」は、「にも包括」において精神科訪問看護事業所がその専門性や役割をしっかりと地
域の中で発揮していくことができるよう資質の向上を目指すものと理解している。目指すものを実現するには、適切に役割を担える
看護管理者・看護師をはじめ充実した体制を整える必要があるため、経済的な支援も含め行政側の支援が必須ではないか。
○ 「地域で拠点となる精神科訪問看護事業所」については、行政が行うアウトリーチ支援への協力・連携の役割を何らかの方法で位
置づけることを考えてはどうか。
○ 「地域で拠点となる精神科訪問看護事業所」は、自立支援協議会や「にも包括」の会議への参加を必須とすることや、基幹相談支
援事業への協力をすること、地域の事例検討会への出席を必須にすることなどの条件を課すことによって「にも包括」の推進に資す
る訪問看護事業所がつくられていくとよいのではないか。また、利用者は、アルコールや薬物などのアディクション群、虐待等のト
ラウマを持つ方、摂食障害のある方、重度の鬱などで自殺念慮が強い方や自殺企図やリストカットを繰り返す方、あるいはひきこも
り状態の方などが考えられるのではないか。ただ、いずれも医療につなぐということだけを目的化するのではなくて、あくまでもそ
の方が暮らしている場所で相談にのり、本人の安心・安全を保障しながら自己実現に向けた支援をするものであるべき。
○ 「地域で拠点となる精神科訪問看護事業所」による支援を提供できる体制を整えるのはよいが、本来必要のない人に過剰な支援に
なってしまうと、本人の力をそぐことにもなってしまうので、そこは留意が必要ではないか。現状でも、必要でない訪問看護を提供
しているようなことが問題になっている。
○ 過重なサービスにならないようにするためには、指示書の在り方について検討する必要がある。
○ 急増している訪問看護事業所においては、サービスの提供状況にかなりのばらつきもあるのではないか。現時点で訪問看護に過度
な期待を託すことには、当事者の立場からは懸念を感じている。
○ 精神科を得意とする、身体科や小児科など他分野を得意とするなど、様々な訪問看護事業が、個別のニーズに応じた看護を提供し
ている。地域においてどのようなニーズがあるのか、現状の在宅生活を支える資源の過不足などを市町村や保健所単位で把握し、体
制を構築していくことが必要。精神科訪問看護も含めて「にも包括」を支える地域資源の実態を行政側は把握し、地域の関係機関と
の協議の場を設けるなど、網目の細かい面のサービス、仕組みをつくる仕掛けが必要ではないか。
○ 精神科訪問看護における身体ケア力の向上に向けては、精神医療・看護の分野での特定行為研修制度の導入・推進を積極的に考え
ていくことが必要。そのためには、精神科の医師、精神科の看護管理者への普及も必要であり、実習協力施設の確保も大切になるの
で、その支援体制についてもぜひ検討してほしい。
○ 訪問看護ステーションに関しては定期的な会議も大事だが、日常的に連絡できない、臨機応変な対応ができない、24時間365日対
応ができないところがあるので、連絡調整として精神保健福祉士、社会福祉士を充実して、ケースワークを充実するような仕組みに
してはどうか。
10