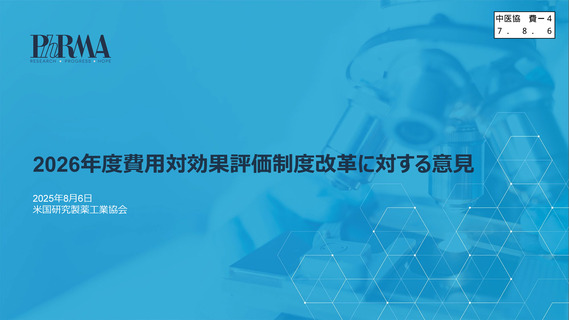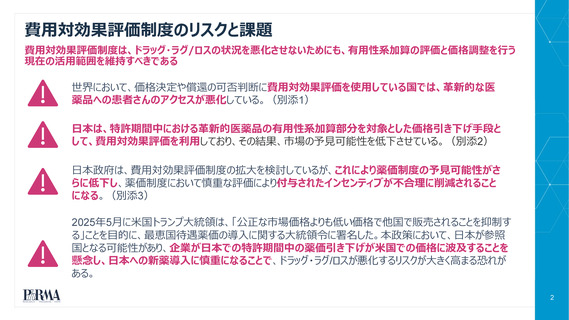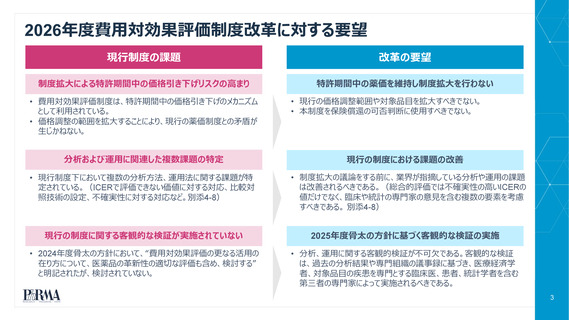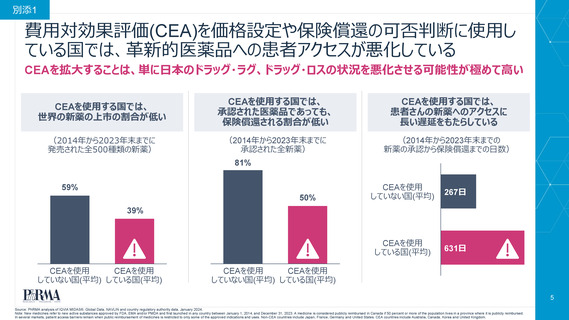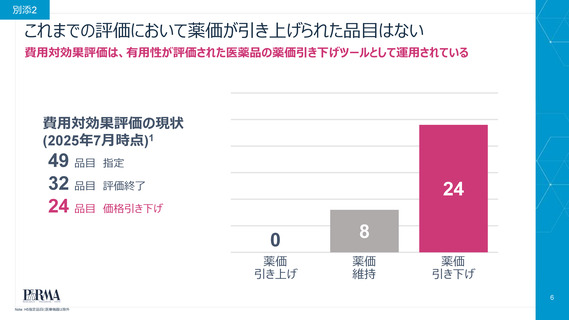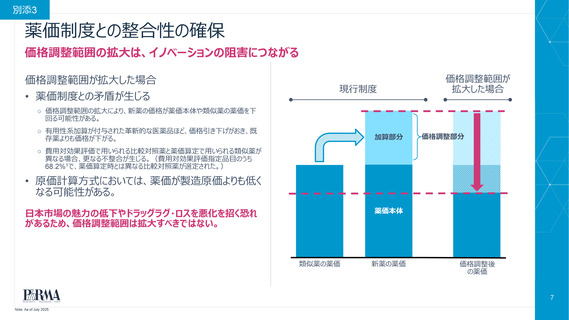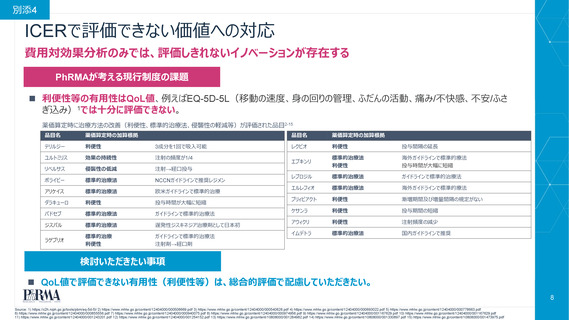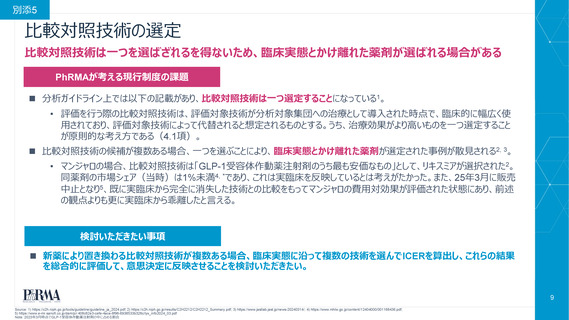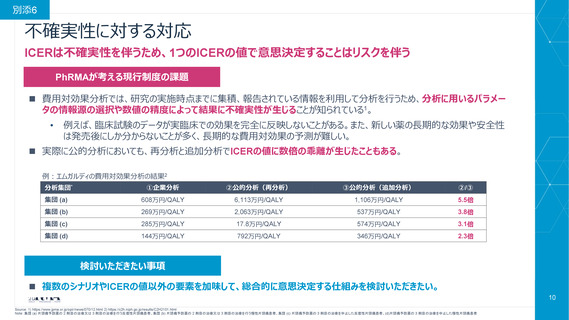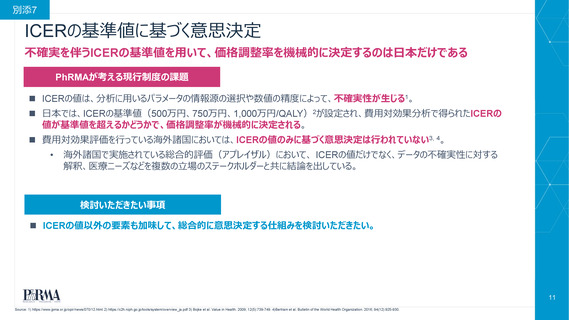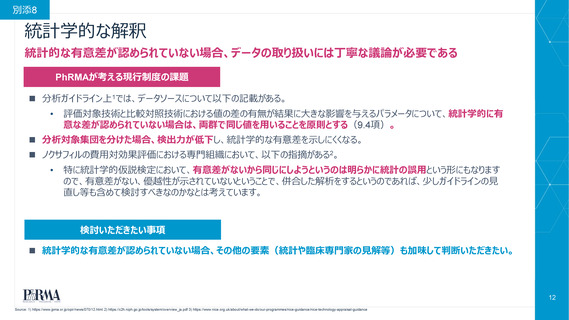よむ、つかう、まなぶ。
費-4米国研究製薬工業協会 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60773.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第71回 8/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2026年度費用対効果評価制度改革に対する要望
現行制度の課題
改革の要望
制度拡大による特許期間中の価格引き下げリスクの高まり
特許期間中の薬価を維持し制度拡大を行わない
• 費用対効果評価制度は、特許期間中の価格引き下げのメカニズム
として利用されている。
• 価格調整の範囲を拡大することにより、現行の薬価制度との矛盾が
生じかねない。
• 現行の価格調整範囲や対象品目を拡大すべきでない。
• 本制度を保険償還の可否判断に使用すべきでない。
分析および運用に関連した複数課題の特定
現行の制度における課題の改善
• 現行制度下において複数の分析方法、運用法に関する課題が特
定されている。(ICERで評価できない価値に対する対応、比較対
照技術の設定、不確実性に対する対応など。別添4-8)
• 制度拡大の議論をする前に、業界が指摘している分析や運用の課題
は改善されるべきである。(総合的評価では不確実性の高いICERの
値だけでなく、臨床や統計の専門家の意見を含む複数の要素を考慮
すべきである。 別添4-8)
現行の制度に関する客観的な検証が実施されていない
2025年度骨太の方針に基づく客観的な検証の実施
• 2024年度骨太の方針において、“費用対効果評価の更なる活用の
在り方について、医薬品の革新性の適切な評価も含め、検討する”
と明記されたが、検討されていない。
• 分析、運用に関する客観的検証が不可欠である。客観的な検証
は、過去の分析結果や専門組織の議事録に基づき、医療経済学
者、対象品目の疾患を専門とする臨床医、患者、統計学者を含む
第三者の専門家によって実施されるべきである。
3
現行制度の課題
改革の要望
制度拡大による特許期間中の価格引き下げリスクの高まり
特許期間中の薬価を維持し制度拡大を行わない
• 費用対効果評価制度は、特許期間中の価格引き下げのメカニズム
として利用されている。
• 価格調整の範囲を拡大することにより、現行の薬価制度との矛盾が
生じかねない。
• 現行の価格調整範囲や対象品目を拡大すべきでない。
• 本制度を保険償還の可否判断に使用すべきでない。
分析および運用に関連した複数課題の特定
現行の制度における課題の改善
• 現行制度下において複数の分析方法、運用法に関する課題が特
定されている。(ICERで評価できない価値に対する対応、比較対
照技術の設定、不確実性に対する対応など。別添4-8)
• 制度拡大の議論をする前に、業界が指摘している分析や運用の課題
は改善されるべきである。(総合的評価では不確実性の高いICERの
値だけでなく、臨床や統計の専門家の意見を含む複数の要素を考慮
すべきである。 別添4-8)
現行の制度に関する客観的な検証が実施されていない
2025年度骨太の方針に基づく客観的な検証の実施
• 2024年度骨太の方針において、“費用対効果評価の更なる活用の
在り方について、医薬品の革新性の適切な評価も含め、検討する”
と明記されたが、検討されていない。
• 分析、運用に関する客観的検証が不可欠である。客観的な検証
は、過去の分析結果や専門組織の議事録に基づき、医療経済学
者、対象品目の疾患を専門とする臨床医、患者、統計学者を含む
第三者の専門家によって実施されるべきである。
3