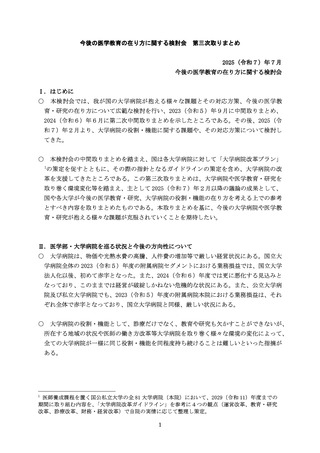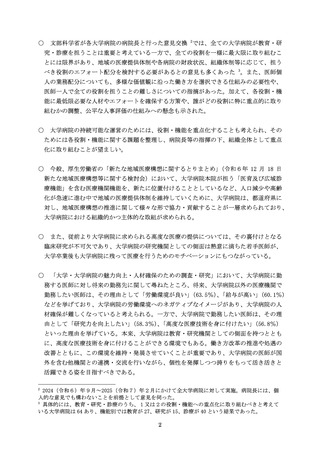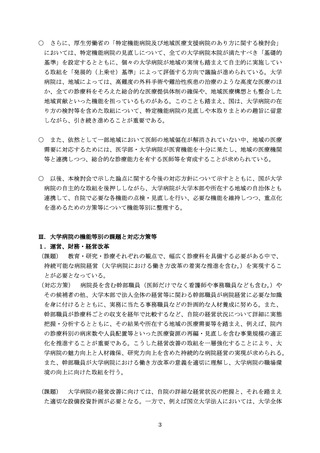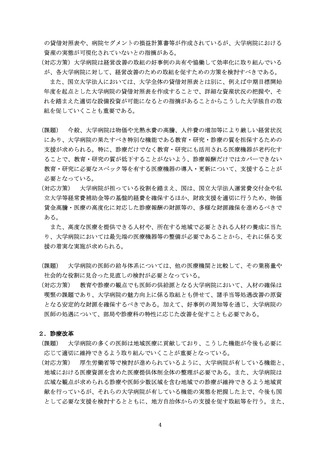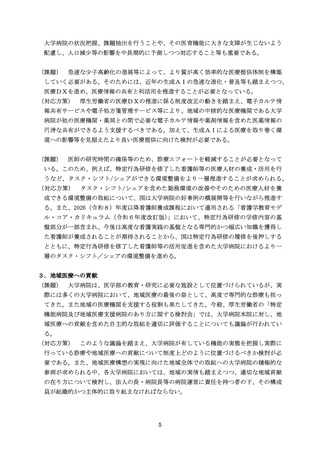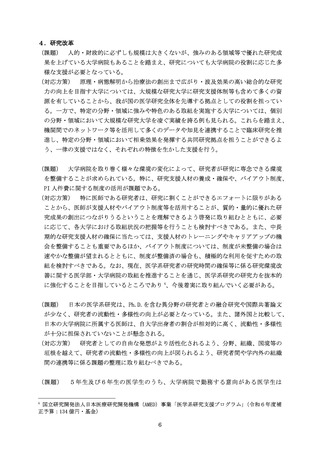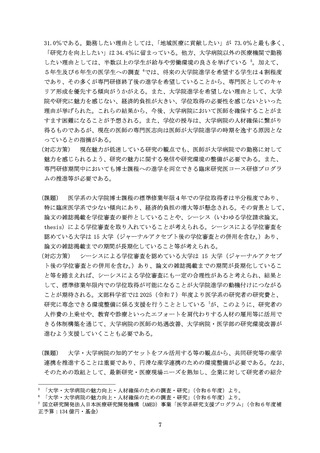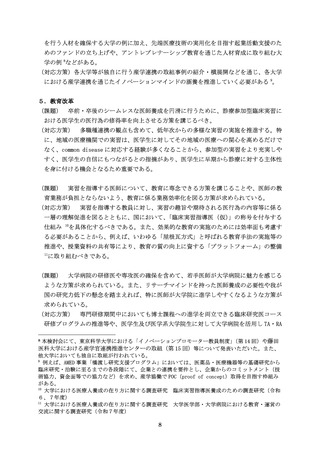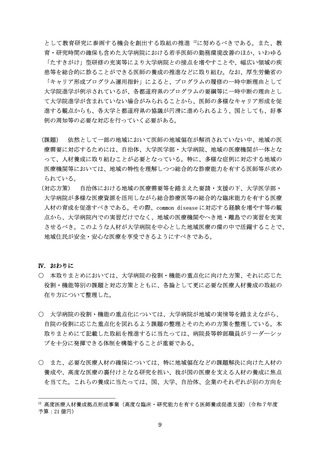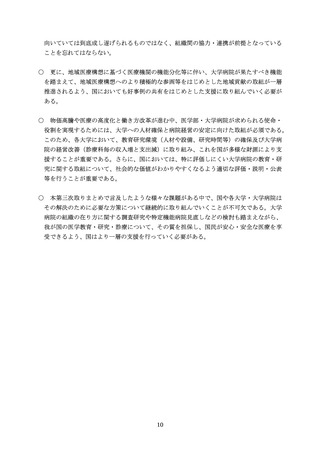よむ、つかう、まなぶ。
今後の医学教育の在り方に関する検討会 第三次取りまとめ (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/124/toushin/mext_00005.html |
| 出典情報 | 今後の医学教育の在り方に関する検討会 第三次取りまとめ(7/14)《文部科学省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
31.0%である。勤務したい理由としては、「地域医療に貢献したい」が 73.0%と最も多く、
「研究力を向上したい」は 34.4%に留まっている。他方、大学病院以外の医療機関で勤務
したい理由としては、半数以上の学生が給与や労働環境の良さを挙げている 5。加えて、
5年生及び6年生の医学生への調査 6では、将来の大学院進学を希望する学生は4割程度
であり、その多くが専門研修終了後の進学を希望していることから、専門医としてのキャ
リア形成を優先する傾向がうかがえる。また、大学院進学を希望しない理由として、大学
院や研究に魅力を感じない、経済的負担が大きい、学位取得の必要性を感じないといった
理由が挙げられた。これらの結果から、今後、大学病院において医師を確保することがま
すます困難になることが予想される。また、学位の授与は、大学病院の人材確保に繋がり
得るものであるが、現在の医師の専門医志向は医師が大学院進学の時期を逸する原因とな
っているとの指摘がある。
(対応方策)
現在魅力が低迷している研究の観点でも、医師が大学病院での勤務に対して
魅力を感じられるよう、研究の魅力に関する発信や研究環境の整備が必要である。また、
専門研修期間中においても博士課程への進学を両立できる臨床研究医コース研修プログラ
ムの推進等が必要である。
(課題)
医学系の大学院博士課程の標準修業年限4年での学位取得者は半分程度であり、
特に臨床医学系で少ない傾向にあり、経済的負担の増大等が懸念される。その背景として、
論文の雑誌掲載を学位審査の要件としていることや、シーシス(いわゆる学位請求論文。
thesis)による学位審査を取り入れていることが考えられる。シーシスによる学位審査を
認めている大学は 15 大学(ジャーナルアクセプト後の学位審査との併用を含む。)あり、
論文の雑誌掲載までの期間が長期化していること等が考えられる。
(対応方策)
シーシスによる学位審査を認めている大学は 15 大学(ジャーナルアクセプ
ト後の学位審査との併用を含む。)あり、論文の雑誌掲載までの期間が長期化しているこ
と等を踏まえれば、シーシスによる学位審査にも一定の合理性があると考えられ、結果と
して、標準修業年限内での学位取得が可能になることが大学院進学の動機付けにつながる
ことが期待される。文部科学省では 2025(令和7)年度より医学系の研究者の研究費と、
研究に専念できる環境整備に係る支援を行うこととしている 7が、このように、研究者の
人件費の上乗せや、教育や診療といったエフォートを肩代わりする人材の雇用等に活用で
きる体制構築を通じて、大学病院の医師の処遇改善、大学病院・医学部の研究環境改善が
進むよう支援していくことも必要である。
(課題)
大学・大学病院の知的アセットをフル活用する等の観点から、共同研究等の産学
連携を推進することは重要であり、円滑な産学連携のための環境整備が必要である。なお、
そのための取組として、最新研究・医療現場ニーズを熟知し、企業に対して研究者の紹介
5
「大学・大学病院の魅力向上・人材確保のための調査・研究」
(令和6年度)より。
「大学・大学病院の魅力向上・人材確保のための調査・研究」
(令和6年度)より。
7
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)事業「医学系研究支援プログラム」(令和6年度補
正予算:134 億円・基金)
6
7
「研究力を向上したい」は 34.4%に留まっている。他方、大学病院以外の医療機関で勤務
したい理由としては、半数以上の学生が給与や労働環境の良さを挙げている 5。加えて、
5年生及び6年生の医学生への調査 6では、将来の大学院進学を希望する学生は4割程度
であり、その多くが専門研修終了後の進学を希望していることから、専門医としてのキャ
リア形成を優先する傾向がうかがえる。また、大学院進学を希望しない理由として、大学
院や研究に魅力を感じない、経済的負担が大きい、学位取得の必要性を感じないといった
理由が挙げられた。これらの結果から、今後、大学病院において医師を確保することがま
すます困難になることが予想される。また、学位の授与は、大学病院の人材確保に繋がり
得るものであるが、現在の医師の専門医志向は医師が大学院進学の時期を逸する原因とな
っているとの指摘がある。
(対応方策)
現在魅力が低迷している研究の観点でも、医師が大学病院での勤務に対して
魅力を感じられるよう、研究の魅力に関する発信や研究環境の整備が必要である。また、
専門研修期間中においても博士課程への進学を両立できる臨床研究医コース研修プログラ
ムの推進等が必要である。
(課題)
医学系の大学院博士課程の標準修業年限4年での学位取得者は半分程度であり、
特に臨床医学系で少ない傾向にあり、経済的負担の増大等が懸念される。その背景として、
論文の雑誌掲載を学位審査の要件としていることや、シーシス(いわゆる学位請求論文。
thesis)による学位審査を取り入れていることが考えられる。シーシスによる学位審査を
認めている大学は 15 大学(ジャーナルアクセプト後の学位審査との併用を含む。)あり、
論文の雑誌掲載までの期間が長期化していること等が考えられる。
(対応方策)
シーシスによる学位審査を認めている大学は 15 大学(ジャーナルアクセプ
ト後の学位審査との併用を含む。)あり、論文の雑誌掲載までの期間が長期化しているこ
と等を踏まえれば、シーシスによる学位審査にも一定の合理性があると考えられ、結果と
して、標準修業年限内での学位取得が可能になることが大学院進学の動機付けにつながる
ことが期待される。文部科学省では 2025(令和7)年度より医学系の研究者の研究費と、
研究に専念できる環境整備に係る支援を行うこととしている 7が、このように、研究者の
人件費の上乗せや、教育や診療といったエフォートを肩代わりする人材の雇用等に活用で
きる体制構築を通じて、大学病院の医師の処遇改善、大学病院・医学部の研究環境改善が
進むよう支援していくことも必要である。
(課題)
大学・大学病院の知的アセットをフル活用する等の観点から、共同研究等の産学
連携を推進することは重要であり、円滑な産学連携のための環境整備が必要である。なお、
そのための取組として、最新研究・医療現場ニーズを熟知し、企業に対して研究者の紹介
5
「大学・大学病院の魅力向上・人材確保のための調査・研究」
(令和6年度)より。
「大学・大学病院の魅力向上・人材確保のための調査・研究」
(令和6年度)より。
7
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)事業「医学系研究支援プログラム」(令和6年度補
正予算:134 億円・基金)
6
7