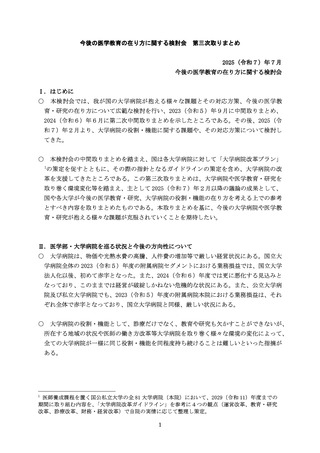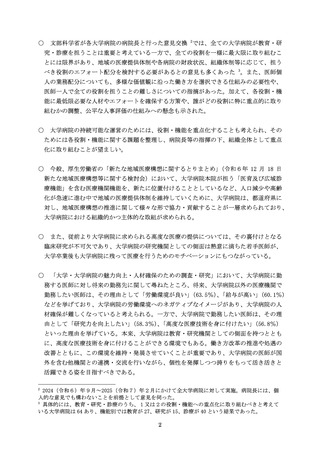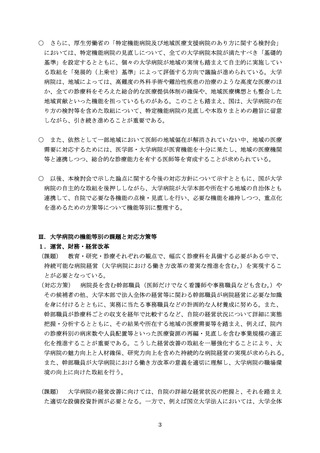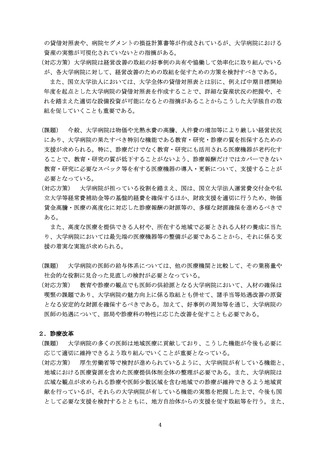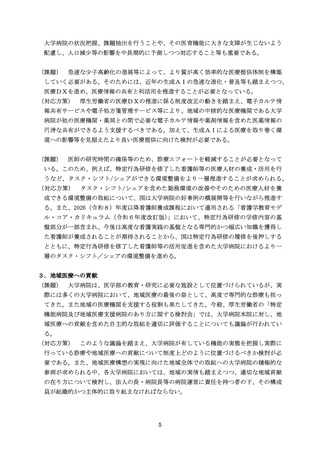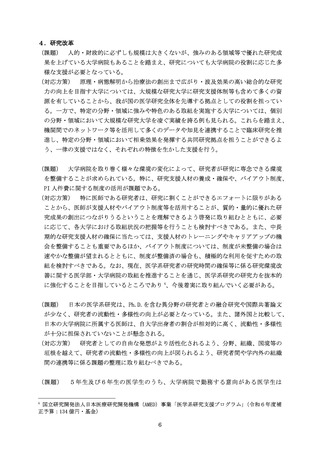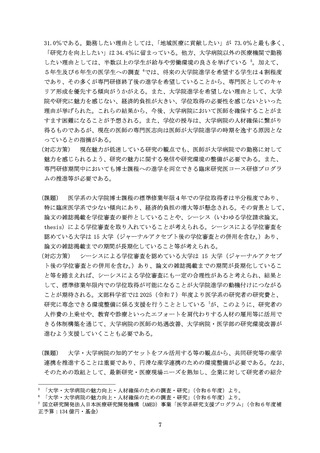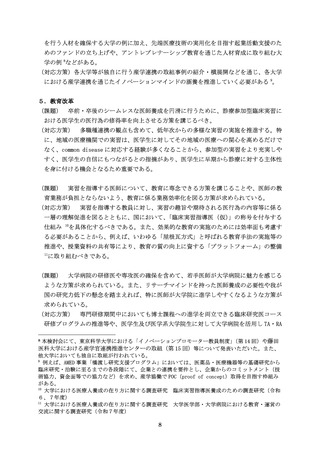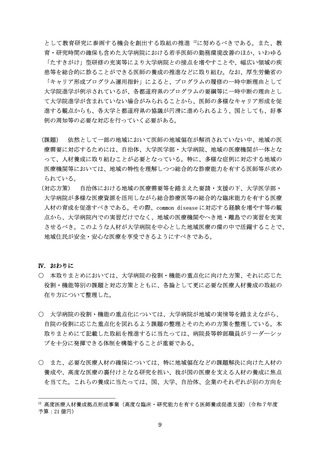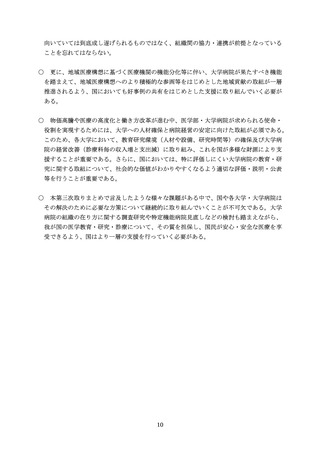よむ、つかう、まなぶ。
今後の医学教育の在り方に関する検討会 第三次取りまとめ (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/124/toushin/mext_00005.html |
| 出典情報 | 今後の医学教育の在り方に関する検討会 第三次取りまとめ(7/14)《文部科学省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
大学病院の状況把握、課題抽出を行うことや、その医育機能に大きな支障が生じないよう
配慮し、人口減少等の影響を中長期的に予測しつつ対応すること等も重要である。
(課題)
急速な少子高齢化の進展等によって、より質が高く効率的な医療提供体制を構築
していく必要がある。そのためには、近年の生成AIの急速な進化・普及等も踏まえつつ、
医療DXを進め、医療情報の共有と利活用を推進することが必要となっている。
(対応方策)
厚生労働省の医療DXの推進に係る制度改正の動きを踏まえ、電子カルテ情
報共有サービスや電子処方箋管理サービス等により、地域の中核的な医療機関である大学
病院が他の医療機関・薬局との間で必要な電子カルテ情報や薬剤情報を含めた医薬情報の
円滑な共有ができるよう支援するべきである。加えて、生成AIによる医療を取り巻く環
境への影響等を見据えたより良い医療提供に向けた検討が必要である。
(課題)
医師の研究時間の確保等のため、診療エフォートを軽減することが必要となって
いる。このため、例えば、特定行為研修を修了した看護師等の医療人材の養成・活用を行
うなど、タスク・シフト/シェアができる環境整備をより一層推進することが求められる。
(対応方策)
タスク・シフト/シェアを含めた勤務環境の改善やそのための医療人材を養
成できる環境整備の取組について、国は大学病院の好事例の横展開等を行いながら推進す
る。また、2026(令和8)年度以降看護師養成課程において適用される「看護学教育モデ
ル・コア・カリキュラム(令和6年度改訂版)」において、特定行為研修の学修内容の基
盤部分が一部含まれ、今後は高度な看護実践の基盤となる専門的かつ幅広い知識を獲得し
た看護師が養成されることが期待されることから、国は特定行為研修の履修を後押しする
とともに、特定行為研修を修了した看護師等の活用促進を含めた大学病院におけるより一
層のタスク・シフト/シェアの環境整備を進める。
3.地域医療への貢献
(課題)
大学病院は、医学部の教育・研究に必要な施設として位置づけられているが、実
際には多くの大学病院において、地域医療の最後の砦として、高度で専門的な診療も担っ
てきた。また地域の医療機関を支援する役割も果たしてきた。今般、厚生労働省の「特定
機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」では、大学病院本院に対し、地
域医療への貢献を含めた自主的な取組を適切に評価することについても議論が行われてい
る。
(対応方策)
このような議論を踏まえ、大学病院が有している機能の実態を把握し実際に
行っている診療や地域医療への貢献について制度上どのように位置づけるべきか検討が必
要である。また、地域医療構想の実現に向けた地域全体での取組への大学病院の積極的な
参画が求められる中、各大学病院においては、地域の実情も踏まえつつ、適切な地域貢献
の在り方について検討し、法人の長・病院長等の病院運営に責任を持つ者の下、その構成
員が組織的かつ主体的に取り組まなければならない。
5
配慮し、人口減少等の影響を中長期的に予測しつつ対応すること等も重要である。
(課題)
急速な少子高齢化の進展等によって、より質が高く効率的な医療提供体制を構築
していく必要がある。そのためには、近年の生成AIの急速な進化・普及等も踏まえつつ、
医療DXを進め、医療情報の共有と利活用を推進することが必要となっている。
(対応方策)
厚生労働省の医療DXの推進に係る制度改正の動きを踏まえ、電子カルテ情
報共有サービスや電子処方箋管理サービス等により、地域の中核的な医療機関である大学
病院が他の医療機関・薬局との間で必要な電子カルテ情報や薬剤情報を含めた医薬情報の
円滑な共有ができるよう支援するべきである。加えて、生成AIによる医療を取り巻く環
境への影響等を見据えたより良い医療提供に向けた検討が必要である。
(課題)
医師の研究時間の確保等のため、診療エフォートを軽減することが必要となって
いる。このため、例えば、特定行為研修を修了した看護師等の医療人材の養成・活用を行
うなど、タスク・シフト/シェアができる環境整備をより一層推進することが求められる。
(対応方策)
タスク・シフト/シェアを含めた勤務環境の改善やそのための医療人材を養
成できる環境整備の取組について、国は大学病院の好事例の横展開等を行いながら推進す
る。また、2026(令和8)年度以降看護師養成課程において適用される「看護学教育モデ
ル・コア・カリキュラム(令和6年度改訂版)」において、特定行為研修の学修内容の基
盤部分が一部含まれ、今後は高度な看護実践の基盤となる専門的かつ幅広い知識を獲得し
た看護師が養成されることが期待されることから、国は特定行為研修の履修を後押しする
とともに、特定行為研修を修了した看護師等の活用促進を含めた大学病院におけるより一
層のタスク・シフト/シェアの環境整備を進める。
3.地域医療への貢献
(課題)
大学病院は、医学部の教育・研究に必要な施設として位置づけられているが、実
際には多くの大学病院において、地域医療の最後の砦として、高度で専門的な診療も担っ
てきた。また地域の医療機関を支援する役割も果たしてきた。今般、厚生労働省の「特定
機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」では、大学病院本院に対し、地
域医療への貢献を含めた自主的な取組を適切に評価することについても議論が行われてい
る。
(対応方策)
このような議論を踏まえ、大学病院が有している機能の実態を把握し実際に
行っている診療や地域医療への貢献について制度上どのように位置づけるべきか検討が必
要である。また、地域医療構想の実現に向けた地域全体での取組への大学病院の積極的な
参画が求められる中、各大学病院においては、地域の実情も踏まえつつ、適切な地域貢献
の在り方について検討し、法人の長・病院長等の病院運営に責任を持つ者の下、その構成
員が組織的かつ主体的に取り組まなければならない。
5