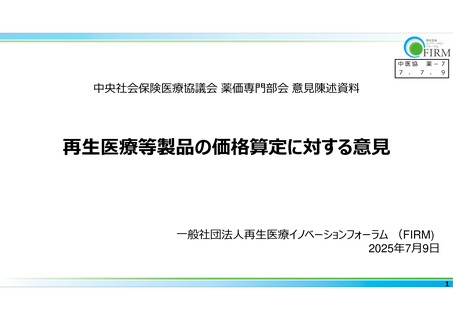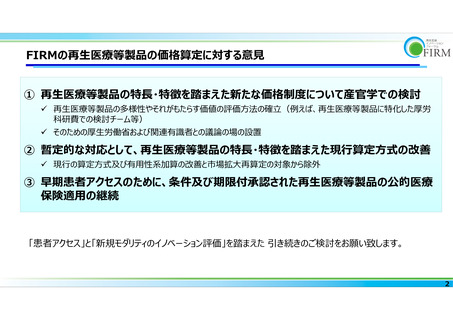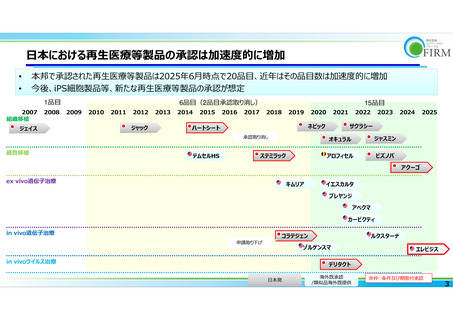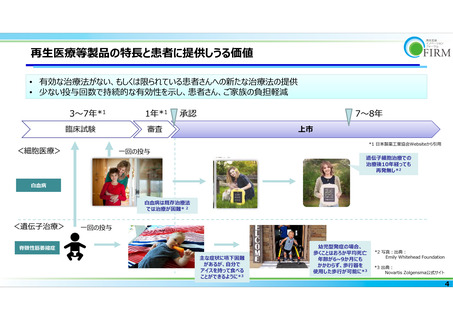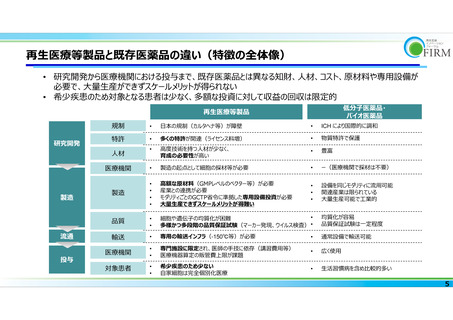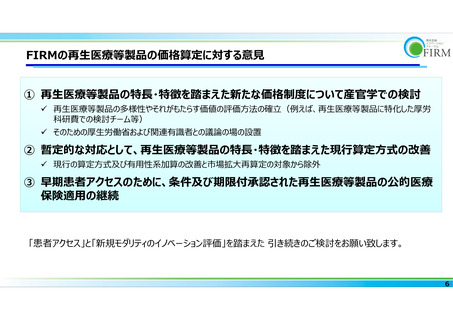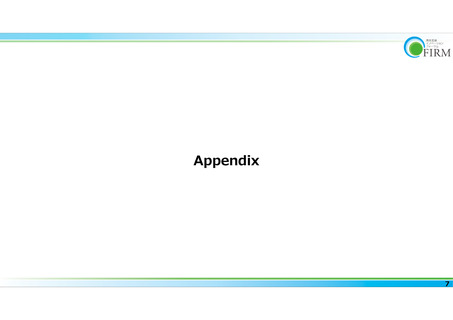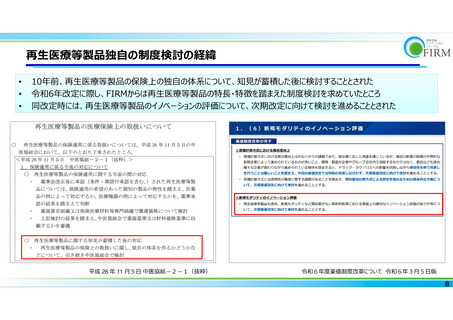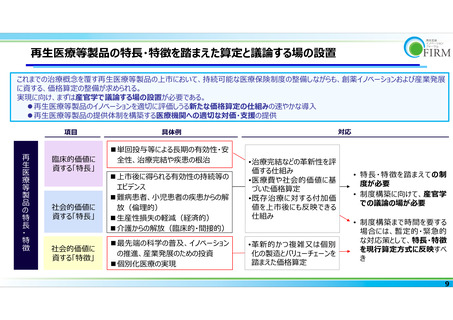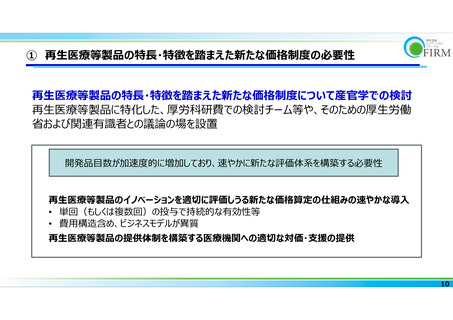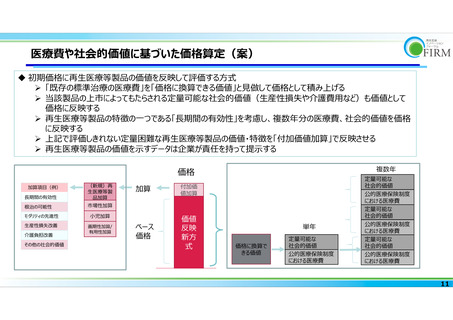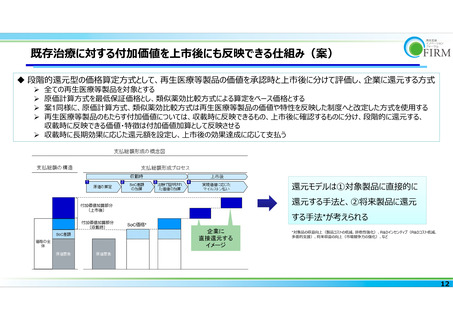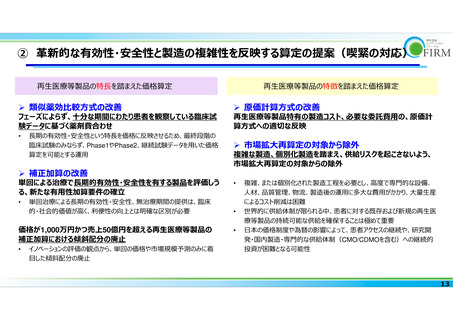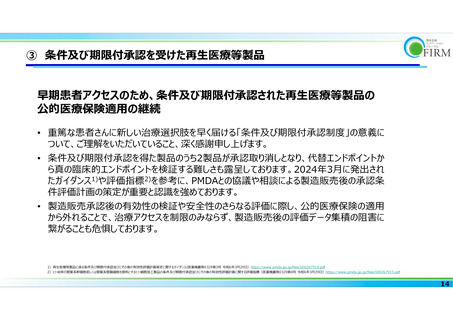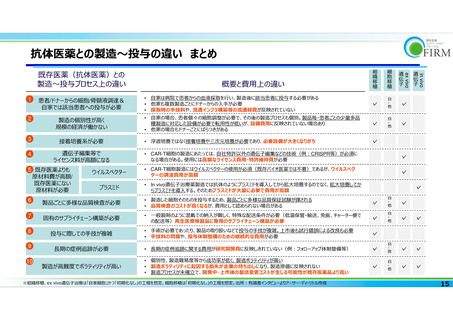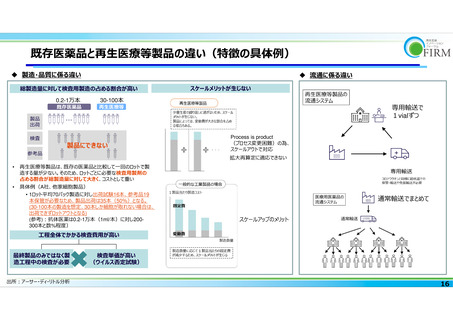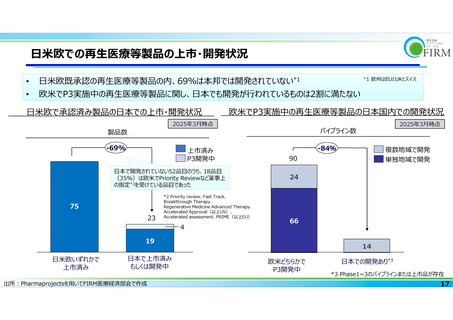よむ、つかう、まなぶ。
薬-7再⽣医療イノベーションフォーラム[1.4MB] (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59378.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第236回 7/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
再⽣医療等製品と既存医薬品の違い(特徴の全体像)
• 研究開発から医療機関における投与まで、既存医薬品とは異なる知財、⼈材、コスト、原材料や専⽤設備が
必要で、⼤量⽣産ができずスケールメリットが得られない
• 希少疾患のため対象となる患者は少なく、多額な投資に対して収益の回収は限定的
低分子医薬品・
バイオ医薬品
再⽣医療等製品
研究開発
製造
流通
投与
規制
•
日本の規制(カルタヘナ等)が障壁
•
ICH により国際的に調和
特許
•
多くの特許が関連(ライセンス料増)
•
物質特許で保護
人材
•
⾼度技術を持つ⼈材が少なく、
育成の必要性が高い
•
豊富
医療機関
•
製造の起点として細胞の採材等が必要
•
ー(医療機関で採材は不要)
製造
•
•
•
•
⾼額な原材料(GMPレベルのベクター等)が必要
産業との連携が必要
モダリティごとのGCTP省令に準拠した専用設備投資が必要
⼤量⽣産できずスケールメリットが得難い
•
•
•
設備を同じモダリティに流⽤可能
関連産業は限られている
⼤量⽣産可能で⼯業的
品質
•
•
•
細胞や遺伝子の均質化が困難
多様かつ多段階の品質保証試験(マーカー発現、ウイルス検査) •
均質化が容易
品質保証試験は⼀定程度
輸送
•
専用の輸送インフラ(-150℃等)が必要
•
通常設備で輸送可能
医療機関
•
•
専門施設に限定され、医師の手技に依存(講習費用等)
医療機器算定の販管費上限が課題
•
広く使用
対象患者
•
•
希少疾患のため少ない
⾃家細胞は完全個別化医療
•
生活習慣病を含め比較的多い
5
• 研究開発から医療機関における投与まで、既存医薬品とは異なる知財、⼈材、コスト、原材料や専⽤設備が
必要で、⼤量⽣産ができずスケールメリットが得られない
• 希少疾患のため対象となる患者は少なく、多額な投資に対して収益の回収は限定的
低分子医薬品・
バイオ医薬品
再⽣医療等製品
研究開発
製造
流通
投与
規制
•
日本の規制(カルタヘナ等)が障壁
•
ICH により国際的に調和
特許
•
多くの特許が関連(ライセンス料増)
•
物質特許で保護
人材
•
⾼度技術を持つ⼈材が少なく、
育成の必要性が高い
•
豊富
医療機関
•
製造の起点として細胞の採材等が必要
•
ー(医療機関で採材は不要)
製造
•
•
•
•
⾼額な原材料(GMPレベルのベクター等)が必要
産業との連携が必要
モダリティごとのGCTP省令に準拠した専用設備投資が必要
⼤量⽣産できずスケールメリットが得難い
•
•
•
設備を同じモダリティに流⽤可能
関連産業は限られている
⼤量⽣産可能で⼯業的
品質
•
•
•
細胞や遺伝子の均質化が困難
多様かつ多段階の品質保証試験(マーカー発現、ウイルス検査) •
均質化が容易
品質保証試験は⼀定程度
輸送
•
専用の輸送インフラ(-150℃等)が必要
•
通常設備で輸送可能
医療機関
•
•
専門施設に限定され、医師の手技に依存(講習費用等)
医療機器算定の販管費上限が課題
•
広く使用
対象患者
•
•
希少疾患のため少ない
⾃家細胞は完全個別化医療
•
生活習慣病を含め比較的多い
5