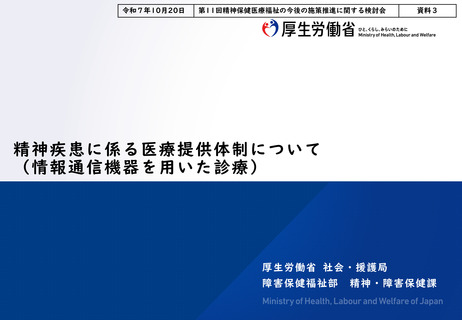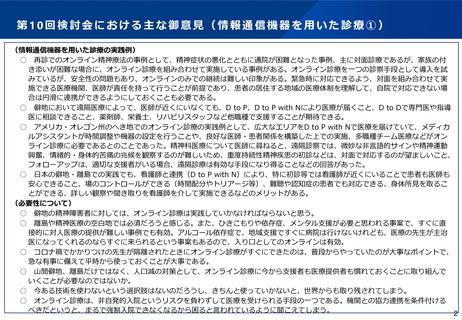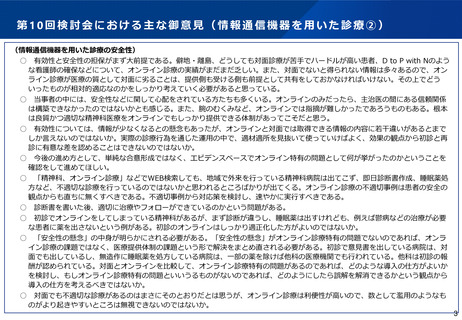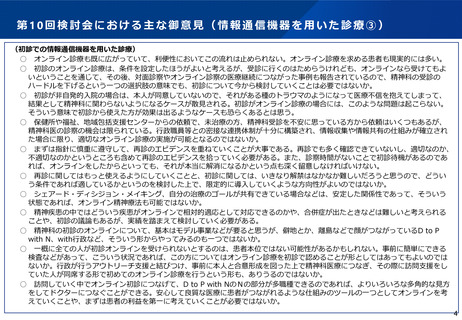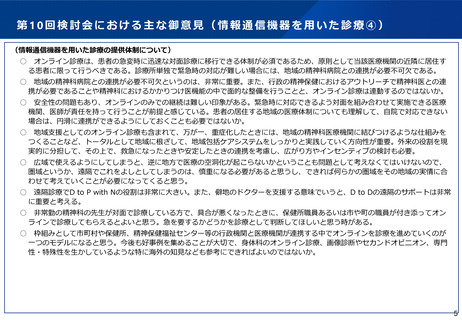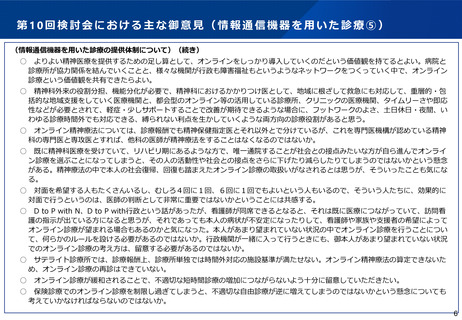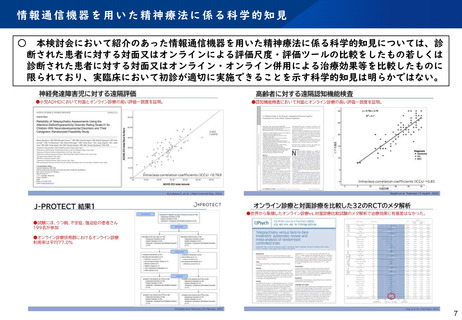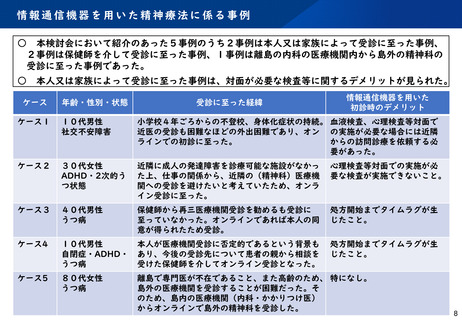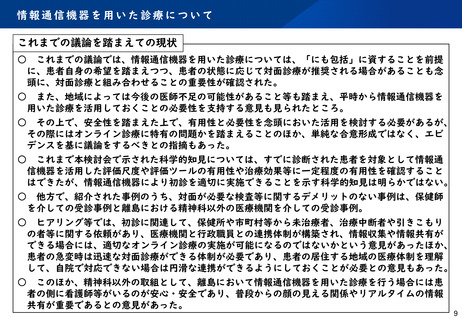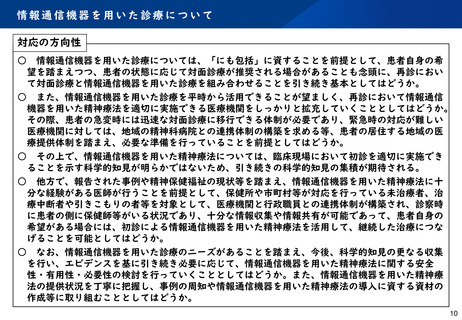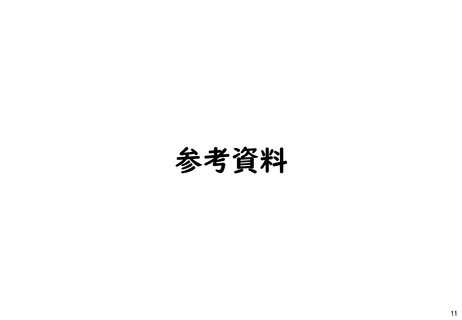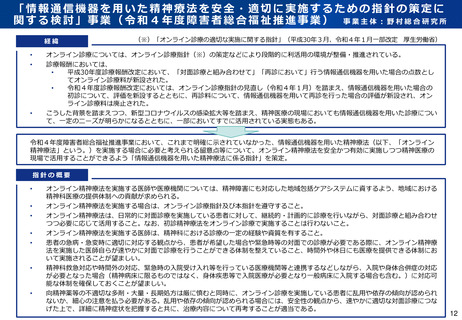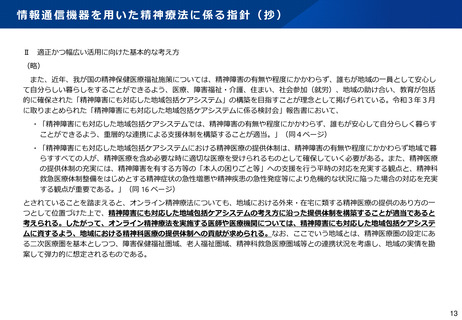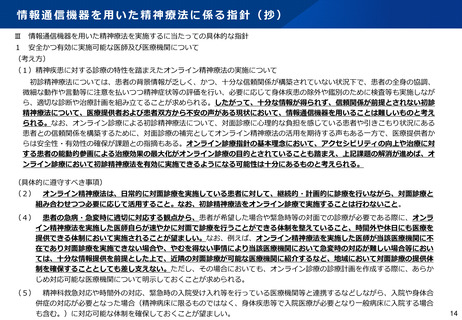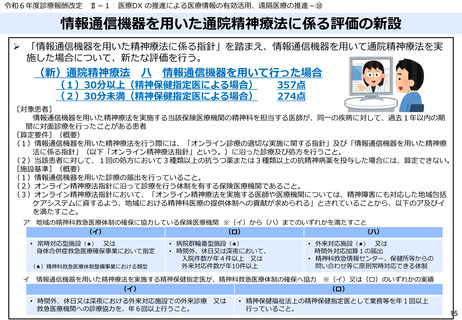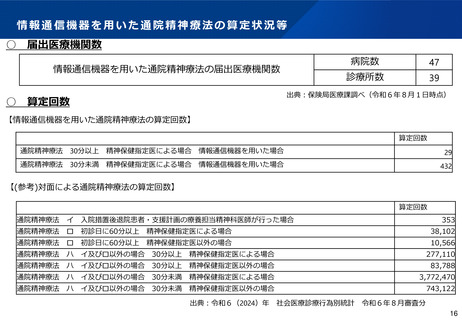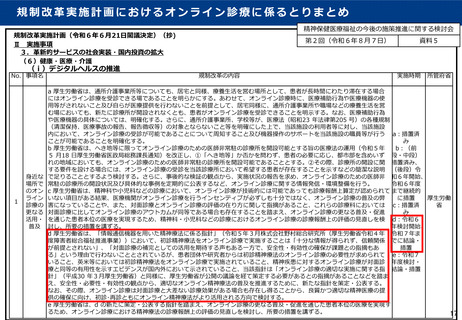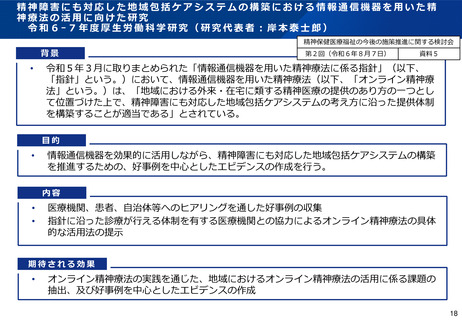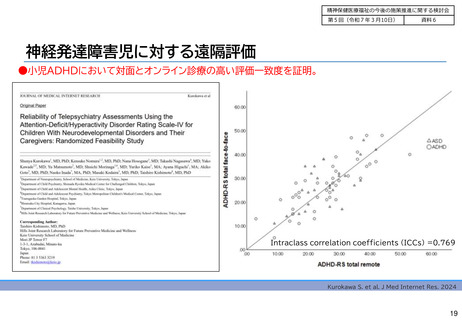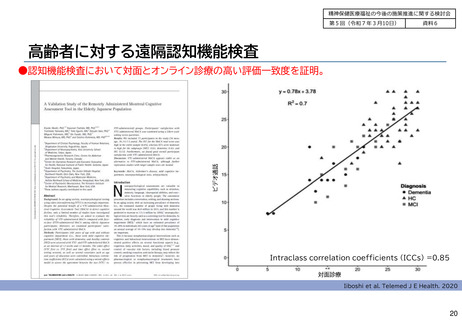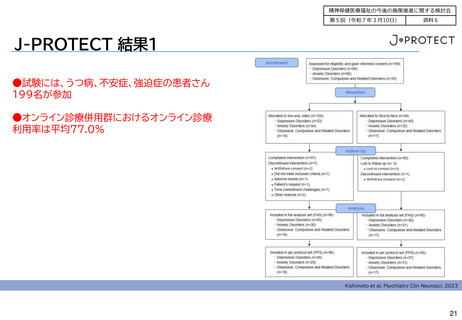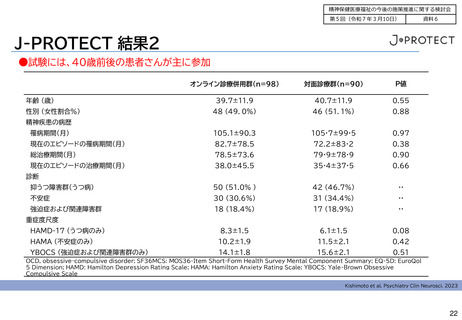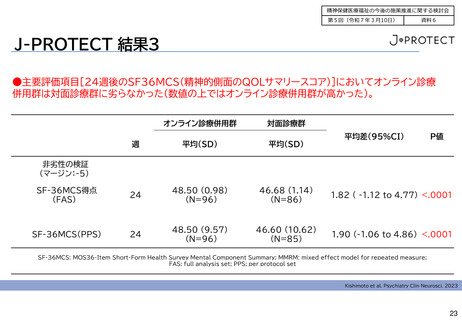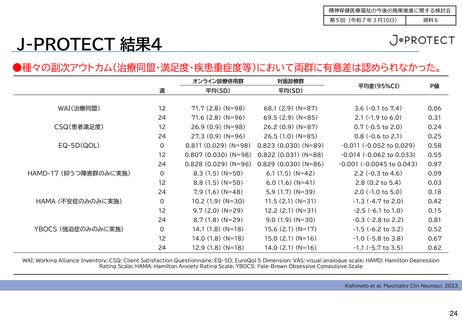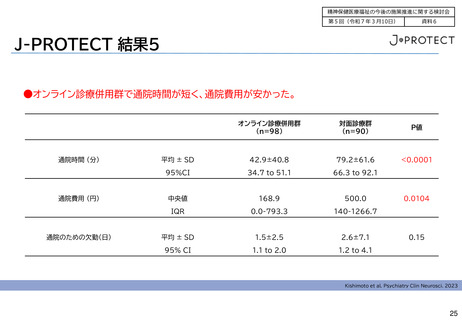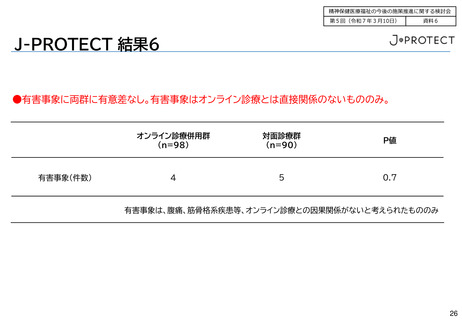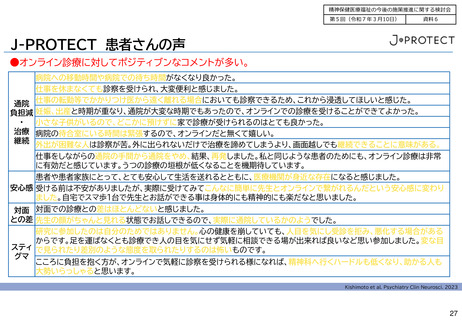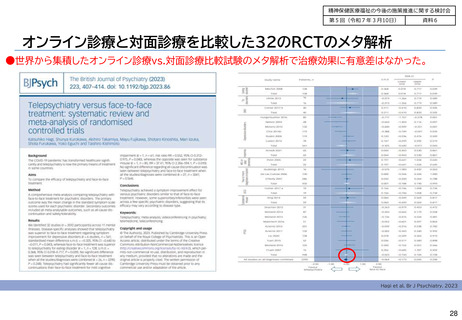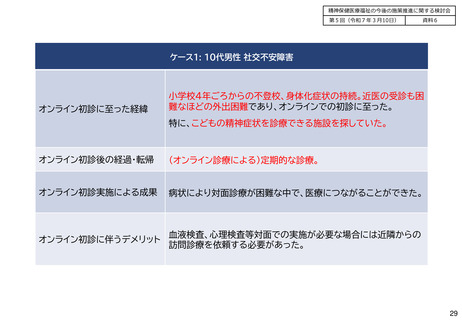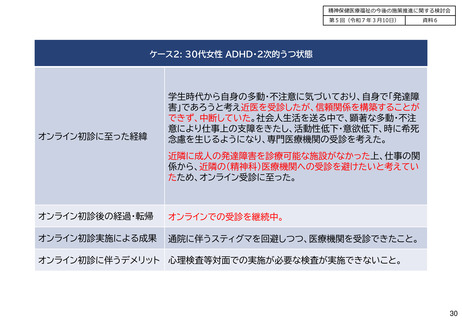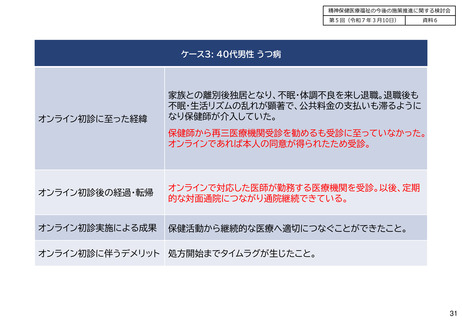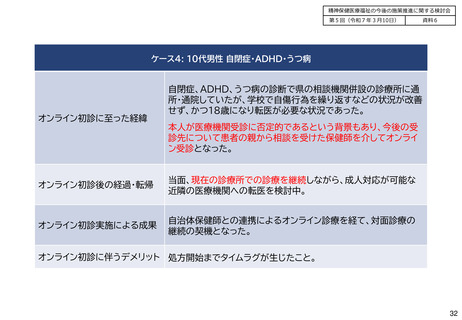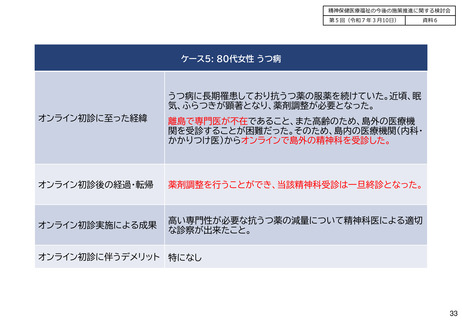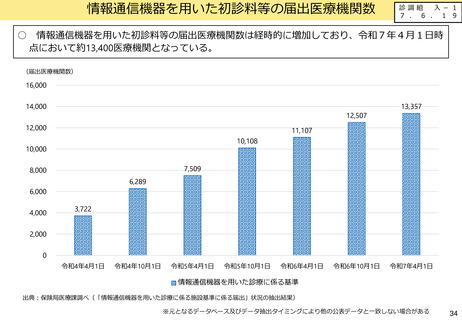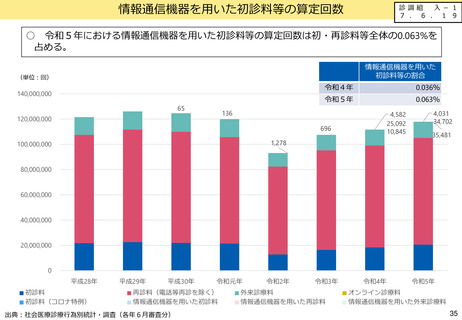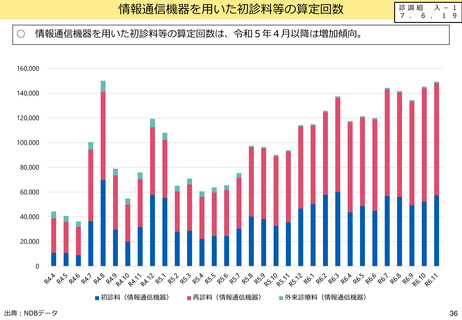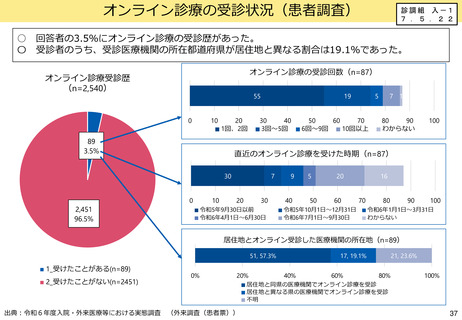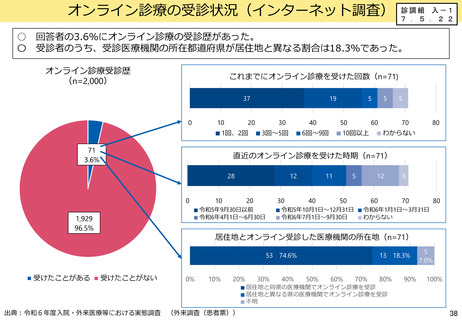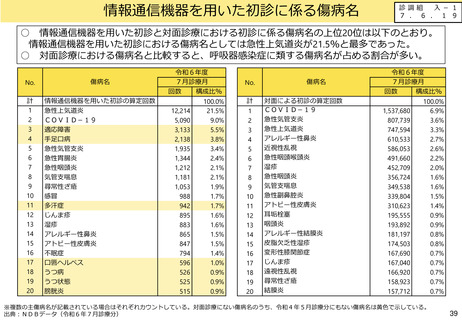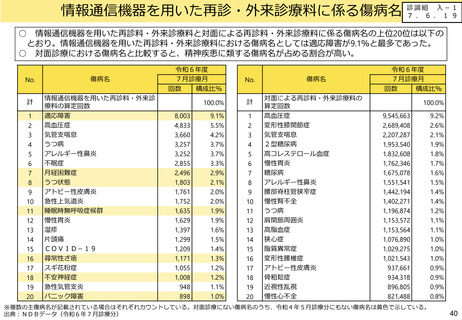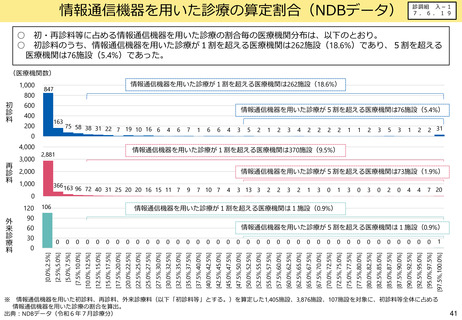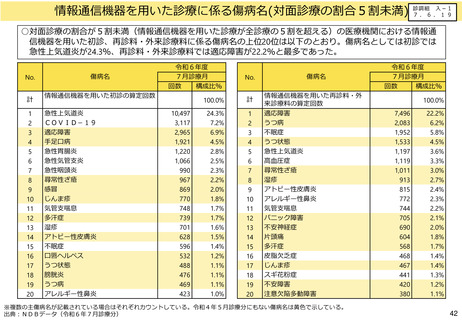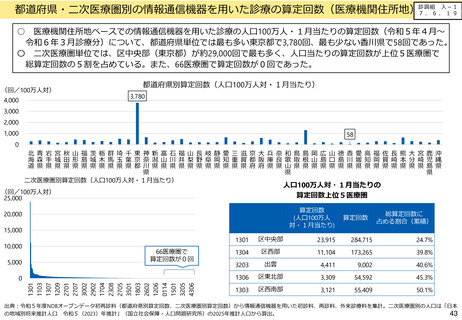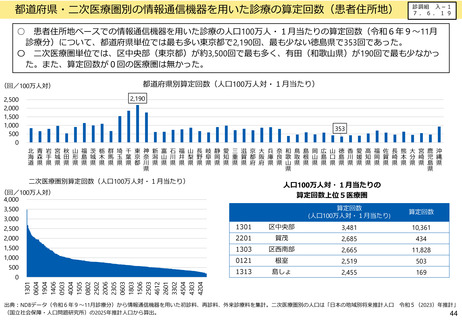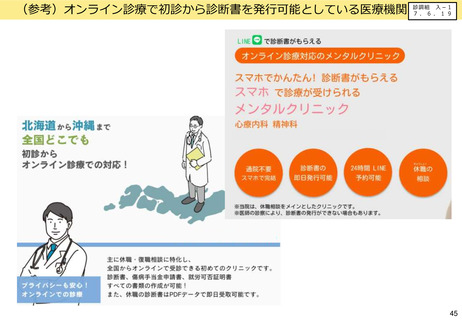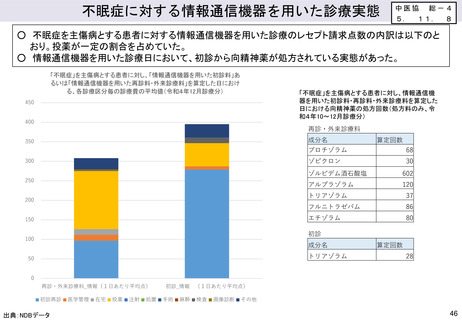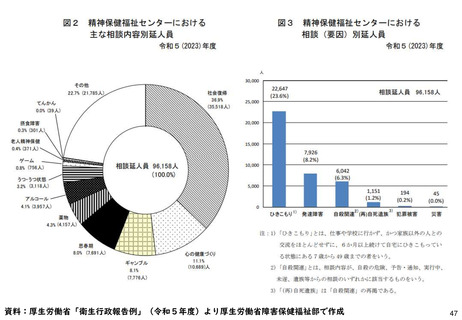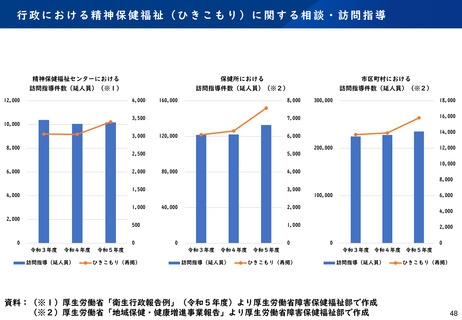よむ、つかう、まなぶ。
【資料3】精神疾患に係る医療体制について(情報通信機器を用いた診療) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64896.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第11回 10/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第10回検討会における主な御意見(情報通信機器を用いた診療⑤)
(情報通信機器を用いた診療の提供体制について)(続き)
○
よりよい精神医療を提供するための足し算として、オンラインをしっかり導入していくのだという価値観を持てるとよい。病院と
診療所が協力関係を結んでいくことと、様々な機関が行政も障害福祉もというようなネットワークをつくっていく中で、オンライン
診療という価値観を共有できたらよい。
○
精神科外来の役割分担、機能分化が必要で、精神科におけるかかりつけ医として、地域に根ざして救急にも対応して、重層的・包
括的な地域支援をしていく医療機関と、都会型のオンライン等の活用している診療所、クリニックの医療機関、タイムリーさや即応
性などが必要とされて、軽症・少しサポートすることで改善が期待できるような場合に、フットワークのよさ、土日休日・夜間、い
わゆる診療時間外でも対応できる、縛られない利点を生かしていくような両方向の診療役割があると思う。
○
オンライン精神療法については、診療報酬でも精神保健指定医とそれ以外とで分けているが、これを専門医機構が認めている精神
科の専門医と専攻医とすれば、他科の医師が精神療法をすることはなくなるのではないか。
○
既に精神科医療を受けていて、リハビリ期にあるような方で、唯一通院することが社会との接点みたいな方が自ら進んでオンライ
ン診療を選ぶことになってしまうと、その人の活動性や社会との接点をさらに下げたり減らしたりてしまうのではないかという懸念
がある。精神療法の中で本人の社会復帰、回復も踏まえたオンライン診療の取扱いがなされるとは思うが、そういったことも気にな
る。
○
対面を希望する人もたくさんいるし、むしろ4回に1回、6回に1回でもよいという人もいるので、そういう人たちに、効果的に
対面で行うというのは、医師の判断として非常に重要ではないかということには共感する。
○
D to P with N、D to P with行政という話があったが、看護師が同席できるとなると、それは既に医療につながっていて、訪問看
護の指示が出ている方になると思うが、それであっても本人の病状が不安定になったりして、看護師や家族や支援者の希望によって
オンライン診療が望まれる場合もあるのかと気になった。本人があまり望まれていない状況の中でオンライン診療を行うことについ
て、何らかのルールを設ける必要があるのではないか。行政機関が一緒に入って行うときにも、御本人があまり望まれていない状況
でのオンライン診療の考え方は、留意する必要があるのではないか。
○
サテライト診療所では、診療報酬上、診療所単独では時間外対応の施設基準が満たせない。オンライン精神療法の算定できないた
め、オンライン診療の再診はできていない。
○
○
オンライン診療が緩和されることで、不適切な短時間診療の増加につながらないよう十分に留意していただきたい。
保険診療でのオンライン診療を制限し過ぎてしまうと、不適切な自由診療が逆に増えてしまうのではないかという懸念についても
考えていかなければならないのではないか。
6
(情報通信機器を用いた診療の提供体制について)(続き)
○
よりよい精神医療を提供するための足し算として、オンラインをしっかり導入していくのだという価値観を持てるとよい。病院と
診療所が協力関係を結んでいくことと、様々な機関が行政も障害福祉もというようなネットワークをつくっていく中で、オンライン
診療という価値観を共有できたらよい。
○
精神科外来の役割分担、機能分化が必要で、精神科におけるかかりつけ医として、地域に根ざして救急にも対応して、重層的・包
括的な地域支援をしていく医療機関と、都会型のオンライン等の活用している診療所、クリニックの医療機関、タイムリーさや即応
性などが必要とされて、軽症・少しサポートすることで改善が期待できるような場合に、フットワークのよさ、土日休日・夜間、い
わゆる診療時間外でも対応できる、縛られない利点を生かしていくような両方向の診療役割があると思う。
○
オンライン精神療法については、診療報酬でも精神保健指定医とそれ以外とで分けているが、これを専門医機構が認めている精神
科の専門医と専攻医とすれば、他科の医師が精神療法をすることはなくなるのではないか。
○
既に精神科医療を受けていて、リハビリ期にあるような方で、唯一通院することが社会との接点みたいな方が自ら進んでオンライ
ン診療を選ぶことになってしまうと、その人の活動性や社会との接点をさらに下げたり減らしたりてしまうのではないかという懸念
がある。精神療法の中で本人の社会復帰、回復も踏まえたオンライン診療の取扱いがなされるとは思うが、そういったことも気にな
る。
○
対面を希望する人もたくさんいるし、むしろ4回に1回、6回に1回でもよいという人もいるので、そういう人たちに、効果的に
対面で行うというのは、医師の判断として非常に重要ではないかということには共感する。
○
D to P with N、D to P with行政という話があったが、看護師が同席できるとなると、それは既に医療につながっていて、訪問看
護の指示が出ている方になると思うが、それであっても本人の病状が不安定になったりして、看護師や家族や支援者の希望によって
オンライン診療が望まれる場合もあるのかと気になった。本人があまり望まれていない状況の中でオンライン診療を行うことについ
て、何らかのルールを設ける必要があるのではないか。行政機関が一緒に入って行うときにも、御本人があまり望まれていない状況
でのオンライン診療の考え方は、留意する必要があるのではないか。
○
サテライト診療所では、診療報酬上、診療所単独では時間外対応の施設基準が満たせない。オンライン精神療法の算定できないた
め、オンライン診療の再診はできていない。
○
○
オンライン診療が緩和されることで、不適切な短時間診療の増加につながらないよう十分に留意していただきたい。
保険診療でのオンライン診療を制限し過ぎてしまうと、不適切な自由診療が逆に増えてしまうのではないかという懸念についても
考えていかなければならないのではないか。
6