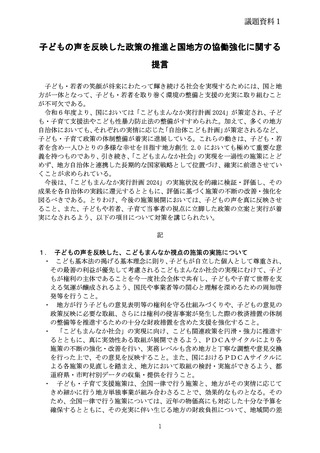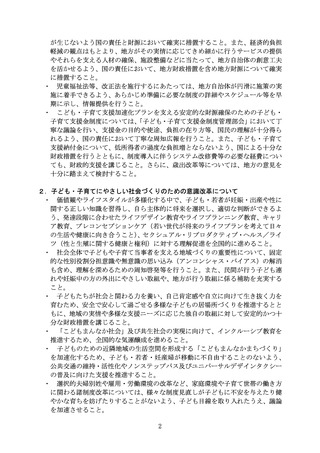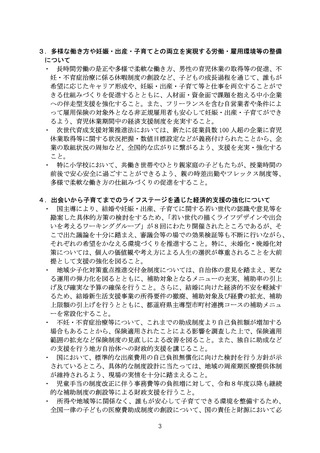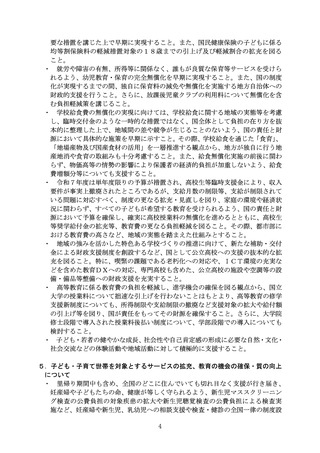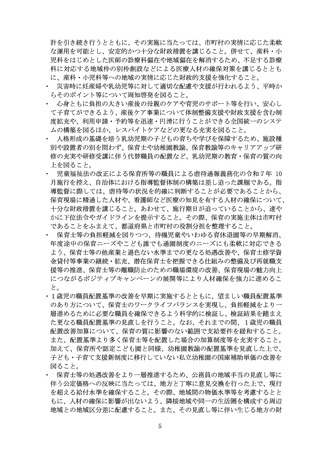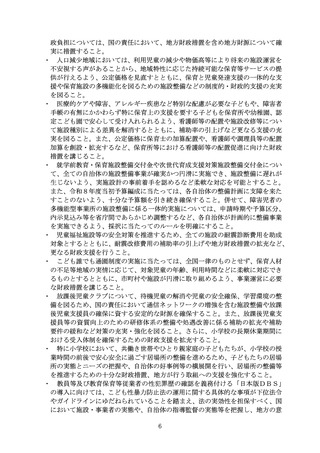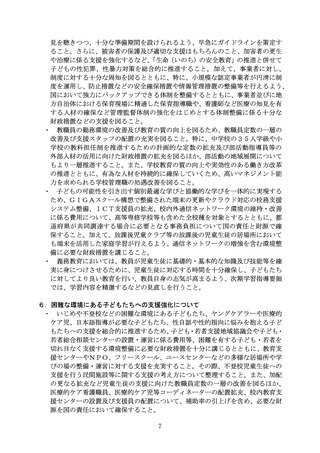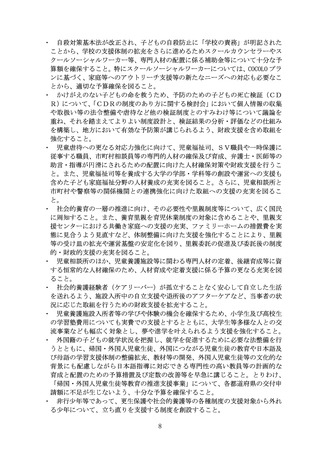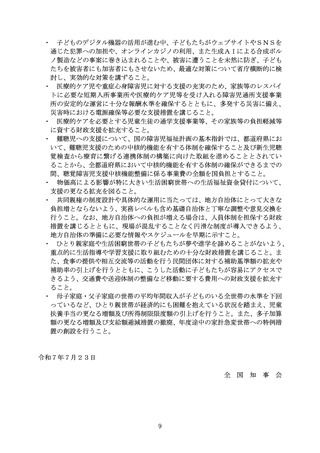よむ、つかう、まなぶ。
【議題(1)資料1】子どもの声を反映した政策の推進と国地方の協働強化に関する提言 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |
| 出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
計を引き続き行うとともに、その実施に当たっては、市町村の実情に応じた柔軟
な運用を可能とし、安定的かつ十分な財政措置を講じること。併せて、産科・小
児科をはじめとした医師の診療科偏在や地域偏在を解消するため、不足する診療
科に対応する地域枠の別枠創設などによる医療人材の確保対策を講じるととも
に、産科・小児科等への地域の実情に応じた財政的支援を強化すること。
・ 災害時に妊産婦や乳幼児等に対して適切な配慮や支援が行われるよう、平時か
らそのポイント等について周知啓発を図ること。
・ 心身ともに負担の大きい産後の母親のケアや育児のサポート等を行い、安心し
て子育てができるよう、産後ケア事業について体制整備支援や財政支援を含む制
度拡充や、利用申請・予約等を迅速・円滑に行うことができる全国統一のシステ
ムの構築を図るほか、レスパイトケアなどの更なる充実を図ること。
・ 人格形成の基礎を培う乳幼児期の子どもの育ちや学びを保障するため、施設種
別や設置者の別を問わず、保育士や幼稚園教諭、保育教諭等のキャリアアップ研
修の充実や研修受講に伴う代替職員の配置など、乳幼児期の教育・保育の質の向
上を図ること。
・ 児童福祉法の改正による保育所等の職員による虐待通報義務化の令和7年 10
月施行を控え、自治体における指導監督体制の構築は差し迫った課題である。指
導監督に際しては、虐待等の状況を的確に判断することが必要であることから、
保育現場に精通した人材や、看護師など医療の知見を有する人材の確保について、
十分な財政措置を講じること。あわせて、施行期日が迫っていることから、速や
かに下位法令やガイドラインを提示すること。その際、保育の実施主体は市町村
であることをふまえて、都道府県と市町村の役割分担を整理すること。
・ 保育士等の負担軽減を図りつつ、待機児童やいわゆる育休退園等の早期解消、
年度途中の保育ニーズやこども誰でも通園制度のニーズにも柔軟に対応できる
よう、保育士等の他産業と遜色ない水準までの更なる処遇改善や、保育士修学資
金貸付等事業の継続・拡充、潜在保育士を把握できる仕組みの整備及び再就職支
援等の推進、保育士等の離職防止のための職場環境の改善、保育現場の魅力向上
につながるポジティブキャンペーンの展開等により人材確保を強力に進めるこ
と。
・1歳児の職員配置基準の改善を早期に実施するとともに、望ましい職員配置基準
のあり方について、保育士のワークライフバランスを実現し、負担軽減をより一
層進めるために必要な職員を確保できるよう科学的に検証し、検証結果を踏まえ
た更なる職員配置基準の見直しを行うこと。なお、それまでの間、1歳児の職員
配置改善加算について、保育の質に影響のない範囲で支給要件を緩和すること。
また、配置基準より多く保育士等を配置した場合の加算制度等を充実すること。
加えて、保育所や認定こども園と同様、幼稚園教諭の配置基準を見直した上で、
子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園の国庫補助単価の改善を
図ること。
・ 保育士等の処遇改善をより一層推進するため、公務員の地域手当の見直し等に
伴う公定価格への反映に当たっては、地方と丁寧に意見交換を行った上で、現行
を超える給付水準を確保すること。その際、地域間の物価水準等を考慮するとと
もに、人材の確保に影響が出ないよう、隣接地域や同一の生活圏を構成する周辺
地域との地域区分差に配慮すること。また、その見直し等に伴い生じる地方の財
5
な運用を可能とし、安定的かつ十分な財政措置を講じること。併せて、産科・小
児科をはじめとした医師の診療科偏在や地域偏在を解消するため、不足する診療
科に対応する地域枠の別枠創設などによる医療人材の確保対策を講じるととも
に、産科・小児科等への地域の実情に応じた財政的支援を強化すること。
・ 災害時に妊産婦や乳幼児等に対して適切な配慮や支援が行われるよう、平時か
らそのポイント等について周知啓発を図ること。
・ 心身ともに負担の大きい産後の母親のケアや育児のサポート等を行い、安心し
て子育てができるよう、産後ケア事業について体制整備支援や財政支援を含む制
度拡充や、利用申請・予約等を迅速・円滑に行うことができる全国統一のシステ
ムの構築を図るほか、レスパイトケアなどの更なる充実を図ること。
・ 人格形成の基礎を培う乳幼児期の子どもの育ちや学びを保障するため、施設種
別や設置者の別を問わず、保育士や幼稚園教諭、保育教諭等のキャリアアップ研
修の充実や研修受講に伴う代替職員の配置など、乳幼児期の教育・保育の質の向
上を図ること。
・ 児童福祉法の改正による保育所等の職員による虐待通報義務化の令和7年 10
月施行を控え、自治体における指導監督体制の構築は差し迫った課題である。指
導監督に際しては、虐待等の状況を的確に判断することが必要であることから、
保育現場に精通した人材や、看護師など医療の知見を有する人材の確保について、
十分な財政措置を講じること。あわせて、施行期日が迫っていることから、速や
かに下位法令やガイドラインを提示すること。その際、保育の実施主体は市町村
であることをふまえて、都道府県と市町村の役割分担を整理すること。
・ 保育士等の負担軽減を図りつつ、待機児童やいわゆる育休退園等の早期解消、
年度途中の保育ニーズやこども誰でも通園制度のニーズにも柔軟に対応できる
よう、保育士等の他産業と遜色ない水準までの更なる処遇改善や、保育士修学資
金貸付等事業の継続・拡充、潜在保育士を把握できる仕組みの整備及び再就職支
援等の推進、保育士等の離職防止のための職場環境の改善、保育現場の魅力向上
につながるポジティブキャンペーンの展開等により人材確保を強力に進めるこ
と。
・1歳児の職員配置基準の改善を早期に実施するとともに、望ましい職員配置基準
のあり方について、保育士のワークライフバランスを実現し、負担軽減をより一
層進めるために必要な職員を確保できるよう科学的に検証し、検証結果を踏まえ
た更なる職員配置基準の見直しを行うこと。なお、それまでの間、1歳児の職員
配置改善加算について、保育の質に影響のない範囲で支給要件を緩和すること。
また、配置基準より多く保育士等を配置した場合の加算制度等を充実すること。
加えて、保育所や認定こども園と同様、幼稚園教諭の配置基準を見直した上で、
子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園の国庫補助単価の改善を
図ること。
・ 保育士等の処遇改善をより一層推進するため、公務員の地域手当の見直し等に
伴う公定価格への反映に当たっては、地方と丁寧に意見交換を行った上で、現行
を超える給付水準を確保すること。その際、地域間の物価水準等を考慮するとと
もに、人材の確保に影響が出ないよう、隣接地域や同一の生活圏を構成する周辺
地域との地域区分差に配慮すること。また、その見直し等に伴い生じる地方の財
5