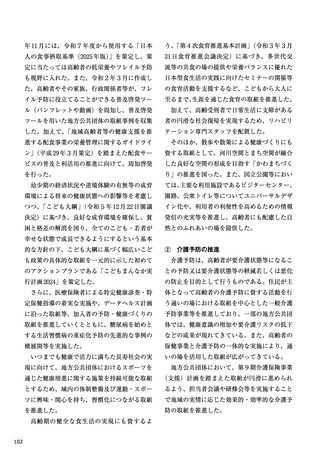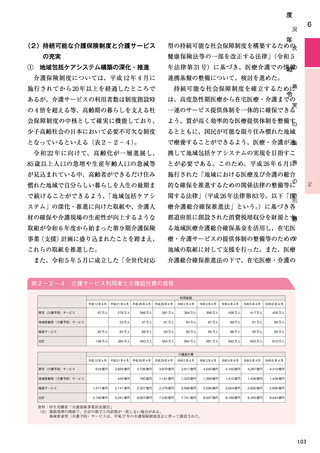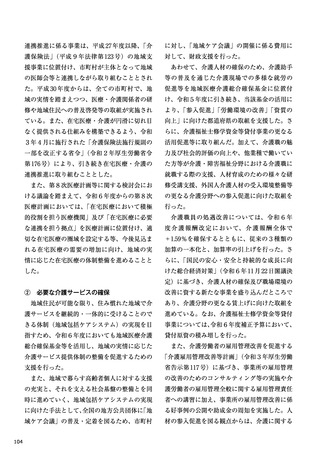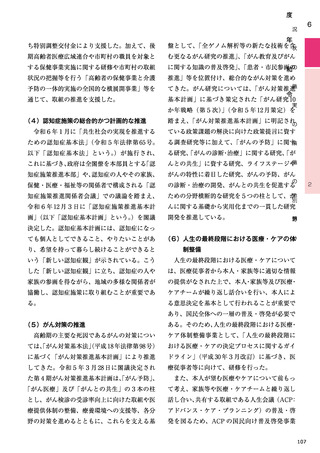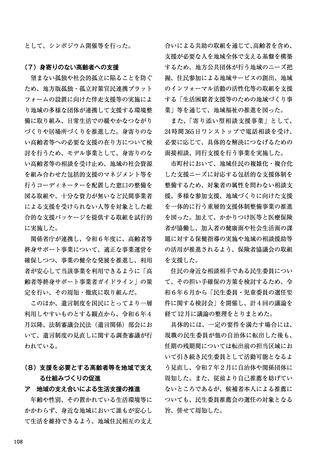よむ、つかう、まなぶ。
2 健康・福祉 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html |
| 出典情報 | 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
に併せて必要な資金の貸付けを行う不動産担保
の 70 歳未満への引上げ、iDeCo の拠出限度額
型生活資金の貸与制度を実施した。
第2章
下「iDeCo」という。
)の加入可能年齢の上限
金・個人年金部会において議論をとりまとめた。
さらに iDeCo について、更なる普及を図るた
2
健康・福祉
め、各種広報媒体を活用した周知・広報を行っ
(1)健康づくりの総合的推進
た(加入者数は、令和7年3月末時点で 363.1
①
生涯にわたる健康づくりの推進
万人)
。退職金制度については、中小企業にお
健康寿命の延伸や生活の質の向上を実現し、
ける退職金制度の導入を支援するため、中小企
健やかで活力ある社会を築くため、平成 12 年
業退職金共済制度の普及促進のための周知等を
度から、生活習慣病の一次予防に重点を置いた
実施した。
「21 世紀における国民健康づくり運動(健康日
本 21)」を開始した。健康日本 21 については、
税制度(以下「NISA」という。)が開始された
平成 25 年度から「21 世紀における第二次国民
ところ、NISA の更なる利便性向上等に向け、
健康づくり運動(健康日本 21(第二次))
」
(以
「令和7年度税制改正の大綱」(令和6年 12 月
下「健康日本 21(第二次)
」という。
)となる
27 日閣議決定)において、金融機関変更時の
運動が開始され、さらに令和6年度からは、健
即日買付を可能とすることや、つみたて投資枠
康日本 21(第二次)の最終評価の結果等も踏
で投資可能な ETF(上場投資信託)に係る要
まえ、
「21 世紀における第三次国民健康づくり
件の見直しなどの措置が講じられることとさ
運動(健康日本 21(第三次))」(以下「健康日
れ、関係法令の整備等を行った。また、NISA
本 21(第三次)
」という。
)を開始し、全ての
の普及の観点から、分かりやすさを追求したガ
国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な
イドブック等の活用や、新しい NISA を含む
社会の実現に向け取り組んでいる。また、
企業、
安定的な資産形成を目的としたイベント・セミ
団体、地方公共団体等と連携し、健康づくりに
ナーの開催等により、適切な周知・広報を行い、
ついて取組の普及啓発を推進する「スマート・
NISA 口座数及び買付額を増加させ、NISA の
ライフ・プロジェクト」を引き続き実施した。
利用の促進を図った。
さらに、健康な高齢期を送るためには、壮年
期からの総合的な健康づくりが重要であるた
イ
資産の有効活用のための環境整備
め、市町村が「健康増進法」(平成 14 年法律第
独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅
103 号)に基づき実施している健康教育、健康
金融支援機構」という。)において、高齢者が
診査、機能訓練、訪問指導等の健康増進事業に
住み替え等のための住生活関連資金を確保する
ついて一層の推進を図った。
ために、リバースモーゲージ型住宅ローンの普
このほか、国民が生涯にわたり健全な食生活
及を促進した。また、低所得の高齢者世帯が安
を営むことができるよう、国民の健康の維持・
定した生活を送れるようにするため、各都道府
増進、生活習慣病の発症及び重症化予防を目的
県社会福祉協議会において、一定の居住用不動
として、「日本人の食事摂取基準」を 2005 年版
産を担保として、世帯の自立に向けた相談支援
の策定以降、5年ごとに改定している。令和6
101
第2節 分野別の施策の実施の状況
また、令和6年1月から新しい少額投資非課
令和6年度高齢社会対策の実施の状況
の引上げ等について、社会保障審議会企業年
の 70 歳未満への引上げ、iDeCo の拠出限度額
型生活資金の貸与制度を実施した。
第2章
下「iDeCo」という。
)の加入可能年齢の上限
金・個人年金部会において議論をとりまとめた。
さらに iDeCo について、更なる普及を図るた
2
健康・福祉
め、各種広報媒体を活用した周知・広報を行っ
(1)健康づくりの総合的推進
た(加入者数は、令和7年3月末時点で 363.1
①
生涯にわたる健康づくりの推進
万人)
。退職金制度については、中小企業にお
健康寿命の延伸や生活の質の向上を実現し、
ける退職金制度の導入を支援するため、中小企
健やかで活力ある社会を築くため、平成 12 年
業退職金共済制度の普及促進のための周知等を
度から、生活習慣病の一次予防に重点を置いた
実施した。
「21 世紀における国民健康づくり運動(健康日
本 21)」を開始した。健康日本 21 については、
税制度(以下「NISA」という。)が開始された
平成 25 年度から「21 世紀における第二次国民
ところ、NISA の更なる利便性向上等に向け、
健康づくり運動(健康日本 21(第二次))
」
(以
「令和7年度税制改正の大綱」(令和6年 12 月
下「健康日本 21(第二次)
」という。
)となる
27 日閣議決定)において、金融機関変更時の
運動が開始され、さらに令和6年度からは、健
即日買付を可能とすることや、つみたて投資枠
康日本 21(第二次)の最終評価の結果等も踏
で投資可能な ETF(上場投資信託)に係る要
まえ、
「21 世紀における第三次国民健康づくり
件の見直しなどの措置が講じられることとさ
運動(健康日本 21(第三次))」(以下「健康日
れ、関係法令の整備等を行った。また、NISA
本 21(第三次)
」という。
)を開始し、全ての
の普及の観点から、分かりやすさを追求したガ
国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な
イドブック等の活用や、新しい NISA を含む
社会の実現に向け取り組んでいる。また、
企業、
安定的な資産形成を目的としたイベント・セミ
団体、地方公共団体等と連携し、健康づくりに
ナーの開催等により、適切な周知・広報を行い、
ついて取組の普及啓発を推進する「スマート・
NISA 口座数及び買付額を増加させ、NISA の
ライフ・プロジェクト」を引き続き実施した。
利用の促進を図った。
さらに、健康な高齢期を送るためには、壮年
期からの総合的な健康づくりが重要であるた
イ
資産の有効活用のための環境整備
め、市町村が「健康増進法」(平成 14 年法律第
独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅
103 号)に基づき実施している健康教育、健康
金融支援機構」という。)において、高齢者が
診査、機能訓練、訪問指導等の健康増進事業に
住み替え等のための住生活関連資金を確保する
ついて一層の推進を図った。
ために、リバースモーゲージ型住宅ローンの普
このほか、国民が生涯にわたり健全な食生活
及を促進した。また、低所得の高齢者世帯が安
を営むことができるよう、国民の健康の維持・
定した生活を送れるようにするため、各都道府
増進、生活習慣病の発症及び重症化予防を目的
県社会福祉協議会において、一定の居住用不動
として、「日本人の食事摂取基準」を 2005 年版
産を担保として、世帯の自立に向けた相談支援
の策定以降、5年ごとに改定している。令和6
101
第2節 分野別の施策の実施の状況
また、令和6年1月から新しい少額投資非課
令和6年度高齢社会対策の実施の状況
の引上げ等について、社会保障審議会企業年