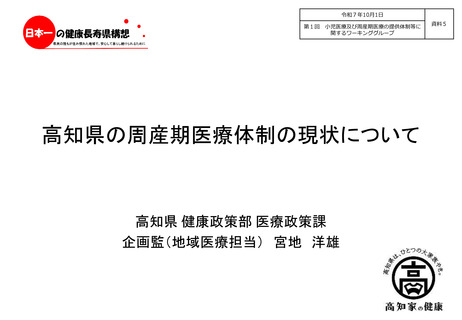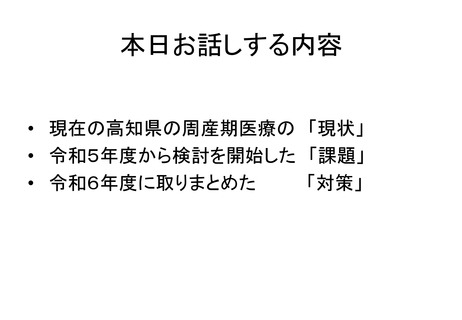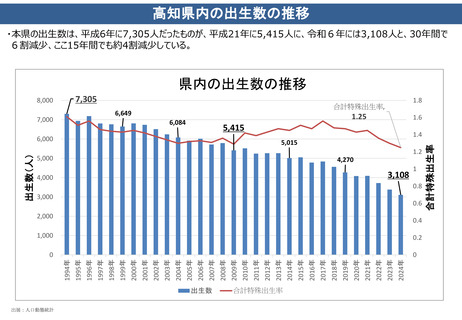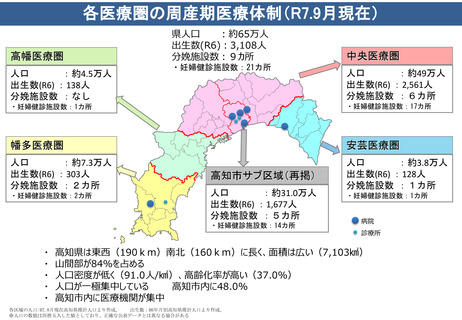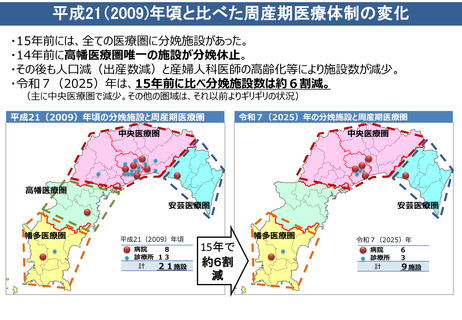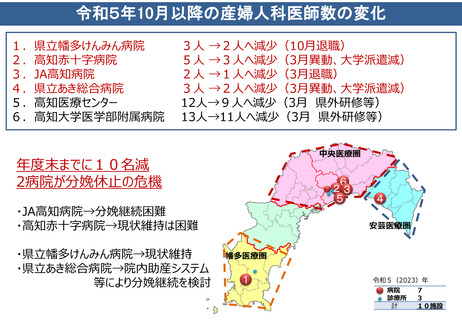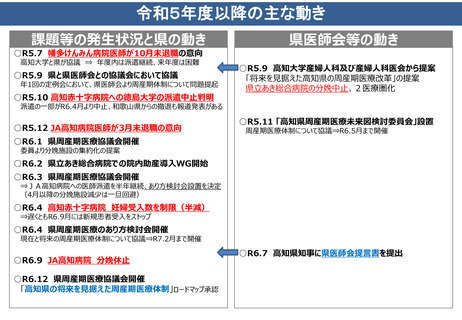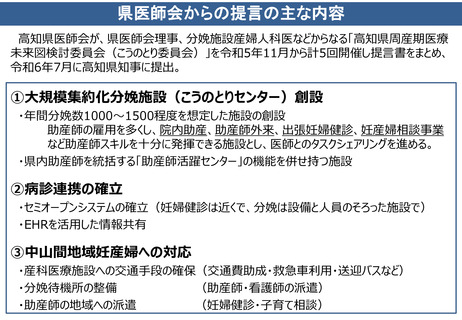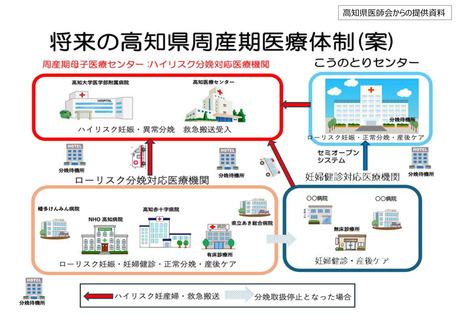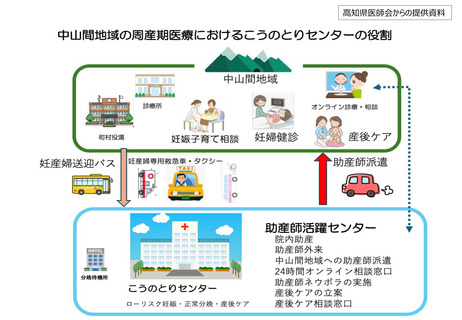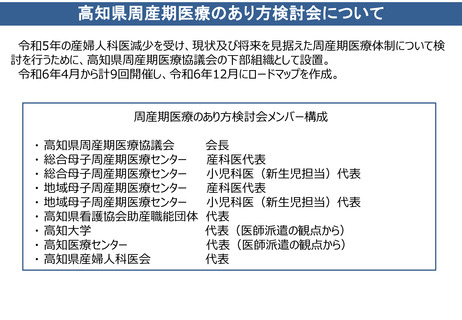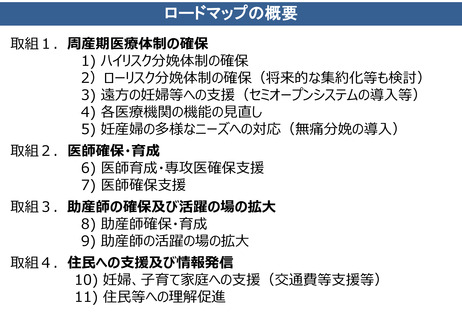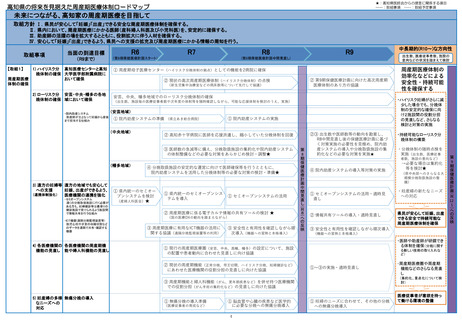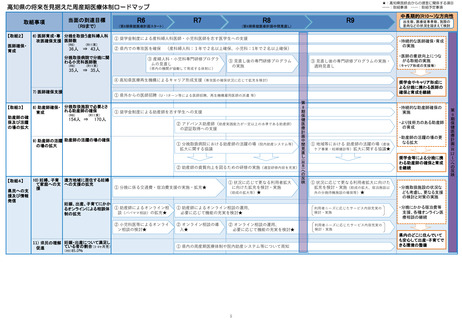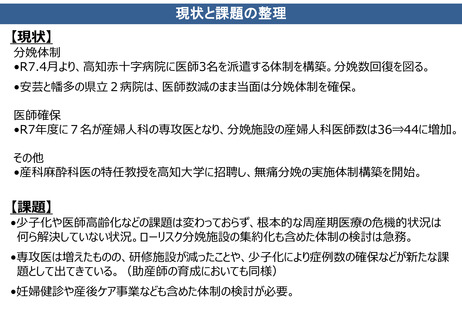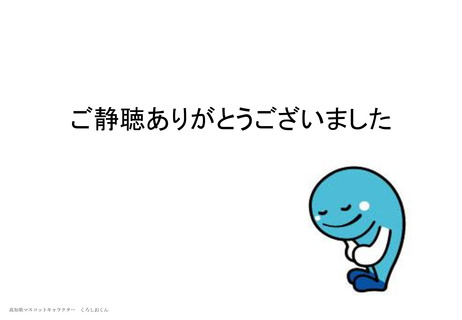よむ、つかう、まなぶ。
資料5_宮地構成員提供資料 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |
| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
★:高知県医師会からの提言に関係する項目
――:取組事項 ----:取組予定事項
高知県の将来を見据えた周産期医療体制ロードマップ
未来につながる、高知家の周産期医療を目指して
取組方針 Ⅰ.県民が安心して「妊娠」「出産」できる安全な周産期医療体制を確保する。
Ⅱ.県内において、周産期医療にかかる医師(産科婦人科医及び小児科医)を、安定的に確保する。
Ⅲ.助産師の活躍の場を拡大するとともに、役割拡大に伴う人材を確保する。
Ⅳ.安心して「妊娠」「出産」できるよう、県民への支援の拡充及び周産期医療にかかる情報の周知を行う。
取組事項
当面の到達目標
R6
(R9まで)
(第8期保健医療計画スタート)
【取組1】
1) ハイリスク分 高知医療センターと高知
娩体制の確保 大学医学部附属病院に
周産期医療
おいて確保
体制の確保
2) ローリスク分 安芸・中央・幡多の各地
娩体制の確保 域において確保
R7
R8
(第8期保健医療計画中間見直し)
① 周産期母子医療センター(ハイリスク分娩体制の拠点)としての機能を2病院に確保
(新生児集中治療室などの病床数等について先行して協議)
安芸、中央、幡多地域でのローリスク分娩体制の確保
(県立あき総合病院)
① 院内助産システムの実施
② 高知赤十字病院に医師を応援派遣し、縮小していた分娩体制を回復
③ 医師数の急減等に備え、分娩取扱施設の集約化や院内助産システム
の体制整備などの必要な対策をあらかじめ検討・調整★
(幡多地域)
・ICT機器(遠隔分娩監視装置等)
胎児心拍や子宮の収縮状態など
のデータを遠隔で共有・確認する
機器
4) 各医療機関の 各医療機関の周産期機
機能の見直し 能や婦人科機能の見直し
④ 分娩取扱施設の安定的な運営に向けて医師確保等を行うとともに、
院内助産システムを活用した分娩体制等の必要な対策の検討・準備★
① 県内統一のセミオー
プンシステムを検討
(産婦人科医会)★
① 県内統一のセミオープンシス
テムを導入
① セミオープンシステムの活用
② 周産期医療に係る電子カルテ情報の共有ツールの検討 ★
(国の医療DXの動向を踏まえながら)
③ 周産期医療に有用なICT機器の活用に
関する協議(遠隔分娩監視装置等の利用)
③ 安全性と有用性を確認しながら順
次導入(機器への習熟と本格導入)
第
8
期
保
健
医
療
計
画
中
間
見
直
し
(
R
8
)
へ
の
反
映
②③ 出生数や医師数等の動向を勘案し、
R8中間見直し後の保健医療計画に基づ
く対策実施の必要性を見極め、院内助
産システムの導入や分娩取扱施設の集
約化などの必要な対策を実施★
④ 院内助産システムの導入等対策の実施
① セミオープンシステムの活用・適時見
直し
② 情報共有ツールの導入・適時見直し
① 無痛分娩の導入準備
(医療従事者の育成など)
① 脳血管や心臓の疾患など医学的
に必要な分娩への無痛分娩導入
4
周産期医療体制の
効率化などによる
安全性・持続可能
性を確保する
・持続可能なローリスク分
娩体制の構築
・分娩体制の随時点検を
実施(出生数、医療従事
→必要な場合は集約化
等を検討★
(県中央部へのさらなる大
規模分娩取扱施設の整
備)
・妊産婦の新たなニーズ
への対応
県民が安心して妊娠、出産
できる安全で持続可能な
周産期医療体制を確保
③ 安全性と有用性を確認しながら順次導入
(機器への習熟と本格導入)
・医師や助産師が研鑽でき
る体制を確保(分娩に関す
る新しい技術の取り入れな
ど)
①~③の実施・適時見直し
・周産期医療圏や周産期
機能などのさらなる見直
し
(集約化、重点化について検
討)
③ 周産期機能と婦人科機能(がん、更年期疾患など)を併せ持つ医療機関
での役割分担(がん手術の集約化など)の見直しに向けた協議
5) 妊産婦の多様 無痛分娩の導入
なニーズへの
対応
出生数、医療従事者数、施設の
意向などの状況を踏まえて検討
者数、施設の意向など)
① 現行の周産期医療圏(安芸、中央、高幡、幡多)の設定について、施設
の配置や患者動向に合わせた見直しに向け協議
② 現状の周産期機能(正常分娩、帝王切開、ハイリスク分娩、妊婦健診など)
にあわせた医療機関の役割分担の見直しに向けた協議
中長期的(R10~)な方向性
・ハイリスク妊婦がさらに減
少した場合でも、分娩体
制の安定的な確保に向
け2施設間の役割分担
の見直しなど、さらなる
検討と対策の実施
(出生数、施設毎の医療従事者数や次年度の体制等を随時確認しながら、可能な応援体制を検討のうえ、実施)
(中央地域)
・セミオープンシステム
遠くの分娩取扱施設に行く必要が
ある方も、妊婦健診等は最寄りの
健診施設で受けられるよう施設間
で情報共有を行う仕組み
② 第9期保健医療計画に向けた高次周産期
医療体制のあり方の協議
② 現状の高次周産期医療体制(ハイリスク分娩体制)の点検
(安芸地域)
・院内助産システム
助産師が主となって妊娠から産後
① 院内助産システムの準備
まで担当する仕組み
3) 遠方の妊婦等 遠方の地域でも安心して
への支援
妊娠、出産ができるよう、
(連携体制強化)
医療機関の連携を強化
R9
① 妊婦のニーズに合わせて、その他の分娩
への無痛分娩導入
医療従事者が意欲を持っ
て働ける環境の整備
第
9
期
保
健
医
療
計
画
(
R
12
~
)
へ
の
反
映
――:取組事項 ----:取組予定事項
高知県の将来を見据えた周産期医療体制ロードマップ
未来につながる、高知家の周産期医療を目指して
取組方針 Ⅰ.県民が安心して「妊娠」「出産」できる安全な周産期医療体制を確保する。
Ⅱ.県内において、周産期医療にかかる医師(産科婦人科医及び小児科医)を、安定的に確保する。
Ⅲ.助産師の活躍の場を拡大するとともに、役割拡大に伴う人材を確保する。
Ⅳ.安心して「妊娠」「出産」できるよう、県民への支援の拡充及び周産期医療にかかる情報の周知を行う。
取組事項
当面の到達目標
R6
(R9まで)
(第8期保健医療計画スタート)
【取組1】
1) ハイリスク分 高知医療センターと高知
娩体制の確保 大学医学部附属病院に
周産期医療
おいて確保
体制の確保
2) ローリスク分 安芸・中央・幡多の各地
娩体制の確保 域において確保
R7
R8
(第8期保健医療計画中間見直し)
① 周産期母子医療センター(ハイリスク分娩体制の拠点)としての機能を2病院に確保
(新生児集中治療室などの病床数等について先行して協議)
安芸、中央、幡多地域でのローリスク分娩体制の確保
(県立あき総合病院)
① 院内助産システムの実施
② 高知赤十字病院に医師を応援派遣し、縮小していた分娩体制を回復
③ 医師数の急減等に備え、分娩取扱施設の集約化や院内助産システム
の体制整備などの必要な対策をあらかじめ検討・調整★
(幡多地域)
・ICT機器(遠隔分娩監視装置等)
胎児心拍や子宮の収縮状態など
のデータを遠隔で共有・確認する
機器
4) 各医療機関の 各医療機関の周産期機
機能の見直し 能や婦人科機能の見直し
④ 分娩取扱施設の安定的な運営に向けて医師確保等を行うとともに、
院内助産システムを活用した分娩体制等の必要な対策の検討・準備★
① 県内統一のセミオー
プンシステムを検討
(産婦人科医会)★
① 県内統一のセミオープンシス
テムを導入
① セミオープンシステムの活用
② 周産期医療に係る電子カルテ情報の共有ツールの検討 ★
(国の医療DXの動向を踏まえながら)
③ 周産期医療に有用なICT機器の活用に
関する協議(遠隔分娩監視装置等の利用)
③ 安全性と有用性を確認しながら順
次導入(機器への習熟と本格導入)
第
8
期
保
健
医
療
計
画
中
間
見
直
し
(
R
8
)
へ
の
反
映
②③ 出生数や医師数等の動向を勘案し、
R8中間見直し後の保健医療計画に基づ
く対策実施の必要性を見極め、院内助
産システムの導入や分娩取扱施設の集
約化などの必要な対策を実施★
④ 院内助産システムの導入等対策の実施
① セミオープンシステムの活用・適時見
直し
② 情報共有ツールの導入・適時見直し
① 無痛分娩の導入準備
(医療従事者の育成など)
① 脳血管や心臓の疾患など医学的
に必要な分娩への無痛分娩導入
4
周産期医療体制の
効率化などによる
安全性・持続可能
性を確保する
・持続可能なローリスク分
娩体制の構築
・分娩体制の随時点検を
実施(出生数、医療従事
→必要な場合は集約化
等を検討★
(県中央部へのさらなる大
規模分娩取扱施設の整
備)
・妊産婦の新たなニーズ
への対応
県民が安心して妊娠、出産
できる安全で持続可能な
周産期医療体制を確保
③ 安全性と有用性を確認しながら順次導入
(機器への習熟と本格導入)
・医師や助産師が研鑽でき
る体制を確保(分娩に関す
る新しい技術の取り入れな
ど)
①~③の実施・適時見直し
・周産期医療圏や周産期
機能などのさらなる見直
し
(集約化、重点化について検
討)
③ 周産期機能と婦人科機能(がん、更年期疾患など)を併せ持つ医療機関
での役割分担(がん手術の集約化など)の見直しに向けた協議
5) 妊産婦の多様 無痛分娩の導入
なニーズへの
対応
出生数、医療従事者数、施設の
意向などの状況を踏まえて検討
者数、施設の意向など)
① 現行の周産期医療圏(安芸、中央、高幡、幡多)の設定について、施設
の配置や患者動向に合わせた見直しに向け協議
② 現状の周産期機能(正常分娩、帝王切開、ハイリスク分娩、妊婦健診など)
にあわせた医療機関の役割分担の見直しに向けた協議
中長期的(R10~)な方向性
・ハイリスク妊婦がさらに減
少した場合でも、分娩体
制の安定的な確保に向
け2施設間の役割分担
の見直しなど、さらなる
検討と対策の実施
(出生数、施設毎の医療従事者数や次年度の体制等を随時確認しながら、可能な応援体制を検討のうえ、実施)
(中央地域)
・セミオープンシステム
遠くの分娩取扱施設に行く必要が
ある方も、妊婦健診等は最寄りの
健診施設で受けられるよう施設間
で情報共有を行う仕組み
② 第9期保健医療計画に向けた高次周産期
医療体制のあり方の協議
② 現状の高次周産期医療体制(ハイリスク分娩体制)の点検
(安芸地域)
・院内助産システム
助産師が主となって妊娠から産後
① 院内助産システムの準備
まで担当する仕組み
3) 遠方の妊婦等 遠方の地域でも安心して
への支援
妊娠、出産ができるよう、
(連携体制強化)
医療機関の連携を強化
R9
① 妊婦のニーズに合わせて、その他の分娩
への無痛分娩導入
医療従事者が意欲を持っ
て働ける環境の整備
第
9
期
保
健
医
療
計
画
(
R
12
~
)
へ
の
反
映