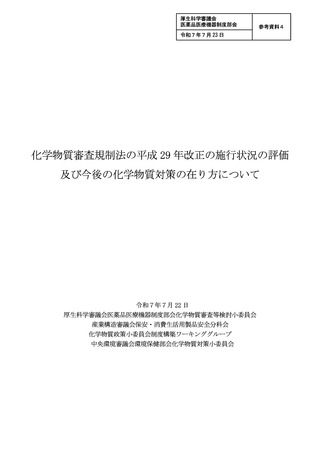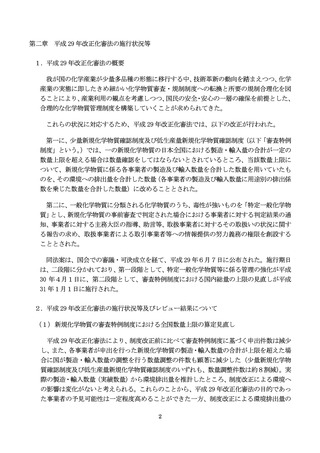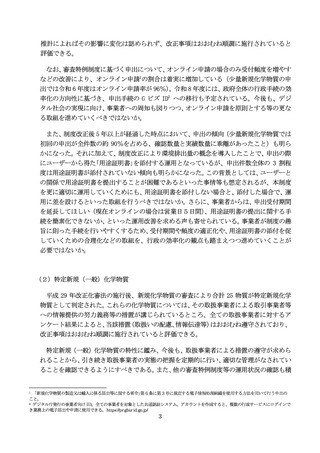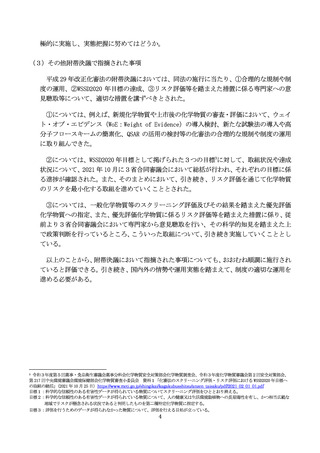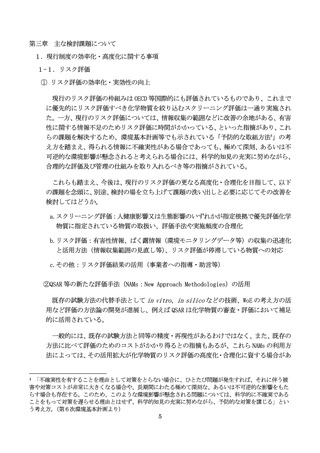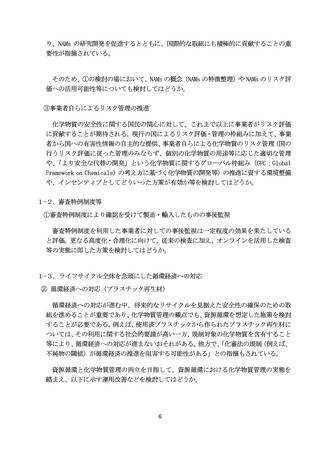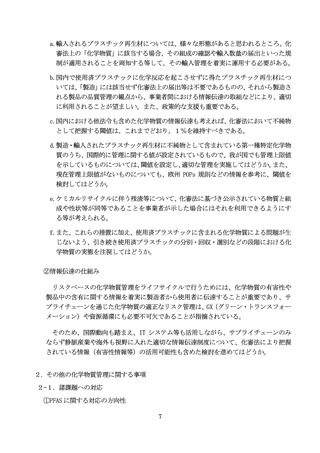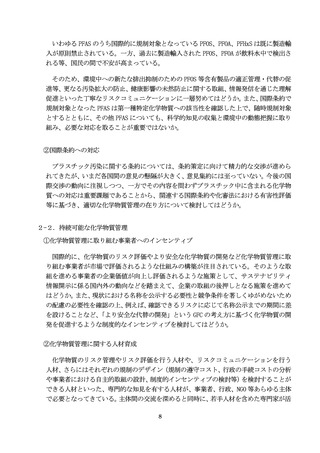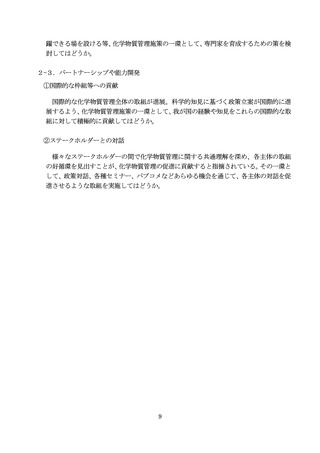よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料4】化学物質審査規制法の平成29 年改正の施行状況の評価及び今後の化学物質対策の在り方について (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59820.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第2回 7/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
a.輸入されるプラスチック再生材については、様々な形態があると思われるところ、化
審法上の「化学物質」に該当する場合、その組成の確認や輸入数量の届出といった規
制が適用されることを周知する等して、その輸入管理を着実に運用する必要がある。
b.国内で使用済プラスチックに化学反応を起こさせずに得たプラスチック再生材につ
いては、
「製造」には該当せず化審法上の届出等は不要であるものの、それから製造さ
れる製品の品質管理の観点から、事業者間における情報伝達の取組などにより、適切
に利用されることが望ましい。また、政策的な支援も重要である。
c.国内における他法令も含めた化学物質の情報伝達も考えれば、化審法において不純物
として把握する閾値は、これまでどおり、1%を維持すべきである。
d.製造・輸入されたプラスチック再生材に不純物として含まれている第一種特定化学物
質のうち、国際的に管理に関する値が設定されているもので、我が国でも管理上限値
を示しているものについては、閾値を設定し、適切な管理を実施してはどうか。また、
現在管理上限値がないものについても、欧州 POPs 規則などの情報を参考に、閾値を
検討してはどうか。
e.ケミカルリサイクルに伴う残渣等について、化審法に基づき公示されている物質と組
成や性状等が同等であることを事業者が示した場合にはそれを利用できるようにす
る等が考えられる。
f.また、これらの措置に加え、使用済プラスチックに含まれる化学物質による問題が生
じないよう、引き続き使用済プラスチックの分別・回収・選別などの段階における化
学物質の実態を注視してはどうか。
②情報伝達の仕組み
リスクベースの化学物質管理をライフサイクルで行うためには、化学物質の有害性や
製品中の含有に関する情報を着実に製造者から使用者に伝達することが重要であり、サ
プライチェーンを通じた化学物質の適正なリスク管理は、GX(グリーン・トランスフォー
メーション)や資源循環にも必要不可欠であることが指摘されている。
そのため、国際動向も踏まえ、IT システム等も活用しながら、サプライチェーンのみ
ならず静脈産業や海外も視野に入れた適切な情報伝達制度について、化審法により把握
されている情報(有害性情報等)の活用可能性も含めた検討を進めてはどうか。
2. その他の化学物質管理に関する事項
2-1.諸課題への対応
①PFAS に関する対応の方向性
7
審法上の「化学物質」に該当する場合、その組成の確認や輸入数量の届出といった規
制が適用されることを周知する等して、その輸入管理を着実に運用する必要がある。
b.国内で使用済プラスチックに化学反応を起こさせずに得たプラスチック再生材につ
いては、
「製造」には該当せず化審法上の届出等は不要であるものの、それから製造さ
れる製品の品質管理の観点から、事業者間における情報伝達の取組などにより、適切
に利用されることが望ましい。また、政策的な支援も重要である。
c.国内における他法令も含めた化学物質の情報伝達も考えれば、化審法において不純物
として把握する閾値は、これまでどおり、1%を維持すべきである。
d.製造・輸入されたプラスチック再生材に不純物として含まれている第一種特定化学物
質のうち、国際的に管理に関する値が設定されているもので、我が国でも管理上限値
を示しているものについては、閾値を設定し、適切な管理を実施してはどうか。また、
現在管理上限値がないものについても、欧州 POPs 規則などの情報を参考に、閾値を
検討してはどうか。
e.ケミカルリサイクルに伴う残渣等について、化審法に基づき公示されている物質と組
成や性状等が同等であることを事業者が示した場合にはそれを利用できるようにす
る等が考えられる。
f.また、これらの措置に加え、使用済プラスチックに含まれる化学物質による問題が生
じないよう、引き続き使用済プラスチックの分別・回収・選別などの段階における化
学物質の実態を注視してはどうか。
②情報伝達の仕組み
リスクベースの化学物質管理をライフサイクルで行うためには、化学物質の有害性や
製品中の含有に関する情報を着実に製造者から使用者に伝達することが重要であり、サ
プライチェーンを通じた化学物質の適正なリスク管理は、GX(グリーン・トランスフォー
メーション)や資源循環にも必要不可欠であることが指摘されている。
そのため、国際動向も踏まえ、IT システム等も活用しながら、サプライチェーンのみ
ならず静脈産業や海外も視野に入れた適切な情報伝達制度について、化審法により把握
されている情報(有害性情報等)の活用可能性も含めた検討を進めてはどうか。
2. その他の化学物質管理に関する事項
2-1.諸課題への対応
①PFAS に関する対応の方向性
7