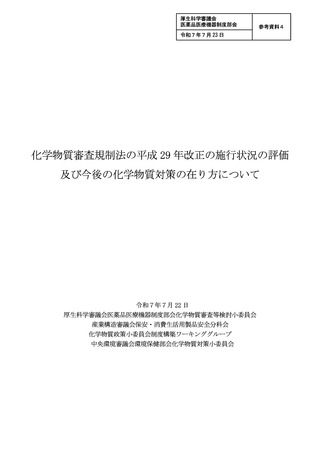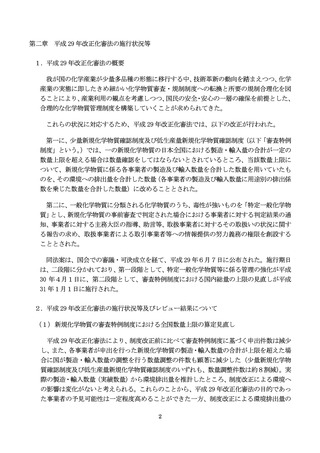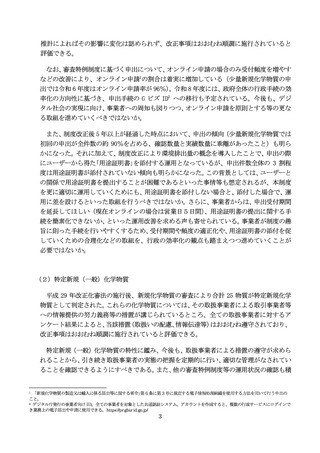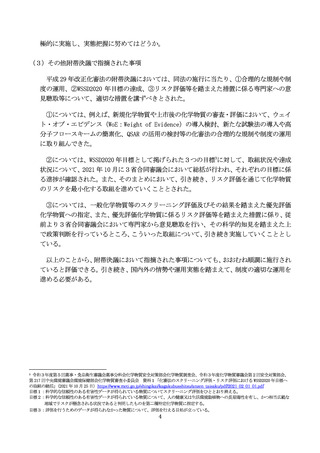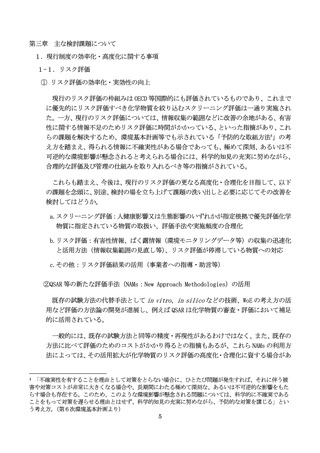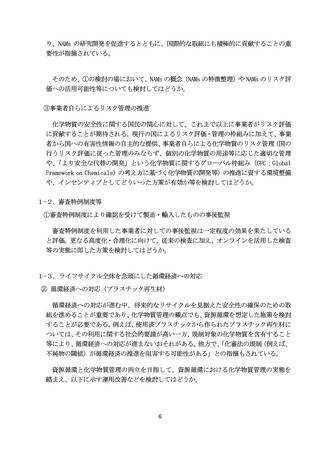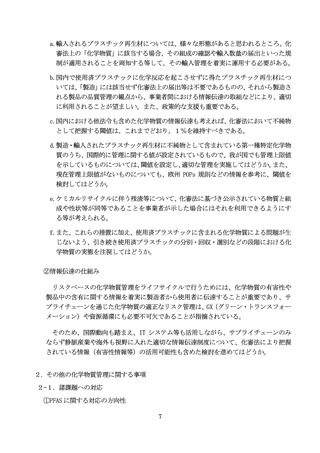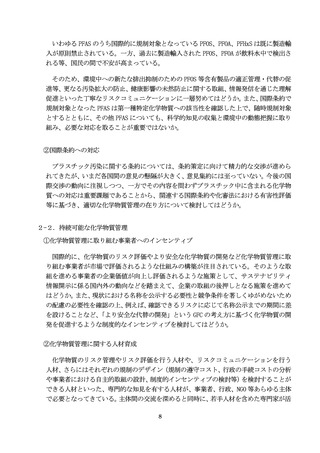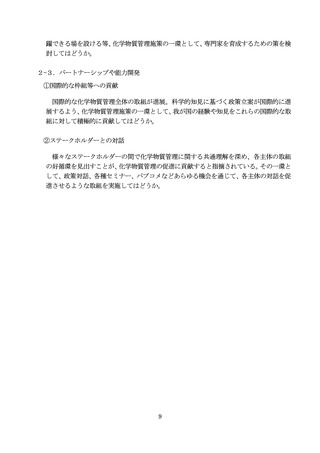よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料4】化学物質審査規制法の平成29 年改正の施行状況の評価及び今後の化学物質対策の在り方について (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59820.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第2回 7/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第二章 平成 29 年改正化審法の施行状況等
1. 平成 29 年改正化審法の概要
我が国の化学産業が少量多品種の形態に移行する中、技術革新の動向を踏まえつつ、化学
産業の実態に即したきめ細かい化学物質審査・規制制度への転換と所要の規制合理化を図
ることにより、産業利用の観点を考慮しつつ、国民の安全・安心の一層の確保を前提とした、
合理的な化学物質管理制度を構築していくことが求められてきた。
これらの状況に対応するため、平成 29 年改正化審法では、以下の改正が行われた。
第一に、少量新規化学物質確認制度及び低生産量新規化学物質確認制度(以下「審査特例
制度」という。
)では、一の新規化学物質の日本全国における製造・輸入量の合計が一定の
数量上限を超える場合は数量確認をしてはならないとされているところ、当該数量上限に
ついて、新規化学物質に係る各事業者の製造及び輸入数量を合計した数量を用いていたも
のを、その環境への排出量を合計した数量(各事業者の製造及び輸入数量に用途別の排出係
数を乗じた数量を合計した数量)に改めることとされた。
第二に、一般化学物質に分類される化学物質のうち、毒性が強いものを「特定一般化学物
質」とし、新規化学物質の事前審査で判定された場合における事業者に対する判定結果の通
知、事業者に対する主務大臣の指導、助言等、取扱事業者に対するその取扱いの状況に関す
る報告の求め、取扱事業者による取引事業者等への情報提供の努力義務の権限を創設する
こととされた。
同法案は、国会での審議・可決成立を経て、平成 29 年6月7日に公布された。施行期日
は、二段階に分かれており、第一段階として、特定一般化学物質等に係る管理の強化が平成
30 年4月1日に、第二段階として、審査特例制度における国内総量の上限の見直しが平成
31 年1月1日に施行された。
2. 平成 29 年改正化審法の施行状況等及びレビュー結果について
(1) 新規化学物質の審査特例制度における全国数量上限の算定見直し
平成 29 年改正化審法により、制度改正前に比べて審査特例制度に基づく申出件数は減少
し、また、各事業者が申出を行った新規化学物質の製造・輸入数量の合計が上限を超えた場
合に国が製造・輸入数量の調整を行う数量調整の件数も顕著に減少した(少量新規化学物
質確認制度及び低生産量新規化学物質確認制度のいずれも、数量調整件数は約8割減)
。実
際の製造・輸入数量(実績数量)から環境排出量を推計したところ、制度改正による環境へ
の影響は変化がないと考えられる。これらのことから、平成 29 年改正化審法の目的であっ
た事業者の予見可能性は一定程度高めることができた一方、制度改正による環境排出量の
2
1. 平成 29 年改正化審法の概要
我が国の化学産業が少量多品種の形態に移行する中、技術革新の動向を踏まえつつ、化学
産業の実態に即したきめ細かい化学物質審査・規制制度への転換と所要の規制合理化を図
ることにより、産業利用の観点を考慮しつつ、国民の安全・安心の一層の確保を前提とした、
合理的な化学物質管理制度を構築していくことが求められてきた。
これらの状況に対応するため、平成 29 年改正化審法では、以下の改正が行われた。
第一に、少量新規化学物質確認制度及び低生産量新規化学物質確認制度(以下「審査特例
制度」という。
)では、一の新規化学物質の日本全国における製造・輸入量の合計が一定の
数量上限を超える場合は数量確認をしてはならないとされているところ、当該数量上限に
ついて、新規化学物質に係る各事業者の製造及び輸入数量を合計した数量を用いていたも
のを、その環境への排出量を合計した数量(各事業者の製造及び輸入数量に用途別の排出係
数を乗じた数量を合計した数量)に改めることとされた。
第二に、一般化学物質に分類される化学物質のうち、毒性が強いものを「特定一般化学物
質」とし、新規化学物質の事前審査で判定された場合における事業者に対する判定結果の通
知、事業者に対する主務大臣の指導、助言等、取扱事業者に対するその取扱いの状況に関す
る報告の求め、取扱事業者による取引事業者等への情報提供の努力義務の権限を創設する
こととされた。
同法案は、国会での審議・可決成立を経て、平成 29 年6月7日に公布された。施行期日
は、二段階に分かれており、第一段階として、特定一般化学物質等に係る管理の強化が平成
30 年4月1日に、第二段階として、審査特例制度における国内総量の上限の見直しが平成
31 年1月1日に施行された。
2. 平成 29 年改正化審法の施行状況等及びレビュー結果について
(1) 新規化学物質の審査特例制度における全国数量上限の算定見直し
平成 29 年改正化審法により、制度改正前に比べて審査特例制度に基づく申出件数は減少
し、また、各事業者が申出を行った新規化学物質の製造・輸入数量の合計が上限を超えた場
合に国が製造・輸入数量の調整を行う数量調整の件数も顕著に減少した(少量新規化学物
質確認制度及び低生産量新規化学物質確認制度のいずれも、数量調整件数は約8割減)
。実
際の製造・輸入数量(実績数量)から環境排出量を推計したところ、制度改正による環境へ
の影響は変化がないと考えられる。これらのことから、平成 29 年改正化審法の目的であっ
た事業者の予見可能性は一定程度高めることができた一方、制度改正による環境排出量の
2