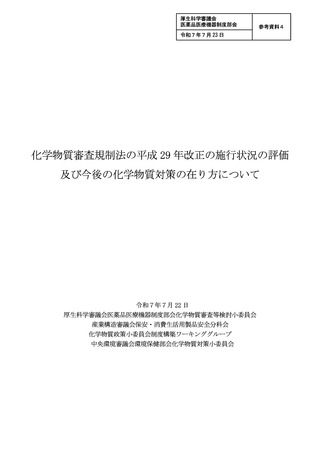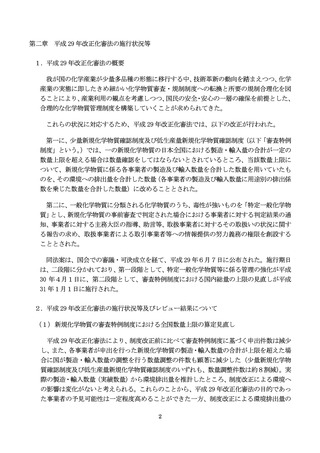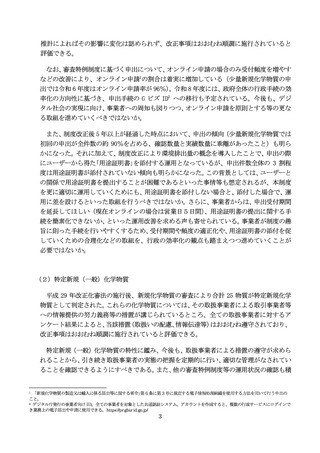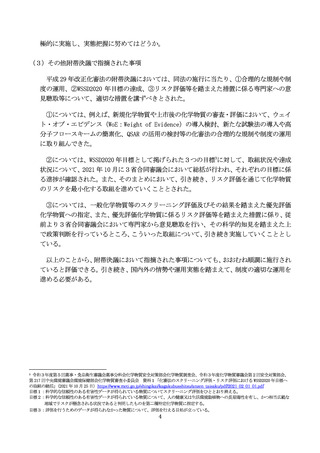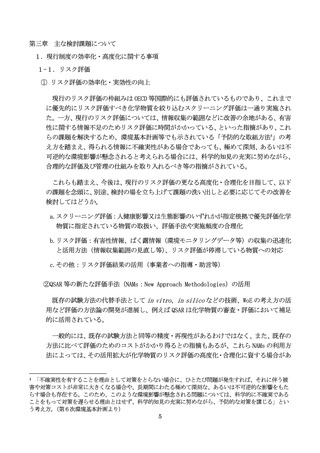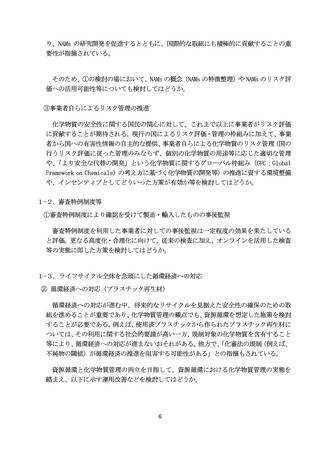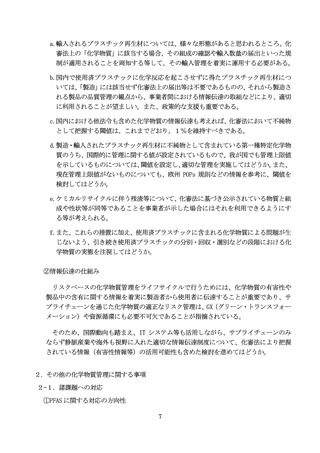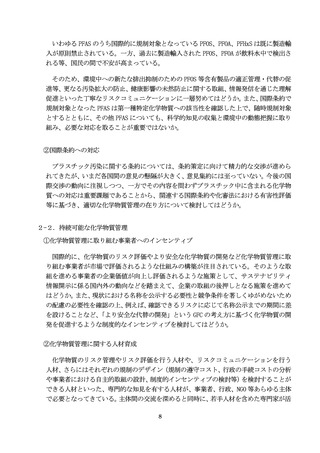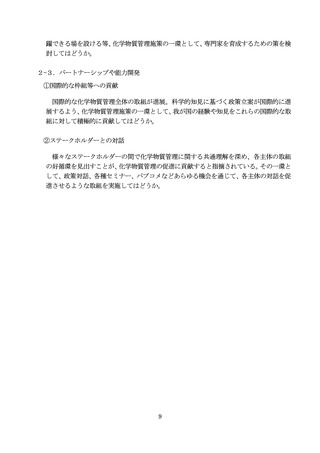よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料4】化学物質審査規制法の平成29 年改正の施行状況の評価及び今後の化学物質対策の在り方について (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59820.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第2回 7/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第三章 主な検討課題について
1. 現行制度の効率化・高度化に関する事項
1-1.リスク評価
① リスク評価の効率化・実効性の向上
現行のリスク評価の枠組みは OECD 等国際的にも評価されているものであり、これまで
に優先的にリスク評価すべき化学物質を絞り込むスクリーニング評価は一通り実施され
た。一方、現行のリスク評価については、情報収集の範囲などに改善の余地がある、有害
性に関する情報不足のためリスク評価に時間がかかっている、といった指摘があり、これ
らの課題を解決するため、環境基本計画等でも示されている「予防的な取組方法4」の考
え方を踏まえ、得られる情報に不確実性がある場合であっても、極めて深刻、あるいは不
可逆的な環境影響が懸念されると考えられる場合には、科学的知見の充実に努めながら、
合理的な評価及び管理の仕組みを取り入れるべき等の指摘がされている。
これらも踏まえ、今後は、現行のリスク評価の更なる高度化・合理化を目指して、以下
の課題を念頭に、別途、検討の場を立ち上げて課題の洗い出しと必要に応じてその改善を
検討してはどうか。
a.スクリーニング評価:人健康影響又は生態影響のいずれかが指定根拠で優先評価化学
物質に指定されている物質の取扱い、評価手法や実施頻度の合理化
b.リスク評価:有害性情報、ばく露情報(環境モニタリングデータ等)の収集の迅速化
と活用方法(情報収集範囲の見直し等)
、リスク評価が停滞している物質への対応
c.その他:リスク評価結果の活用(事業者への指導・助言等)
②QSAR 等の新たな評価手法(NAMs:New Approach Methodologies)の活用
既存の試験方法の代替手法として in vitro、in silico などの技術、WoE の考え方の活
用など評価の方法論の開発が進展し、例えば QSAR は化学物質の審査・評価において補足
的に活用されている。
一般的には、既存の試験方法と同等の精度・再現性があるわけではなく、また、既存の
方法に比べて評価のためのコストがかかり得るとの指摘もあるが、これら NAMs の利用方
法によっては、その活用拡大が化学物質のリスク評価の高度化・合理化に資する場合があ
4 「不確実性を有することを理由として対策をとらない場合に、ひとたび問題が発生すれば、それに伴う被
害や対策コストが非常に大きくなる場合や、長期間にわたる極めて深刻な、あるいは不可逆的な影響をもた
らす場合も存在する。このため、このような環境影響が懸念される問題については、科学的に不確実である
ことをもって対策を遅らせる理由とはせず、科学的知見の充実に努めながら、予防的な対策を講じる」とい
う考え方。
(第6次環境基本計画より)
5
1. 現行制度の効率化・高度化に関する事項
1-1.リスク評価
① リスク評価の効率化・実効性の向上
現行のリスク評価の枠組みは OECD 等国際的にも評価されているものであり、これまで
に優先的にリスク評価すべき化学物質を絞り込むスクリーニング評価は一通り実施され
た。一方、現行のリスク評価については、情報収集の範囲などに改善の余地がある、有害
性に関する情報不足のためリスク評価に時間がかかっている、といった指摘があり、これ
らの課題を解決するため、環境基本計画等でも示されている「予防的な取組方法4」の考
え方を踏まえ、得られる情報に不確実性がある場合であっても、極めて深刻、あるいは不
可逆的な環境影響が懸念されると考えられる場合には、科学的知見の充実に努めながら、
合理的な評価及び管理の仕組みを取り入れるべき等の指摘がされている。
これらも踏まえ、今後は、現行のリスク評価の更なる高度化・合理化を目指して、以下
の課題を念頭に、別途、検討の場を立ち上げて課題の洗い出しと必要に応じてその改善を
検討してはどうか。
a.スクリーニング評価:人健康影響又は生態影響のいずれかが指定根拠で優先評価化学
物質に指定されている物質の取扱い、評価手法や実施頻度の合理化
b.リスク評価:有害性情報、ばく露情報(環境モニタリングデータ等)の収集の迅速化
と活用方法(情報収集範囲の見直し等)
、リスク評価が停滞している物質への対応
c.その他:リスク評価結果の活用(事業者への指導・助言等)
②QSAR 等の新たな評価手法(NAMs:New Approach Methodologies)の活用
既存の試験方法の代替手法として in vitro、in silico などの技術、WoE の考え方の活
用など評価の方法論の開発が進展し、例えば QSAR は化学物質の審査・評価において補足
的に活用されている。
一般的には、既存の試験方法と同等の精度・再現性があるわけではなく、また、既存の
方法に比べて評価のためのコストがかかり得るとの指摘もあるが、これら NAMs の利用方
法によっては、その活用拡大が化学物質のリスク評価の高度化・合理化に資する場合があ
4 「不確実性を有することを理由として対策をとらない場合に、ひとたび問題が発生すれば、それに伴う被
害や対策コストが非常に大きくなる場合や、長期間にわたる極めて深刻な、あるいは不可逆的な影響をもた
らす場合も存在する。このため、このような環境影響が懸念される問題については、科学的に不確実である
ことをもって対策を遅らせる理由とはせず、科学的知見の充実に努めながら、予防的な対策を講じる」とい
う考え方。
(第6次環境基本計画より)
5