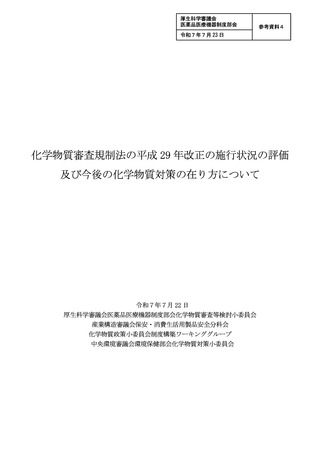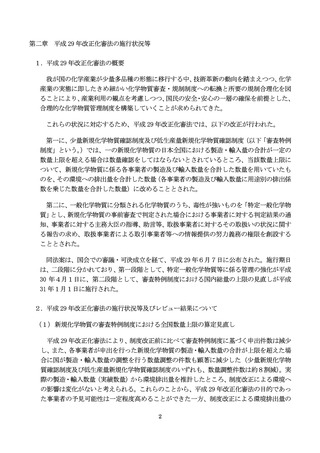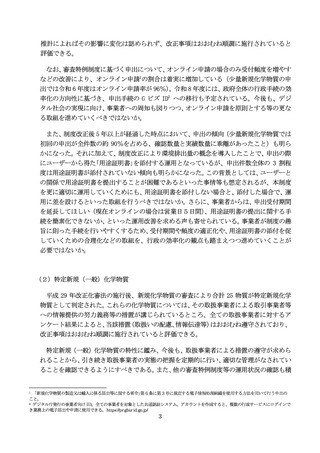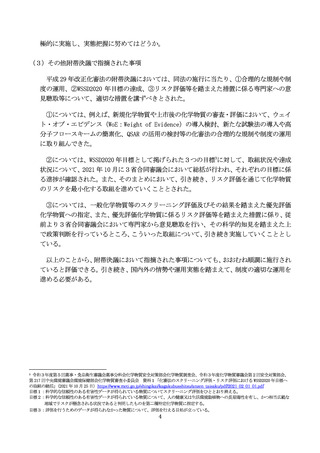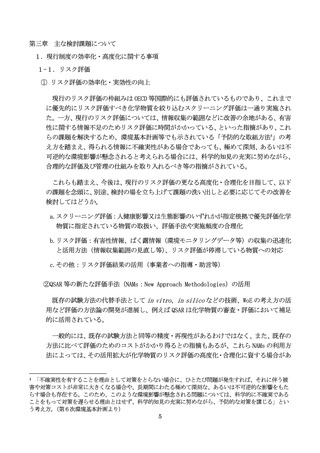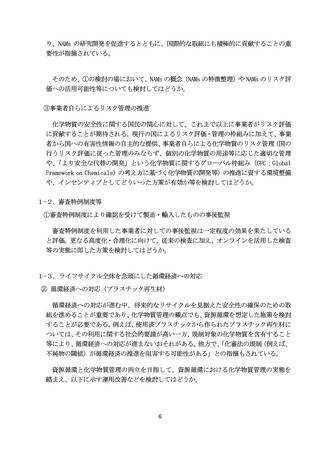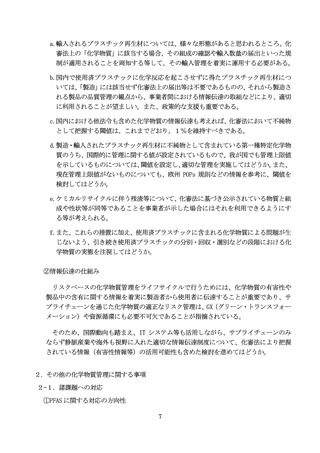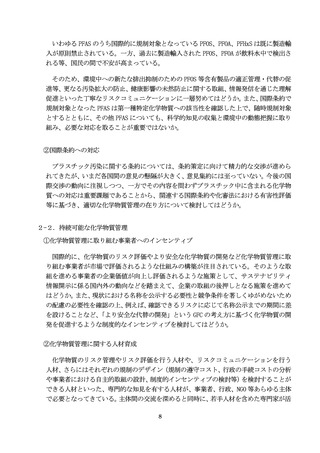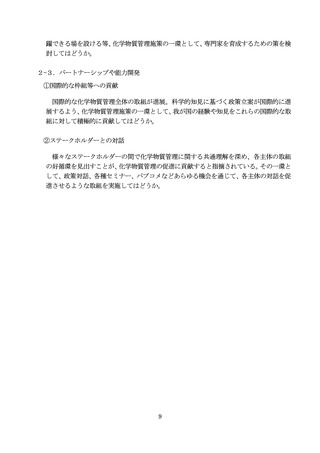よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料4】化学物質審査規制法の平成29 年改正の施行状況の評価及び今後の化学物質対策の在り方について (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59820.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第2回 7/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
いわゆる PFAS のうち国際的に規制対象となっている PFOS、PFOA、PFHxS は既に製造輸
入が原則禁止されている。一方、過去に製造輸入された PFOS、PFOA が飲料水中で検出さ
れる等、国民の間で不安が高まっている。
そのため、環境中への新たな排出抑制のための PFOS 等含有製品の適正管理・代替の促
進等、更なる汚染拡大の防止、健康影響の未然防止に関する取組、情報発信を通じた理解
促進といった丁寧なリスクコミュニケーションに一層努めてはどうか。また、国際条約で
規制対象となった PFAS は第一種特定化学物質への該当性を確認した上で、随時規制対象
とするとともに、その他 PFAS についても、科学的知見の収集と環境中の動態把握に取り
組み、必要な対応を取ることが重要ではないか。
②国際条約への対応
プラスチック汚染に関する条約については、条約策定に向けて精力的な交渉が進めら
れてきたが、いまだ各国間の意見の懸隔が大きく、意見集約には至っていない。今後の国
際交渉の動向に注視しつつ、一方でその内容を問わずプラスチック中に含まれる化学物
質への対応は重要課題であることから、関連する国際条約や化審法における有害性評価
等に基づき、適切な化学物質管理の在り方について検討してはどうか。
2-2.持続可能な化学物質管理
①化学物質管理に取り組む事業者へのインセンティブ
国際的に、化学物質のリスク評価やより安全な化学物質の開発など化学物質管理に取
り組む事業者が市場で評価されるような仕組みの構築が注目されている。そのような取
組を進める事業者の企業価値が向上し評価されるような施策として、サステナビリティ
情報開示に係る国内外の動向などを踏まえて、企業の取組の後押しとなる施策を進めて
はどうか。また、現状における名称を公示する必要性と競争条件を著しくゆがめないため
の配慮の必要性を確認の上、例えば、確認できるリスクに応じて名称公示までの期間に差
を設けることなど、
「より安全な代替の開発」という GFC の考え方に基づく化学物質の開
発を促進するような制度的なインセンティブを検討してはどうか。
②化学物質管理に関する人材育成
化学物質のリスク管理やリスク評価を行う人材や、リスクコミュニケーションを行う
人材、さらにはそれぞれの規制のデザイン(規制の遵守コスト、行政の手続コストの分析
や事業者における自主的取組の設計、制度的インセンティブの検討等)を検討することが
できる人材といった、専門的な知見を有する人材が、事業者、行政、NGO 等あらゆる主体
で必要となってきている。主体間の交流を深めると同時に、若手人材を含めた専門家が活
8
入が原則禁止されている。一方、過去に製造輸入された PFOS、PFOA が飲料水中で検出さ
れる等、国民の間で不安が高まっている。
そのため、環境中への新たな排出抑制のための PFOS 等含有製品の適正管理・代替の促
進等、更なる汚染拡大の防止、健康影響の未然防止に関する取組、情報発信を通じた理解
促進といった丁寧なリスクコミュニケーションに一層努めてはどうか。また、国際条約で
規制対象となった PFAS は第一種特定化学物質への該当性を確認した上で、随時規制対象
とするとともに、その他 PFAS についても、科学的知見の収集と環境中の動態把握に取り
組み、必要な対応を取ることが重要ではないか。
②国際条約への対応
プラスチック汚染に関する条約については、条約策定に向けて精力的な交渉が進めら
れてきたが、いまだ各国間の意見の懸隔が大きく、意見集約には至っていない。今後の国
際交渉の動向に注視しつつ、一方でその内容を問わずプラスチック中に含まれる化学物
質への対応は重要課題であることから、関連する国際条約や化審法における有害性評価
等に基づき、適切な化学物質管理の在り方について検討してはどうか。
2-2.持続可能な化学物質管理
①化学物質管理に取り組む事業者へのインセンティブ
国際的に、化学物質のリスク評価やより安全な化学物質の開発など化学物質管理に取
り組む事業者が市場で評価されるような仕組みの構築が注目されている。そのような取
組を進める事業者の企業価値が向上し評価されるような施策として、サステナビリティ
情報開示に係る国内外の動向などを踏まえて、企業の取組の後押しとなる施策を進めて
はどうか。また、現状における名称を公示する必要性と競争条件を著しくゆがめないため
の配慮の必要性を確認の上、例えば、確認できるリスクに応じて名称公示までの期間に差
を設けることなど、
「より安全な代替の開発」という GFC の考え方に基づく化学物質の開
発を促進するような制度的なインセンティブを検討してはどうか。
②化学物質管理に関する人材育成
化学物質のリスク管理やリスク評価を行う人材や、リスクコミュニケーションを行う
人材、さらにはそれぞれの規制のデザイン(規制の遵守コスト、行政の手続コストの分析
や事業者における自主的取組の設計、制度的インセンティブの検討等)を検討することが
できる人材といった、専門的な知見を有する人材が、事業者、行政、NGO 等あらゆる主体
で必要となってきている。主体間の交流を深めると同時に、若手人材を含めた専門家が活
8